学位論文要旨
| No | 110887 | |
| 著者(漢字) | 奥野,広樹 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | オクノ,ヒロキ | |
| 標題(和) | 入射核破砕片のスピン偏極 | |
| 標題(洋) | ||
| 報告番号 | 110887 | |
| 報告番号 | 甲10887 | |
| 学位授与日 | 1995.03.13 | |
| 学位種別 | 課程博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 博理第2840号 | |
| 研究科 | 理学系研究科 | |
| 専攻 | 物理学専攻 | |
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 原子核は陽子と中性子等のハドロンを構成要素とした少数多体系であり、我々に多様な現象を提供してくれる。ここ十年の原子核物理は、その多様性を拡大するという点で、大きく進展したが、中でも陽子・中性子数の均衡が破れており、 本研究の主要な目的は、上記の様な入射核破砕反応による不安定核生成法に適合したスピン偏極法を新たに確立し、幅広い応用を開拓することにある。その為にまず、我々は、生成に用いる核反応過程そのものの性質を利用して、偏極核を得る可能性を追及した。この際、重要となる条件は、1)生成物が核反応を通じて、スピン偏極することと、2)反応機構が理解され、スピン偏極の反応条件への依存性が予測可能となることである。 入射核破砕片のスピン偏極現象は、低エネルギー領域においては、既に知られていたが、中高エネルギー領域では未解の問題であった。本研究の目的の一つは、中高エネルギー領域の入射核破砕反応に関して、上記の二点を明らかにすることにあった。このため、様々な反応条件下での入射核破砕片のスピン偏極度を、100MeV/核子領域で測定し、偏極発生機構を調べた。 初期の実験から1)の条件に見合う、偏極現象が見い出された。(図1)その解析法として、破砕片偏極は運動学的な整合条件によって生じ、放出運動量依存性を表わす偏極スペクトラムは、反応条件によって決まるNear-side軌道とFar-side軌道の競合関係によって変化するというモデルが考えられた。  このモデルを検証するために、我々は、様々な反応糸において、入射核破砕片のスピン偏極度の測定を系統的に行った。その結果、偏極度は、一般に数%を超え、反応系によっては20%達することが見い出され、偏極現象が普遍的であることが確認された。また、偏極スペクトラムの基本的性質は、当初立てたモデルで理解することが出来、14N(39.4MeV/u)+197Au→12B+X反応と15N(68.0MeV/u)+27Al→12B+X反応の反応系で得られた結果は、それぞれ、Near-side軌道とFar-side軌道が優勢の場合の典型例として理解出来た。その他の反応条件におけるスペクトラムは、より複雑で、反応条件に応じて変化するが、その振る舞いは、これら二つの偏極スペクトラムの間を推移している様に見える(図2)。この推移は、その規則性から、Near-sideとFar-side軌道の競合関係によって発生すると理解された。図2の偏極スペクトラム中の数字は、この競合関係を表わす指標RNF(RNFが1より十分大きい(小さい)時に、Near-side(Far-side)軌道が優勢)の値であるが、実際RNFの値が+3.6から-1.0へと変化するに従って、偏極スペクトラムの形も、Near-side軌道の形からFar-side軌道の形へと推移して行くのがわかる。 一方、当初のモデルから顕著にづれる現象も幾つか観測された。その中で、とりわけ興味ある現象として、偏極スペクトラムがモデルの予想よりも、全体的に負の方向ヘシフトする傾向が見い出された(図2)。この現象は、効率の良い偏極核生成法の可能性を示唆するものであり、我々は、その発現機構の理解を画った。破砕片の持つ角運動量を詳しく考察した結果、入射核破砕反応の剥ぎ取り過程において、もし、核子群が剥ぎ取られる核内位置が後部にずれた場合、偏極度が負の方向にずれることを見い出し、この効果を考慮することによって、測定結果をより再現出来ることを明らかにした。図2中の偏極スペクトトラムに添えられた実線及び1点鎖線はその効果を取り入れて計算されたものであるが、測定結果を良く再現している。核子群の剥ぎ取られる位置が後部にづれる現象は、これまでの中間エネルギー重イオン反応の研究では、二義的に考えられてきたが、我々は、剥ぎ取り過程を核子核子衝突の描象に基づいて再考することにより、剥ぎ取られた核子が、破砕片中で再散乱を起こす事によって、剥ぎ取りの起こる位置に、実際、有為なずれを起こし得ることを確認出来た。以上の測定と考察により、入射核破砕反応に適合する偏極法(以下、入射核破砕反応法と称する)を開発することができた。 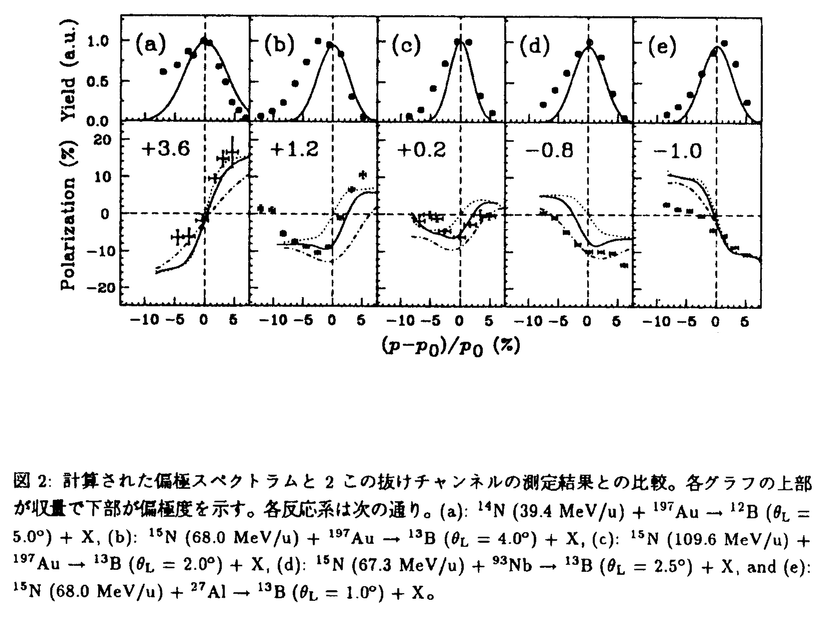  L=5.0°)+X,(b):15N(68.0MeV/u)+197Au→13B( L=5.0°)+X,(b):15N(68.0MeV/u)+197Au→13B( L=4.0°)+X,(c):15N(109.6MeV/u)+197Au→13B( L=4.0°)+X,(c):15N(109.6MeV/u)+197Au→13B( L=2.0°)+X,(d):15N(67.3MeV/u)+93Nb→13B( L=2.0°)+X,(d):15N(67.3MeV/u)+93Nb→13B( L=2.5°)+X,and(e):15N(68.0MeV/u)+27Al→13B( L=2.5°)+X,and(e):15N(68.0MeV/u)+27Al→13B( L=1.0°)+X。 L=1.0°)+X。入射核破砕反応法の特徴は以下の様にまとめられる。得られた偏極度の大きさは数%である。不安定核の収量は、高い生産性をもつ入射核破砕反応を生成反応として使っているため高い。例えば、14Bに関して本研究で得られた収量は、無偏極の14Bを生成するために(d,p)反応で得られた収量の約1000倍である。入射核破砕反応法のFigure of Meritsは他の方法と比べても顕著である。例えば11Liの場合、光ポンピング法に依れば、10%偏極した毎秒2×103個の11Liが生成可能であるのに対し、入射核破砕反応法では数%偏極した毎秒5×104個の11Liの生成が可能であり、この入射核破砕反応法は光ポンピング法に十分匹敵する。この手法の際立った特徴は、光ポンピング法などとは異なり、元素に依らず、普遍的に様々な核種に適応が可能な点にある。さらに、この手法では、偏極した不安定核を得るために、破砕片の放出運動量と放出角度を選択するだけでよく、その単純さ故、効率的で平易な応用が可能となる。 本研究の第二の目的は、入射核破砕反応法の幅広い応用を開拓することにあった。我々はまず、原子核の基本量であり、原子核を応用する上でも重要な核モーメントの測定を行い、現在まで、14B,15B,21F,17N,17Bの磁気モーメントおよび14B,15Bの電気四重極モーメントの測定に成功した(図3)。 測定結果を、主に標準的な殼模型による計算値と比較し、B同位体の結果を中心に、安定核から不安定核にわたって変異する核構造的性質の抽出が試みた。その結果、奇奇核である14Bに関しては、s1/2の1粒子エネルギー準位が標準的な値よりも約1MeV低エネルギー側ヘシフトしているという示唆を得た。s1/2準位が降下する傾向は、N=7の同中性子核で知られており、中性子過剰とともに、顕著になる現象として興味を集めてきた。上の結果は、14Bの様なN=9においても、同様な現象が起こり、それが磁気モーメントの性質を規定することを意味し、興味深い。また、奇核である15Bに関しては、磁気モーメントの減少に寄与している主要な要因は、配位混合であり、内でも、sd殻に居る2個の中性子が2+状態に組む配位の寄与の重要性が理解された。一方、2+励起に関わるこれらの配位は、通常、電気四重極モーメントに強く反映する筈のものでありながら、実測された結果はこの予測と合致しなかった。この矛盾は、中性子の有効電荷の減少を示唆するもので、外側の殻,sd殻中の2個の中性子の2+励起の自由度と内側の殻,p殻,中の核子群のE2巨大共鳴の自由度との結合が、通常の核と違って、弱まっていることを意味しており、中性子過剰領域の原子核構造の特徴を表わす現象として、興味深い。   線の上下計数比、横軸にrf磁場の周波数を示す。 線の上下計数比、横軸にrf磁場の周波数を示す。 | |
| 審査要旨 | 本論文の主な内容は2つの部分からなり、前半は第3章入射核破砕片のスピン偏極発生機構、後半は第4章核モーメント測定による不安定核の構造研究として記述されている。 近年進展が著しい中高エネルギー重イオンビームを用いた不安定核を生成する実験法において、ビームとして入射する原子核が標的核と衝突し反応する際に、入射原子核が持つ速度に近い速度で前方に放出される入射核の破砕片を利用する分光学的研究がよく行われている。提出論文の研究の前半においては、この入射破砕片として生まれる原子核がどのようにスピン偏極しているかをいくつかの系で実験的に観測し、その結果を説明するモデルを提唱し、定量的な説明を試みている。 実験は理化学研究所リングサイクロトロンで得られる核子当り39MeVの14Nビームと67.3MeV-109.6MeVの15Nビームを197Au、159Tb、93Nb、27Alなどの標的にあて、入射核破砕片として得られる12B、13Bなどの核を対象とした。実験は、スピン偏極した破砕片をビーム光学的に分離したのち減速させ、白金薄板にとめる。これらの過程で、減偏極が無視出来ることを考察したうえで、スピン偏極した核から放出される異方的ベータ線放出をプローブとする核磁気共鳴の方法で偏極度を求めた。さらにそれを入射ビームの速度を持つ破砕片の運動量 論文提出者は、このような偏極度スペクトルが何故生じるか説明を試みた。その結果、原子核内で破砕の起こる場所が後方にずれていると考えると説明が出来ることを見い出した。さらに、この後方へのずれをよ、はぎ取られた核子が破砕片中で再散乱を起こすことで定量的に説明出来る可能性があることが示された。 論文の後半では、このように実験手法と現象の解釈とが確立されたスピン偏極した入射核破砕片を用いた応用実験として、14B、15B、21F、17N、17Bの磁気モーメント及び14B、15Bの電気四電極モーメントの測定を行った。これらの測定も、全く新しいものである。論文申請者は、現在の核構造理論で得られる核波動函数の知識を導入してこれらの測定結果を理解しようと試みた。この過程で、14Bに関してs1/2の1粒子エネルギー準位が約1MeV低いエネルギーを持つこと、及び、15Bに関してsd殻の中性子の有効電荷が減少していることなどを見い出している。 これらの2つに大別される学術的成果は、全て、世界を主導する新しく重要な結果であり、博士論文としての要請を十分に満たすものである。 なお、本論文の2つの部分は、石原正泰氏との共同研究であるが、論文提出者が主体となって分析及び検証を行ったもので、論文提出者の寄与が十分であると判断する。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/53838 |
 で規格化した運動量の関数として収集し偏極度スペクトルを得る。行われた実験は、このエネルギー領域では初めてのものである。結果は、破砕片のとる軌道がNear-sideかFar-sideかで予想される偏極度スペクトルを示す場合を両極端として、この2つの競合関係できまる一連の偏極度スペクトルが得られた。実験結果は、これらの傾向の他に、全体的に負の方向ヘシフトしている傾向を持つ結果が得られた。
で規格化した運動量の関数として収集し偏極度スペクトルを得る。行われた実験は、このエネルギー領域では初めてのものである。結果は、破砕片のとる軌道がNear-sideかFar-sideかで予想される偏極度スペクトルを示す場合を両極端として、この2つの競合関係できまる一連の偏極度スペクトルが得られた。実験結果は、これらの傾向の他に、全体的に負の方向ヘシフトしている傾向を持つ結果が得られた。