| 内容要旨 | | 本研究は、恒星進化の末期の激しい質量放出によって形成されたエンベロープの構造を、一酸化炭素の同位体分子13CO輝線による初めての高空間分解能観測と、精密なモデル解析により明らかにしたものである。本研究によって、原始惑星状星雲の内部に存在するディスク構造が、これまでの予想よりずっと小さいことが分かった。 小・中質量星の進化の最終段階は、Asymptotic Giant Branch(AGB)と呼ばれる赤色巨星期である。この時期の星は、脈動と自らの輻射圧により、「質量放出」を起こす。質量放出は星自身の質量を大きく変化させ、AGBでの進化を決める最も重要な要素となる。質量放出によって形成されたエンベロープの構造を観測から決定し、質量放出の履歴を調べることは、AGB進化の解明に重要な意味を持つ。ミリ波干渉計の発達は、分子輝線によるエンベロープの高感度・高空間分解能観測を可能にした。 本研究においては、特に原始惑星状星雲と呼ばれる天体に注目した。原始惑星状星雲とはAGBを終え、中心星の表面温度が上昇して惑星状星雲へと移行する過程にある天体であり、AGB最末期の質量放出を調べるための貴重な資料である。これらの天体は可視光などで双極反射星雲として観測され、エンベロープ中にディスク状の軸対称構造が存在すると考えられる。本研究の目的は、この軸対称構造の大きさ、形状などを分子輝線観測から明らかにし、AGB末期の質量放出を理解することにある。 本研究の特徴のひとつは、一酸化炭素の同位体である13COのJ=1-0回転遷移輝線のミリ波干渉計による高空間分解能観測を行ったことである。13COはエンベロープ中にほぼ一様に分布し、また12COに比べて光学的に薄くなるため、密度分布を探るのに適当な分子の一つである。しかし惑度などの問題から、本研究以前にこの分子によって星周縁や原始惑星状星雲の高分解能観測が行われた例はなかった。 研究対象として、まず非常に若い惑星状星雲CRL618を取り上げた(第2章;Yamamura et al.1994)。ここでは、得られた13COの観測データをShibata et al.(1993)による12COの観測データと合わせて解析し、分子輝線の輻射輸達の計算によって、速度マップの一点ごとに対応するエンベロープ中の密度及び温度の分布を求めた。その結果、この天体のエンベロープ中のディスク構造は観測の分解能より小さいことがわかった。この結果は、それまでの予想を覆すものである。 CRL618の研究で得られた結論を検証・補強するために、さらに別の原始惑星状星雲CRL 2688について観測と解析を行なった(第3章;Yamamura et al.1995)。観測は、国立天文台野辺山宇宙電波観測所の5素子ミリ波干渉計によって行われた。CRL2688の分子エンベロープは空間的に広がっており、その全貌を明らかにするために、45m電波望遠鏡でも観測を行い、両者の結果を合成するという、これまで余り行なわれていない手法を試みた(第4章)。観測の結果の一部を図1に示す。結果は次のように要約される。 1.CRL2688のエンベロープはつぎの3つの成分に分けられる。すなわち、強く輝く「コア」、コアを取り囲む広がった成分、およびコアの内側にある高速で運動する成分である。 2.コアの形状はCRL618の場合と同様ほぼ丸く、ディスク的な構造は見られない。 3.広がった成分中に南側に長く伸びた構造がある。 4.高速のガスは双極的に吹き出しているように見える。しかし、その方向は双極星雲の軸と一致しない。 5.干渉計のみでは、本来の輻射の1/3しか捕らえられておらず、45m鏡のデータとの合成が広がった天体について有効な方法であることが示された。しかし一方で、有意義な合成結果を得るためには45mの観測データの質が極めて重要であることも確認された。  図1:(左)干渉計のみ、(右)45mのデータとの合成によるCRL2688の13CO輝線の積分強度マップ。コントア間隔は0.153Jy beam-1(左)、0.450Jy beam-1(左)でそれぞれノイズレベルの3 図1:(左)干渉計のみ、(右)45mのデータとの合成によるCRL2688の13CO輝線の積分強度マップ。コントア間隔は0.153Jy beam-1(左)、0.450Jy beam-1(左)でそれぞれノイズレベルの3 に相当する。右下の楕円は観測のビームサイズ。点線は双極星雲の軸の向き。 に相当する。右下の楕円は観測のビームサイズ。点線は双極星雲の軸の向き。 CRL618の場合と同様、この天体についても観測で得られた速度マップからエンベロープの密度構造を決定した。今回は12COのデータが得られなかったので、決定できるパラメータは密度あるいは温度のどちらかになる。本研究の主目的は密度構造の解明にあるため、温度はCRL618の結果から得られた温度分布を中心星からの半径を変数とする指数関数で近似したものを用いた。輻射輸達の計算は独自に開発したプログラムにより、非局所熱平衡のもとで行なわれ、観測結果を再現するようなガス密度の3次元分布を求めたところ、次のことが分かった。 1.密度分布は基本的に球対称で、ディスク構造は見られない(図2)。 2.各半径ごとの平均密度を調べると、現在から約2000年前に質量放出率が著しく上昇し、約3×10-4 yr-1に達した。 yr-1に達した。 3.コア成分の内径は1×1016cm程度であり、このことはこの星が約200年前に質量放出を停止したことを意味する。 これまで、CRL2688のディスク構造についてはさまざまな議論があった。例えば、Bieging & N-Q-Rieu(1988)は、HCN分子のJ=1-0輝線による干渉計観測から、回転するディスクの存在を主張している。双極反射星雲が見られることから、ディスクの存在自体は否定できないが、今回の研究によってその大きさは観測の分解能(約4"、6×1016cm)より小さく、中心部のみに存在することが明らかになった。HCNによる観測は、例えば中心星の光による化学反応の影響を受けているものと考えられる。また、今回の結果を元にコア部分の速度構造を調べたところ、回転運動を支持する大きな速度の変化はなかった。 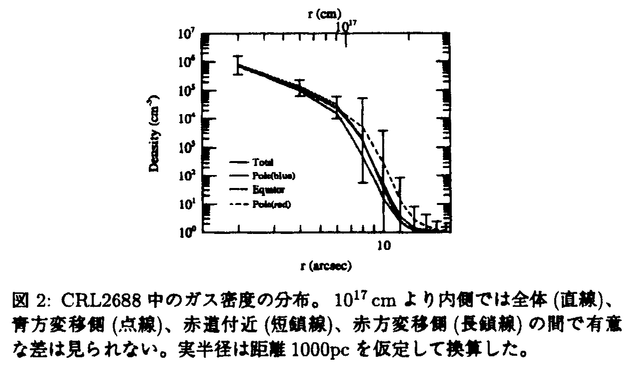 図2:CRL2688中のガス密度の分布。1017cmより内側では全体(直線)、青方変移側(点線)、赤道付近(短鎖線)、赤方変移側(長鎖線)の間で有意な差は見られない。実半径は距離1000pcを仮定して換算した。 図2:CRL2688中のガス密度の分布。1017cmより内側では全体(直線)、青方変移側(点線)、赤道付近(短鎖線)、赤方変移側(長鎖線)の間で有意な差は見られない。実半径は距離1000pcを仮定して換算した。 高速度成分については、精度のよい計算をするための十分な情報がないため、おおよその値の見積もりにとどめた。赤方変移側と青方変移側の位置のずれやその広がりなどから、輻射している位置に制限が付けられる。それによると、高速度成分はコアの内部から輻射していると考えられる。このことは、近赤外でのH2分子輝線の観測の結果とも一致する。すなわち、コアを形成する厚いエンベロープに内側から細いビーム状の超高速のガスが衝突し、加速・加熱しているといった状態が考えられる。双極星雲の軸と一致しないことに関しては歳差運動の可能性が考えられる。 以上の研究より、原始惑星状星雲の内部にあるとされるディスク構造はこれまで考えられていたよりずっと小さい場合があることが明らかになった。このことは、ディスク構造がAGBの最後の高々数百年の間に急激に発達するものであることを意味する。これまで、いくつかのディスク形成のメカニズムが提唱されているが、いずれも今回の結果をうまく説明できるとはいえず、今後理論の再検討が必要とされる。 ReferencesBieging,J.H.,& Nguyen-Quang-Rieu1988,ApJ,324,516Shibata,K.M.,Deguchi,S.,Hirano,N.,Kameya,O.,& Tamura,S.1993,ApJ,415,708Yamamura,I.,Shibata,K.M.,Kasuga,T.,& Deguchi,S.1994,ApJ,427,406Yamamura,I.,Onaka,T.,Kamijo,F.,Deguchi,S.,& Ukita,N.1995,ApJ(letter),in press |
| 審査要旨 | | 小・中質量星の進化の最終段階は、Asymptotic Giant Branch(AGB)と呼ばれる赤色巨星期である。この時期の星の進化は大きな質量放出により特徴づけられている。その結果形成されたエンベロープの構造を観測から決定し、質量放出の履歴を調べることは、AGB進化の解明に重要な意味を持つ。ミリ波干渉計の発達は、分子輝線によるエンベロープの高感度・高空間分解能観測を可能にした。13COはエンベロープ中にほぼ一様に分布し、またCOに比べて光学的に薄くなるため、密度分布を探るのに適当な分子の一つである。しかし感度などの問題から、本研究以前にこの分子によって星周縁や原始惑星状星雲の高分解能観測が行われた例はなかった。 本論文は、代表的な原始惑星状星雲であるCRL618及びCRL2688に対して、13CO J=1-0回転遷移輝線によるミリ波干渉計観測を行い、さらに45m電波望遠鏡の観測結果をあわせて非局所平衡モデル解析に基づいて、星周エンベロープの3次元構造を明らかにしたものである。とりわけ、本論文に於いてはこれらの天体の星周縁中に存在することが予想されている軸対称構造、すなわちディスク構造の解明に重点が置かれている。 論文第1章においては、AGB星から惑星状星雲に至る進化と質量放出の関係、及び星周縁の構造について、これまでに行われた観測的、理論的研究が簡潔に述べられ、それらの問題点が指摘されている。特に、それらの解決のためには高空間分解能観測が決定的重要性を持つことが強調されている。 第2章においては、非常に若い惑星状星雲CRL618を取り上げ、得られた13COの観測データを以前に行われたShibata et al.(1993)による12COの観測データと合わせて解析し、分子輝線の輻射輸達の計算によって、速度マップの一点ごとに対応するエンベロープ中の密度及び温度の分布を求めた。この研究の結果、CRL618のエンベロープ中に存在するディスク構造は観測の分解能より小さいことがわかった。この結果は、それまでの予想を覆すものである。なお、第2章の結果は、既にYamamura et al.(1994)としてAstrophysical Journal誌に発表されている。 第3章は本論分の中心となるものであり、CRL618よりさらに前の進化段階にある原始惑星状星雲CRL2688について議論が行われている。この研究においては、空間的に大きく広がった分子エンベロープの全貌を明らかにするために、ミリ波干渉計の他に45m電波望遠鏡によっても観測が行われ、さらに両者の観測データをデータ整約の段階で合成するという、これまで余り行なわれていない手法を試みている。観測の結果、この天体の星周縁が3つの成分、すなわち、明るく輝く「コア」、コアを取り囲む広がった成分、およびコアの内側にある高速で運動する成分から成り立っていることが分かった。コアの形状はCRL618の場合と同様球対称で、ディスク的な構造は見られなかった。また、コア内部の速度構造の詳しい解析が行われ、速度構造の点からもこの星周縁が球対称であることが分かった。従って中心部に想定されるディスク構造は、今回の干渉計観測の分解能(約4")より小さくなくてはいけないことが結論される。一方、広がった成分はコアの南側に卓越していることが分かった。これは今回の観測で初めて明らかになったことである。また、高速度成分の解析の結果、その輻射はコアの内部から出ていることが明らかになった。 エンベロープ内の密度構造を決定するため、輻射輸達の詳しい計算が行われた。計算は、局所非平衡の条件下で行われ、観測の速度マップの結果を満足するような3次元密度構造が求められた。その結果、この天体の過去の質量放出率が約2000年前に増加し、この激しい質量放出によって中心星はAGBでの進化を終えたと考えられる。また、エンベロープの内径もモデル計算によって決定され、質量放出が約200年前に終了したことが分かった。 第4章では、CRL2688の研究において行われた、干渉計と45mの観測データの合成過程と、合成された結果の評価が述べられている。両者のデータの比較から、干渉計のみでは、本来の輻射の1/3しか捕らえられておらず、45m鏡のデータとの合成が広がった天体について有効な方法であることが示された。合成の結果は、広がった輻射成分の構造を明確に示している。 以上の研究の結論として、原始惑星状星雲の内部にあるとされるディスク構造はこれまで考えられていたよりずっと小さいことが明らかになった。このことは、ディスク構造がAGBの最後の高々数百年の間に急激に発達するものであることを意味し、これまでなされてきたディスク構造の形成や惑星状星雲への進化の議論は、本研究の結果に基づきもう一度見直す必要があることが明らかになった。 以上本論文は、代表的原始惑星状星雲の分子エンベロープについて、干渉計観測に基づき精密な分析を行い、従来の定説を覆す重要な知見を得たと認められる。なお、これらの研究は論文提出者が共著者の協力を得て進めたものであるが、大部分が自らの着想・実行に基づくものであり、学位論文申請に供することは共著者全員の同意が得られている。よって、本論文提出者山村一誠は、博士(理学)の学位を受けるに十分な資格があると認定する。 |