有機金属錯体を触媒とする均一系有機合成において二種以上の金属を混合して用いる混合金属錯体触媒は、単一の金属でなし得ない反応を実現したり、著しい高活性を示すといった相乗効果を持つ可能性があり、注目を集めている。実際にそのような相乗効果を示す例がいくつか報告されているが、系中に多くの金属種を含むために、詳細な反応機構を解明した例は限られている。そこで本研究ではパラジウムを含む混合金属錯体触媒の開発、カルボニル化反応への応用、並びにその詳細な反応機構の解明を行った。 1)Pd錯体を触媒とし、CO、H2加圧下でヨードアレーンがホルミル化され、アルデヒドが生成することはよく知られているが、温和な条件下ではPd単独の触媒活性はあまり高くない。そこでPhIのホルミル化において、単独ではほとんど触媒活性を持たないCr、Mn、Fe、Ru、Co等のカルボニル錯体をPd錯体に添加して、活性の変化を検討した(式1、表1)。  Table 1.Formylation of PhI Catalyzed by Pd and/or Ru Complexesa Table 1.Formylation of PhI Catalyzed by Pd and/or Ru Complexesa 70℃の温和な条件で反応を行ったところ、Pd単独の触媒による収率は17%に過ぎず、またRu以外のカルボニル錯体を添加しても、活性に変化は見られなかったのに対し、Ruカルボニルを原子比1:2で添加した場合、収率が約4倍に向上することが見いだされた。各種ヨードアレーン、ヨードアルケンのホルミル化でも同様にPd-Ruによる相乗効果が見られ、特にヨードアルケンのホルミル化では基質の立体化学の保持されたアルデヒドが優先的に生成することを見いだした。  Pdのみを触媒とする反応ではPdアロイル中間体が水素分子により水素化を受け、アルデヒドを生ずることが知られており、またこの水素化が律速であると考えられろ(スキーム1、左)。また本反応条件のようなCO、H2加圧、塩基存在下ではRu3(CO)12は[HRu3(CO)11]のようなヒドリド錯体を生ずることが知られている。そこで4-TolCOPdI(PPh3)2と式2に示す金属ヒドリドアニオン錯体の反応を検討したところ、いずれも温和な条件(0-40℃)で4-TolCHOを収率よく与えることが見いだされた。これに対し、40℃という温度ではH2による水素化はほとんど進行しなかった。この結果アロイルPd中間体の水素化が金属ヒドリド錯体との二分子間還元的脱離により、速やかに進行することが明らかとなった。  以上の結果から、本反応の機構として、スキーム1に示す機構を提案した。Ruを添加した場合、律速段階であるアロイルPd中間体の水素化がRuヒドリド錯体との二分子間還元的脱離により、より効率的に進行するために全体の反応速度が向上するものと考えられる。  Scheme 1. Scheme 1. 2)遷移金属錯体に対しH2とHSiR3はよく似た挙動を示すことが知られている。そこで式1の水素の代わりにHSiEt3を用いたArIのカルボニル化を検討した。その結果、表2に示すようにPdおよびCoの錯体が単独ではほとんど活性を示さないのに対し、Pd-Coの混合系とすることでカルボニル化に活性を示すことを見いだした。式1のホルミル化ではHIを中和するために塩基が必須であったのに対し、この反応は塩基なしで進行してEt3SiIを副生した。また、NEt3非存在下ではベンジルシリルエーテル(1)が、NEt3存在下では1,2-ジアリル-1,2-ジシロキシエタン(2)が主生成物になるという興味深い結果が得られた(式3、4)。他のArIのカルボニル化についても同様の結果が得られた。 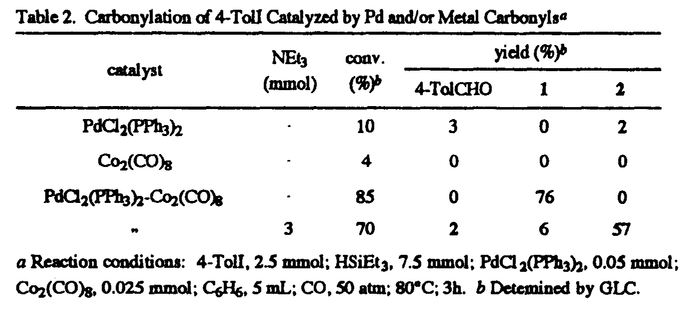 Table 2.Carbonylation of 4-TolI Catalyzed by Pd and/or Metal Carbonylsa Table 2.Carbonylation of 4-TolI Catalyzed by Pd and/or Metal Carbonylsa 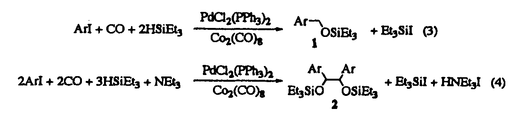 次にこのカルボニル化の反応機構を検討した。1、2の生成に際しアルデヒドを中間体とする機構が考えられることから、CO50atm下での4-TolCHOのヒドロシリル化を様々な条件下で行った(式5)。  その結果、PdまたはCo錯体を単独で用いた場合には1または2が収率よく得られることはなかったが、PdとCoを混合して用い、触媒量の4-TolIを加え、NEt3を添加しない場合にはヒドロシリル化が進行して、ほぼ選択的に1が得られることが明らかとなり、NEt3非存在下ではアルデヒドを中間体とする機構が示唆された。しかし、NEt3を添加した場合には活性は失われ、2は得られなかったことから、NEt3を添加したカルボニル化ではアルデヒドを経由せずに2を生成するものと考えられる。 CO2(CO)8とHSiEt3の反応ではまずH(SiEt33)Co(CO)3のようなヒドリドコバルト種が生成することが報告されている。式3のカルボニル化では、このようなヒドリドコバルト種がアロイルPd錯体の水素化を行い、式2で示したようなアロイルPd錯体との二分子間還元的脱離によりアルデヒドを与え、このアルデヒドがPd-Co系によりさらなるヒドロシリル化を受けて1を与えるという機構を推定した(スキーム2)。この機構おいてホルミル化、ヒドロシリル化両ステップがPd-Coの相乗効果により進行することは興味深い。  Scheme 2. Scheme 2. 一方、NEt3存在下においてはH(SiEt3)Co(CO)3のようなヒドリドコバルト種は速やかにプロトンの引き抜きを受け、[Co(CO)4]-アニオンを生成すると考えられる。従って式4のカルボニル化では[Co(CO)4]-が活性種になり得ると考え、ArIと[Co(CO)4]-の反応を検討し、3)に示すPdを触媒とするArIと[Co(CO)4]-からのアロイルCo錯体の生成を見いだした。このことは式4のカルボニル化反応系中でアロイルCo錯体が中間体として関与していることを示すものである。 アシル錯体とヒドロシランの反応についてはいくつかの報告例があるが、CO加圧下での反応例はなく、また2のようなカップリング型の生成物を与える例も報告されていない。そこでCO50atm下でのArCOCo(CO)3(PPh3)(Ar=Ph,4-Tol,4-MeOC6H4,4-FC6H4)とHSiEt3の反応を検討し、2が36-76%の収率で主生成物として得られることを見いだした。この反応ではアロイルCo錯体のヒドロシリル化によってシロキシベンジルCo錯体を生成し、シロキシベンジル基のラジカルカップリングにより2をあたえるものと考えられる。 以上の知見より、NEt3存在下でのカルボニル化反応機構をスキーム3に示すように提案した。ArIはまずPdに酸化的付加することで活性化されたのち、Coアニオンとの反応によりCo上にトランスファーされ、アロイルCo錯体を生成する。さらにCo上でヒドロシリル化を受け、シロキシベンジルCo錯体を経てラジカルカップリングにより2を生成し、Co(0)価種を再生するという機構である。本機構は有機基が第一の金属で活性化されたのち、第二の金属へ移行し、そのうえでさらなる変換を受け、最終生成物を与えるという従来例のない機構であり、新規な混合金属錯体触媒の開発という面からも興味深いといえる。 3)スキーム3の反応機構において、重要な役割を果たしていると考えられるPdからCoへの有機基の移行によるアロイルCo錯体の生成について検討した。ArIはハロアルカン、酸ハライドと異なり、[Co(CO)4]による求核攻撃を受けないが、Pd(0)錯体を触媒量添加することで、アロイルCo錯体が収率81-32%で生成することが明らかとなった(式6)。   Scheme 3. Scheme 3. 本反応では、ArIがPdに酸化的付加した後、[Co(CO)4との反応によりPd-Co複核錯体を生成し、Pdからの還元的脱離によりアロイルCo錯体を生ずるという機構が推定される。そこで中間体と考えられる複核錯体の単離を試みたが、触媒反応と同じPPh3を配位子とするアリールPd錯体とK[Co(CO)4]の反応では還元的脱離が速く進行するため複核錯体は単離されなかった。そこでPd錯体のかわりにPt錯体を用いたところ、錯体3の単離に成功した。一方PPh3のかわりに電子供与能の強いPMe3を配位子として用いることにより、Pd-Co錯体4、Pt-Co錯体5を単離した。  また合成した複核錯体の反応性を検討した結果、3bはC6D6中CO雰囲気下50℃で加熱することにより4-TolCOCo(CO)3(PPh3)を47%の収率で与えた。これにより式6の触媒反応中において、Pd-Co複核錯体の生成と、Pdからの還元的脱離を経てアロイルCo錯体を生成するという反応が進行していることが判明した。 |