本稿の課題は、植民地における雇用制度の生成過程を明らかにし、脱植民地化以降の現代社会への影響を展望することである。この分析過程を通じて、帝国主義の立場から描写してきた近代史像を、植民地の立場から再構成することを試みた。本稿では、近代移行過程で植民地を経験した朝鮮を具体的な分析対象とし、大きく変貌した1920・30年代を分析時期とした。さらに、同じ東アジアに位置し類似する社会伝統をもちながらも帝国主義化しつつ近代へ移行した日本との比較を通じて、植民地としての特質を浮き彫りしてみた。以下では、本稿の考察からどういうことが明らかになり、それがもつ歴史的含意は如何なるものであるか、について叙述する。 第1章。両地域における伝統的労働慣行である共同労働慣行の成立要件は、東アジアの社会伝統という側面から類似しており、その運用のあり方も似ていた。作業組織という面からみた場合も類似する面が多かったが、構成員に対する組織の拘束力は日本より朝鮮が強かったため、農村共同体が解体される過程において構成員に与えたインパクトが朝鮮の方が大きかったと推測される。他方、両地域とも共同労働慣行の基本的なモラルは相互扶助であったが、村において一人前の能力者として公認される唯一な機会である共同作業が行われるときには互いに競争的に働いていた。両地域における農村共同労働は身分制社会を前提にした慣行であって、構成員の関係は基本的には伝統的上下関係に基づいていた。しかし、農村共同体を維持し、農繁期に労働力を合理的に交換するためには構成員の間には協力関係も併存させなければならなかった。日本の工業化は、朝鮮に先行して進んでいたが、急速に導入された膨大な量の技術に基づいて進められた点においては両地域とも同様であった。すなわち、徒弟制度の伝統が弱く、技術の導入によって工業化が進められたため、多様な技術に適用できる職務区分ができないまま職場編成が行われた。経営者は、このような状況を踏まえて、労働者の不満を生み出さないように、労働者の意識の面において伝統社会から連続していたために受け入れられ易かったルールである「年功制」を適用しようとし、それが定着しつつあった。以上のような朝鮮における「雇用制度の固有の生成原理」は、東アジアの特質として日本と類似する面をもっている一方、植民地であったため雇用制度の生成過程には異なる形で影響を及ぼした。 第2章。朝鮮人労働者は、個人として社会的経済的な自立を自指しつつ農村共同体から離れて、自分がもっている伝統的労働観・慣習と支配民族である日本人のそれとぶつかり合いながら、新たな生活様式を築き上げつつあった。また、それは新しい世帯を形成する形で行われたと推測される。その際に、労働市場は、工場の規模、そして技能・学歴、並びに性や民族という「資格」によって分節する形で、契約期間、契約形態に規定されながら形成された。賃金構造は、性格差、民族格差が見られ、賃金体系は、日本の年齢別賃金カーブと比較して検討した結果、「年功制」的な体系がうかがえる。他方、1930年代前半朝鮮の工場における雇用構造を日本の同時代及び1900年前後と比較した結果、同時代とは異なる構造をもっていたが、1900年前後とは類似する構造をもっていた。また、朝鮮人労働者は、労働力過剰の状態で、植民地でみられる民族別に分節された労働市場という前提の上で労働市場に参入し、競争の相手が朝鮮人労働者たちに限定された。そのため、日本の工業化初期段階における日本人労働者よりも「過熱化された競争意識」を経験するようになった。 第3章。日本人工場に雇われた朝鮮人労働者は、最初には熟練をもたなかったため下級労働者として配置され、日本の本社工場から派遣された日本人労働者は上級労働者として配置され朝鮮人労働者の作業指揮や監督の役割を担うようになった。しかし、経営者は高賃金の日本人労働者を低賃金の朝鮮人労働者に代替させるために、社内養成制度を通じて自社工場に使えられるような熟練を身につけさせた。彼らの熟練は、勤続年数が長くなるほど自社工場に特化する傾向が強まった。そして、経営者はインセンティブ制度を朝鮮人労働者にも適用したが、古参労働者になるとその制度による特典が多くなり、彼らの定着の傾向が強くなった。労働組織は、技術の急速な導入に基づいて編成されたため職務区分が詳細にわけられず、かつ日本人労働者が朝鮮人労働者に作業指揮をする形で組織された。こうした状況で、経営者は、日本人労働者と朝鮮人労働者が不満をもたない労務管理のルールとして考え、適用したのが「年功制」と「インセンティブ制度」であった。すなわち、民族別格差を前提にし、職務区分が明確でなく、それほど熟練の差がない朝鮮人労働者に対し彼らがもっている伝統的価値観に基づいた「年功制」を基準に職場の秩序を維持した上で、「インセンティブ制度」を適用して年齢や勤続年数が同じである労働者たちを競争をさせるようにした。すなわち、朝鮮人労働者は、民族別労働市場の分節を前提に入職し、工場内においても同じ年齢や勤続年数の朝鮮人労働者に競争が制限された結果、日本の工業化初期段階における日本人労働者よりも「過熱化された競争」を経験するようになったのである。一方、朝鮮人労働者は、古参労働者にはなれたが中間管理監督労働者までには昇進できなかった。その理由は、経営者が朝鮮人労働者に対し責任能力がないと判断したことと、彼らを昇進させると日本人労働者を軸にして運用されていた労務管理体制自体が崩壊するためであった。こうした根本的な背景には、経営者が朝鮮人労働者に対し民族差別意識に基づいて「集団的人格無視」をしたところにあって、これを前提に経営者と朝鮮人労働者の間のルールは形成されていた。これは、本社工場では懇談会や産業報国会が形成される一方、平壌工場では同様の協議機構が形成されなかったことから裏付けられる。他方、朝鮮人労働者は、昇給・昇級はできても中間管理労働者に昇進できないという事態が、経営者の「集団的人格無視」による「民族」の「資格」化によってもたらされていることを自覚するようになった。それにもかかわらず、経営者は、工場稼働に不可欠な下級労働者として彼らを雇わざるを得なかったため、以上のような性格をもつ雇用制度は両者の緊張を益々高めるようになったのである。 第4章。雇用制度が生成されて行く中で、政策介入がどのように行われ、その影響は如何なるものであったのか。これについて、個人的なレベルにおける労使関係に介入する政策手段であった「工場法」の論議を中心に考察した結果は、以下のようなものであった。工場法施行の意義は、理念的には企業主の恣意的な判断により規定される労使関係を権利と義務という関係に変え、実際的には企業間の競争が過度に激しくなることを防げ、労働力保全を実現し、安定的な資本制生産を維持するところにあった。朝鮮の場合に、同法が施行されなかったことによって、経営者と労働者の間には明文化されたルールに基づいた関係が形成されず、経営者の判断に基づいた恣意的な関係が続けられた。ただし、戦時体制に入った以降には「帝国臣民」として「工場法」より理念が後退した形で「工場就業時間制限令」の適用を受けるようなった。また、労働力の過剩の状態で、労働時間を制限する工場法が施行されなかったため、朝鮮人労働者間の競争を過熱化させる結果をもたらした。朝鮮人労働者が日本人労働者の半分以下の賃金であったため、自らの労働時間を延長することによってより多くの収入を確保しようとした。このような状況で労働時間を制限する工場法が施行されなかったことは、労働者間の競争、とりわけ民族別分節された労働市場を前提にしていた朝鮮人労働者の間の「無制限の競争」を「放任」する結果になったのである。 補論。朝鮮人労働者は、何故日本人経営者によって「集団的人格無視」されたのか、すなわち、両者の間には何故人格承認を前提にした雇用制度が形成されなかったのか。日本人経営者の思想的背景という側面から、彼の考え方に影響を及ぼしていた知識人や官僚の朝鮮人労働者観、並びに彼ら自身の朝鮮人労働者観、そしてこれが形成された歴史的背景、に関する考察を通じて検討した。総督府は、統治のイデオロギーとして同化の論理を、被支配民族である朝鮮人に、さらに自分が認識するかしないかにかかわらず最末端の統治の担い手になる日本人に、植民地期全体にわたって引き続いて普及させようとした。その論理が生まれるようになった根底的な背景は、朝鮮人について、思想が伝統的に中国に従属しており主体的な思想を今後とも持つ可能性がないと認識するところにあった。総督府並びに日本の知識人は、彼らを文明人へと改善させるために教育訓練を行う際に一般日本人の役割の重大さを強調しつつ、朝鮮人はそれを受け入れるような従順な性質を持っているものと判断した。こうした認識は、3・1運動によってインパクトを受けたものの、根本的には変わらず、朝鮮人労働者に対する認識にも引き継がれるようになった。朝鮮人労働者を認識するときに、知識人を始めとして日本人の眼には多様な朝鮮人労働者像が描かれた。しかし、勤勉・勤続・責任感という伝統的な日本人の労働観に基づいて描かれた朝鮮人労働者像は怠惰・無責任・付和雷同であり、時間観念・衛生思想という近代移行期に形成された労働観に基づいて認識した際の日本人の眼には朝鮮人労働者が時間観念がなく衛生思想を欠如していると映ったことは共通していた。こうした認識は、日本人経営者が朝鮮人労働者を認識する際に影響を及ぼした。他方、総督府の官僚は、かかる認識の上で民族別地位を考えながら、民族別作業配置を構想していた。こうした官僚の考え方は、労務管理を円滑化させかつ朝鮮人労働者を確実に掌握するために、日本人労働者を管理者として配置しようとした日本人経営者の労務管理方針に影響を与えていた。 以上のように、1920・30年代の植民地朝鮮において、雇用制度が新たな社会の運川原理として生成されつつあった。これがもつ歴史的含意はどういうものであったのかについて、現代韓国の雇用制度に関する筆者の問題意識を念頭におきながら述べる。 朝鮮における雇用制度の生成過程は、異民族の支配によって旧支配構造が解体され、各階層間の移動が激しく展開するなかで行われた。さらに、産米増殖計画や水利組合事業を通じた農業の「合理化」によって過剰人口が急速に発生し、かつ短期集中的に工業化が展開したため、各社会集団の間の移動が激しく行われた。こうした状況のもとで、朝鮮人労働者は、彼らの間に競争が限定される民族別に分節された労働市場を前提に日本人工場に雇われるようになるが、そのなかでも昇給・昇級をめぐって彼らの競争が続けられた。要するに、1920・30年代の工業化の過程で朝鮮人労働者が経験する競争意識は、日本の工業化初期段階における日本人労働者の経験よりも「過熱化」したのである。それは、労働時間を制限する「工場法」が施行されなかったために増幅させられた。他方、日本人経営者と朝鮮人労働者の関係は、日本人経営者の朝鮮人労働者に対する「集団的人格無視」を前提に形成されたため、日本人経営者の恣意的な判断による労務管理が続けられた。さらに、この関係は、「就業規則」の制定を義務化する「工場法」が施行されなかったため、明文化されたルールに基づかないものでもあった。ところで、当時の工業化は、職務区分が詳細にわけられなかった状況の上で技術の導入する段階で進められたため、朝鮮人労働者の伝統的な価値観に基づいた「年功制」が雇用制度の一つのルールとして定着するようになった。かかる伝統的価値観に基づいたルールは、当時、人々の社会集団の間の移動が激しく、各々の集団における具体的なルールが定着しにくい状況では、その作用がより強く働く可能性が高いと考えられる。 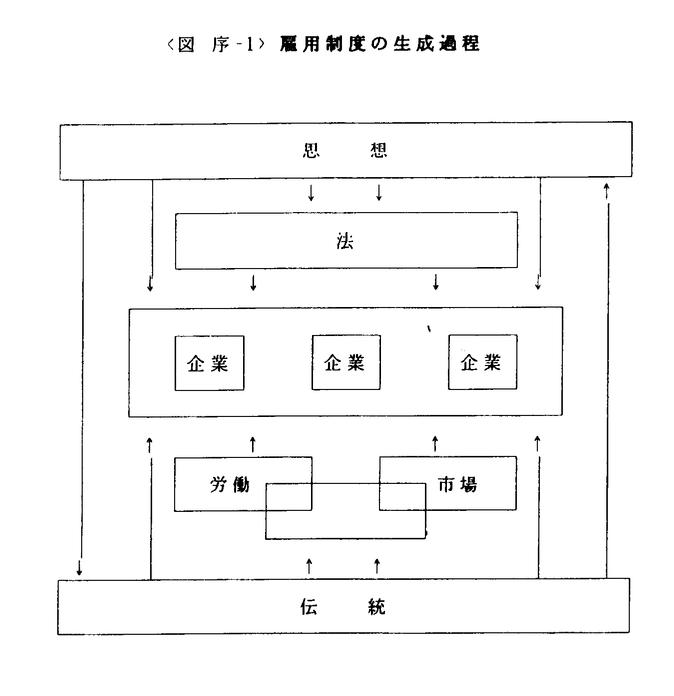 〈図 序-1〉雇用制度の生成過程 〈図 序-1〉雇用制度の生成過程 |