表面物理学は、始めに単一の固体の表面(一元系)が独特の様々な性質を示すことから興味が持たれ、次に固体表面と外部の物質の示す様々な相互作用の影響を調べる二元系の研究に新たな興味を見出した。更に興味を推し進めるならば、一層変化に富む系として三元系の研究が重要な分野となるであろう。表面物理学における三元系の面白さは、今まで二元系が示していた表面物質間の相互作用が新たな物質の介在によって変更を受けることである。この論文では、電子構造が実験的に調べられている、単原子層グラファイトとアルカリ原子のNi(111)表面上共吸着系を計算物理の手法によって調べ、特にグラファイト層の バンドに注目して電子状態がどのような原理に従って決定されるかを議論の中心に据えて解明していくこととする。 バンドに注目して電子状態がどのような原理に従って決定されるかを議論の中心に据えて解明していくこととする。 遷移金属や遷移金属炭化物の表面に成長した単原子層グラファイトは、その研究の初期の頃には孤立した単原子層グラファイトと同じ電子状態を持つものと思われていた。[1]しかし、角度分解光電子分光法(ARUPS)やトンネル走査顕微鏡(STM)の実験によって、この考え方は重大な修正を受けた。即ち、ブリルアン域K点の付近では バンドは下地の軌道と強い混成を起こし、著しく変形することが観測された。[2][3]理論の方からもこの軌道混成が バンドは下地の軌道と強い混成を起こし、著しく変形することが観測された。[2][3]理論の方からもこの軌道混成が バンドを変形することが裏付けられている。[4][5] バンドを変形することが裏付けられている。[4][5] 最近になって、単原子層グラファイトとNi(111)表面の吸着層間にアルカリ原子層を挟んだ共吸着系のバンド構造が長島らのARUPS実験によって調べられた。その結果、一般的な傾向としてグラファイト層の バンドはアルカリ原子の半径が大きくなるに従って バンドはアルカリ原子の半径が大きくなるに従って バンドのK点におけるギャップが縮小してよりバルクのグラファイトに近づくことが観察された。長島らは、この傾向をグラファイト層と下地のニッケル原子との軌道混成が弱くなるためであると説明したが、アルカリ原子がグラファイト層に及ぼす影響については疑問が少なくなかった。どの因子がグラファイト層の電子状態を決定的に支配するかを正確に知るために、筆者は計算物理の手法を用いた議論を上記の三元系に適用する価値が十分にあると考えた。 バンドのK点におけるギャップが縮小してよりバルクのグラファイトに近づくことが観察された。長島らは、この傾向をグラファイト層と下地のニッケル原子との軌道混成が弱くなるためであると説明したが、アルカリ原子がグラファイト層に及ぼす影響については疑問が少なくなかった。どの因子がグラファイト層の電子状態を決定的に支配するかを正確に知るために、筆者は計算物理の手法を用いた議論を上記の三元系に適用する価値が十分にあると考えた。 全ての系の計算は密度汎関数法の一つであるDV-X 法を用いて行った。単原子層グラファイトのNi(111)表面上吸着層と、様々な吸着密度に対応する単原子層グラファイト/アルカリ原子層/Ni(111)表面のモデルを図1と図2に描いておく。バンド構造の中から 法を用いて行った。単原子層グラファイトのNi(111)表面上吸着層と、様々な吸着密度に対応する単原子層グラファイト/アルカリ原子層/Ni(111)表面のモデルを図1と図2に描いておく。バンド構造の中から バンドなどの特定のバンドを容易に選び出せるように、LCAO法を用いることとし、各原子軌道は周辺の原子からの影響を平均化した原子ポテンシャルを解くことにより決定した。 バンドなどの特定のバンドを容易に選び出せるように、LCAO法を用いることとし、各原子軌道は周辺の原子からの影響を平均化した原子ポテンシャルを解くことにより決定した。 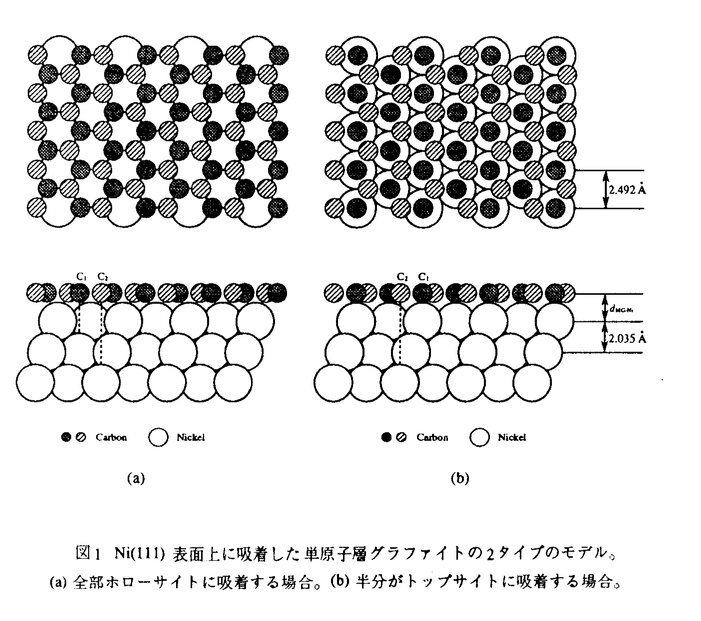 図1 Ni(111)表面上に吸着した単原子層グラファイトの2タイプのモデル。(a)全部ホローサイトに吸着する場合。(b)半分がトップサイトに吸着する場合。 図1 Ni(111)表面上に吸着した単原子層グラファイトの2タイプのモデル。(a)全部ホローサイトに吸着する場合。(b)半分がトップサイトに吸着する場合。 図2 Ni(111)表面上に共吸着した単原子層グラファイトとアルカリ原子層の様々な周期構造。(a) 図2 Ni(111)表面上に共吸着した単原子層グラファイトとアルカリ原子層の様々な周期構造。(a) ,(b)2×2,(c)3/2×3/2. ,(b)2×2,(c)3/2×3/2. まず、二元系である単原子層グラファイトのNi(111)表面上吸着層の電子状態が吸着サイトと層間距離を様々に変えて調べられた。最も吸着サイトが近い場合、元々二本だった バンドが四本に分裂して増えたように見える。これは下地の3d電子との強い軌道混成によって一つのレベルが結合性軌道と反結合性軌道の二つに分かれるためである。典型的な単原子層グラファイト/Ni(111)系のバンド構造を図3に掲げておく。グラファイト層と下地との距離が広がるにつれ軌道混成は弱まっていく傾向を見せる。層間距離の変化に応じた バンドが四本に分裂して増えたように見える。これは下地の3d電子との強い軌道混成によって一つのレベルが結合性軌道と反結合性軌道の二つに分かれるためである。典型的な単原子層グラファイト/Ni(111)系のバンド構造を図3に掲げておく。グラファイト層と下地との距離が広がるにつれ軌道混成は弱まっていく傾向を見せる。層間距離の変化に応じた バンドのこのような振る舞いは、原子や分子の化学吸着に非常に近い傾向を持つと言えよう。一方、グラファイト層の電子状態は吸着サイトの違いによっても大きく左右される。炭素原子の半分が下地原子のトップサイトにあって残りの半分がホローサイトにあるというモデルを採用した場合、K点での バンドのこのような振る舞いは、原子や分子の化学吸着に非常に近い傾向を持つと言えよう。一方、グラファイト層の電子状態は吸着サイトの違いによっても大きく左右される。炭素原子の半分が下地原子のトップサイトにあって残りの半分がホローサイトにあるというモデルを採用した場合、K点での バンドは、図4に示すごとくホローサイト原子の軌道だけから成るバンドとトップサイト原子の軌道だけから成るバンドにエネルギー準位が別れ、それらが交互に並ぶ構造を見せる。全ての炭素原子がホローサイトにあるとした場合には、この構造はなく、二重に縮退した バンドは、図4に示すごとくホローサイト原子の軌道だけから成るバンドとトップサイト原子の軌道だけから成るバンドにエネルギー準位が別れ、それらが交互に並ぶ構造を見せる。全ての炭素原子がホローサイトにあるとした場合には、この構造はなく、二重に縮退した バンドの組が二組見える。どちらのモデルが実際の系に近いかは明確に断定できない。 バンドの組が二組見える。どちらのモデルが実際の系に近いかは明確に断定できない。  図3 Ni(111)表面上に吸着した単原子層グラファイトのバンド構造。図1(b)のモデルを使い、dMG-Ni=2.15Åとして計算した。 図3 Ni(111)表面上に吸着した単原子層グラファイトのバンド構造。図1(b)のモデルを使い、dMG-Ni=2.15Åとして計算した。 図4 図3の 図4 図3の バンドの微細構造。 バンドの微細構造。 グラファイト層とニッケル表面との間にアルカリ原子を挟んだ三元系では、グラファイト層とニッケル表面とが引き離され、軌道混成相互作用は弱くなる。図5に示す Kの挟まれた系では、K点において Kの挟まれた系では、K点において バンドに依然としてギャップが残ってはいるものの、その幅は0.8eV程度しかない。意外にも、下地のニッケルを除いてもギャップは残る。このことは、グラファイト層の相互作用の相手がもはやニッケルでなくカリウム原子層の方に入れ代わったことを示している。カリウムのコアの3p軌道は バンドに依然としてギャップが残ってはいるものの、その幅は0.8eV程度しかない。意外にも、下地のニッケルを除いてもギャップは残る。このことは、グラファイト層の相互作用の相手がもはやニッケルでなくカリウム原子層の方に入れ代わったことを示している。カリウムのコアの3p軌道は バンドと軌道混成を起こすほど近付いており、この原子の作る摂動ポテンシャルがK点において バンドと軌道混成を起こすほど近付いており、この原子の作る摂動ポテンシャルがK点において バンドを変形させるものと考えられる。 バンドを変形させるものと考えられる。  図5 Ni(111)表面上に共吸着した単原子層グラファイトと 図5 Ni(111)表面上に共吸着した単原子層グラファイトと カリウム層のバンド構造。 カリウム層のバンド構造。 グラファイト層とニッケル表面との層間に挟む原子をナトリウムに変更した場合、グラファイト層とニッケル表面の距離は軌道混成を起こし得るほどに近くなる。図6に示したバンド構造では、K点の付近で バンドが幅を持っている。これは単原子層グラファイトとニッケル表面の直接の軌道混成の結果である。というのも、ニッケルを取り除いて単原子層グラファイトとナトリウム原子層の二元系にした場合には バンドが幅を持っている。これは単原子層グラファイトとニッケル表面の直接の軌道混成の結果である。というのも、ニッケルを取り除いて単原子層グラファイトとナトリウム原子層の二元系にした場合には バンドは全く幅を持たないからである。更にこの二元系では、カリウムを含む同様の二元系と異なりK点での バンドは全く幅を持たないからである。更にこの二元系では、カリウムを含む同様の二元系と異なりK点での バンドにギャップがない。これはナトリウムの作る摂動ポテンシャルがカリウムのものと比べて極めて小さいからだと考えられる。実際、ナトリウムのコア2pレベルは バンドにギャップがない。これはナトリウムの作る摂動ポテンシャルがカリウムのものと比べて極めて小さいからだと考えられる。実際、ナトリウムのコア2pレベルは バンドのレベルよりもはるかに低く、軌道がグラファイト層に影響を及ぼすほど遠くまで広がっていないことを示唆する。以上の点から、ナトリウムの三元系の場合にはグラファイト層とニッケル下地との軌道混成相互作用がナトリウムを挟むことで弱められた系であると結論される。実験的に観測されたナトリウム三元系は、実は バンドのレベルよりもはるかに低く、軌道がグラファイト層に影響を及ぼすほど遠くまで広がっていないことを示唆する。以上の点から、ナトリウムの三元系の場合にはグラファイト層とニッケル下地との軌道混成相互作用がナトリウムを挟むことで弱められた系であると結論される。実験的に観測されたナトリウム三元系は、実は ではなく3/2×3/2という周期を持っている[3]が、単原子層グラファイトとナトリウムの相互作用の弱さを考慮すれば、周期構造の違いが ではなく3/2×3/2という周期を持っている[3]が、単原子層グラファイトとナトリウムの相互作用の弱さを考慮すれば、周期構造の違いが バンドの劇的な変形を引き起こすとは思えない。 バンドの劇的な変形を引き起こすとは思えない。  図6 Ni(111)表面上に共吸着した単原子層グラファイトと 図6 Ni(111)表面上に共吸着した単原子層グラファイトと ナトリウム層のバンド構造。 ナトリウム層のバンド構造。 もう一つの原子種であるセシウムの三元系は2×2の周期構造で計算された。図7にそのバンド構造を示す。 バンドはカリウムの三元系と異なり、K点において全くギャップを見せない。セシウムのコアの5pバンドは バンドはカリウムの三元系と異なり、K点において全くギャップを見せない。セシウムのコアの5pバンドは バンドと混成を起こしているので、ナトリウムの系の場合と違ってセシウムのポテンシャルが弱いとは思えない。これは2×2周期の構造が持つ対称性が バンドと混成を起こしているので、ナトリウムの系の場合と違ってセシウムのポテンシャルが弱いとは思えない。これは2×2周期の構造が持つ対称性が 周期のものと異なるために起こったことである。即ち、単純にグラファイト層とニッケル下地との間にセシウム原子が詰まった系を想定する限り、ARUPS実験[3]で観測されたような 周期のものと異なるために起こったことである。即ち、単純にグラファイト層とニッケル下地との間にセシウム原子が詰まった系を想定する限り、ARUPS実験[3]で観測されたような バンドのギャップは理論的に導かれないことが結論されるのである。従って、セシウムを含む三元系の場合に限って表面構造は再構成していると予想せざるを得ない。 バンドのギャップは理論的に導かれないことが結論されるのである。従って、セシウムを含む三元系の場合に限って表面構造は再構成していると予想せざるを得ない。  図7 Ni(111)表面上に共吸着した単原子層グラファイトと2x2セシウム層のバンド構造。 図7 Ni(111)表面上に共吸着した単原子層グラファイトと2x2セシウム層のバンド構造。 単原子層グラファイト層とニッケル表面との相互作用は、ニューンズとアンダーソンによる化学吸着の理論モデル[6]によって解析できる。両層の周期が整合的なので理論は1次元のモデルに還元される。従来は1次元ニューンズ=アンダーソン模型は単に元の模型の理論的な単純化であると思われてきたが、単原子層グラファイト層とニッケル表面の二元系には実際に適用できる。吸着サイトの違いによる影響も論じられたが、ニューンズ=アンダーソン模型だけでは図4の様なバンド構造は得られないことが判明した。そこで、三元系の場合にグラファイト層がアルカリ原子から受けているような摂動ポテンシャルがニッケルの場合でも バンドの変形に寄与しているものと結論される。 バンドの変形に寄与しているものと結論される。 アルカリ原子から単原子層グラファイトへの摂動論的影響はタイトバインディング模型によって論じられる。 の周期を持つ系ではブリルアンゾーンの折りたたみによって2種類のK点が同じ の周期を持つ系ではブリルアンゾーンの折りたたみによって2種類のK点が同じ 点に移される。2つのK点に対応するブロッホ波は互いに結合し、結果として 点に移される。2つのK点に対応するブロッホ波は互いに結合し、結果として バンドの縮退が解けることになる。2×2の周期を持つ系では2種類のK点が同じ点に移されることがなく、従って2種類のブロッホ波の結合もない。結果として バンドの縮退が解けることになる。2×2の周期を持つ系では2種類のK点が同じ点に移されることがなく、従って2種類のブロッホ波の結合もない。結果として バンドの縮退は維持される。このように、アルカリ原子によるグラファイト層の バンドの縮退は維持される。このように、アルカリ原子によるグラファイト層の バンドのギャップへの影響は系が持つ対称性に著しく左右されるものである。以上述べてきたような結果は、一般の三元系というものの複雑さを伺わせる。 バンドのギャップへの影響は系が持つ対称性に著しく左右されるものである。以上述べてきたような結果は、一般の三元系というものの複雑さを伺わせる。 参考文献[1]R.Rosei,S.Modesti,F.Sette,C.Quaresima,A.Savoia and P.Perfetti:Phys.Rev.B29(1984)3416[2]H.Itoh,T.Ichinose,C.Ochima,T.Ichinokawa and T.Aizawa,Surf.Sci.254(1991)437[3]A.Nagashima,N.Tejima,and C.Oshima,Phys.Rev.50(1994)17487[4]K.Kobayashi,Y.Souzu,N.Isshiki and M.Tsukada,Appl.Surf.Sci.60/61(1992)443[5]Y.Souzu and M.Tsukada,Surf.Sci.326(1995)42[6]D.M.Newns,Phys.Rev.178(1969)1123 |