学位論文要旨
| No | 111648 | |
| 著者(漢字) | 坂本,成彦 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | サカモト,ナルヒコ | |
| 標題(和) | 重陽子-陽子散乱のEd=270MeVでの研究 | |
| 標題(洋) | A study of the d-p elastic scattering at Ed=270MeV | |
| 報告番号 | 111648 | |
| 報告番号 | 甲11648 | |
| 学位授与日 | 1996.03.29 | |
| 学位種別 | 課程博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 博理第3012号 | |
| 研究科 | 理学系研究科 | |
| 専攻 | 物理学専攻 | |
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | この研究の動機は、"多核子系の現象、特にスピンに依存する現象は、2体の核力を用いてどの程度記述することができるか"という原子核物理の大局的な興味に因る。多核子系としていろいろな系が考えられるが、その中でも重陽子-陽子散乱、特に中間エネルギー領域(E/A ・重陽子-陽子散乱は核子-原子核散乱の考えうる最も簡単な系である。 ・豊富なスピン観測量(スピン1とスピン1/2の粒子の散乱)が測定可能である。 ・重陽子の構造そのものが興味の対象(テンソルカ)である。 ・核子-核子相互作用が低いエネルギー領域より比較的良く決まっている。 ・偏極分解能が大きい値を持つ。 ・ドブロイ波長が核子の大きさ程度になる為、インパルス近似的な非常に簡単な描像で重陽子-陽子散乱を記述できると期待される。 ・重陽子-陽子散乱をFaddeevの計算と比べる場合、低いエネルギー領域で計算に取り入れる際に問題になるクーロンカの影響が小さいので厳密な比較を行うことができる。 ところが、これまで適当な実験施設が無かったために、中間エネルギー領域での重陽子-陽子散乱の研究は非常に遅れている。 重陽子-陽子散乱の散乱振幅を全てのスピンの自由度に関して実験的に求めるのは不可能であり、よく分かっている核子-核子散乱の散乱振幅を用いて重陽子-陽子散乱を簡単なモデルで記述できるとすると、例えば中間エネルギーでの重陽子-核子散乱の解析を行うのに非常に有用である。 Faddeevの計算は、低いエネルギー領域でのデータをあまりよく再現しないことが知られている。その理由はひとつにはクーロンカの取り扱いが難しい為である。クーロンカの影響が小さく、かつ、核子-核子相互作用が比較的良く分かっている中間エネルギー領域で実験と計算の比較を行うことは有意義であると考える。 そこで我々は、270メガ電子ボルトの重陽子ビームを用いた重陽子陽子散乱の精度の良い実験を行い、2つの理論計算、インパルス近似とFaddeev計算、との比較を行った。偏極重陽子-陽子散乱の散乱微分断面積は、 と表される。ここで、 我々はこの実験に先立って、大強度、高偏極度の偏極イオン源(図1)、標的上でのスピンの向きを任意に制御できるスピン制御システム、ビーム偏極度を測定するための偏極度計の開発、整備を行って来た。中でも偏極イオン源は、偏極度80%、ビーム強度100  実験はサイクロトロンによって270メガ電子ボルトまで加速された重陽子ビームを用いて行った。測定量は、 重陽子-陽子散乱の非対称性を上下左右方向に検出器を配置し、偏極・非偏極ビームを用いて測定した。散乱重陽子と反跳陽子を、運動学の計算によって求めた角度に検出器を配することにより同時に計測した。検出器は、プラスチック検出器(NE102a1cmt+H1161)を用いた。角度の分解能は、陽子検出器によって決まり、 偏極分解能は、測定した上下左右の散乱の非対称から得られる。Ay、Ayy、Axxは、スピンの向きが鉛直方向を向いたビームを用いた計数率から、Axzは水平面内45度にスピンを傾けたビームでの計数率から求められる。測定結果を図2に黒丸で示す。特徴的なのは、ベクトル偏極分解能Ayが、60度と140度でゼロを横切るのに対して、テンソル偏極分解能は一定の符号の大きな絶対値を持つことである。誤差は、統計誤差が約±3%以下、系統誤差が±2%(偏極度の絶対値の較正)、Axzに関しては更に±2%(スピンの角度)、である。 微分散乱断面積の測定は、非偏極ビームを用いて独立に行った。偏極分解能の測定と同様に、重陽子と陽子の同時計測法を用いた。測定結果を図3に黒丸で示す。誤差は、統計誤差が±1%、系統誤差が±2%(標的厚み)±3%(測定系)±5%(電荷量)である。 炭素標的の陽子ノックアウト反応は、その出射粒子が重陽子-陽子弾性散乱と同じため重陽子-陽子散乱との区別ができない。標的としてポリエチレン(CH2)を用いたので、標的中の炭素の影響を調べる必要がある。そこで微分散乱断面積の測定に際し、炭素標的に対して重陽子-陽子の重心系の角度86.6度のセットアップで同時計測されるイベントの計数率を測定した。その結果、ポリエチレン標的中の炭素の影響は、測定された重陽子-陽子散乱の微分散乱断面積に対して1%以下であることが分かった。これにより、偏極分解能への影響も十分小さいということが言える。 実験データとインパルス近似、Faddeev計算の2つのモデルによる計算値との比較を行った。 重陽子の中の一つの核子が標的陽子と一度だけ散乱するという非常に簡単な描像での重陽子-陽子散乱の散乱行列を核子-核子散乱の散乱振幅を用いて求めた。この過程の散乱行列を求める際、重陽子の中の散乱に関わる核子の運動量の広がりをある運動量で代表させるという近似(因子化近似)を行った。計算結果を図2、3に一点鎖線で示す。簡単のため、中性子交換反応、重陽子のD状態の効果は無視した。比較の結果、微分散乱断面積の形は90度より前方で概ね再現されているが他の観測量の再現性はあまりよくないことがわかった。そこでこの計算で無視された効果のうち、中性子交換反応に関して考察を行った。重陽子の中の中性子が標的陽子に移行して重陽子になるという過程に関してその散乱振幅を求めて微分散乱断面積及び重陽子偏極分解能を求めた。結果を点線で示す。この反応過程は、後方角でおおきな断面積を持つことがわかった。しかしながら、この過程を考慮しても微分散乱断面積が最小になる領域での断面積の絶対値を再現することはできない。我々の測定範囲で、データの再現性を良くするためには、計算で無視された他の効果、特に重陽子のD状態を考慮する必要があると考えられる。 Faddeevの理論は、二体の相互作用を用いて三体系を厳密に記述する。図2、3に実線で示した三体計算の結果(実線及び破線)は小池氏(法政大)により分離型ポテンシャル法で三体のFaddeev方程式を解いて得られたものである。核子-核子相互作用としてはArgonne 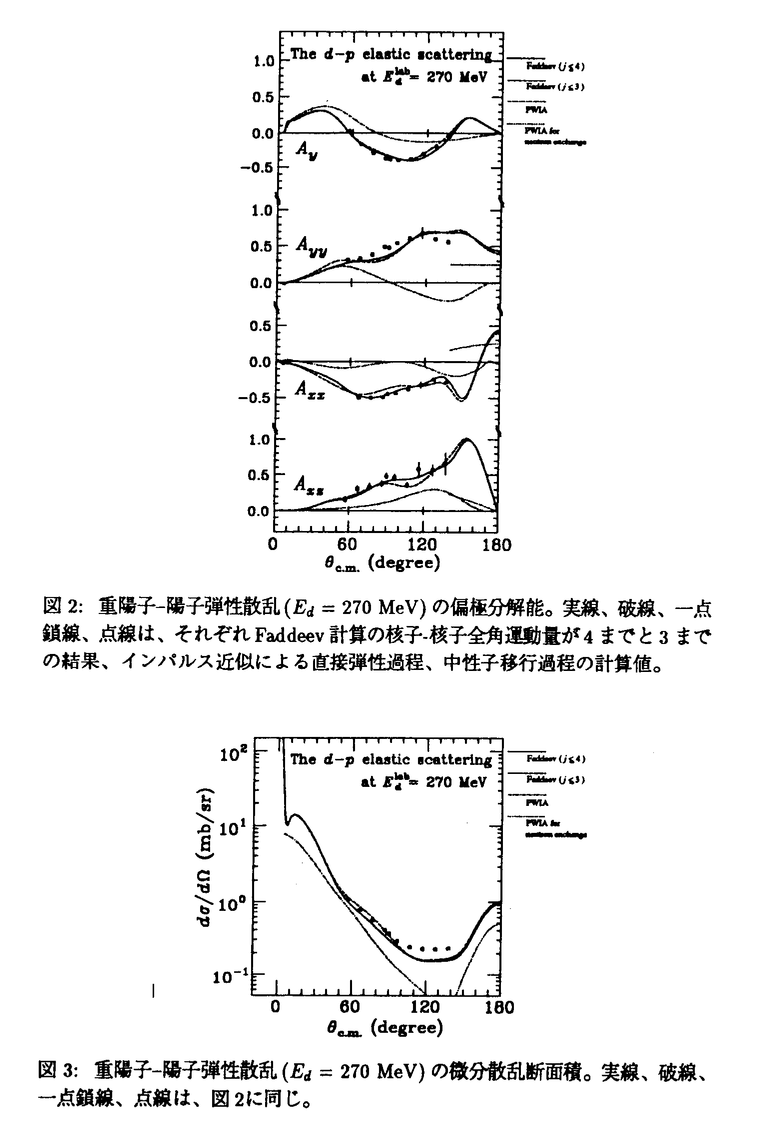 中間エネルギー領域で初めて、重陽子-陽子散乱の微分散乱断面積と全ての偏極分解能の高精度のデータを得た。 最初にその実験結果とインパルス近似の計算との比較を行った。微分散乱断面積が90度より前方で概ね再現されたものの、他の観測量については再現性はあまりよくなかった。本論文では取り入れなかった重陽子のD状態がどの程度効くのかを調べるのは今後の課題である。 Faddeev計算との比較では、非常に良い再現性が得られた。低エネルギー領域での状況を考えると非常に興味深い。しかしながら、断面積が最小になる部分で30%程度の不一致が見られた。この事は、Argonne | |
| 審査要旨 | 本論文は、6章からなり、1章のIntroductionと6章のSummaryを除くと、スピン偏極した重陽子と陽子との断面積の偏極依存性(非対称度、偏極分解能)の測定および微分断面積の測定に関する実験研究と、それらの結果をインパルス近似およびFaddeev理論によって解釈を試みている研究との2つに大別されている。 前半の実験研究では、まず偏極重陽子ビームの陽子散乱における非対称度測定に関し、使用した実験装置が簡潔に記述されている。実験は理化学研究所のリングサイクロトロンを用いてスピン偏極した重陽子を270MeVに加速して行われた。偏極重陽子ビームは、入射器であるリングサイクロトロンの入射器であるAVFサイクロトロンの前に偏極イオン源を作成し設置することによって得ている。この際最も重要な開発要素である重陽子の偏極イオン源が、申請者を中心とするグループによって製作され設置され、実験に使用されている。このイオン源は、「原子ビーム法」による最先端のものと云ってよく、低温ノズル、ECRイオン化法、などの採用により80%もの高い偏極度と100 偏極ビームの実験には、ビームの偏極度の高精度の測定と、実験時における偏極度の安定した維持とモニターが重要である。ビーム偏極の測定は、入射AVFサイクロトロンからの14MeV重陽子に対して12C(d,p)反応を用いて行われた。14MeVにおけるこの反応の偏極分解能の測定が、申請者を中心として九州大学タンデムバンデグラーフを用いて行われ、偏極測定に適していることがわかっている。実験はさらにリングサイクロトロンで270MeVまで加速したビームを用いて行われたため、14MeVでの偏極がそのまま保たれるかという疑問がわく。申請者は、リングサイクロトロンによる加速中減偏極をひきおこす共鳴現象がないことを確かめ、14MeVの測定で十分であると結論している。同時にスピン・パリティの組合せが0++1+→0++0-という反応の特殊性を用いて、200MeVの高エネルギーでの偏極度測定を行うことが出来ることを示し、今後に解決すべき課題としている。 非対称度の測定は、ポリエチレン(CnH2n)膜を標的として行われ、反跳陽子と重陽子の同時計測を、上下左右に置かれたプラスチックカウンターを用いて行うことにより実行された。その際偏極方向を20秒ごとに反転するなどして、系統誤差を除去している。重心系の角度で57度から135度の範囲で測定された結果は、スピンの向きが鉛直方向を向いたビームで得られるAy,Ayy,Axxと、水平面内45度傾いたビームで得られるAxyの形にまとめられ、統計誤差は±3%以下、系統誤差±2%の高精度で得られている。 微分断面積の測定は、絶対値測定に必要不可欠なビーム強度測定における系統誤差を減少させるために、非偏極ビームを用いて、ビーム強度モニターであるファラデーカップを下流遠方に置く別の実験レイアウトを用いて行われた。統計誤差は±1%、系統誤差は±2%(標的厚)±3%(測定系)±5%(電荷量)におさえられた。 それらの実験において実験上の系統誤差を生む可能性のある次のいくつかの点に関して、申請者は十分な考察を行っている。(1)炭素標的のノックアウト反応の効果、(2)重陽子ビームの標的通過後の散乱効果、(3)非対称度測定に用いられたAlアブゾーバーの効果、など。 得られた実験結果は、2つのモデルによる理論計算値と比較された。まず、インパルス近似によって、重陽子-陽子散乱振幅を核子-核子散乱振幅を用いて表し、微分断面積を計算して実験との比較がなされた。結果は、中性子交換反応を考慮に入れても、微分断面積の値を定量的に再現することはできず、その定性的な振舞いを説明するにとどまった。 一方、2体の相互作用を用いて3体系を厳密に記述するFaddeevの理論は、実験結果をよりよく再現する計算結果を与えた。計算は、分離型ポテンシャル法で3体Faddeev方程式を解いて得られたもので、小池氏(法政大)によって行われた。この際核子-核子相互作用はArgonne これらの理論計算との比較は、必ずしも申請者のみの研究成果でないことは明らかであるが、中高エネルギー領域の3体系の原子核散乱において、Faddeev理論の有効性を実験的に確かめた典型的な例であり、重要な業績として評価されるべきであろう。 以上のことから明らかなように、申請者の提出した論文には、次のような顕著な学術的成果が記述されている。1)偏極イオン源の開発から検出器や計測系に至る実験遂行に関する全ての作業を主導的に行っている;2)実験のテーマを重陽子と陽子の問題にしぼり、中高エネルギーの偏極度依存性測定の世界的にリードできるデータを提供している;3)実験の解釈において中間エネルギーの3体系核反応におけるFaddeev理論の有効性を明確に示している。 これらの結論をふまえて、論文審査において、提出された論文は、東京大学博士(理学)としての評価基準を十分に満たしていて、審査委員全員は「合格」であるとの判定を下した。 なお、本論文の研究は、酒井英行、岡村弘之、上坂友洋、石田悟、大津秀暁、若狭智嗣、佐藤義輝、新関隆、加藤健一、山下利幸、畑中吉治、小池康郎、各氏との共同研究であるが、論文提出者が主体となって分析及び検証を行ったもので、論文提出者の寄与が十分であると判断する。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/53899 |
 100MeV)での重陽子-陽子散乱が以下に挙げる理由により最も興味深い。
100MeV)での重陽子-陽子散乱が以下に挙げる理由により最も興味深い。
 は、ビームが偏極していないときの微分散乱断面積、pは重陽子の偏極を表す。Aが偏極分解能で、Axx+Ayy+Azz=0を満たす。測定したのは、微分散乱断面積と独立な全ての偏極分解能、Ay、Ayy、Axx、Axzであり、中間エネルギー領域では世界で初めての測定である。
は、ビームが偏極していないときの微分散乱断面積、pは重陽子の偏極を表す。Aが偏極分解能で、Axx+Ayy+Azz=0を満たす。測定したのは、微分散乱断面積と独立な全ての偏極分解能、Ay、Ayy、Axx、Axzであり、中間エネルギー領域では世界で初めての測定である。 Aを達成しており世界最高水準の性能を持つ。
Aを達成しており世界最高水準の性能を持つ。 、Ay(
、Ay( )、Ayy(
)、Ayy(
 14が用いられ、核子-核子間の全角運動量が4の成分まで計算に取り入れられた。低エネルギー領域では、実験データの再現性が良くないのに対し、270メガ電子ボルトでは、特に偏極分解能が非常によく再現されることが分かった。Faddeev計算の結果を詳しくみてみると、偏極分解能が非常によく再現されているのに対して、微分散乱断面積はその値が最小となる90度から140度で計算値が最大30%ほど小さくなっている。また、重陽子のエネルギーで130メガ電子ボルトと190メガ電子ボルトに相当するエネルギーに対して行った同様の計算結果と存在する実験データとを比べて見ると、これらのエネルギーでも計算値が同程度に実験値より小さくなることがわかった。この不一致の理由は未だ明らかになっていない。この計算で考慮されていない、三体力や相対論の効果が断面積や偏極分解能にどの程度寄与するかは興味のあるところである。
14が用いられ、核子-核子間の全角運動量が4の成分まで計算に取り入れられた。低エネルギー領域では、実験データの再現性が良くないのに対し、270メガ電子ボルトでは、特に偏極分解能が非常によく再現されることが分かった。Faddeev計算の結果を詳しくみてみると、偏極分解能が非常によく再現されているのに対して、微分散乱断面積はその値が最小となる90度から140度で計算値が最大30%ほど小さくなっている。また、重陽子のエネルギーで130メガ電子ボルトと190メガ電子ボルトに相当するエネルギーに対して行った同様の計算結果と存在する実験データとを比べて見ると、これらのエネルギーでも計算値が同程度に実験値より小さくなることがわかった。この不一致の理由は未だ明らかになっていない。この計算で考慮されていない、三体力や相対論の効果が断面積や偏極分解能にどの程度寄与するかは興味のあるところである。