臨界現象においてはスケーリング則が一般に成り立つと考えられている。すなわち物理量の特異性が、発散の強さを表す臨界指数とスケーリング関数で表される。そして、この臨界指数とスケーリング関数は、系の基本的な対称性や次元だけで普遍的に決まると考えられている。 本論文では、このスケーリング則を研究する対象として、任意のスピンSをもつ強磁性ハイゼンベルグ鎖を取り扱う。この系は磁性体のモデルとして頻繁に使われ、絶対温度T=0で特異性をもつ。なお、系のハミルトニアンHを以下のように定義する。  ここで、結合定数Jは正、そしてhは磁場を表わす。なお、境界条件として周期な場合と自由端の両方を考える。この系HのT=0近傍で磁化mのスケーリング関数がSに寄らず同一の関数であるとの予想を立てた。実際に、線形帯磁率と非線形帯磁率のスケーリング関数を古典極限(S→∞)で求め、S=1/2とS=1の系の数値結果がそれに従うことを確認した。 S=1/2の熱力学的極限で、この系は、"熱力学的"ベーテ仮設をつかった数値計算が、行なわれていた。それによるとゼロ磁場の線形帯磁率 1の温度に関する特異性が 1の温度に関する特異性が 1〜1/T2(臨界指数 1〜1/T2(臨界指数 =2)、そして相関長の特異性が =2)、そして相関長の特異性が 〜1/T(臨界指数 〜1/T(臨界指数 =1)と古典系と同じになることがわかっていた。 =1)と古典系と同じになることがわかっていた。 われわれは、この古典系との類似性に着目し、さらに磁化の高次の磁場依存性を調べた。それには、"熱的"ベーテ仮設をつかった数値計算を使った。この方法は、先に行なわれていた"熱力学的"ベーテ仮設の方法より、より容易に自由エネルギーを計算できると期待されていた。これにより、ある温度Tと磁化mにおけるヘルムホルツの自由エネルギーgの値を得た。そしてこれが とm2で展開できると仮定し、その係数を最小二乗法により以下のように得ることができた。 とm2で展開できると仮定し、その係数を最小二乗法により以下のように得ることができた。 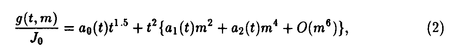 ここで、J0=J/S2,t=T/J0.そして  これより、ゼロ磁場の線形帯磁率 1を以下のように求めた。 1を以下のように求めた。  これは先の"熱力学的"ベーテ仮設による結果と一致した。さらに、ゼロ磁場の三次の非線形帯磁率 3の温度依存性も得られた。 3の温度依存性も得られた。  x≡Jh/T2を固定して、T→0の極限(スケーリング極限)では、xt1/2,xt,x3t1/2,x3t1/2等の項を無視できる。Jh/T2の小さいところでの、磁化mのスケーリング極限の振る舞いは(6)と(7)より  と書けることがわかった。一方、古典系でも 1と 1と 3を解析計算し、Jh/T2の小さいところで磁化mのスケーリング極限の振る舞いを以下のごとく得た。 3を解析計算し、Jh/T2の小さいところで磁化mのスケーリング極限の振る舞いを以下のごとく得た。 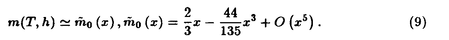 ここで、(44/135)〜0.32なので、この古典系のスケーリング関数m0は、S=1/2の場合の(8)式と一致することが示せた。このように、熱力学的極限でS=1/2,∞の系Hの磁化はあるスケーリング関数でかける。それらはスケーリング変数をxとして、このx3の項まで一致した。さらに、高次の項も一致するとして、S=1/2,∞の系はxをスケーリング変数とする同一のスケーリング関数m0で書けると予想した。なお、高次の項は、古典系より求められる。さらに他のスピンの場合もスケーリング関数がこのm0になると予想とした。また、この(9)式はすべてのスピンで臨界指数 = = =2を意味する。 =2を意味する。 次に、この予想を他のスピンで確認する。その際S=1/2,∞以外で熱力学的極限の磁化を求めるのは困難である。故に有限サイズの系を考える必要が出てくる。われわれは、この系がT=0で特異性を持つことからスケーリング関係式 = = = = +1を任意のスピンで導いた。(この関係式はS=1/2,∞では確認できる。)さらに先の予想からあらゆるスピンで +1を任意のスピンで導いた。(この関係式はS=1/2,∞では確認できる。)さらに先の予想からあらゆるスピンで =1と期待できる。すると、系のサイズが相関長 =1と期待できる。すると、系のサイズが相関長 〜1/Tでスケールできると考えられる。これより長さに関するスケーリング変数としてy≡J/TLを導入する。そして、熱力学的極限のスケーリング関数(9)式を一般化して以下のようにかけると予想する。 〜1/Tでスケールできると考えられる。これより長さに関するスケーリング変数としてy≡J/TLを導入する。そして、熱力学的極限のスケーリング関数(9)式を一般化して以下のようにかけると予想する。  なお、熱力学的極限(T,hを固定して、L→∞)を取る操作はy→0とすることで実現できる。これより、以下の関係が導かれる。  これよりm(x,y)がスピンによらず不変であれば、m0(x)もスピンによらず不変となる。ここでは、スケールされた磁場xが有限な場合に磁化を調べるのは困難なので、熱力学的極限の時と同様にゼロ磁場の帯磁率を調べてみる。  古典系で、ゼロ磁場(x=0)の場合、周期及び自由端のいずれの境界条件でも分配関数、二点と四点相関関数、線形及び三次の帯磁率 1, 1, 3を第二章で解析的に求めた。得られたこれらの物理量のスケーリング極限をとると、スケーリング変数yのみを含んだスケーリング関数でかけるを確認した。特に、 3を第二章で解析的に求めた。得られたこれらの物理量のスケーリング極限をとると、スケーリング変数yのみを含んだスケーリング関数でかけるを確認した。特に、 1, 1, 3は(12)式を満たしている。これより、この 3は(12)式を満たしている。これより、この 1と 1と 3を古典系で解析的に求めた。 3を古典系で解析的に求めた。  ここで、前者は周期境界、後者は自由端である。  は分配関数のスケーリング関数である。三次の帯磁率の周期境界のスケーリング関数は を使い次のように求められる。 を使い次のように求められる。  自由端の場合は次のようにスケーリング関数を古典系で解析的に得た。  我々の予想にしたがえば、他のスピンでもこれら(14),(16),(17)式がスケーリング関数になる。 次に、第三章では他のスピンとしてS=1/2,1をとりあげ、第二章で得られたスケーリング関数(14),(16),(17)が満たされることを数値計算で示す。数値計算では、系のハミルトニアンHをハウスホルダー法で対角化して全エネルギー固有値を求める。これを使い相関関数を求め、それをすべてのサイトで和を取った。なお、系のサイズLはS=1/2でL 14,S=1でL 14,S=1でL 10である。図1で対角化より得られたS=1/2の 10である。図1で対角化より得られたS=1/2の 1periのデータをスケーリング極限への外挿を行なった。この際、S=1/2の熱力学的極限の計算結果の解析(6)と(7)と同様に 1periのデータをスケーリング極限への外挿を行なった。この際、S=1/2の熱力学的極限の計算結果の解析(6)と(7)と同様に で展開できると仮定した。線形,三次の帯磁率を周期境界と自由端のあらゆる組み合わせに対してS=1/2,1の系に同様の解析を行なう。そして、スケーリング極限に外挿し、スケーリング関数の値を得る。 で展開できると仮定した。線形,三次の帯磁率を周期境界と自由端のあらゆる組み合わせに対してS=1/2,1の系に同様の解析を行なう。そして、スケーリング極限に外挿し、スケーリング関数の値を得る。  図1:スケーリング関数に対する 図1:スケーリング関数に対する 1T2/Jの補正。S=1/2周期境界の強磁性ハイゼンベルグ鎖。y=J/(TL)=0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,5.0,L 1T2/Jの補正。S=1/2周期境界の強磁性ハイゼンベルグ鎖。y=J/(TL)=0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,5.0,L 8.なお、補正は 8.なお、補正は で展開できるとし、原点に近い方から三点を二次曲線で外挿した。 で展開できるとし、原点に近い方から三点を二次曲線で外挿した。 こうやって得られたスケーリング極限における各スケーリング関数の値を図2,3,4,5にまとめた。  図表図2:周期境界条件の強磁性ハイゼンベルグ鎖の線形帯磁率のスケーリング関数 図表図2:周期境界条件の強磁性ハイゼンベルグ鎖の線形帯磁率のスケーリング関数 1peri(y)。実線は古典系より解析的に得られた関数(14)。 / 図3:自由端の強磁性ハイゼンベルグ鎖の線形帯磁率のスクーリング関数 1peri(y)。実線は古典系より解析的に得られた関数(14)。 / 図3:自由端の強磁性ハイゼンベルグ鎖の線形帯磁率のスクーリング関数 1open(y)。実線は古典系より解析的に得られた関数(14)。 / 図4:周期境界の強磁性ハイゼンベルグ鎖の三次の非線形帯磁率のスケーリング関数 1open(y)。実線は古典系より解析的に得られた関数(14)。 / 図4:周期境界の強磁性ハイゼンベルグ鎖の三次の非線形帯磁率のスケーリング関数 3peri(y)。実線は古典系より解析的に得られた関数(16)。S=1/2の熱力学的極限でのベーテ仮設による値 3peri(y)。実線は古典系より解析的に得られた関数(16)。S=1/2の熱力学的極限でのベーテ仮設による値 3peri(y=0)(x3の係数)(8)を示した。 / 図5:自由端の強磁性ハイゼンベルグ鎖の三次の非線形帯磁率のスケーリング関数 3peri(y=0)(x3の係数)(8)を示した。 / 図5:自由端の強磁性ハイゼンベルグ鎖の三次の非線形帯磁率のスケーリング関数 3open(y)。実線は古典系より解析的に得られた関数(17)。 3open(y)。実線は古典系より解析的に得られた関数(17)。 第二章で任意のスピンでのスケーリング関数の解析的な形を求めるのに古典強磁性ハイゼンベルグ鎖を使った。第四章では、この周期境界の古典系を連続体に近似してスケーリング関数を得る。この際の計算は元の格子モデルより見通しがよくなる。さらに、この連続体モデルは有限範囲の長距離相互作用の場合にも応用できる可能性がある。古典強磁性ハイゼンベルグ鎖は、格子定数がゼロになる連続体極限では、次の"重力場"(x)中の球面上に束縛された一体の量子回転子モデルHrotの温度yでの熱力学と解釈できる。  このハミルトニアンHrotはスケーリング変数x,yしか含まない。故に得られる物理量はスケーリング関数そのものと考えられる。実際にHrotを使って、元の系Hの分配関数、相関関数、帯磁率を解析計算した。そしてこれらが、期待どおり格子モデルで得られた結果(14),(16)と同じになった。特に、格子模型の熱力学的極限y→0はHrotの基底状態に相当する。この場合は、Hrotの行列要素が求まる。故に(9)式で与えられるm0(x)が数値的にxの全てに対して求まる(図6参照)。この図にはS=1/2のベーテ仮説からのデータも同時にプロットした。温度が下がるにつれ、m0(x)に近づく様子が、定性的に確認できる。さらに、m0(x)の漸近形が摂動論より左式のように求まる。このように、回転子モデルで強磁性ハイゼンベルグ鎖のスケーリング関数を求められることがわかった。故に、高次の相関長や帯磁率はこの方法を使い見通しよく求まると思われる。また、元のハミルトニアンHでスケーリング極限をとることは、連続体近似を取ることに相当することがわかった。  図6:連続体近似から得られたy=0のスケーリング関数m0とベーテ仮説に寄る計算結果。 図6:連続体近似から得られたy=0のスケーリング関数m0とベーテ仮説に寄る計算結果。 まとめると、本研究では任意のスピンの強磁性ハイゼンベルグ鎖がスピンによらない不変なスケーリング関数を持つことを予想した。S=1/2,1,∞の系で解析的におよび数値的に厳密に物理量を計算し、それらがスケーリング極限で同じ値を取ることを示し、この予想を確認した。さらに、そのスケーリング関数が連続体近似の磁場中の量子回転子モデルより解析計算で求られることを示した。 |