学位論文要旨
| No | 111703 | |
| 著者(漢字) | 沼子,千弥 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | ヌマコ,チヤ | |
| 標題(和) | 生体硬組織における金属元素濃集現象に関する研究 : ヒザラガイの歯舌中の鉄の状態分析 | |
| 標題(洋) | ||
| 報告番号 | 111703 | |
| 報告番号 | 甲11703 | |
| 学位授与日 | 1996.03.29 | |
| 学位種別 | 課程博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 博理第3067号 | |
| 研究科 | 理学系研究科 | |
| 専攻 | 化学専攻 | |
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 生物界には特定の元素を特定の器官に濃集する、いわゆる生体濃縮現象がしばしば観察される。例えばホヤやエラコは血液中にVを、ワスレガイやシャコガイ類は腎臓組織に生成する顆粒状物質にMn・Znを、またヒザラガイ類やカサガイ類は歯の中に十万ppmものFeを濃集することが知られている。ヒザラガイの歯のように、生物が体内に濃集した元素を用いて無機質の硬組織(生体鉱物)を形成する現象を生体鉱物化現象と呼ぶ。 生物は一般的に歯などの硬組織を形成する際、主成分としてカルシウム塩を用いるが、鉄を主成分として歯を形成する生物はヒザラガイやカサガイの他に例を見ない。特にヒザラガイの歯は磁性を有する磁鉄鉱を主成分としていることから、歯の持つ磁性とヒザラガイの生態との関連について生物学的な興味が持たれている。しかし、非生物系では常温・常圧で湿式合成することが困難である磁鉄鉱を、歯の主成分として生成するこの歯は、物質科学的に見ても興味深い。なぜヒザラガイの歯の構成成分が磁鉄鉱でなければないのか、またどの様に磁鉄鉱を形成しているのか、これらの問題は未だ解決されていない。そこで本研究では、ヒザラガイの歯の形成に伴う鉄などの構成元素の化学形の変化を捉え、化学的な立場から歯への特異的な鉄の沈着メカニズムを明らかにすることを目的とし、各成熟段階における歯を試料として、粉末X線回折法、X線吸収微細構造法(XAFS法)、Mossbauer分光法等の非破壊状態分析法を適用し、分析を行った。さらに歯の構成元素の種類とその二次元分布を明らかにするためX線プローブマイクロアナリシス(EPMA)を用いた。 実験には、神奈川県の油壺湾で採取したヒザラガイ(Acanthopleura japonica)の歯舌を使用した。歯舌は軟体動物に特有の摂餌関連機関で、有機質の基底膜の上に多数の歯(歯冠部)が並んでいる。種や属が異なると,歯の形や本数、並び方などが異なることから、貝殻の形態と共に貝類の分類における標徴として重要視されている。Photo.1にヒザラガイの外観、Photo.2にヒザラガイの歯舌の光学顕微鏡写真を示す。ヒザラガイから摘出した歯舌はエタノールで固定し、各種測定用試料とした。ヒザラガイ(Photo.1)の鉄を濃集した歯は歯舌上に2列に、また約70対存在している。口の中に露出している歯舌先端部(Photo.2,左側)の歯は摂餌に十分な硬度を有するが、その反対側に位置する歯舌嚢(Photo. 2,右端)では、常に新しい歯が形成されている。歯舌嚢で形成された歯は基底膜と共にベルトコンベアのように口のほうへ徐々に押し出され、摂餌により破損した歯を新しい歯が補充してゆく。その過程で歯の成熟が進む。最初は未成熟で硬度も低い褐色の歯は、次第に表面の色を灰色、赤色、黒色と変え、硬度を増してゆく。この色の変化に対応して、ヒザラガイの歯の成熟段階はStage IからStage IVに分類される。本研究では、光学顕微鏡下でこの色ごとに分別した歯を試料として各種測定に用いた。  EPMAによる定性分析より、ヒザラガイの歯の構成元素は酸素の他にFeCa・P・Mgの4元素であることが確認された。この4元素について二次元元素マッピングを行った結果、摂餌に用いられる歯の先端から腹の部分(摂餌面)に鉄が濃集し、Ca・Pをマトリクスとする物質が歯の背面に分布していることが明らかになった(Fig. 1)。この2つの物質に対し顕微赤外分光法によりIRスペクトルの測定を行ったところ、摂餌面に濃集した鉄は酸化鉄の状態、また背面に濃集したリンはリン酸PO4の状態で存在することがわかった。両者の境界線は鮮明で、双方に渡る元素の移動の痕跡が見られないことから、酸化鉄の濃集部である摂餌面とリン酸カルシウムをマトリクスとする歯の背面の形成が独立していることが示唆された。また、灰色、赤色の歯についても同様にマッピングを行い、各形成段階での元素分布を比較した。その結果、鉄は成熟の第2段階に相当する灰色の歯ですでに摂餌面を形成しているが、リン酸カルシウムは灰色の段階ではほとんど歯の中に存在せず、その後、赤色、黒色と歯の成熟度が高くなるにつれ蓄積されてゆく様子が観察された。  これらの歯に対して粉末X線回折の測定も行ってみたところ、最も未成熟な褐色の歯の部分は全くピークを示さず、X線的には非晶質であることがわかった。灰色・赤色・黒色の歯からはいずれもmagnetite(Fe3O4)に相当するピークのみが検出され、歯の背面に分布するリン酸カルシウムは非晶質であることが分かった。 歯の成熟に伴う濃集された鉄の状態の変化を調べるために、4色の歯に対してMossbauer分光法による分析を試みたが、最も未成熟な褐色の歯では鉄の含有量が低くMossbauer分光法の検出限界以下であった。そこで、他の3つについてMossbauer測定の結果得られたスペクトルの比較を行った(Fig.2)。 ヒザラガイの歯の各スペクトルには逆スピネル型構造を持つmagnetite(Fe3O4)に相当する2組のsextetと常磁性high spinのFe3+に相当するdoubletが1組見られた。粉末X線回折の結果を併せて、このdoubletの成分はX線的に非晶質であることが推測された。また、歯の成熟度が上がるにつれて、doubletの相対強度が10%から25%, 30%と増加する傾向が見られた。このdoubletに相当する鉄の化学種のついては同定を行うために、さらに液体窒素温度でのMossbauer測定から、このdoubletの成分はferritinという鉄貯蔵タンパクに含まれる鉄ミセルに類似した物質であることがわかった(Fig.3)。  さらにMossbauer法で知見を得ることができなかった褐色の歯について情報を得るため、より感度の高い蛍光XAFS法により分析を行った。褐色の歯のXANESスペクトルのケミカルシフトと形状をみると、ferritinと類似することがわかった(Fig.4)。よって、ヒザラガイの歯の中にはすべての成熟段階で磁鉄鉱以外の非晶質成分としてferritinに類似した3価の鉄化合物が混在することが明らかとなった。  一般にX線吸収スペクトルには加成性があり、混合物のスペクトルはその成分のスペクトルの和になる。褐色の歯ではスペクトルの形状・シフト共にほぼferritinと一致するので、この歯にはほとんどmagnetite(Fe3O4)は混在しないことが推察されたが、これに対し灰色の歯はmagnetiteに近いシフトを見せており、magnetiteは、成熟段階初期の褐色から灰色にかけて、歯に含まれる鉄が急激に還元されることにより形成されることが推察された。また赤色と黒色の歯のスペクトルは、いずれもmagnetiteとFeOOHのほぼ中間のシフトを示し、magnetiteと3価の鉄化合物の混合物であることなど、Mossbauer法での結果を支持した。 ヒザラガイの歯のように、いくつかの化学種が混在する試料の場合に、X線吸収スペクトルがどのように変化するかを調べるために、標準試料である磁鉄鉱(magnetite)と、3価の鉄化合物の代表例として試薬の   -FeOOH混合試料のXANESスペクトル(蛍光法) -FeOOH混合試料のXANESスペクトル(蛍光法)このプレエッジ強度と試料中のmagnetite比をプロットすると、Fig.6のような一次の相関を得ることができた。このようにXANESスペクトルでもその形状は混合物の成分比を反映し変化することから、ヒザラガイの歯の成熟に伴い歯に存在する鉄の化学種の混在比が変化しているというこれまでの見解の妥当性が支持された。以上の結果を総合しFig.7に示すようなヒザラガイの歯の形成プロセスを知ることができた。 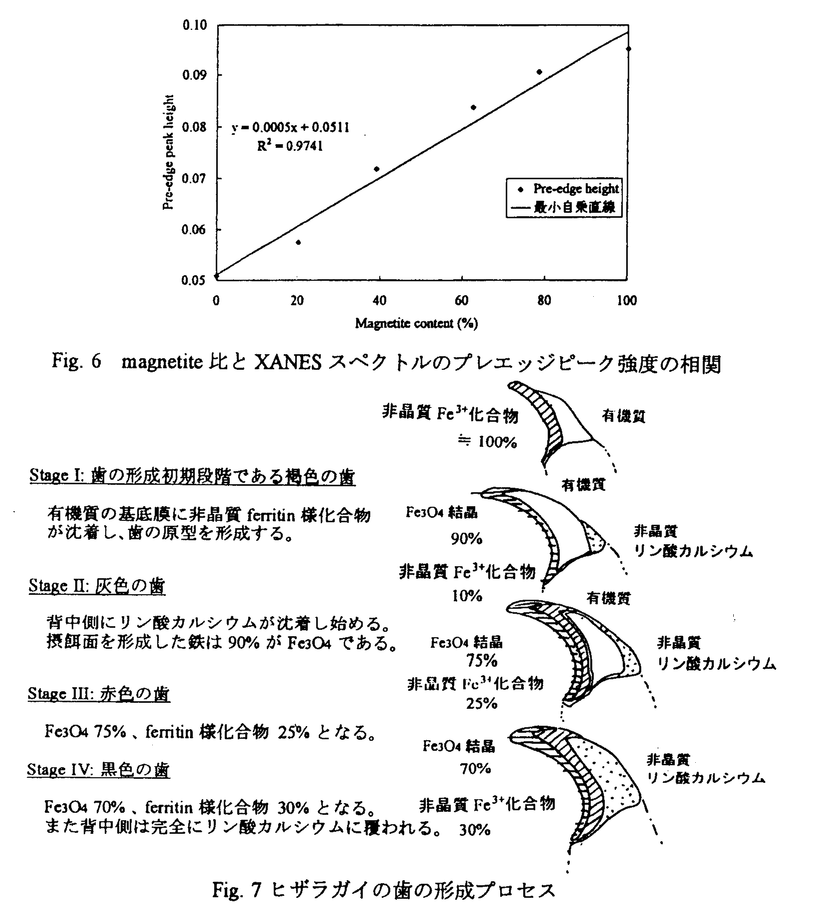 | |
| 審査要旨 | 本論文は4章から成り,第1章は序論,第2章は実験,第3章は結果及び考察,第4章は結論について述べられている. 生命体は自己保存に必要な形態を維持するために特別にデザインされた硬組織を持っている.この硬組織を形成する材質,組織,形状は生物の進化を通じて特別の意味を付与されたものであろうとの推定がなされているが,それら生物硬組織の持つ生物進化上の意味を個々に探ろうとすると,多くの通説が乏しい実験事実を基にした推測のつながりから形成されていることが明らかとなる.論文提出者は第1章序論において主として海洋軟体動物の硬組織研究において,重金属を特異的濃集する生物種に関する研究を総括し,重金属濃集の必然性と濃集メカニズムの解明はほとんどの場合なされていないことを述べている.例えばワスレガイやシャコ貝類の腎臓顆粒がマンガンや亜鉛を濃集していることが知られているが.それらの濃集メカニズムは勿論,単なる解毒のためなのか,体内金属濃度維持のための蓄積なのか全く明らかではない. 論文提出者は此処で研究の焦点を,歯の中心にマグネタイトを形成することで有名なヒザラガイに当てている.マグネタイトは他の生物では走磁性細菌のように軟組織に微小鉱物粒として,また方向を知るために.渡り鳥,ミツバチ,イルカ,サメなどでは耳石として取り込まれているが,ヒザラガイではマグネタイトが歯の構成鉱物として利用されている点で特異的である.このような生物はヒザラガイ類の他には見られない.なぜ歯の成分がマグネタイトでなければならないのか,どのように歯の中にマグネタイトを形成しているのか.このような疑問に答えるために論文提出者はヒザガイの歯の化学組成と組織形態の発達を明らかにしようとした.この方法論は,ヒザラガイにおいては歯舌というベルト上の,未成熟から成熟までの約70対の歯が,磨耗に応じて口腔中に押し出されてゆくという特性を持つことから当を得たものである. 第2章では,ヒザラガイの歯の化学組成分布および構成物質の特性を明らかにする方法が述べられている.歯舌の長さは18〜25mm,1片の歯は約200 第3章では,第2章で述べた方法で得られた結果を用いて,これまでに知られていなかったヒザラガイの歯の成長プロセスを元素分布,組織鉱物の観点から明らかにした.成熟した歯は断面が三日月の半分の形状をしており,その凹面はマグネタイトのみ,また凸面はリン酸カルシウムのみから成っていることがEPMAおよび顕微赤外分光分析の結果明らかになった.また粉末X線回折法により,ヒザラガイの歯は摂餌に用いる内側をより硬度の高い結晶性のマグネタイト,外側は非晶質のリン酸カルシウムという二つの物質が鮮明な境界線を示しながら接合していることをはじめて明らかにした.次に歯の成熟度による歯の中の鉄の化学状態を調べた.歯の成熟度はその外観の色とよく対応しているので,最も未成熟な褐色部から灰色,赤色,最も成熟した黒色部の4つの部分(段階)に分けられた.このうち鉄濃度の低い最も未成熟の褐色部を除いて,他の三つの成熟段階の歯についてEPMA,Mossbauer法による情報が得られている.第二段階の成熟度を示す灰色の歯には,内側にマグネタイト層が早くも形成され,それを支える外側の物質はカルシウムを少量沈着した有機質物質から成っている.第三段階にある赤色部から,最終段階の黒色部へと成熟度が増すにつれ.外側の有機質部分がリン酸カルシウムで充填されてゆき,この間マグネタイト部分の成長は顕著ではないことが分かった.第一段階である褐色部の歯における鉄の状態を高感度の蛍光XANES法で調べたところ,3価の鉄を含むタンパク質であるフェリチンに非常に類似したスペクトルが得られた.このことから褐色部の歯にはマグネタイトはほとんど混在しないことが推察された.中間の成熟度を示す歯のXANESスペクトルはマグネタイトとレピドクロサイトの中間のスペクトルを示すので,歯の成熟にともない,鉄の一部はフェリチン様非晶質の3価から2価に還元され,マグネタイトを形成してゆくことが明らかにされた. 第4章ではそれまでに得られた実験結果を総合し,ヒザラガイの歯の形成過程を4段階に分け,それぞれにおける歯の中の鉄濃集とマグネタイト沈着のプロセスをはじめて明らかにした. 以上のように論文提出者は,従来のバイオミネラリゼーション研究に最新の微量微小部分分析の手法を縦横に駆使し,それらの手法がこの分野の研究に極めて有効であることを明示し,なお且つ軟体動物の歯における鉄の濃集過程と歯組織の成熟過程の一つの典型を,現在望み得る限りの具体性を以って示したと評価できる.従って審査委員会は以上を総合的に判定して,論文提出者沼子千弥は博士(理学)の学位を受けるに十分な資格があるものと認定する. なお本論文の第3章は石井紀明,大越健嗣,中井 泉,高野穆一郎の諸氏との共同研究であるが,論文提出者が主体となって分析及び検証を行ったもので,論文提出者の寄与は十分であると判断する. | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/54501 |
 mと小さいため.研究手段として微小部分分析法に優れた方法,即ちEPMA.SEM/EDS,顕微赤外分光法,Mossbauer分光法,XAFS法が用いられた.
mと小さいため.研究手段として微小部分分析法に優れた方法,即ちEPMA.SEM/EDS,顕微赤外分光法,Mossbauer分光法,XAFS法が用いられた.