| 内容要旨 | | 1Introduction この論文では、米国のブルックヘブン国立研究所(BNL)において著者らが行った9ΣBeハイパー核の実験結果の報告及び考察を行った。  ハイパー核は1980年にスイスのCERN研究所において ハイパー核は1980年にスイスのCERN研究所において ハイパー核実験の副産物として初めて報告された[1](図.1参照)。彼らは ハイパー核実験の副産物として初めて報告された[1](図.1参照)。彼らは 0の生成閾値より上に 0の生成閾値より上に ハイパー核の励起状態に似た2本の巾の狭い(8MeV程度)ピークを発見した。 ハイパー核の励起状態に似た2本の巾の狭い(8MeV程度)ピークを発見した。 粒子は強い相互作用により 粒子は強い相互作用により N→ N→ N崩壊し、Batty、Galらの計算([2][3])によるとその巾は20から30MeV程度と予測されていたため、巾の狭い N崩壊し、Batty、Galらの計算([2][3])によるとその巾は20から30MeV程度と予測されていたため、巾の狭い ハイパー核の報告は驚きであった。その後、CERNやBNLにおいて6Li(K-, ハイパー核の報告は驚きであった。その後、CERNやBNLにおいて6Li(K-, )、7Li(K-, )、7Li(K-, -)、12C(K-, -)、12C(K-, )、16O(K-, )、16O(K-, )反応でも巾の狭いピークが )反応でも巾の狭いピークが 粒子の連続状態上に報告されている[4][5][6][7]。しかし、その後統計精度を上げた実験が行われ、7Li(K-, 粒子の連続状態上に報告されている[4][5][6][7]。しかし、その後統計精度を上げた実験が行われ、7Li(K-, +)と12C(K-, +)と12C(K-, +)反応におけるシグマハイパー核は存在しないことが証明された[8][9]。 +)反応におけるシグマハイパー核は存在しないことが証明された[8][9]。 多くのシグマハイパー核の存在が疑問視されるなか、9Beシグマハイパー核は比較的はっきりとした構造が見えており、かつその構造が と似通っていたために、統計精度の悪さにかかわらずその存在が信じられることが多かった。しかし、その後追試実験が行われることもなかったので、統計精度の高い実験が待ち望まれていた。そこで我々は、BNLのシンクロトロン加速器(AGS)のビームを用いて統計精度をあげた9Beシグマハイパー核実験を行い、かつての実験で報告された狭い巾の成否を検証することにした。 と似通っていたために、統計精度の悪さにかかわらずその存在が信じられることが多かった。しかし、その後追試実験が行われることもなかったので、統計精度の高い実験が待ち望まれていた。そこで我々は、BNLのシンクロトロン加速器(AGS)のビームを用いて統計精度をあげた9Beシグマハイパー核実験を行い、かつての実験で報告された狭い巾の成否を検証することにした。 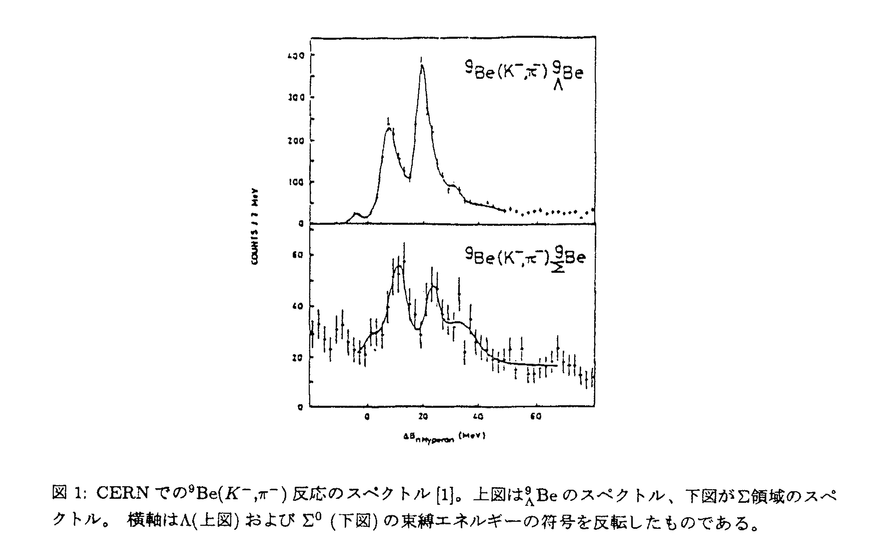 図1:CERNでの9Be(K-, 図1:CERNでの9Be(K-, -)反応のスペクトル[1]。上図は -)反応のスペクトル[1]。上図は のスペクトル、下図が のスペクトル、下図が 領域のスペクトル。横軸は 領域のスペクトル。横軸は (上図)および (上図)および 0(下図)の束縛エネルギーの符号を反転したものである。2実験内容 0(下図)の束縛エネルギーの符号を反転したものである。2実験内容 我々はこの実験をBNLのAGSにあるLESB2ビームラインで実験887として行った。負のK中間子を実験標的に照射して放出される 中間子の運動量を測定し質量欠損を測る方法を用いた。実験装置は図.2に示してある。K中間子の運動量は、 中間子の運動量を測定し質量欠損を測る方法を用いた。実験装置は図.2に示してある。K中間子の運動量は、 粒子の生成断面積と 粒子の生成断面積と 粒子への運動量移行を考慮にいれ、600MeV/cとした。入射K中間子は運動量を磁気スペクトロメータ(Kaon spectrometer)によって選びだされ、かつ実験標的まで運ばれる。実験標的としてベリリウム、そして検定用にCH2を用いた。標的との反応後に放出された 粒子への運動量移行を考慮にいれ、600MeV/cとした。入射K中間子は運動量を磁気スペクトロメータ(Kaon spectrometer)によって選びだされ、かつ実験標的まで運ばれる。実験標的としてベリリウム、そして検定用にCH2を用いた。標的との反応後に放出された 中間子の運動量は標的の後ろにある磁気スペクトロメータ(Pion spectrometer)によって測定される。 中間子の運動量は標的の後ろにある磁気スペクトロメータ(Pion spectrometer)によって測定される。 Kaon spectrometerは4つの四重極磁石(Q)と1つの二重極磁石(D)がQQDQQ(Q5、Q6、D2、Q7、Q8 図.2参照)という順番でならんでいる収束タイプのスペクトロメータである。粒子の動きを捕らえるために、Q6の上流にHodoscopeとDrift Chamber(DX1)、Q8の下流から実験標的の前までに6つのDrift Chamberを置いた。さらに粒子識別はQ6の上流のscintillation counter(S1)と実験標的の直前のscintillation counter(ST)との間の飛行時間差およびLucite Cerenkov counter(CP)とによって行った。 Poin spectrometerも基本的にはKaon spectrometerと同じ形のスペクトロメータである。このスペクトロメータは実験標的のある位置で回転することができ、今回の実験ではK中間子の入射方向に対して、反応後に放出される 中間子の検出方向が4°になるように設定した。Drift ChamberをQ9の前に5つ、Q12の後に3つ配置し、粒子識別はSTとQ12の後方にあるscintillation counter(S2)との飛行時間差を用いて行った。さらにK中間子の崩壊からくる電子および 中間子の検出方向が4°になるように設定した。Drift ChamberをQ9の前に5つ、Q12の後に3つ配置し、粒子識別はSTとQ12の後方にあるscintillation counter(S2)との飛行時間差を用いて行った。さらにK中間子の崩壊からくる電子および 粒子はバックグラウンドとなるため、 粒子はバックグラウンドとなるため、 粒子のみを検出する鉄ブロックとscintillation counter(MU)からなる装置を最下流に配置し、 粒子のみを検出する鉄ブロックとscintillation counter(MU)からなる装置を最下流に配置し、 粒子を除いた。 粒子を除いた。 1スピルあたり平均して50000個のK中間子が得られ、 :K比は15:1であった。 :K比は15:1であった。 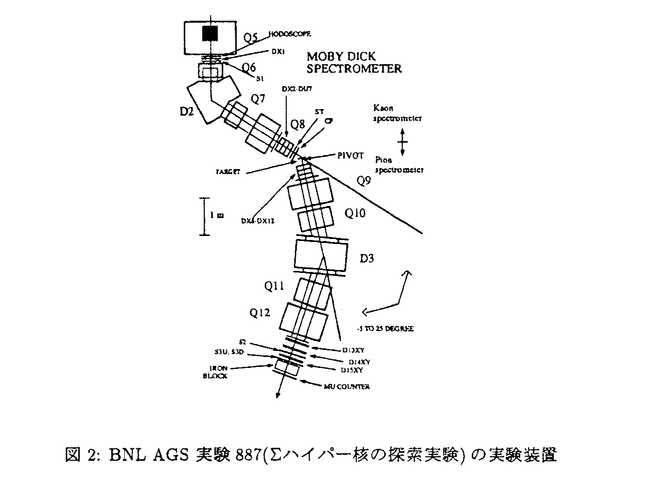 図2:BNL AGS実験887( 図2:BNL AGS実験887( ハイパー核の探索実験)の実験装置3実験結果 ハイパー核の探索実験)の実験装置3実験結果 以下に示すスペクトルは全て、Pion spectrometerのアクセプタンス補正を行ったあとで縦軸を反応断面積にしてプロットしてある。 3.19Be(K-, -) -) 反応 反応 図3に実験結果のexcitation energyのスペクトルを示す。Excitation energy(EE)の定義は、EE=(ハイパー核の質量)-(残留核の質量+hyperonの質量)である。EE=0MeVはhyperonの生成閾値をあらわし、EEが負の領域はhyperonが束縛されていることを示す。 この図でのEE=0MeVは 生成の閾値であり、EE>0MeVは 生成の閾値であり、EE>0MeVは の非束縛領域にあたる。 の非束縛領域にあたる。 EE=-10MeVから 0生成のはじまるまえ(EE=75MeV)までのエネルギーで積分した断面積は2739±251(statistical) 0生成のはじまるまえ(EE=75MeV)までのエネルギーで積分した断面積は2739±251(statistical) (systematic) (systematic) b/srであり、有効中性子数は2.12±0.58 b/srであり、有効中性子数は2.12±0.58 である。 である。 3.2 生成領域での9Be(K-, 生成領域での9Be(K-, +)反応 +)反応 Excitaion energy(EE)のスペクトルを図.4に示す。EE=0MeVは -の生成閾値であり、EE>0MeVは -の生成閾値であり、EE>0MeVは -の非束縛状態である。 -の非束縛状態である。 EE=0MeVからEE=80MeVまでの断面積の積分値は741±78(statistical) (systematic) (systematic) b/srであり、有効陽子数は1.18±0.14である。 b/srであり、有効陽子数は1.18±0.14である。 3.3 生成領域での9Be(K-, 生成領域での9Be(K-, -)反応 -)反応 Excitaion energy(EE)のスペストルを図.5に示す。EE=0MeVを 0の生成閾値とした。EE>0MeVは 0の生成閾値とした。EE>0MeVは 0の非束縛状態である。9Be(K-, 0の非束縛状態である。9Be(K-, -)反応では -)反応では +も生成されうるが、その閾値はこの図においてはEE=13.3MeVである。 +も生成されうるが、その閾値はこの図においてはEE=13.3MeVである。 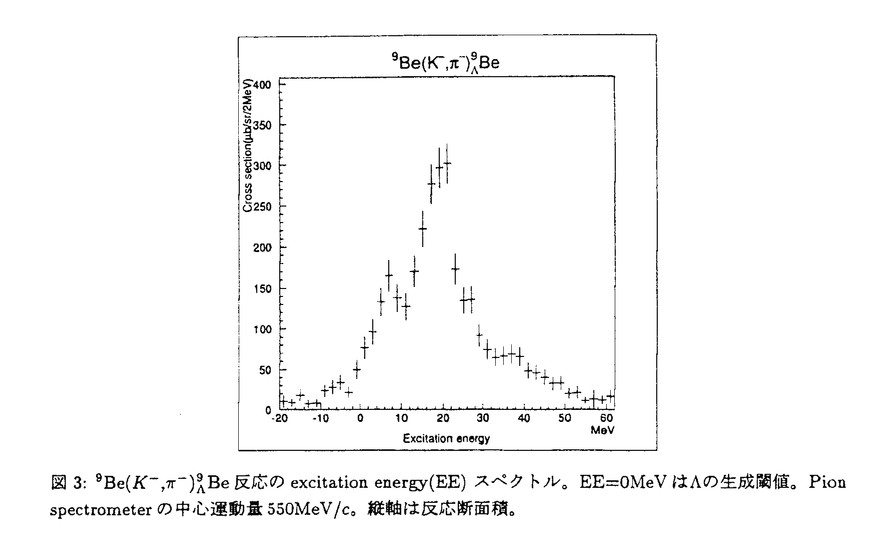 図3:9Be(K-, 図3:9Be(K-, -) -) 反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは 反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは の生成閾値。Pion spectrometerの中心運動量550MeV/c。縦軸は反応断面積。 の生成閾値。Pion spectrometerの中心運動量550MeV/c。縦軸は反応断面積。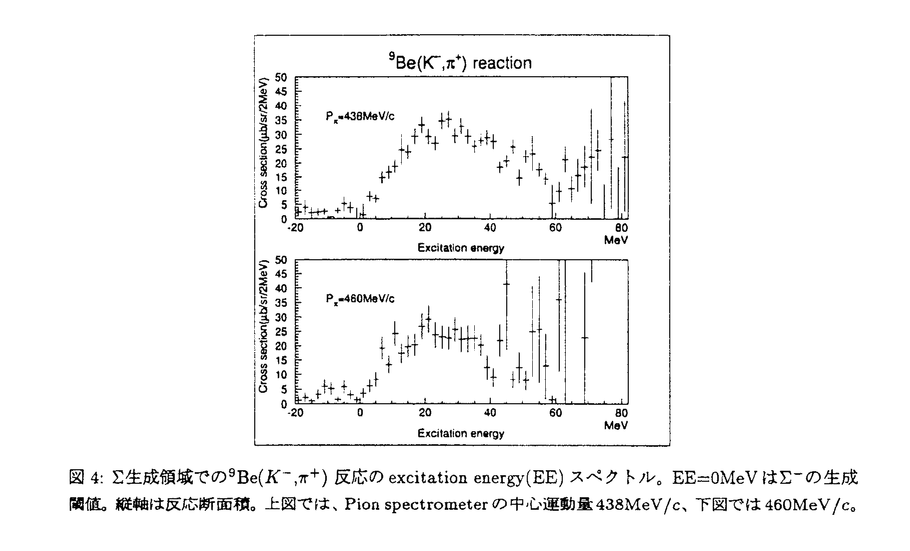 図4: 図4: 生成領域での9Be(K-, 生成領域での9Be(K-, +)反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは +)反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは -の生成閾値。縦軸は反応断面積。上図では、Pion spectrometerの中心運動量438MeV/c、下図では460MeV/c。 -の生成閾値。縦軸は反応断面積。上図では、Pion spectrometerの中心運動量438MeV/c、下図では460MeV/c。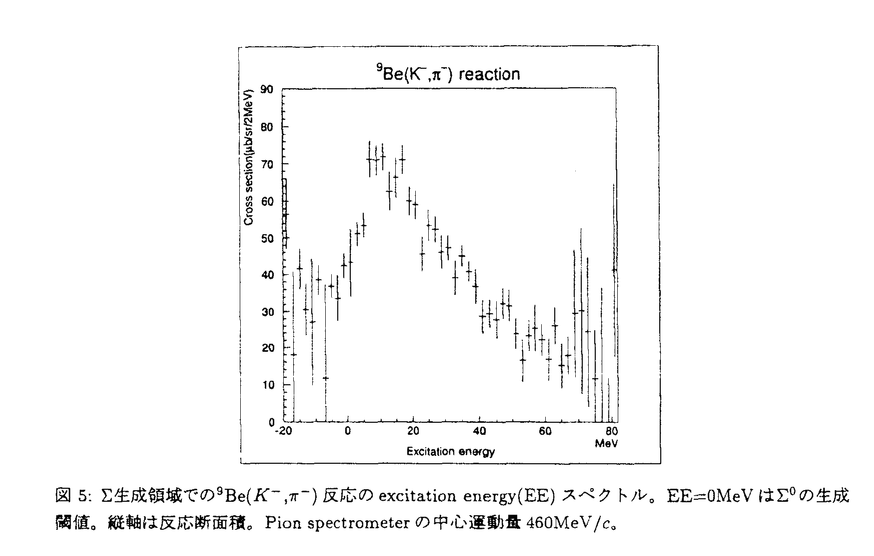 図5: 図5: 生成領域での9Be(K-, 生成領域での9Be(K-, -)反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは -)反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは 0の生成閾値。縦軸は反応断面積。Pion spectrometerの中心運動量460MeV/c。 0の生成閾値。縦軸は反応断面積。Pion spectrometerの中心運動量460MeV/c。  生成からの寄与を差し引いた後、EE=0MeVからEE=80MeVまでの領域をエネルギーで積分した断面積は、1157±86(statistical) 生成からの寄与を差し引いた後、EE=0MeVからEE=80MeVまでの領域をエネルギーで積分した断面積は、1157±86(statistical) (systematic) (systematic) b/srである。 b/srである。 4議論 CERNの実験と我々の実験では実験条件が異なる。この実験条件の差異を議論し、両者を直接比較してかまわないという結論を得た。CERNの のスペクトルと我々のスペクトルを比較するために、両者を重ねた図を示す(図.6参照)。両者を比較してみると全領域にわたってよく一致しているが、CERNのデータの2つの共鳴状態のあいだのへこみのところだけが我々の実験とあい入れない。我々の実験装置のエネルギー分解能は4.2MeV FWHMであり、彼らの巾8MeVのピークが検出できないことはありえない。さらに我々のデータの統計精度はCERNの実験の10倍あるので、CERNで報告された8MeVほどの狭い巾を持つ2つのピークは存在しないと結論出来る。 のスペクトルと我々のスペクトルを比較するために、両者を重ねた図を示す(図.6参照)。両者を比較してみると全領域にわたってよく一致しているが、CERNのデータの2つの共鳴状態のあいだのへこみのところだけが我々の実験とあい入れない。我々の実験装置のエネルギー分解能は4.2MeV FWHMであり、彼らの巾8MeVのピークが検出できないことはありえない。さらに我々のデータの統計精度はCERNの実験の10倍あるので、CERNで報告された8MeVほどの狭い巾を持つ2つのピークは存在しないと結論出来る。 次に9Be(K-, +)反応のスペクトルを見てみると、 +)反応のスペクトルを見てみると、 -の束縛領域にも非束縛領域にも何の構造もないことが分かる。 -の束縛領域にも非束縛領域にも何の構造もないことが分かる。 さらに、 の非束縛領域にある連続状態を準自由生成の見地から見て、スペクトルの議論を行った。ここではGal[10]らの導入した方法を用いた。詳しくは本論文を参照されたい。Galの方法は過去BNL、CERNで行われた の非束縛領域にある連続状態を準自由生成の見地から見て、スペクトルの議論を行った。ここではGal[10]らの導入した方法を用いた。詳しくは本論文を参照されたい。Galの方法は過去BNL、CERNで行われた ハイパー核の実験スペクトルを良く再現しているが、我々のデータはスペクトルの立ち上がりを再現することは出来なかった。さらなる理論的解析が必要であろう。 ハイパー核の実験スペクトルを良く再現しているが、我々のデータはスペクトルの立ち上がりを再現することは出来なかった。さらなる理論的解析が必要であろう。 5まとめ 我々は9Be核について(K-, -)、(K-, -)、(K-, +)反応を用いて +)反応を用いて ハイパー核の実験を行った。その結果過去のCERNの実験での2つの狭い巾の ハイパー核の実験を行った。その結果過去のCERNの実験での2つの狭い巾の の共鳴状態は発見されなかった。さらに、 の共鳴状態は発見されなかった。さらに、 粒子の準自由生成でexcitaion energyスペクトルを議論したが、(K-、 粒子の準自由生成でexcitaion energyスペクトルを議論したが、(K-、 )反応のスペクトルとも、準自由生成では説明出来なかった。より詳しい理論的解析が必要であろう。いずれにせよ、この実験データが )反応のスペクトルとも、準自由生成では説明出来なかった。より詳しい理論的解析が必要であろう。いずれにせよ、この実験データが 核子間の相互作用の理解に大いに役立つことは間違いない。 核子間の相互作用の理解に大いに役立つことは間違いない。 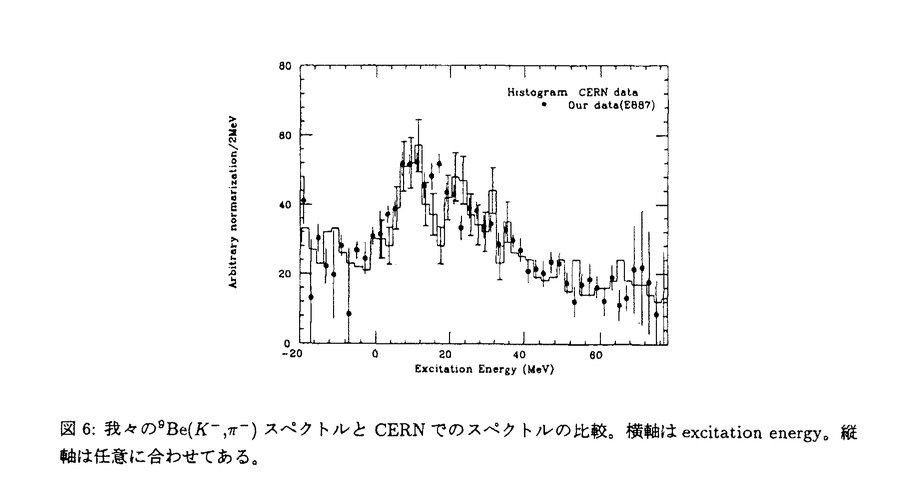 図6:我々の9Be(K-, 図6:我々の9Be(K-, -)スペクトルとCERNでのスペクトルの比較。横軸はexcitation energy。縦軸は任意に合わせてある。[1]R.Bertini et al.,Phys.Lett.B 90(1980)375.[2]C.J.Batty et al.,Nucl.Phys.A402(1983)349.[3]A.Gal and C.B.Dover,Phys.Rev.Lett.44(1980)379,962(E).[4]H.Piekarz et al.,Phys.Lett.B110(1982)428.[5]T.Yamazaki et al.,Phys.Rev.Lett.54(1985)428.[6]R.Bertini et al.,Phys.Lett.B136(1984)29.[7]R.Bertini et al.,Phys.Lett.B158(1985)19.[8]L.G.Tang et al.,Phys.Rev.C38(1988)846.[9]M.Iwasaki,doctoral dissertation,Univ.of Tokyo(1987),unpublished.[10]A.Gal,Proc.of 1986 INS Inter.Sympo.on Hypernuclear Physics(Tokyo Japan)31. -)スペクトルとCERNでのスペクトルの比較。横軸はexcitation energy。縦軸は任意に合わせてある。[1]R.Bertini et al.,Phys.Lett.B 90(1980)375.[2]C.J.Batty et al.,Nucl.Phys.A402(1983)349.[3]A.Gal and C.B.Dover,Phys.Rev.Lett.44(1980)379,962(E).[4]H.Piekarz et al.,Phys.Lett.B110(1982)428.[5]T.Yamazaki et al.,Phys.Rev.Lett.54(1985)428.[6]R.Bertini et al.,Phys.Lett.B136(1984)29.[7]R.Bertini et al.,Phys.Lett.B158(1985)19.[8]L.G.Tang et al.,Phys.Rev.C38(1988)846.[9]M.Iwasaki,doctoral dissertation,Univ.of Tokyo(1987),unpublished.[10]A.Gal,Proc.of 1986 INS Inter.Sympo.on Hypernuclear Physics(Tokyo Japan)31. |
| 審査要旨 | | 本論文は、9ΣBeハイパー核スペクトルを高統計で測定し、その結果を基にシグマ・ハイパー核の構造および生成過程を議論したものである。特に、1980年のCERNでの実験により信じられてきた9ΣBeハイパー核の存在を十倍以上の統計をもって再検証することを目指した研究である。 本論文は6章から成り、第1章は序文、第2章は実験の詳細、第3章は解析、第4章は結果、について述べている。第5章でデータに基づきCERNのデータとの比較、準自由生成模型によるスペクトルの検討をおこない、第6章において本論文のまとめをおこなっている。 原子核中の ハイペロンは強い相互作用による ハイペロンは強い相互作用による N→ N→ N反応のためラムダ・ハイペロンに転換する。したがって、シグマ・ハイパー核の幅は20-30MeVと非常に広く、ラムダ・ハイパー核の場合とは異なり、実験的に観測されることはないと考えられてきた。上記CERNの実験により、非束縛領域に狭いピークが認められたことは、こうした予測に反することであり、その後この狭いピークを説明するため様々な理論的解析が行われてきた。一方、最近の研究により実験的には、シグマハイパー核の存在は、この9ΣBeと東大グループによって精力的に研究が進められているHeシグマハイパー核を除いてはほぼ否定されたといえよう。このCERNで観測された9ΣBeについては、実験スペクトルが他にくらべて格段と信頼できる質を持っており、シグマ・ハイパー核を理解するために9ΣBeハイパー核の狭いピークを説明することは避けて通ることが出来なかった。そのため、より高統計かつ質の高い再実験によってその存否を明確にすること強く望まれていた。 N反応のためラムダ・ハイペロンに転換する。したがって、シグマ・ハイパー核の幅は20-30MeVと非常に広く、ラムダ・ハイパー核の場合とは異なり、実験的に観測されることはないと考えられてきた。上記CERNの実験により、非束縛領域に狭いピークが認められたことは、こうした予測に反することであり、その後この狭いピークを説明するため様々な理論的解析が行われてきた。一方、最近の研究により実験的には、シグマハイパー核の存在は、この9ΣBeと東大グループによって精力的に研究が進められているHeシグマハイパー核を除いてはほぼ否定されたといえよう。このCERNで観測された9ΣBeについては、実験スペクトルが他にくらべて格段と信頼できる質を持っており、シグマ・ハイパー核を理解するために9ΣBeハイパー核の狭いピークを説明することは避けて通ることが出来なかった。そのため、より高統計かつ質の高い再実験によってその存否を明確にすること強く望まれていた。 本研究では、米国ブルックヘブン国立研究所にあるAGS陽子加速器を用い、高強度負K中間子ビームをベリリューム標的に照射して、ラムダ・ハイペロン、シグマ・ハイペロン生成に対応する運動量の正負パイ中間子を磁気スペクトロメータで測定、分析した。具体的には、9Be(K-, -) -) 反応、シグマ・ハイペロン生成領域での9Be(K-, 反応、シグマ・ハイペロン生成領域での9Be(K-, -)反応、シグマ・ハイペロン生成領域での9Be(K-, -)反応、シグマ・ハイペロン生成領域での9Be(K-, +)反応について高統計スペクトルが得られた。CERNの実験でシグマ・ハイパー核が観測されたとされている9Be(K-, +)反応について高統計スペクトルが得られた。CERNの実験でシグマ・ハイパー核が観測されたとされている9Be(K-, -)反応の10倍の統計を持つスペクトルでは、スペクトル全体の形は良く一致しているものの幅8MeVのピークは検出できなかった。本論文では実験のエネルギー分解能が4.2MeVであること、統計が10倍あることを考慮すると、このシグマハイパー核のピークが本実験で観測されないことはあり得ないと主張した。さらに、実験の運動学的条件が若干異なることについても検討を加え、ピークの検出について影響を与えないことも示した。結論として、CERNで観測されたと報告された2つの狭い -)反応の10倍の統計を持つスペクトルでは、スペクトル全体の形は良く一致しているものの幅8MeVのピークは検出できなかった。本論文では実験のエネルギー分解能が4.2MeVであること、統計が10倍あることを考慮すると、このシグマハイパー核のピークが本実験で観測されないことはあり得ないと主張した。さらに、実験の運動学的条件が若干異なることについても検討を加え、ピークの検出について影響を与えないことも示した。結論として、CERNで観測されたと報告された2つの狭い の共鳴状態は観測されなかった。 の共鳴状態は観測されなかった。 また、シグマ・ハイペロンの非束縛領域にある連続状態を準自由生成反応模型に基づき計算し、今回得られた9Be(K-, -)、9Be(K-, -)、9Be(K-, +)反応のスペクトルとの比較も行われた。連続状態が始まる領域で、計算されたスペクトルは実験スペクトルと一致せず、 +)反応のスペクトルとの比較も行われた。連続状態が始まる領域で、計算されたスペクトルは実験スペクトルと一致せず、 N相互作用に関する情報を与えていると考えられる。 N相互作用に関する情報を与えていると考えられる。 このように、本論文は、これまで原子核内における N相互作用に関して、強い制約を加えてきた9ΣBeのピークを否定したものである。また、準自由シグマ生成反応スペクトルを与えたものであり、シグマ・ハイパー核研究への貢献は大きい。この結果のストレンジネス核物理に与える影響は非常に深い。従って、審査委員一同、本論文は博士(理学)学位論文として合格であると判定する。 N相互作用に関して、強い制約を加えてきた9ΣBeのピークを否定したものである。また、準自由シグマ生成反応スペクトルを与えたものであり、シグマ・ハイパー核研究への貢献は大きい。この結果のストレンジネス核物理に与える影響は非常に深い。従って、審査委員一同、本論文は博士(理学)学位論文として合格であると判定する。 なお、本実験は、BNL-AGS・E887共同実験として行われたものである。論文提出者はこの実験の中心メンバーとして参加し、データ解析を自ら詳細にわたり行ったものであり、論文提出者の寄与は十分と認められる。 |
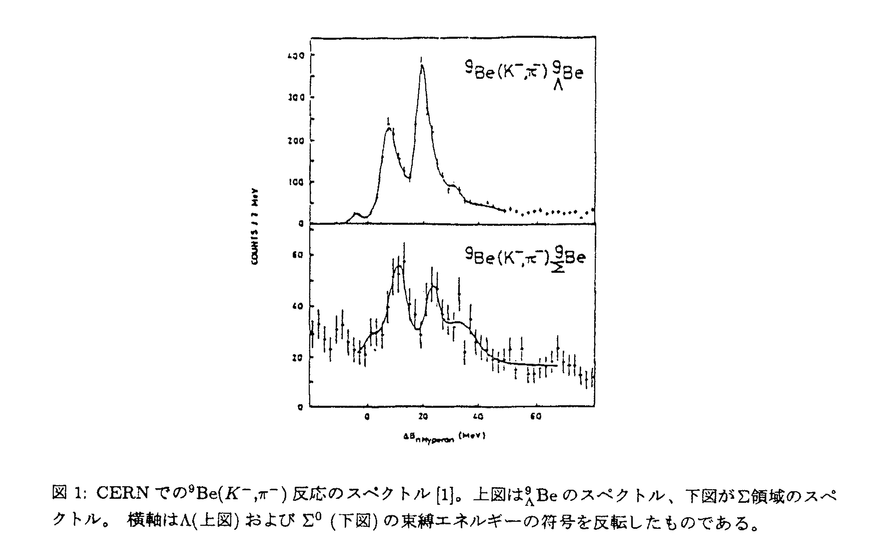
 -)反応のスペクトル[1]。上図は
-)反応のスペクトル[1]。上図は のスペクトル、下図が
のスペクトル、下図が 領域のスペクトル。横軸は
領域のスペクトル。横軸は (上図)および
(上図)および 0(下図)の束縛エネルギーの符号を反転したものである。
0(下図)の束縛エネルギーの符号を反転したものである。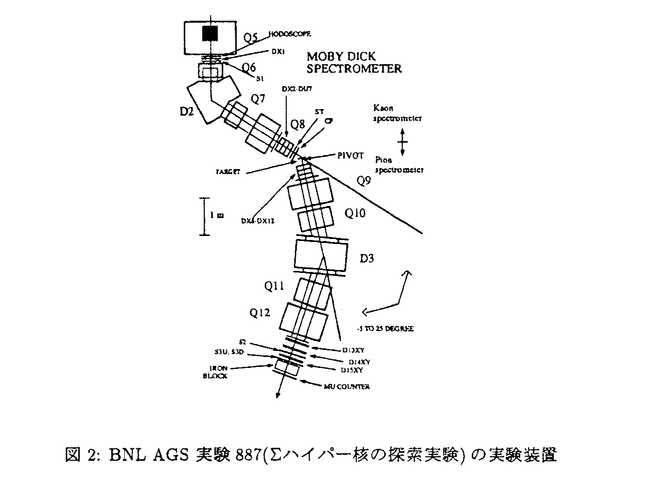
 ハイパー核の探索実験)の実験装置
ハイパー核の探索実験)の実験装置 -)
-) 反応
反応 生成領域での9Be(K-,
生成領域での9Be(K-, +)反応
+)反応 生成領域での9Be(K-,
生成領域での9Be(K-, -)反応
-)反応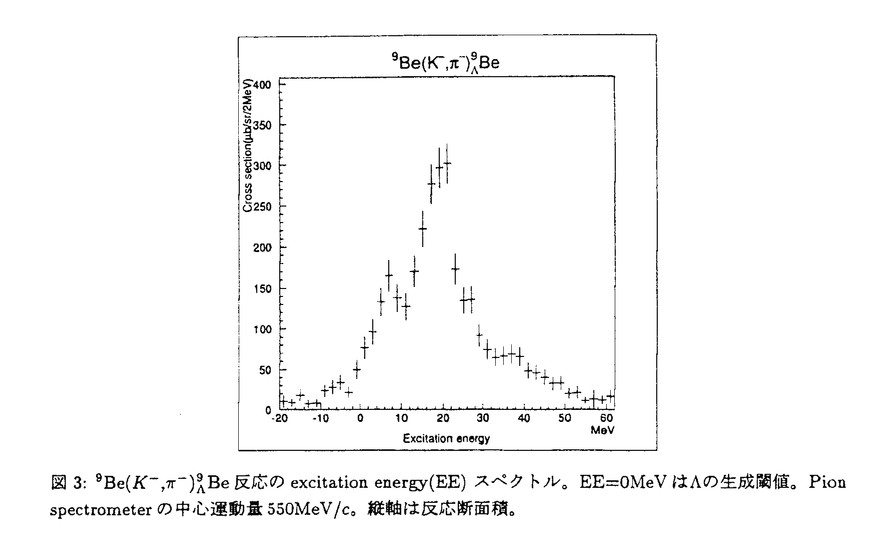
 -)
-) 反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは
反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは の生成閾値。Pion spectrometerの中心運動量550MeV/c。縦軸は反応断面積。
の生成閾値。Pion spectrometerの中心運動量550MeV/c。縦軸は反応断面積。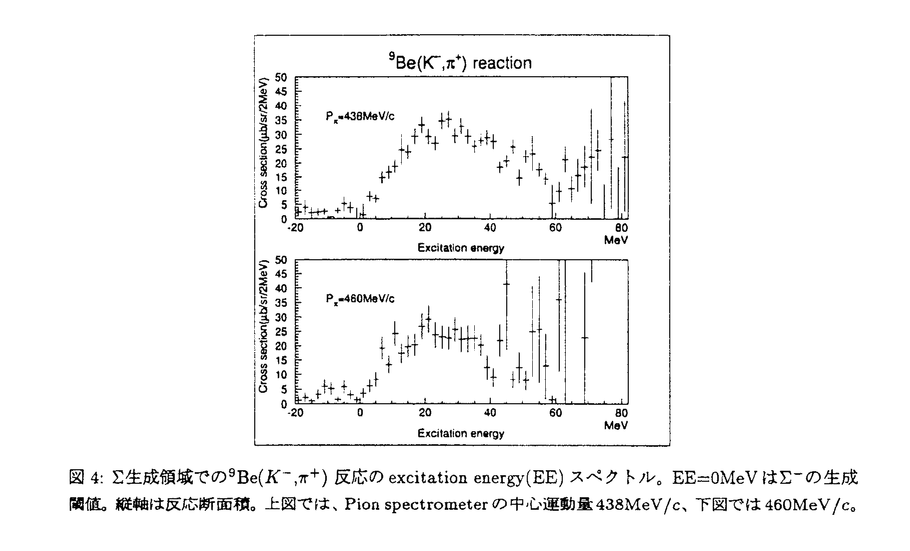
 生成領域での9Be(K-,
生成領域での9Be(K-, +)反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは
+)反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは -の生成閾値。縦軸は反応断面積。上図では、Pion spectrometerの中心運動量438MeV/c、下図では460MeV/c。
-の生成閾値。縦軸は反応断面積。上図では、Pion spectrometerの中心運動量438MeV/c、下図では460MeV/c。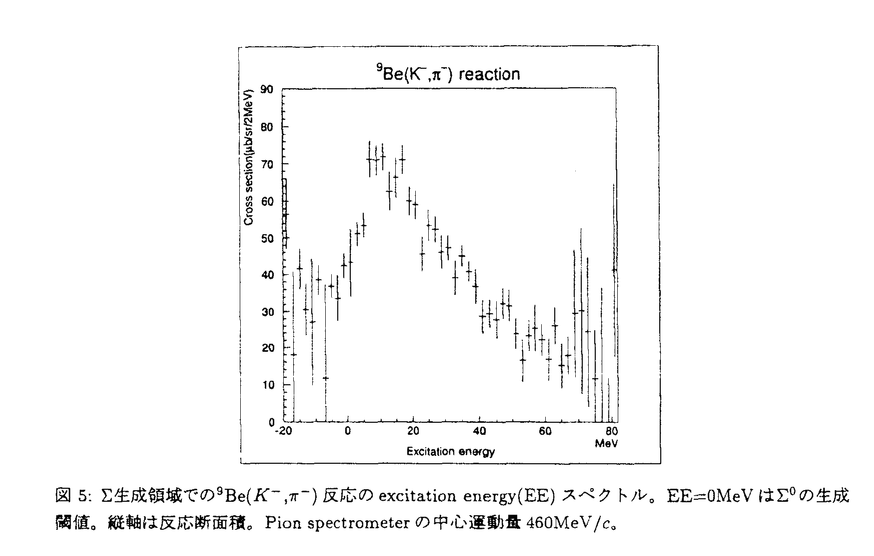
 生成領域での9Be(K-,
生成領域での9Be(K-, -)反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは
-)反応のexcitation energy(EE)スペクトル。EE=0MeVは 0の生成閾値。縦軸は反応断面積。Pion spectrometerの中心運動量460MeV/c。
0の生成閾値。縦軸は反応断面積。Pion spectrometerの中心運動量460MeV/c。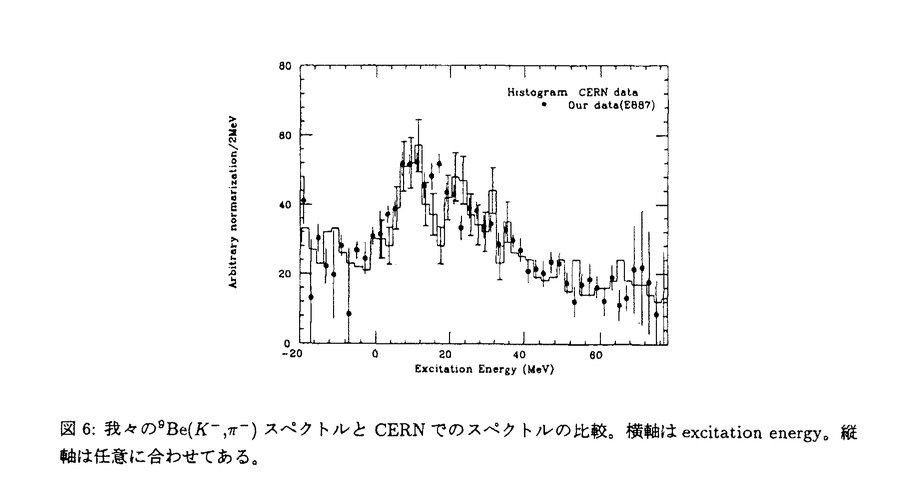
 -)スペクトルとCERNでのスペクトルの比較。横軸はexcitation energy。縦軸は任意に合わせてある。
-)スペクトルとCERNでのスペクトルの比較。横軸はexcitation energy。縦軸は任意に合わせてある。 )、7Li(K-,
)、7Li(K-, 粒子はバックグラウンドとなるため、
粒子はバックグラウンドとなるため、 (systematic)
(systematic) である。
である。 (systematic)
(systematic) (systematic)
(systematic) のスペクトルと我々のスペクトルを比較するために、両者を重ねた図を示す(図.6参照)。両者を比較してみると全領域にわたってよく一致しているが、CERNのデータの2つの共鳴状態のあいだのへこみのところだけが我々の実験とあい入れない。我々の実験装置のエネルギー分解能は4.2MeV FWHMであり、彼らの巾8MeVのピークが検出できないことはありえない。さらに我々のデータの統計精度はCERNの実験の10倍あるので、CERNで報告された8MeVほどの狭い巾を持つ2つのピークは存在しないと結論出来る。
のスペクトルと我々のスペクトルを比較するために、両者を重ねた図を示す(図.6参照)。両者を比較してみると全領域にわたってよく一致しているが、CERNのデータの2つの共鳴状態のあいだのへこみのところだけが我々の実験とあい入れない。我々の実験装置のエネルギー分解能は4.2MeV FWHMであり、彼らの巾8MeVのピークが検出できないことはありえない。さらに我々のデータの統計精度はCERNの実験の10倍あるので、CERNで報告された8MeVほどの狭い巾を持つ2つのピークは存在しないと結論出来る。