近年、高強度の重イオン加速器を利用した不安定核ビーム生成技術が発展し、広範囲の不安定核領域の研究が可能となってきた。なかでもドリップライン付近の原子核は、中性子と陽子の比が極端に異なる高アイソスピン核であること、束縛エネルギーが通常の核より極端に小さいことから、これまでの安定核付近の原子核にはみられない性質や現象を内包している可能性があり、関心を集めている。実際、最近の不安定核ビームを用いた研究によって、11Liや11Beといった軽い中性子ドリップライン付近の原子核が中性子ハローと呼ばれる特異な構造をもっていることがわかってきた。中性子ハロー構造は、通常の飽和した原子核密度をもつコア部と、中性子だけからなる希薄な外縁部、いわゆる中性子ハロー部からなる二重構造によって特徴づけられる。 中性子ハロー構造を持つ原子核(以後中性子ハロー核と呼ぶ)の基底状態の特異性は、反応機構や励起モードの性質にも反映される可能性がある。様々な原子核応答を支配している巨大共鳴の特性のあり方は特に興味深い。通常の原子核では,電磁気的励起、あるいはスピン、アイソスピン励起に対して、構成核子がコヒーレントに運動した共鳴状態を形成することが知られている。例えば原子核のE1応答に対しては、中性子流体と陽子流体が逆位相で振動するE1巨大共鳴状態(励起エネルギー=80A-1/3)に強度が集中する。一方、中性子ハロー核の励起では、中性子ハロー部の核子はコアから空間的に分離しているためにコアの運動に追随できず、このコヒーレンス性が破られる可能性がある。実際、11Liの場合、励起エネルギー約1MeVという通常では考えられない低エネルギー非束縛領域に1W.uものE1とおぼしき強度が集中的に現れることが、クーロン分解反応実験により認められている。この現象について、以下の様に2種類の相対立するモデルが提出された。すなわち、第一のモデルによると、この現象はソフトE1共鳴状態と呼ばれる共鳴準位の励起に対応するもので、この共鳴は中性子ハロー部とコア部の間のゆるやかな振動モードであり、E1強度の一部がコヒーレンス性の破れによって低い励起エネルギーにとどまったものであると説明される。一方のモデルでは、このE1遷移は共鳴状態の形成を伴わない直接分解反応であると考えられ、低励起エネルギーE1強度の発現は基底状態のハロー部の空間的拡がりがもたらす性質であると解釈される。上記どちらの反応機構によるものか、これまでの11Liによる研究では解明できていない。この区別は、後述するように、単に反応機構そのものの性質の決定という点にとどまらず,クーロン励起や逆反応のスペクトロスコピー的側面や,また中性子ハロー核の動的性質への影響という点でも,重要な意味を持っている。 本論文の主要目的は、11Be(72MeV/u)+Pb反応を用いたクーロン分解反応実験によって、中性子ハロー核における低励起エネルギー非束縛領域へのE1的遷移の発現機構を明らかにすることにある。そのためには構造が単純でよく理解されている原子核を利用するのが適切であるが,11Beはまさにその条件に適した稀有な中性子ハロー核である。すなわち,11Beの基底状態( =1/2+)の主要成分は、10Beコアと1個のS-波中性子(分離エネルギー504±6keV)から構成される単純な構造をもち、1個の中性子がハローを形成しており11Liで問題となる2ハロー中性子間の相関に起因する不明瞭性を含まない。本研究では、まず、放出粒子の角度分布によって、励起モードがE1であることを実験的に確認し、さらにB(E1)のエネルギースペクトルから低励起エネルギーE1遷移の発現機構を明らかにすることを目指す。また、クーロン分解で問題となるクーロン加速効果についても調べ、中性子ハロー核のクーロン励起の性質を総合的に解明することを目的としている。 =1/2+)の主要成分は、10Beコアと1個のS-波中性子(分離エネルギー504±6keV)から構成される単純な構造をもち、1個の中性子がハローを形成しており11Liで問題となる2ハロー中性子間の相関に起因する不明瞭性を含まない。本研究では、まず、放出粒子の角度分布によって、励起モードがE1であることを実験的に確認し、さらにB(E1)のエネルギースペクトルから低励起エネルギーE1遷移の発現機構を明らかにすることを目指す。また、クーロン分解で問題となるクーロン加速効果についても調べ、中性子ハロー核のクーロン励起の性質を総合的に解明することを目的としている。 本実験で決定すべきスペクトルは、入射11Beの運動量ベクトルと共に、クーロン分解反応において放出される10Beと中性子の運動量ベクトルを同時に完全測定することにより初めて求められるものである。すなわち、放出粒子の11Be静止系での角度分布は放出粒子の運動量ベクトルを11Be静止系へのローレンツ変換することにより求められ、B(E1)励起エネルギースペクトルは放出される2粒子の運動量からその不変質量を導出することにより求められる。この不変質量法は二次ビームの強度の弱さや分解能の悪さを補う特長を持っている。実験は、理化学研究所の不安定核ビームラインRIPSにおいて生成された平均エネルギー72MeV/uの11Beビームを用いて行った。クーロン分解後放出される10Beの粒子識別及び運動量ベクトルは大立体角電磁スペクトロメータによって、また中性子の運動量ベクトルは80本のプラスチックホドスコープにより位置と飛行時間を測定することにより求めた。 実験の結果得られた、11Be静止系における放出粒子10Beの角度分布を図1に示す。図中の曲線はE1励起に対する理論計算の結果であり良い一致を示している。この結果から、11Beのクーロン励起が確かにE1励起であることが証明された。 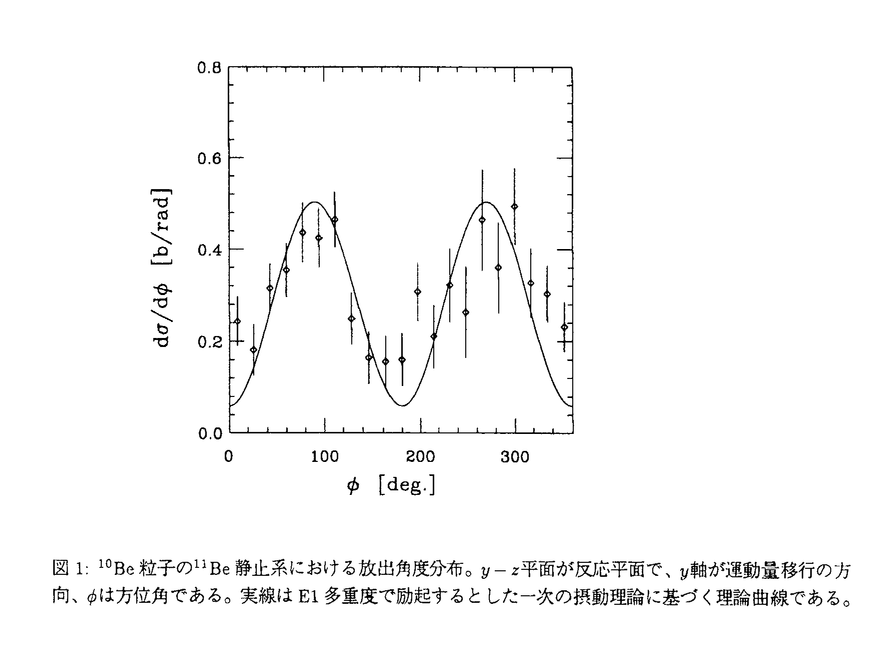 図1:10Be粒子の11Be静止系における放出角度分布。y-z平面が反応平面で、y軸が運動量移行の方向、 図1:10Be粒子の11Be静止系における放出角度分布。y-z平面が反応平面で、y軸が運動量移行の方向、 は方位角である。実線はE1多重度で励起するとした一次の摂動理論に基づく理論曲線である。 は方位角である。実線はE1多重度で励起するとした一次の摂動理論に基づく理論曲線である。 次にB(E1)励起エネルギースペクトルdB(E1)/dExの実験結果について述べる。このスペクトルはクーロン分解反応断面積のエネルギースペクトルから、仮想光子の理論を用いた解析により求められる。仮想光子理論適用の正当性については、付随的に本実験とは別に行なわれた11Beの第一励起状態( =1/2-)へのクーロン励起実験により確認されている。得られたスペクトルを図2に示す。図に見られるように、励起エネルギーEx=約800keV付近に4.0±0.9W.u.というE1としては非常に顕著なピークが現れる。このピークは11Liにみられたピークと類似しており、低励起エネルギーE1遷移が中性子ハロー核に普遍的に現れるものであることを示唆している。 =1/2-)へのクーロン励起実験により確認されている。得られたスペクトルを図2に示す。図に見られるように、励起エネルギーEx=約800keV付近に4.0±0.9W.u.というE1としては非常に顕著なピークが現れる。このピークは11Liにみられたピークと類似しており、低励起エネルギーE1遷移が中性子ハロー核に普遍的に現れるものであることを示唆している。 このスペクトルに対し直接分解反応モデルに基づく解析を行なった。直接分解反応では、その遷移確率は湯川型の波動関数を持つ基底状態が、E1のオペレーターを介し、10Beと中性子の相対運動量qを持つ平面波を終状態とする行列要素によって表され、次の様に簡単な形で書ける。 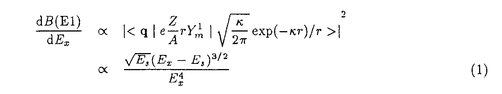 ここで、スペクトルの形が中性子の分離エネルギーEsのみの関数であることに注目したい。全B(E1)強度はEsに反比例し、またピークが励起エネルギーEx=8/5Esの位置に現れるので、Esが小さい程低励起エネルギーにE1強度が集中することになる。Esとして11Beの中性子分離エネルギー504keVをとって、強度のみを自由パラメータとしてフィッテイングを行なったのが図2の実線であり、非常に良い一致が見られる。このことは、ハロー核に現れる低励起エネルギーE1遷移が、直接分解反応を主要な過程としていることを示している。 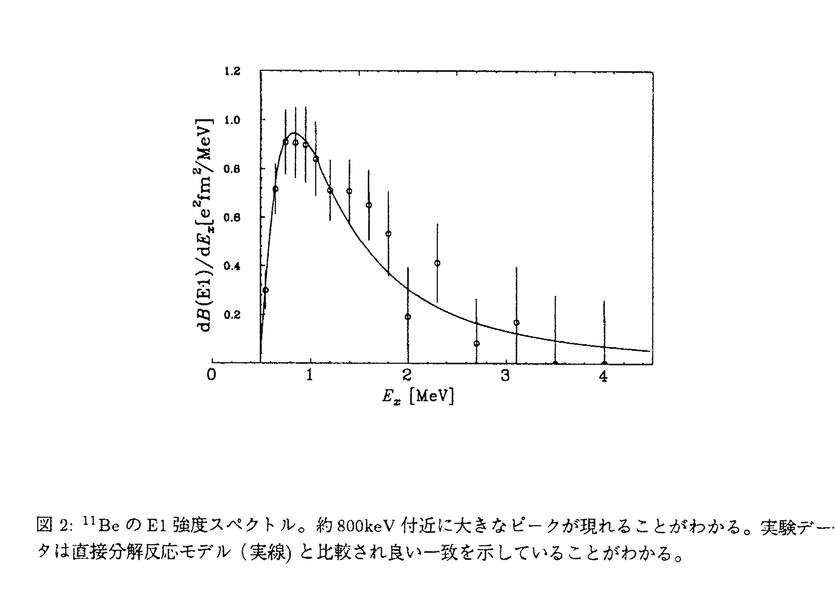 図2:11BeのE1強度スペクトル。約800keV付近に大きなピークが現れることがわかる。実データは直接分解反応モデル(実線)と比較され良い一致を示していることがわかる。 図2:11BeのE1強度スペクトル。約800keV付近に大きなピークが現れることがわかる。実データは直接分解反応モデル(実線)と比較され良い一致を示していることがわかる。 この過程が直接分解反応である場合、分解は励起と同時にほぼ標的核付近で起こることになる。その時、標的核の遠距離力的クーロン力のために、結果的に、入射11Beの速度に対して10Beは加速され中性子は減速されることになる。図3は放出粒子10Beと中性子の縦方向運動量分布を11Be重心系の散乱角( 衝突係数の逆数)についてプロットしたものである。実験結果は10Beと中性子それぞれに対し、直接分解反応に対する半古典的クーロン加速モデルの予想する線(図中実線)に沿っていることがわかった。従って、この結果も直接分解反応とコンシステントであると言える。 衝突係数の逆数)についてプロットしたものである。実験結果は10Beと中性子それぞれに対し、直接分解反応に対する半古典的クーロン加速モデルの予想する線(図中実線)に沿っていることがわかった。従って、この結果も直接分解反応とコンシステントであると言える。 以上ように、本実験の結果、11Beにおいても低励起エネルギーE1遷移の巨大なピークが現れ、この遷移がE1の直接分解反応であるとするモデルと完全に合致することがわかった。すなわち、中性子ハロー核のクーロン分解はE1直接分解反応が重要な役割をなしていることが証明されたと言える。実際、我々は、その後11Liのクーロン分解反応について、本論文のこの結果をふまえた解析を行い、直接分解反応で説明することに成功した。一方、我々は、この様なクーロン分解反応の機構は、逆反応である中性子捕獲反応にも適用されることを指摘した。例えば、天体核反応で重要な、12Cの1中性子捕獲反応はこの原理で反応断面積が高められることを予想した。一方、本実験の結果、この反応が核構造解析に応用できることがわかった。すなわち、直接分解反応では、B(E1)スペクトルが式1のように表せるので、その強度から、基底状態の殻模型構造が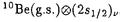 であるスペクトロスコピック因子を求めることが可能となる。実際、本実験で得られたスペクトロスコピック因子は、基底状態が球形であることを仮定すると、0.95±0.2である。この方法は将来、19Cや14Bのスペクトロスコピーに応用できるであろうと思われる。この様に、本論で試みたソフトE1励起機構の様々な解明は、中性子ハロー核の動的な性質を理解する上で重要な基盤を提示するものと考えられる。 であるスペクトロスコピック因子を求めることが可能となる。実際、本実験で得られたスペクトロスコピック因子は、基底状態が球形であることを仮定すると、0.95±0.2である。この方法は将来、19Cや14Bのスペクトロスコピーに応用できるであろうと思われる。この様に、本論で試みたソフトE1励起機構の様々な解明は、中性子ハロー核の動的な性質を理解する上で重要な基盤を提示するものと考えられる。 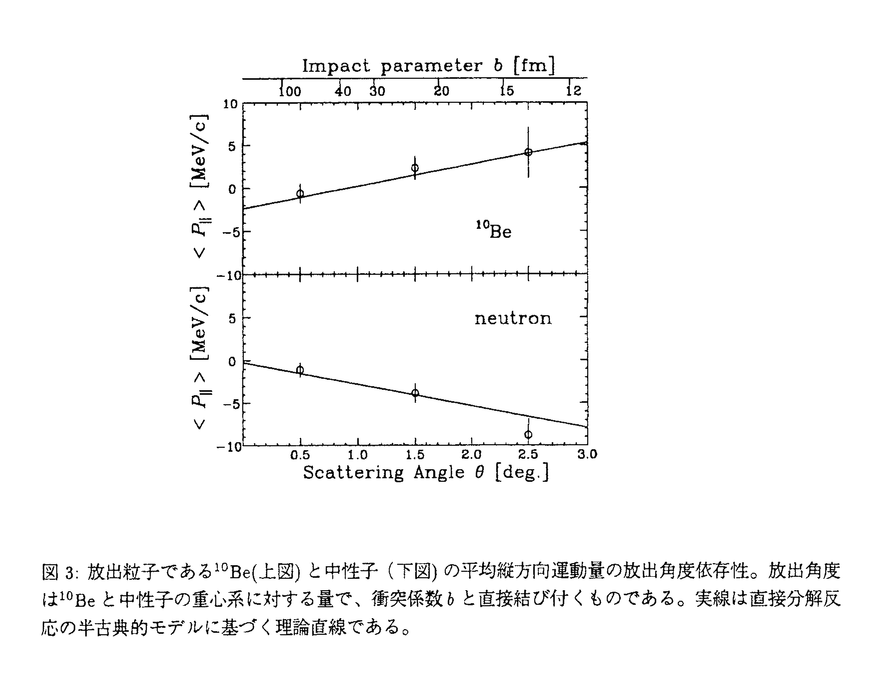 図3:放出粒子である10Be(上図)と中性子(下図)の平均縦方向運動量の放出角度依存性。放出角度は10Beと中性子の重心系に対する量で、衝突係数bと直接結び付くものである。実線は直接分解反応の半古典的モデルに基づく理論直線である。 図3:放出粒子である10Be(上図)と中性子(下図)の平均縦方向運動量の放出角度依存性。放出角度は10Beと中性子の重心系に対する量で、衝突係数bと直接結び付くものである。実線は直接分解反応の半古典的モデルに基づく理論直線である。 |