近年、有機物、例えば層間化合物や低次元物質の研究が盛んに行なわれ、超伝導や擬一次元伝導体における様々な性質など、豊富な物性が観測されてきた。 鎖状のアセン系列の有機物はドーピングに重要と思われるバンドギャップや電子親和力などの量をベンゼン環の数を変えることで、パラメーターとして制御できる。ペンタセン(PEN)はアクセプターもドナーもドープできる母体として適当な位置にあると思われる。既にヨウ素ドープしたペンタセン薄膜の抵抗が測定されており、ドープ前は絶縁体(伝導が約10-8S/cm)であるが、ドープにより伝導は約150S/cmになり、大きな異方性(108)もあることが知られていた。240K以上では伝導の温度依存性が半導体的であり、240K以下では金属的である。これが金属非金属転移であると予想されているが、そのメカニズムが不明であり、高温では半導体、低温で金属になるという非常に珍しいものである。 我々はこの振る舞いをより詳しく調べるため、またアルカリ金属ドープも行って、その性質を初めて広い温度域において調べるために、電子状態のミクロなプローブとしてESR(電子スピン共鳴法)、及びSQUID(超伝導量子干渉計)装置による帯磁率を測定した。 ESR、NMR(核磁気共鳴法)に用いた試料は、粒状(微結晶)のペンタセンで、これに、ヨウ素やカリウムを飽和ドープしたものである。得られた試料の組成はPEN1l2.5-2.7とPEN1K3.6である。 ESRは2つの著しく異なる周波数領域で行った。X-バンド9.3GHzのESRの測定温度域は300K〜4Kであり、7.7MHzにおけるESRは3He-4He希釈冷凍機を用いて最低温度50mKまで測定した。 静帯磁率測定も300K-2K、そして3He-4He希釈冷凍機を用いて最低温度40mKまで測定した。絶対スピン帯磁率を求めるためにESR/NMRを測定した。 (1)ヨウ素ドープした試料について: 240K以上では伝導の温度依存性は半導体的であり、240K以下では金属的であったが、一方、ESRのスピン帯磁率、また、静帯磁率は240Kで変化しなかった。つまりフェルミ面における状態密度は240Kを境に変化していない。このことより金属と非金属の間の転移が起こっているとは考えにくい。 最も特徴的な実験結果として、図1に示すように、gシフトについて大きな温度依存性が観測された。このような挙動は珍しく、gシフトがそのような温度依存性を持つメカニズムは説明できなかった。 gシフト g、及びESR吸収線幅dHにおいて共に、抵抗と同様に240Kにおいて温度依存性の変化が観測された(図1)。ここで仮に、温度の全域においてエリオットの緩和機構 g、及びESR吸収線幅dHにおいて共に、抵抗と同様に240Kにおいて温度依存性の変化が観測された(図1)。ここで仮に、温度の全域においてエリオットの緩和機構  が有効であるとして、実験結果から緩和時間 Rを計算した結果、抵抗の特徴的な温度依存性と定性的に似た振る舞いを示した。つまり、スピン帯磁率の結果も考え合わせると、伝導の振舞いが金属非金属転移によるのでなく、電子の散乱による緩和時間が240Kで何等かの原因で極小を持つことによる可能性があると考えられる。散乱による緩和時間がこのような極小を持つことを説明する可能性として、ペンタセン分子の熱振動運動や、何等かの構造相転移(インターカレントの安定な配置の変化など)に関係していることが考えられる。 Rを計算した結果、抵抗の特徴的な温度依存性と定性的に似た振る舞いを示した。つまり、スピン帯磁率の結果も考え合わせると、伝導の振舞いが金属非金属転移によるのでなく、電子の散乱による緩和時間が240Kで何等かの原因で極小を持つことによる可能性があると考えられる。散乱による緩和時間がこのような極小を持つことを説明する可能性として、ペンタセン分子の熱振動運動や、何等かの構造相転移(インターカレントの安定な配置の変化など)に関係していることが考えられる。 (2)カリウムドープした試料について: X線回折の測定により、カリウムドープによって格子定数の変化が認められ、その大きさから、PEN分子の並んだ層間に挿入されるヨウ素の場合に比べ、よりPEN分子の間に挿入されていることが示唆された。 ESRにおいて、吸収信号に2つの成分が観測された:線幅のシャープなもの(室温で約0.8G)とその幅の約3倍のものである。微量な空気を導入した試料の測定結果との比較などから、鋭い方の成分が酸化に起因するもの--例えば酸素によってピン止めされたスピン--であり、広い方の成分のみがカリウムドープに本質的に因るものであることが分かった。 次に、ESRをより低温まで測定した結果、線幅、及びスピン帯磁率が0.2K以下において急激に小さくなった(図2)ので、0.2Kにおいて何らかの転移が起こり、最低温度までに広い方の信号がほぼ消えてなくなっていると考えられる。これを説明するのに超伝導転移や、パイエルス転移や、強磁性的な転移なども考えられるが、図3に示すように、超伝導転移に期待される静帯磁率やQ値の変化が観測されなかったこと、パイエルス転移に期待される静帯磁率の変化や1次元性を示すESR線幅の周波数依存性が見られなかったこと、そして強磁性的な転移に期待される静帯磁率の増加やESR線幅が狭まることが観察されなかったことより、以上の可能性は除外される。それらの結果と、Xバンドにおいて広い信号が低温側においてキュリーワイス則に従い、漸近キュリー温度 が負であることや、0.2K直上の静帯磁率もやはりキュリーワイス則に従い、 が負であることや、0.2K直上の静帯磁率もやはりキュリーワイス則に従い、 が負であること、を考え合わせると、反強磁性的な転移であると結論できる。 が負であること、を考え合わせると、反強磁性的な転移であると結論できる。 更に、静帯磁率の測定によって上記の反強磁性的転移温度が磁場の増大に対し、250G近傍で0Kに近づいた。この臨界磁場は局在モーメントの場合に期待されるものより1桁以上低いこと、及び、局在モーメントを仮定してキュリーワイス則から見積もったスピンの数が、飽和モーメントから見積もったスピンの数の約3倍であること、を考えると、この転移が遍歴電子系における反強磁性転移であると考えられる。 しかし、温度ヒステリシス(図4)、及び磁場ヒステリシスが観測され、通常の反強磁性転移ではない特徴を持つものであった。 まとめると、ペンタセンに対し、アクセプターであるヨウ素だけでなく、ドナーであるアルカリ金属(カリウム)のドープも行った結果、著しく異なる物性を示した。 ヨウ素ドープの場合は、散乱をミクロな面から見ることにより、抵抗の特徴的な温度依存性は、従来から考えられていた金属非金属転移によるものではないことを明らかにし、電子の散乱時間が240Kで極小を持つことに起因すると解釈できる。そうした振る舞いの原因として、ペンタセン分子の熱振動励起や構造相転移などが考えられる。 カリウムドープ試料において、ESRや静帯磁率測定における顕著な振る舞いの変化から、0.2Kにおいて反強磁性的な転移が起きていることを見い出した。アルカリドープした 電子系でこのような転移が観測されるのは初めてである。 電子系でこのような転移が観測されるのは初めてである。 また、この転移は、単純な反強磁性的な転移にはない上に挙げたような特異な特徴を持ち、新しい磁気転移が起っている可能性がある。 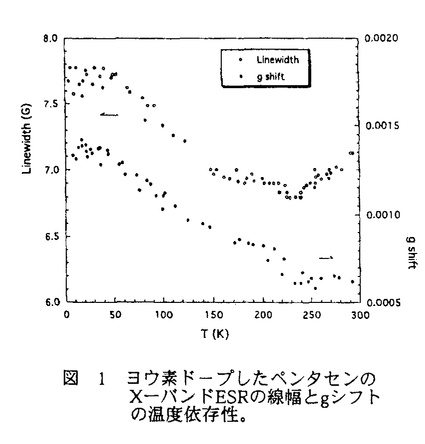 図1 ヨウ素ドープしたペンタセンのX-バンドESRの線幅とgシフトの温度依存性。 図1 ヨウ素ドープしたペンタセンのX-バンドESRの線幅とgシフトの温度依存性。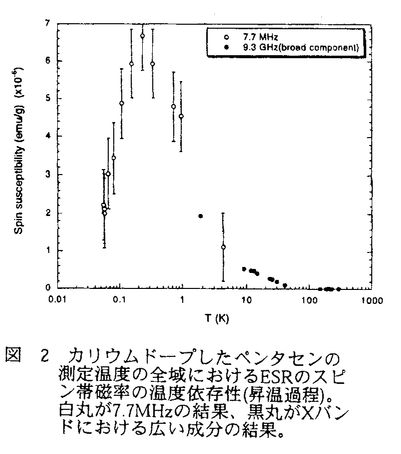 図2 カリウムドープしたペンタセンの測定温度の全域におけるESRのスピン帯磁率の温度依存性(昇温過程)。白丸が7.7MHzの結果、黒丸がXバンドにおける広い成分の結果。 図2 カリウムドープしたペンタセンの測定温度の全域におけるESRのスピン帯磁率の温度依存性(昇温過程)。白丸が7.7MHzの結果、黒丸がXバンドにおける広い成分の結果。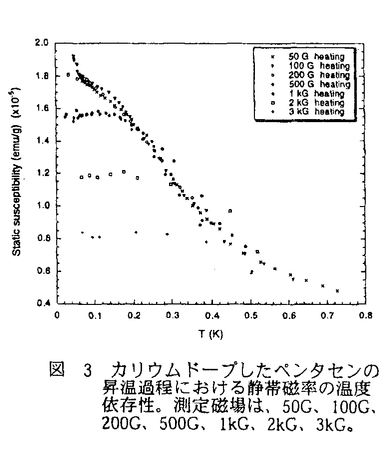 図3 カリウムドープしたペンタセンの昇温過程における静帯磁率の温度依存性。測定磁場は、50G、100G、200G、500G、1kG、2kG、3kG。 図3 カリウムドープしたペンタセンの昇温過程における静帯磁率の温度依存性。測定磁場は、50G、100G、200G、500G、1kG、2kG、3kG。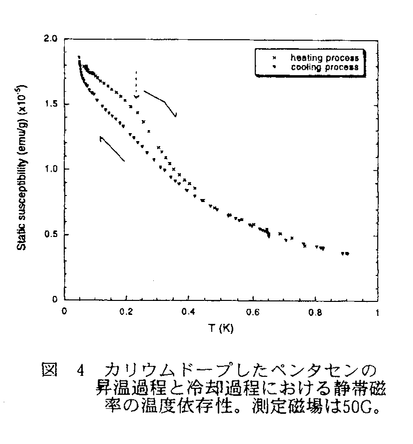 図4 カリウムドープしたペンタセンの昇温過程と冷却過程における静帯磁率の温度依存性。測定磁場は50G。 図4 カリウムドープしたペンタセンの昇温過程と冷却過程における静帯磁率の温度依存性。測定磁場は50G。 |