最近、低エネルギー宇宙線反陽子( )の観測において、大きな進展があった。今まで、流速の上限値しか得られていなかった運動エネルギー500MeV以下の領域において、BESS実験(Balloon-borne Experiment with a Superconducting Solenoidal magnet Spectrometer)が数例の反陽子観測に成功した。宇宙線反陽子は通常、二次生成によるものと考えられており、銀河系内を伝播する一次宇宙線(陽子など)が星間ガスと衝突して、反陽子を生成するモデルで説明が試みられる。とくにStandard Leaky Box(SLB)modelは宇宙線原子核の流束比をよく説明しており、同じモデルで反陽子を説明できるか否かは興味深い。二次生成の反陽子は生成時の運動学より、低エネルギー成分が非常に少なくなることが地上実験で確かめられている。このため、BESS以前の実験では500MeV以下の領域においては、SLBモデルの預言値に観測の感度が達していなかったので、モデルの検証の段階ではなかった。BESS実験で観測された反陽子の流束は、預言値にほぼ近い値を示しているかに見える。しかし、預言値にもいくつかの異なる値があり、現在の計算ではデータの解釈に不足である。そこで、最新の宇宙線データを用いてより詳細なモデル計算を行ない、観測された反陽子がSLBモデルで説明できるか否かを検証する。また、最近Heinbachたちの提唱した宇宙線伝播モデル、"Diffusive Reacceleration(DR)model"では、SLBモデルと異なり伝播中のFermi加速を考慮しているが、SLBモデルと同様、原子核の流束比をよく説明している。そこでDRモデルでも反陽子流束の計算を行ない、データおよびSLBモデルの預言値と比較し、Ferimi加速の効果について考察する。同様の計算を、やはり最近精度のよい観測が行なわれた陽電子についても行なう。現在の宇宙線伝播の理解は1%程度の微量成分である原子核のデータに基づいているので、宇宙線の主成分である陽子の二次生成物である反陽子、陽電子によるモデル検証は非常に重要である。 )の観測において、大きな進展があった。今まで、流速の上限値しか得られていなかった運動エネルギー500MeV以下の領域において、BESS実験(Balloon-borne Experiment with a Superconducting Solenoidal magnet Spectrometer)が数例の反陽子観測に成功した。宇宙線反陽子は通常、二次生成によるものと考えられており、銀河系内を伝播する一次宇宙線(陽子など)が星間ガスと衝突して、反陽子を生成するモデルで説明が試みられる。とくにStandard Leaky Box(SLB)modelは宇宙線原子核の流束比をよく説明しており、同じモデルで反陽子を説明できるか否かは興味深い。二次生成の反陽子は生成時の運動学より、低エネルギー成分が非常に少なくなることが地上実験で確かめられている。このため、BESS以前の実験では500MeV以下の領域においては、SLBモデルの預言値に観測の感度が達していなかったので、モデルの検証の段階ではなかった。BESS実験で観測された反陽子の流束は、預言値にほぼ近い値を示しているかに見える。しかし、預言値にもいくつかの異なる値があり、現在の計算ではデータの解釈に不足である。そこで、最新の宇宙線データを用いてより詳細なモデル計算を行ない、観測された反陽子がSLBモデルで説明できるか否かを検証する。また、最近Heinbachたちの提唱した宇宙線伝播モデル、"Diffusive Reacceleration(DR)model"では、SLBモデルと異なり伝播中のFermi加速を考慮しているが、SLBモデルと同様、原子核の流束比をよく説明している。そこでDRモデルでも反陽子流束の計算を行ない、データおよびSLBモデルの預言値と比較し、Ferimi加速の効果について考察する。同様の計算を、やはり最近精度のよい観測が行なわれた陽電子についても行なう。現在の宇宙線伝播の理解は1%程度の微量成分である原子核のデータに基づいているので、宇宙線の主成分である陽子の二次生成物である反陽子、陽電子によるモデル検証は非常に重要である。 また反粒子である反陽子、陽電子は、特殊な一次sourceの可能性も指摘されている。たとえば、宇宙初期に生成された可能性のある原初ブラックホール(Primordial Black Hole,PBH)の蒸発(Hawking radiation)によって反陽子、陽電子が放出される。とくに反陽子は、二次生成の場合低エネルギーの流束が小さくなるのに対して、PBHの蒸発で放出される反陽子(PBH- )は低エネルギーほど流束が大きくなるため、もしこのようなsourceが存在すれば、発見できる可能性がある。PBHは宇宙初期の密度ゆらぎなどから生成されると考えられているので、その存否を知ることは宇宙論にとって重要である。そこで、PBH- )は低エネルギーほど流束が大きくなるため、もしこのようなsourceが存在すれば、発見できる可能性がある。PBHは宇宙初期の密度ゆらぎなどから生成されると考えられているので、その存否を知ることは宇宙論にとって重要である。そこで、PBH- の伝播計算にはじめて3-D Monte Carloを導入し、太陽系付近の流束を求め、データとの比較を行なう。 の伝播計算にはじめて3-D Monte Carloを導入し、太陽系付近の流束を求め、データとの比較を行なう。 SLBモデルにおける 流束計算では、まず親の陽子の流束が重要である。最近のLEAP実験(Low-Energy Antiproton)および、BESS実験の陽子観測と、太陽風によるモジュレーション(Solar modulation)の考察から、星間空間の陽子流束を決定した。次に宇宙線陽子と星間ガス陽子の衝突で反陽子が生成される断面積について、二つの独立に行なわれたparametrizationを用いて計算し、20%以内で一致することを確認した。陽子流速と反陽子生成断面積を畳み込んで、さらに陽子以外の原子核成分からの反陽子生成の分として因子( 流束計算では、まず親の陽子の流束が重要である。最近のLEAP実験(Low-Energy Antiproton)および、BESS実験の陽子観測と、太陽風によるモジュレーション(Solar modulation)の考察から、星間空間の陽子流束を決定した。次に宇宙線陽子と星間ガス陽子の衝突で反陽子が生成される断面積について、二つの独立に行なわれたparametrizationを用いて計算し、20%以内で一致することを確認した。陽子流速と反陽子生成断面積を畳み込んで、さらに陽子以外の原子核成分からの反陽子生成の分として因子( と書く)を掛けて、星間空間の反陽子源のスペクトルを求める。 と書く)を掛けて、星間空間の反陽子源のスペクトルを求める。 因子について、過去の計算ではWebber達が 因子について、過去の計算ではWebber達が =1.59、Gaisser達が =1.59、Gaisser達が =1.17と大きく異なっていたが、原子核実験のデータからGaisser達がほぼ正しい事が分かったので1.17を用いる。次に反陽子の銀河系内閉じ込めを決めるescape length =1.17と大きく異なっていたが、原子核実験のデータからGaisser達がほぼ正しい事が分かったので1.17を用いる。次に反陽子の銀河系内閉じ込めを決めるescape length escを決めるため、HEAO3衛星などで観測された原子核のデータをfitする。原子核のデータから、 escを決めるため、HEAO3衛星などで観測された原子核のデータをfitする。原子核のデータから、 escがrigidity5GVあたりにピークを持つことが以前から分かっていたが、低エネルギー側が escがrigidity5GVあたりにピークを持つことが以前から分かっていたが、低エネルギー側が (粒子の速度の光速に対する比)の関数で落ちるのか、rigidityの関数で落ちるのかが分かっていなかった。そこでこの二つのケースについてfittingを行なった。後にのべるように、低エネルギー側がrigidityの関数で落ちる場合、陽電子の流速が観測を大きく下回ってしまうので、 (粒子の速度の光速に対する比)の関数で落ちるのか、rigidityの関数で落ちるのかが分かっていなかった。そこでこの二つのケースについてfittingを行なった。後にのべるように、低エネルギー側がrigidityの関数で落ちる場合、陽電子の流速が観測を大きく下回ってしまうので、 の関数で落ちる の関数で落ちる escを用いる。最後に反陽子が伝播するうち、さらに星間ガスに衝突して、より低エネルギーの反陽子が生成される過程を扱うため、反陽子ビームの陽子ターゲット衝突実験のデータを用いた。過去の計算では、この過程で生成される反陽子を無視しているか、近似で評価して低エネルギー反陽子をoverestimateしていたことが分かった。こうしてSLBで計算された反陽子流束はBESSの観測とよく一致した(図1左)。したがって現在のところ反陽子もSLBモデルで説明できそうであるが、より精度のよい観測が待たれる。 escを用いる。最後に反陽子が伝播するうち、さらに星間ガスに衝突して、より低エネルギーの反陽子が生成される過程を扱うため、反陽子ビームの陽子ターゲット衝突実験のデータを用いた。過去の計算では、この過程で生成される反陽子を無視しているか、近似で評価して低エネルギー反陽子をoverestimateしていたことが分かった。こうしてSLBで計算された反陽子流束はBESSの観測とよく一致した(図1左)。したがって現在のところ反陽子もSLBモデルで説明できそうであるが、より精度のよい観測が待たれる。 DRモデルでの反陽子流束計算はすでにHeinbach達が行なっているが、Ferimi加速を引き起こす磁気雲との衝突が一次元で扱われているので、ここではそれを三次元に拡張して計算する。Fermi加速以外の過程はすべてSLBモデルと同様に扱う。計算された反陽子流束は、低エネルギー領域でSLBの約1/2となった。Fermi加速によって、低エネルギー成分が高エネルギー側に移ったためである。原子核などでは、さらに低エネルギー側から加速されて補充されるため、このような不足は起こらないが、反陽子はもともと低エネルギー成分が少ないのでSLBとの違いが現れる。データはSLBの方を支持しているように見えるが、まだ誤差の範囲内で、どちらとも無矛盾である。 陽電子の計算ではSLBモデルの代わりに一次元diffusionモデルを用いる。SLBモデルは一次元diffusionモデルの近似と考えられるが、陽電子ではシンクロトロン放射によるエネルギー損失があるためSLB近似が使えないからである。すでに述べたように原子核のデータだけからだと、低エネルギー粒子の閉じ込めに関して、 escが escが の関数で落ちる場合とrigidityの関数で落ちる場合が考えられる。しかし、陽電子に関しては、rigidityの関数で落ちる の関数で落ちる場合とrigidityの関数で落ちる場合が考えられる。しかし、陽電子に関しては、rigidityの関数で落ちる escを用いて計算すると、100MeVから1GeV領域で観測を大きく下回ってしまう(図1右)。いっぽう、軽い陽電子はこのエネルギー領域においてもほとんど escを用いて計算すると、100MeVから1GeV領域で観測を大きく下回ってしまう(図1右)。いっぽう、軽い陽電子はこのエネルギー領域においてもほとんど =1であるから、 =1であるから、 の関数で落ちる の関数で落ちる escを用いると流束はあまり落ちず、観測と良く一致する。それゆえ、反陽子の計算では後者を用いた。陽電子のDRモデル計算では、高エネルギーでのシンクロトロン.エネルギー損失と低エネルギーでのFermi加速にはさまれて、1GeV付近に粒子が溜る傾向があることが分かった。データとの合いはdiffusionモデルよりやや悪い。 escを用いると流束はあまり落ちず、観測と良く一致する。それゆえ、反陽子の計算では後者を用いた。陽電子のDRモデル計算では、高エネルギーでのシンクロトロン.エネルギー損失と低エネルギーでのFermi加速にはさまれて、1GeV付近に粒子が溜る傾向があることが分かった。データとの合いはdiffusionモデルよりやや悪い。 以上により、現在の反陽子および陽電子流束の観測データは、diffusionモデル(反陽子ではSLBモデルに相当)で、説明できることが分かった。DRモデルはややデータと合わないが、否定する事はできない。今後の観測に期待される。 データを良く説明するdiffusionモデルを用いて、PBH- の流束計算を行なう。PBHは銀河ハロと同じ質量分布を過程し、その蒸発で放出された の流束計算を行なう。PBHは銀河ハロと同じ質量分布を過程し、その蒸発で放出された を3-D Monte Carloで追う。計算された地球での流束は低エネルギー側で大きくなり、二次 を3-D Monte Carloで追う。計算された地球での流束は低エネルギー側で大きくなり、二次 とは対照的なスペクトルとなった(図1左)。データは明らかに二次 とは対照的なスペクトルとなった(図1左)。データは明らかに二次 的であるので、PBHの存在に対して上限をつける。得られた90%C.L.上限値はPBHの蒸発rateにして、1.2×10-2pc-3yr-1であり、これは 的であるので、PBHの存在に対して上限をつける。得られた90%C.L.上限値はPBHの蒸発rateにして、1.2×10-2pc-3yr-1であり、これは 線バーストによるPBH探索より8桁強い制限である。 線バーストによるPBH探索より8桁強い制限である。 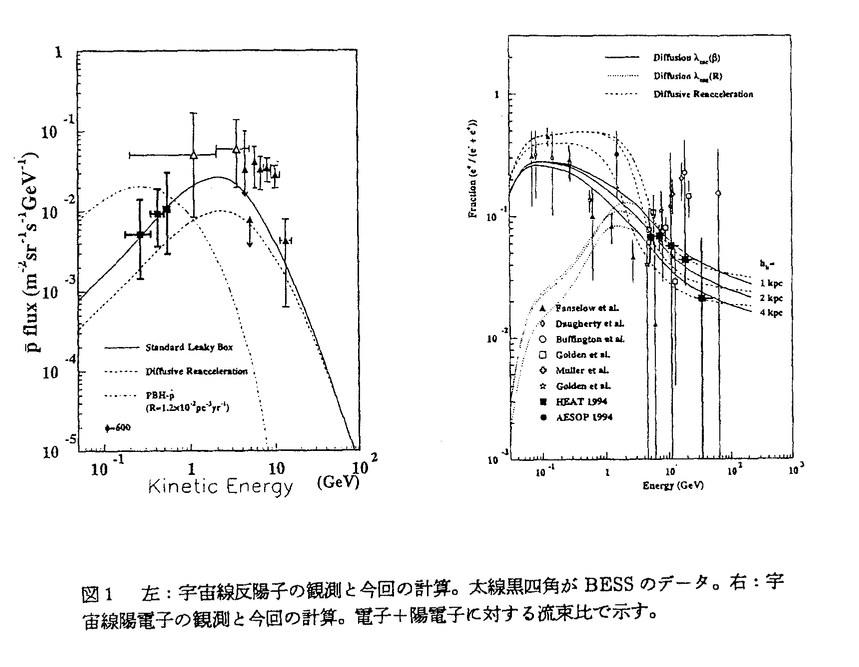 図1 左:宇宙線反陽子の観測と今回の計算。太線黒四角がBESSのデータ。右:宇宙線陽電子の観測と今回の計算。電子+陽電子に対する流束比で示す。 図1 左:宇宙線反陽子の観測と今回の計算。太線黒四角がBESSのデータ。右:宇宙線陽電子の観測と今回の計算。電子+陽電子に対する流束比で示す。 |