原子間力顕微鏡(atomic force microscpe;AFM)は絶縁体の試料の観察が従来にない高い分解能で可能であるとされ、実用評価手段として科学、産業の両面の広い分野へと浸透していった。特に、一部の物質の原子構造に対応する像が得られたことにより、走査トンネル顕微鏡(scanning tunneling microscope;STM)に匹敵する原子分解能を有するものと期待されたが、その解像メカニズムについては解明されていない点が多く、このような高分解能観察の信頼性については疑問視されてきた。これを解決するには、表面に吸着層が存在しうる大気中という測定環境では不十分で、良く制御された環境、つまり超高真空(ultrahigh vacuum;UHV)で観察を行うことが必要である。 また、現在用いられている多くの表面分析手法は超高真空環境を前提としたものが圧倒的に多い。AFMをこれらと複合的に用いたり、データをこれらの手法の結果と同列に論じたりするには、やはり共通の実験条件としての超高真空環境が不可欠である。 また、超高真空という環境は、活性な試料表面を、気体分子の吸着・反応から隔離することが出来るので、従来の観察環境では研究対象から除かれてしまった試料、特に半導体表面に対しての適用が期待される。一般に半導体表面は、原子の配置構造と電子状態分布の間に大きな差を持っていることが多い。これを実空間で評価する手段としてはまずUHV-STMが考えられるが、厳密にはSTMは電子状態の分布を観察するものである。これに対し、AFM像は全電荷密度、つまり原子の位置を反映するとされる。したがってUHV-AFMのデータをSTMの結果と組み合わせると、原子構造と電子状態という2つの観点から複合的に半導体表面の実空間評価を行うことができるのである。 以上の様に、超高真空中で動作するAFMを実現することは、AFMという手法自体の確立に大きな意味を持つと同時に、半導体等表面の研究に新たな研究手段を提供する可能性をも持つ。本研究ではこのような2つの視点からUHV-AFMの開発を行い、様々な表面の観察を行った。 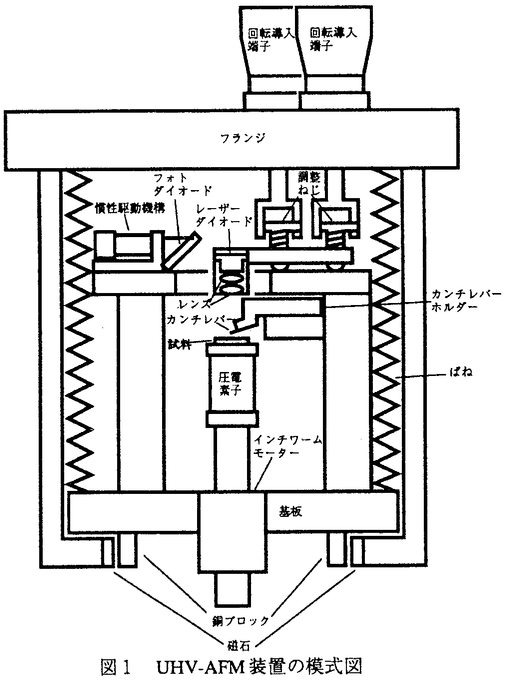 図1 UHV-AFM装置の模式図 図1 UHV-AFM装置の模式図 図1に示すのが本研究において開発したUHV-AFM装置の概略図である。本装置の特色としては以下のような事が挙げられる。 ・高い感度と真空中での高い操作性を実現した光てこ方式の変位検出機構を採用した。 ・光てこ用光源に高い安定性をもつレーザーダイオードを採用し、これを真空中で使用した。 ・8本までのカンチレバーを同時に導入し交換できる交換機構を備え、実験効率の向上を図った。 ・受光用フォトダイオードの位置調整に慣性駆動機構を採用し、20mm以上のストロークで双方向移動可能、運動中の発熱もなく、静止時の安定性も高い機構を実現した。 ・試料をカンチレバーに接近させる機構にインチワームモーターを採用し、25mmのストロークと、4nm/sから1mm/sまでの速度可変性を実現した。 また、本装置を収納する超高真空槽は、ベーキングの温度を下げてレーザーダイオードへの熱損傷を回避するための特殊アルミニウム合金製AFM室と、試料加熱機構、蒸着用セル、ガス導入バルブ、低速電子線回折(LEED)装置を装備した試料処理室の2室構成とした。本真空システムの到達真空度は2×10-10Torrである。 図2に示すのが超高真空中で加熱によって清浄化した清浄Si(111)面のAFM像である。表面が多くのステップによって区切られているのがわかる。これらのステップは数原子層分の高さを持つものが多い。 また島状の吸着物がステップの運動をピニングした痕跡も観察される。しかし、平坦なテラス上で走査領域を縮小して行くと、数Åの間隔を持つ不規則で再現性のない凹凸構造は観察されたが、清浄表面特有の7×7再構成構造の原子配列の痕跡を観察することは不可能であった。これは試料表面に残っている未結合手が探針と試料の凝着を引き起こし、微視的レベルで表面が破壊されたためであると考えられる。 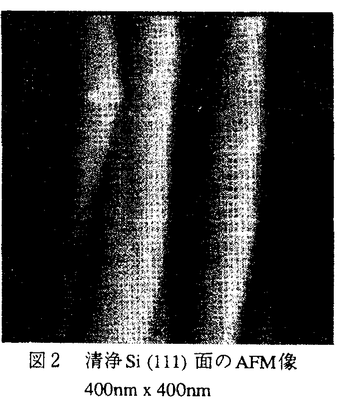 図2 清浄Si(111)面のAFM像400nm×400nm 図2 清浄Si(111)面のAFM像400nm×400nm そこで未結合手のない半導体表面として、ウェット処理により作製した水素終端Si(111)表面を観察した。ここでは図3に示すような約3.8Å間隔の3回対称性の周期的凹凸が観察された。これは、方位、周期から考えて、モノハイドライド相として吸着した水素原子の配列構造の像であると考えられる。これは半導体表面の原子配列を反映する構造をAFMで捉えた最初の例である。この像中の原子の凹凸の大きさは1.0〜1.2Å程度であった。この値は、探針先端の原子を酸素と仮定し、各原子をファン・デル・ワールス半径の球で近似した剛体球モデルで得られた1.2Åという計算結果とよく一致する。また、この値は従来のSTM観察での値と比較して約1桁大きく、STM像が表面の電子状態を反映しているのに対し、AFMは原子の凹凸構造を直接反映する、という認識を強く裏付けるものとなっている。 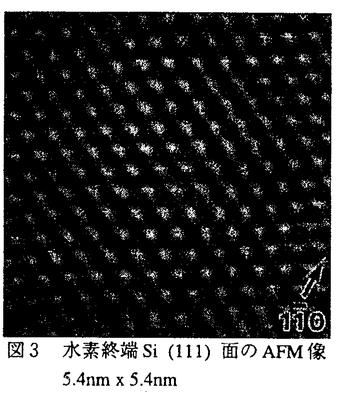 図3 水素終端Si(111)面のAFM像5.4nm×5.4nm 図3 水素終端Si(111)面のAFM像5.4nm×5.4nm さらに、図4に示すように、一度試料に激突して表面の酸化層が破壊されたと思われる探針で試料上の別の領域を観察した際、最初は正常な規則的配列を示していた表面が数画面の走査のうちに乱れていく様子も観察された。これは探針先端に活性なSiが露出し、走査中に試料と反応を起こして表面を破壊したためと考えられる。これは探針が化学的に活性か不活性かによっても観察による表面破壊の可能性が左右されることを示唆している。 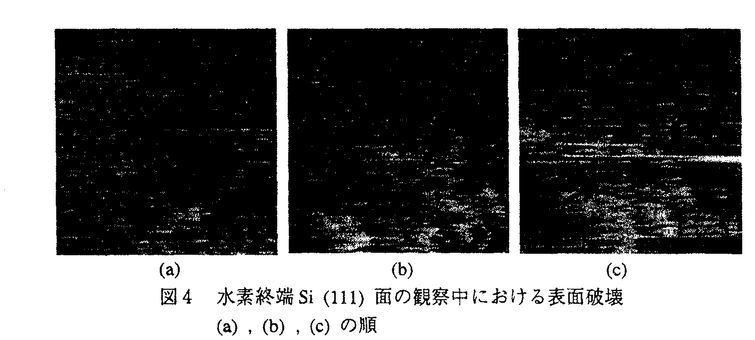 図4 水素終端Si(111)面の観察中における表面破壊(a),(b),(c)の順 図4 水素終端Si(111)面の観察中における表面破壊(a),(b),(c)の順 続いて、同じく未結合手を持たない表面としてSi(111)面にGaを蒸着し、LEEDによって√3×√3構造の生成を確認した表面を観察したところ、走査の最初の数回だけ図5に示すような畝状の構造を示す像が得られ、次第に不明瞭になっていった。この畝の方向は√3×√3構造の表面Ga原子配列の方向にほぼ一致し、間隔もそれに近い。探針と試料が破壊的に相互作用して異方性をもつ広い面積で接触して得られた像である可能性がある。 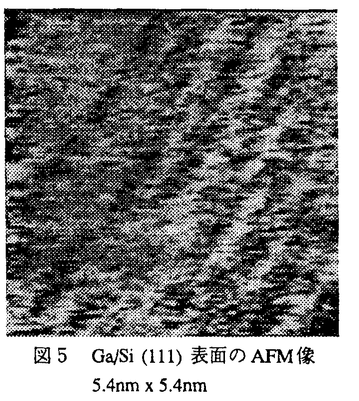 図5 Ga/Si(111)表面のAFM像5.4nm×5.4nm 図5 Ga/Si(111)表面のAFM像5.4nm×5.4nm また、Gaの被覆量を増やして得られる、同じく未結合手を持たない6.3×6.3(不整合)構造の表面の観察では、探針と試料の凝着が大きく、原子配列の構造を観察することはできなかった。過剰なGaが表面に島状に残って凝着を起こした可能性がある。 以上の結果は全て、探針と試料が斥力相互作用を及ぼす条件で得られたものである。これらの研究から、斥力領域動作のAFMが原子スケールでの観察において信頼性を持ちうるには、化学的相互作用を排除できる適切な試料-探針の組み合わせが不可欠であることが確認された。特に未結合手が終端された安定な表面であれば非常に安定して観察できることもある。その場合、得られたデータはSTMのような特定の電子状態密度の分布ではなく、実際の原子配置記をよく反映することも確認された。しかしその反面、探針の材質や化学的性質によって観察の安定度が左右されることも示唆されている。 現在の、半導体微細加工技術を応用した探針加工技術では、実現できる探針の材質や加工法に限界がある。そのため観察する試料ごとに多くの中から探針を選択するほどの自由度はない。また実際の観察では同一の表面に性質の異なる部分が存在することもあるので、さらに選択は困難になる。こうした状況を考慮すると、高分解能を目的とした半導体表面の斥力領域のAFM観察は不可能ではないが非常に制約が多く、現実的には限界に近い状況にあると言える。 そこで従来に替わり、引力領域での非接触観察法を採用し、その分解能と感度を可能な限り向上させることを目標とした。図6に示すのが、カンチレバーを試料の近傍で共振させ、試料と探針の引力相互作用による共振周波数変化をFM復調で検出して得られたSi(111)面の像である。単原子ステップと見られる構造が明瞭に観察されることから、3Aの縦方向感度が達成できていることがわかる。原子スケールの観察を実現するには横方向分解能、縦方向感度、帯域、安定度などの向上が不可欠である。ただし現段階でも、得られた像自体の信頼性は、探針の接触による摩擦力等の影響を排除できている分だけ高いと考えられる。ただし非接触観察での解像メカニズムについては不明瞭な点も多く、また実験の再現性の点でも不十分なのが現状である。非接触式AFMが原子レベルの観察手段としての地位を得るには、実験条件の確立だけではなく、理論面での裏付けも必用であり、道はまだ遠いと言えるだろう。  図6 Si(111)面の非接触AFM像250nm×250nm 図6 Si(111)面の非接触AFM像250nm×250nm 一方、斥力領域でのAFMの将来としては、像を得ることを目的とした方向よりも、摩擦力や凝着力等の試料-探針相互作用を積極的に活用して、試料の化学的性質を探査するという方向が適していると考えられる。ただしそのためには、探針の形状、表面状態に関する現在の技術以上の緻密な制御と評価が必要である。 |