| 内容要旨 | | 1序章 近年KamiokandeやIMBなどの地下検出器で観測された大気ニュートリノ欠損は,素粒子の標準模型では説明できない例外的な現象の一つとして注目されており,大統一理論など標準模型を越えた新しい物理から予言されるニュートリノ振動と関連付けて多くの議論が成されている.この大気ニュートリノのフラックスを知る上で重要なパラメータの一つに,それらの崩壊元粒子である宇宙線ミューオンのスピン偏極度が挙げられる.宇宙線ミューオンのスピン偏極を考慮すると eは前方に放出され易く, eは前方に放出され易く, は後方に放出され易いために, は後方に放出され易いために, eのエネルギースペクトルは高エネルギー側に, eのエネルギースペクトルは高エネルギー側に, のエネルギースペクトルは低エネルギー側にシフトし,その結果,スピン偏極を考慮しない場合に比べて, のエネルギースペクトルは低エネルギー側にシフトし,その結果,スピン偏極を考慮しない場合に比べて, / / e比の計算値が最大で約20%も小さくなる. e比の計算値が最大で約20%も小さくなる. 上記の大気ニュートリノ欠損は,ニュートリノエネルギーとして約1GeVおよび約6GeV付近で観測されたので,これらのエネルギー領域において宇宙線ミューオンのスピン偏極度を実験的に確認することは極めて重要である.これまで1950年代から1970年代にかけて,地表レベルにおけるエネルギーとして数GeV以下について多くの宇宙線ミューオンのスピン偏極度測定がなされた.また最近では(1990年),約1TeVにおいて測定がなされた.ところが1GeV近辺に関して最近の測定はなく,これまでの測定結果は非常にばらついている.さらに10GeV付近には一つの測定しか存在せず,その値も小さい. したがって我々は,スピン偏極度のわかっているミューオンビームを用いて較正された検出器を用いて,地表レベルにおけるエネルギーとして1GeVおよび14GeVの宇宙線ミューオンについてスピン偏極度の測定を行なった. 2測定方法 水平に寝かせたアルミ板を用いて上方より飛来する宇宙線ミューオンを止め,その崩壊電子の上下非対称度を測定することにより,スピン偏極度を求めた.検出器の基本構造は,4cm厚アルミ板の上下に1cm厚プラスチックシンチレータを配置したものである.九つの基本構造を三層三段に組み上げ,その周りをアンタイカウンタで囲んだ. ミューオンは弱い相互作用により電子と二つのニュートリノに三体崩壊する.この際,崩壊電子はスピン方向に出易いので,その性質を利用してスピン方向を知ることができる.具体的には,上下シンチレーションカウンタで検出される崩壊電子数の非対称度は,崩壊元ミューオンのスピン偏極度に比例する. 各カウンタの読みだしは光電子増倍管を用いて行なった.カウンタゲインの相違を相殺する目的で,上下カウンタを周期的に入れ換えて測定を行なった.ミューオンが入射してから崩壊するまでの時間を,Time-to-Digital Converterを用いて各事象毎に測定した. 宇宙線中には正負ミューオンが存在する.アルミで止まった -はアルミ原子核に捕獲され,瞬時にスピン偏極情報を失う.そのうちいくつかの -はアルミ原子核に捕獲され,瞬時にスピン偏極情報を失う.そのうちいくつかの -は崩壊する前に核に吸収され消滅してしまうため,その寿命は約0.86 -は崩壊する前に核に吸収され消滅してしまうため,その寿命は約0.86 sと sと +の寿命2.2 +の寿命2.2 sに比べ短くなる.この寿命の違いを利用して,オフライン解析において,正負ミューオンを統計的に区別した. sに比べ短くなる.この寿命の違いを利用して,オフライン解析において,正負ミューオンを統計的に区別した. 3ビームテスト 高エネルギー物理学研究所内の東京大学中間子科学研究センターのブースター中間子施設において,偏極ミューオンビームを用いて,検出器の較正テストを実施した. 検出器に使用したのと同種のアルミ小サンプルに偏極 +ビームを入射して止め,サンプルに約30Gの外部垂直磁場をかけることにより,スピン歳差運動を観測した.歳差運動の振幅の時間変化を測定し, +ビームを入射して止め,サンプルに約30Gの外部垂直磁場をかけることにより,スピン歳差運動を観測した.歳差運動の振幅の時間変化を測定し, +のスピン緩和時間として約53 +のスピン緩和時間として約53 sを得た.偏極 sを得た.偏極 -ビームを用いて同じことを行ない,アルミ中における静止 -ビームを用いて同じことを行ない,アルミ中における静止 -はほぼ完全に偏極情報を失うことを確かめた.同時にアルミ中における -はほぼ完全に偏極情報を失うことを確かめた.同時にアルミ中における +および +および -の寿命を測定し,それぞれ2.20±0.02 -の寿命を測定し,それぞれ2.20±0.02 sおよび0.82±0.07 sおよび0.82±0.07 sと,文献値と合致する結果を得た. sと,文献値と合致する結果を得た. 検出器の基本構造に対して垂直に偏極 ±ビームを入射し止め,偏極 ±ビームを入射し止め,偏極 ±に対する検出器の応答を調べた.ビーム運動量は固定し,検出器の前に置いた減速アルミ板の厚さを調整することにより, ±に対する検出器の応答を調べた.ビーム運動量は固定し,検出器の前に置いた減速アルミ板の厚さを調整することにより, ±を検出器のアルミ内の異なる深さに止め,各位置について,崩壊非対称度を測定した.その結果,崩壊非対称度はミューオンの静止する深さと直線関係にあり,その傾きはモンテカルロシミュレーションと一致した.またミューオンの静止する深さを固定すれば,崩壊非対称度はカウンタの長さ方向の場所に寄らないことを確認した.さらに崩壊非対称度は前後カウンタの入れ換えに寄らないことも確認した. ±を検出器のアルミ内の異なる深さに止め,各位置について,崩壊非対称度を測定した.その結果,崩壊非対称度はミューオンの静止する深さと直線関係にあり,その傾きはモンテカルロシミュレーションと一致した.またミューオンの静止する深さを固定すれば,崩壊非対称度はカウンタの長さ方向の場所に寄らないことを確認した.さらに崩壊非対称度は前後カウンタの入れ換えに寄らないことも確認した. 4実験場所 宇宙線ミューオンのスピン偏極度測定は,宇宙線研究所の明野観測所と大谷観測所で行なった.明野観測所内に点在するミューオンステーションのうちの一つ(M1)に検出器を設置し,測定を行なった.ミューオンステーションは厚さ2mのコンクリートの天井で覆われており,観測できる宇宙線ミューオンの海水面におけるエネルギー下限は約1GeVである.大谷観測所には大谷石採掘跡地として地下約33mに巨大な地下空間があり,そこに検出器を設置して測定を行なった.ミューオンのエネルギー下限は約14GeVである.明野,大谷ともに同じ検出器を用いて測定を行なった. 5データ解析 1995年度5月から6月にかけて明野観測所において,同年7月から11月にかけて大谷観測所において取得したデータをもとに,宇宙線ミューオンのスピン偏極度を求めた.それぞれ実験場所において,約106および105個のミューオン崩壊事象を取得した. 取得したデータの崩壊時間スペクトルより, ±を統計的に区別し,各々の事象数を上下カウンタそれぞれについて算出した.主なバックグランド事象は,上側カウンタで静止したミューオンの崩壊事象である.上下カウンタを同時にヒットする崩壊事象を用いて,このバックグランド事象数を見積もった. ±を統計的に区別し,各々の事象数を上下カウンタそれぞれについて算出した.主なバックグランド事象は,上側カウンタで静止したミューオンの崩壊事象である.上下カウンタを同時にヒットする崩壊事象を用いて,このバックグランド事象数を見積もった. 検出器の立体角によるアクセプタンスの違いから,ミューオンは検出器上方に止まり易い.この静止位置の上下非対称性に起因する崩壊非対称度を,スピン偏極0%と仮定してGEANTモンテカルロシミュレータにより見積もった.観測された崩壊非対称度からこの量を引くことにより,スピン偏極度に比例する正味の崩壊非対称度を得た.また崩壊非対称度はスピン偏極度に比例すると述べたが,その比例係数をスピン偏極100%と仮定してGEANTにより見積もった. 大気と減速材(コンクリートおよび大谷石)を通過することによる減偏極はクーロン散乱により起こり,両実験場で約5%と見積もられた.アルミ減速板に静止した +のスピン緩和による減極度は,ビームテストの結果より約4%と見積もられた. +のスピン緩和による減極度は,ビームテストの結果より約4%と見積もられた. 宇宙線ミューオンの運動量および天頂角分布の不定性,減速材およびアルミ中における減偏極度の不定性,カウンタしきい値やゲインの不定性などによる系統誤差を見積もり,全ての不定性の二乗和平方根をとり約±0.07を得た. 6結果 減偏極による補正も行ない,最終的に宇宙線ミューオンのスピン偏極度として,0.227±0.017(stat)±0.070(syst)(明野),および0.327±0.056(stat)±0.072(syst)(大谷)を得た.これまでの他の実験結果と合わせて図1に示す. 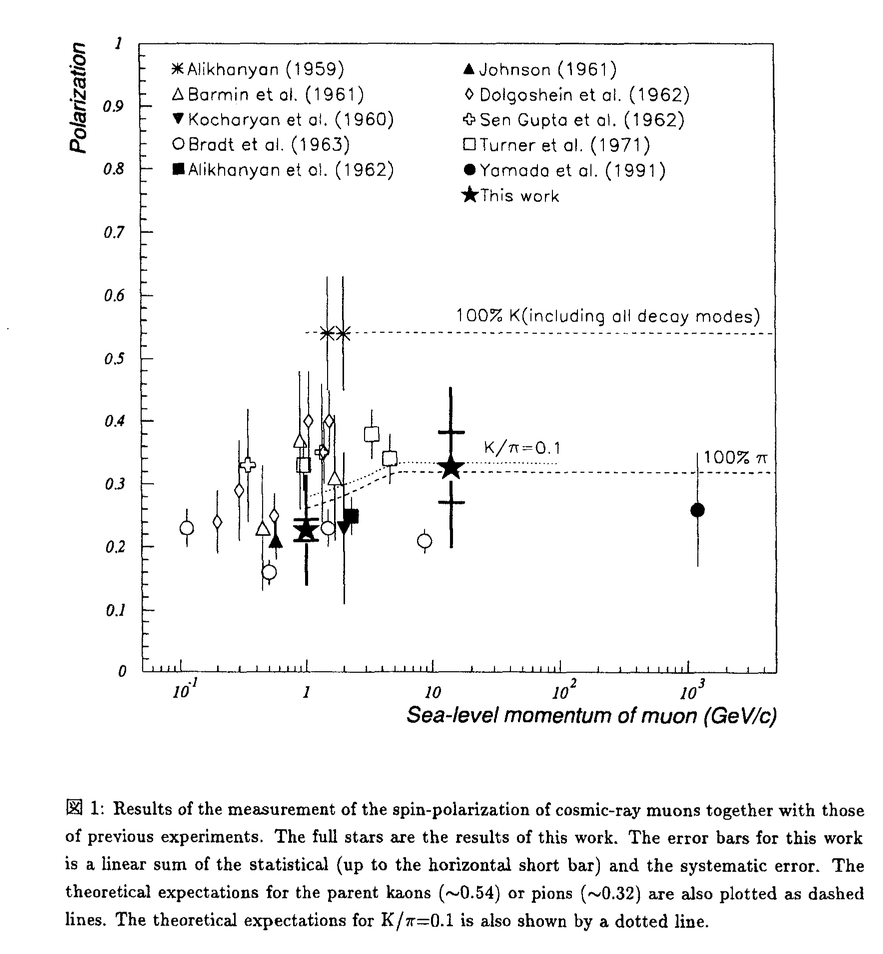 図1:Results of the measurement of the spin-polarization of cosmic-ray muons together with those of previous experiments. The full stars are the results of this work.The error bars for this work is a linear sum of the statistical(up to the horizontal short bar)and the systematic error.The theoretical expectations for the parent kaons(〜0.54)or pions(〜0.32)are also plotted as dashed lines.The theoretical expectations for K/ 図1:Results of the measurement of the spin-polarization of cosmic-ray muons together with those of previous experiments. The full stars are the results of this work.The error bars for this work is a linear sum of the statistical(up to the horizontal short bar)and the systematic error.The theoretical expectations for the parent kaons(〜0.54)or pions(〜0.32)are also plotted as dashed lines.The theoretical expectations for K/ =0.1 is also shown by a dotted line. =0.1 is also shown by a dotted line. 図1中には,ミューオンの親中間子が100% および100%Kのみと仮定した場合の理論曲線,および加速器実験のデータなどに基づいきK/ および100%Kのみと仮定した場合の理論曲線,および加速器実験のデータなどに基づいきK/ 比(=0.1)と仮定した場合の理論曲線を示した.最近の宇宙線空気シャワーのモンテカルロシミュレーションではK/ 比(=0.1)と仮定した場合の理論曲線を示した.最近の宇宙線空気シャワーのモンテカルロシミュレーションではK/ 〜0.1と仮定されているが,我々はここで仮定されているスピン偏極度を支持する結果を得た. 〜0.1と仮定されているが,我々はここで仮定されているスピン偏極度を支持する結果を得た. 7考察 我々の実験の特徴を他と比較すると以下の様になる. ・偏極ミューオンビームを用いて検出器を較正した.これまでの実験ではTurnerらの実験を除いて,ビームテストは行なわれていなかった. ・GEANTモンテカルロシミュレータにより検出器の基本定数,例えば崩壊非対称度や検出効率などを求めた.GEANTでは崩壊電子の多重散乱などを扱うことができ,また正確な検出器のジオメトリも定義できる.これらを使った補正が重要であるが,これまでの実験ではほとんどなされていなかった. ・崩壊時間をTDCを用いて測定した.これまでの実験では遅延コインシデンスの方法により行なわれていたので,これらに比べて単時間で統計を貯めることができた. 明野(1GeV)における測定結果は同じ運動量領域にあるTurner,Barmin,Sen Gupta,Dol-gosheinらの結果と一致した.大谷(14GeV)における測定結果を比較的運動量の近い他の実験結果と比較すると,Turner,Bradtの結果と実験誤差内で一致した. 我々の得たスピン偏極度をもとに,宇宙線ミューオンのスピン偏極度の大気ニュートリノフラックスへの影響を調べた.スピン偏極を考慮すると,大気ニュートリノ比 / / eの計算値は,スピン偏極を考慮しない場合に比べて約16%小さくなることがわかった.この効果を含めるとFrejusおよびNUSEXの測定値は標準模型の枠内で説明できるが,Kamiokande,IMB-3,およびSoudan-2で観測された欠損は依然標準模型の枠内では説明できないことがわかった. eの計算値は,スピン偏極を考慮しない場合に比べて約16%小さくなることがわかった.この効果を含めるとFrejusおよびNUSEXの測定値は標準模型の枠内で説明できるが,Kamiokande,IMB-3,およびSoudan-2で観測された欠損は依然標準模型の枠内では説明できないことがわかった. |
| 審査要旨 | | 本論文は大気中でつくられる宇宙線ミューオンのスピン偏極度を地表近くで測定した実験に関するものである。 カミオカンデ実験で、大気中で作られたミューニュートリノ( )と電子ニュートリノ( )と電子ニュートリノ( e)の比が2:1のはずなのに、観測結果はほぼ1:1であることが示され、大気ニュートリノ異常として注目されている。もし確認されれば、ニュートリノ振動が起こったこと、従ってニュートリノが有限な質量を持つことを示唆する素粒子物理学にとって根本的に重要な課題である。 e)の比が2:1のはずなのに、観測結果はほぼ1:1であることが示され、大気ニュートリノ異常として注目されている。もし確認されれば、ニュートリノ振動が起こったこと、従ってニュートリノが有限な質量を持つことを示唆する素粒子物理学にとって根本的に重要な課題である。 大気ニュートリノフラックスの計算は幾つかのグループで精力的におこなわれ、 と と eの比が2:1より小さくなるであろうことが予測されている。すなわちニュートリノの崩壊元粒子である宇宙線ミューオンのスピン偏極を考慮すると eの比が2:1より小さくなるであろうことが予測されている。すなわちニュートリノの崩壊元粒子である宇宙線ミューオンのスピン偏極を考慮すると eは前方に放出され易く, eは前方に放出され易く, は後方に放出され易いために, は後方に放出され易いために, eのエネルギースペクトルは高エネルギー側に, eのエネルギースペクトルは高エネルギー側に, のエネルギースペクトルは低エネルギー側にシフトし,その結果,スピン偏極を考慮しない場合に比べて, のエネルギースペクトルは低エネルギー側にシフトし,その結果,スピン偏極を考慮しない場合に比べて, / / e比の計算値が最大で約20%も小さくなる。 e比の計算値が最大で約20%も小さくなる。 カミオカンデの大気ニュートリノ異常は,ニュートリノエネルギーとして約1GeVおよび約6GeV付近で観測されたので,これらのエネルギー領域において宇宙線ミューオンのスピン偏極度を実験的に確認することは極めて重要である。これまで1950年代から1970年代にかけて,地表レベルにおけるエネルギーとして数GeV以下について多くの宇宙線ミューオンのスピン偏極度測定がなされた.しかし1GeV近辺に関して最近の測定はなく,かつ古い測定結果は非常にばらついている。さらに10GeV付近には一つの測定しか存在しない。 本論文は,スピン偏極度のわかっているミューオンビームを用いて較正した検出器を、1GeVおよび14GeVの閾エネルギー相当の地下に設置し、宇宙線ミューオンについてスピン偏極度の測定を行なったものである。 ミューオンは弱い相互作用により電子と二つのニュートリノに三体崩壊する.この際,崩壊電子はスピン方向に出易いので,その性質を利用してスピン方向を知ることができる。4cm厚アルミ板の上下に1cm厚プラスチックシンチレータ検出器を配置し、アルミ板中で宇宙線ミューオンを止め、その崩壊電子数の上下非対称度から崩壊元ミューオンのスピン偏極度を求める。 宇宙線中には正負ミューオンが存在するが,アルミで止まった -はアルミ原子核に捕獲されるため、寿命は -はアルミ原子核に捕獲されるため、寿命は +の寿命比べ短くなる。この寿命の違いを利用して,オフライン解析において,正負ミューオンを統計的に区別している。 +の寿命比べ短くなる。この寿命の違いを利用して,オフライン解析において,正負ミューオンを統計的に区別している。 まず高エネルギー物理学研究所内の東京大学中間子科学研究センターのブースター中間子施設において,偏極ミューオンビームを用いて,検出器の較正テストを実施している。 +のスピン緩和時間、アルミ中における +のスピン緩和時間、アルミ中における +および +および -の寿命を測定し,文献値と合致する結果を得ており、基本的に装置が正常に稼働していることが確認できる。又、検出器に垂直に偏極した -の寿命を測定し,文献値と合致する結果を得ており、基本的に装置が正常に稼働していることが確認できる。又、検出器に垂直に偏極した ±ビームを入射し,検出器の前に置いた減速アルミ板の厚さを調整することにより, ±ビームを入射し,検出器の前に置いた減速アルミ板の厚さを調整することにより, ±を検出器のアルミ内の異なる深さに止め,崩壊非対称度の深さ依存性や、アルミの長さ方向の静止位置依存性等検出器の特性を測定している。 ±を検出器のアルミ内の異なる深さに止め,崩壊非対称度の深さ依存性や、アルミの長さ方向の静止位置依存性等検出器の特性を測定している。 本測定は1995年度5月から6月にかけて宇宙線研究所明野観測所において,7月から11月にかけて大谷観測所において実施され、それぞれ約106および105個のミューオン崩壊事象を得ている。取得したデータの崩壊時間情報より, ±を統計的に区別し,各々の事象数を上下カウンタそれぞれについて算出するのであるが、上側カウンタで静止したミューオンの崩壊事象等、崩壊事象に対するバックグランド事象の評価、検出器の立体角による上下検出器のアクセプタンスの違いによる上下非対称性、大気および吸収層(コンクリートおよび大谷石)中での減偏極、宇宙線ミューオンの運動量分布、天頂角分布や、東西効果に基づく方位角依存性の影響、検出器ゲインの長期安定性、しきい値の変動による誤差などを、実験やシミュレーションにより実施し、統計誤差、系統誤差を評価している。 ±を統計的に区別し,各々の事象数を上下カウンタそれぞれについて算出するのであるが、上側カウンタで静止したミューオンの崩壊事象等、崩壊事象に対するバックグランド事象の評価、検出器の立体角による上下検出器のアクセプタンスの違いによる上下非対称性、大気および吸収層(コンクリートおよび大谷石)中での減偏極、宇宙線ミューオンの運動量分布、天頂角分布や、東西効果に基づく方位角依存性の影響、検出器ゲインの長期安定性、しきい値の変動による誤差などを、実験やシミュレーションにより実施し、統計誤差、系統誤差を評価している。 これらの評価の後、宇宙線ミューオンのスピン偏極度として,1GeVで0.227±0.017(stat)±0.064(syst)を、14GeVで0.327±0.056(stat)±0.066(syst)を得ている。これらの明野、大谷での結果はそれぞれ同じ又は近い運動量領域でのこれまでの結果では一番低い値を示しているが、これまでの実験の中でも、評価の高い実験結果と実験誤差内で一致している。 本実験で得られたスピン偏極を考慮すると,大気ニュートリノ比 / / eの計算値は,スピン偏極を考慮しない場合に比べて約16%小さくなる。これは計算で示されていた結果を実験的に確認したことになる。すなわちカミオカンデ,IMB-3等の大気ニュートリノの異常は偏極度を考慮しても説明できない。 eの計算値は,スピン偏極を考慮しない場合に比べて約16%小さくなる。これは計算で示されていた結果を実験的に確認したことになる。すなわちカミオカンデ,IMB-3等の大気ニュートリノの異常は偏極度を考慮しても説明できない。 本実験の結果は1960年代の実験と大筋で一致しており、測定精度も決定的に向上していないように見える。これは古い実験では、偏極ミューオンビームを用いた較正実験や、GEANTなどのような信頼できるソフトを用いたシミュレーション等による系統誤差を推定することができなく、誤差棒も殆ど統計誤差のみで、本実験と同じ性質ではないことに注意する必要があろう。一見地味な実験であり、誤差も大きいが、きちんと系統誤差を評価した実験として、新しい知見と言える。 当初本論文の審査は1月におこなわれたが、審査委員から幾つかの疑問点が提起され、6月までかけて、追実験、較正実験、シミュレーションを実施し、6月に再度審査を実施した。その際新たに出された問題点につき8月までかけて加筆した結果、審査委員一同は本論文は博士(理学)の学位論文として合格であると判定した。 なお本論文の実験は、装置の組み立て、偏極ミューオンビームを用いた較正実験、本実験、解析を通じてほぼ一人で実施しており、大規模実験の一部を分担する最近の多くの実験に比して、苦労も多かったと推測されるが、研究遂行に際しバランスのとれた貢献が出来たと言える。 |