| I.[CII]輝線と光解離領域 [CII]158 m輝線は、星間ガス中に存在する炭素の一回電離イオン(C+)の基底状態がもつ微細構造(2P3/2→2P1/2)遷移により放射される、銀河系で最も明るい輝線のひとつである。この輝線は、これまで、主にKAO(Kuiper Airbome Observatory)によって観測されてきた。KAOに観測された[CII]輝線は12CO(J=1-0)輝線とよい相関をもっていたため、星からの紫外光が分子雲の表面のCO分子を光解離してC+イオンをつくり、またガスを加熱して[CII]輝線が放射されると解釈された。このような、入射紫外光がガス中の化学過程や熱収支に大きな影響を与える中性ガス領域を、光解離領域とよぶ。 m輝線は、星間ガス中に存在する炭素の一回電離イオン(C+)の基底状態がもつ微細構造(2P3/2→2P1/2)遷移により放射される、銀河系で最も明るい輝線のひとつである。この輝線は、これまで、主にKAO(Kuiper Airbome Observatory)によって観測されてきた。KAOに観測された[CII]輝線は12CO(J=1-0)輝線とよい相関をもっていたため、星からの紫外光が分子雲の表面のCO分子を光解離してC+イオンをつくり、またガスを加熱して[CII]輝線が放射されると解釈された。このような、入射紫外光がガス中の化学過程や熱収支に大きな影響を与える中性ガス領域を、光解離領域とよぶ。 KAOで観測された[CII]/COの輝線強度比は、Tielens & Hollenbach(1985)の光解離領域モデルを用いることによって、定量的にもよく説明できた。このモデルは、一次元構造をもつ中性ガス雲に、遠紫外光(6eV hv hv 13.6eV)が片側から差し込む構造をしている。KAOが観測したような大質量星形成領域においては、この仮定は妥当なものであった。 13.6eV)が片側から差し込む構造をしている。KAOが観測したような大質量星形成領域においては、この仮定は妥当なものであった。 近年になって、気球望遠鏡BICE(Balloon-borne Infrared Carbon Explorer)は、銀河面にそって広い領域(-12° l l +26°)から[CII]輝線を検出した(Nakagawa et al.1995)。この観測によると、銀河面での[CII]/COの輝線強度比は、典型的に[CII]/CO=1.3×103であった。この強度比に従来の一次元光解離領域モデルを適用すると、分子雲を照らす紫外光の強度は、太陽近傍の値の100倍にも及ぶことになる。このような強い紫外光は大質量星の近傍に限られ、一般の銀河面を満たすことはできないはずである。この矛盾から、銀河面の[CII]輝線の支配的な源は光解離領域ではないとする意見が有力視されるようになった。 +26°)から[CII]輝線を検出した(Nakagawa et al.1995)。この観測によると、銀河面での[CII]/COの輝線強度比は、典型的に[CII]/CO=1.3×103であった。この強度比に従来の一次元光解離領域モデルを適用すると、分子雲を照らす紫外光の強度は、太陽近傍の値の100倍にも及ぶことになる。このような強い紫外光は大質量星の近傍に限られ、一般の銀河面を満たすことはできないはずである。この矛盾から、銀河面の[CII]輝線の支配的な源は光解離領域ではないとする意見が有力視されるようになった。 この意見に対し、われわれは、矛盾の原因は、本来KAOで観測される大質量星形成領域のために作られたモデルを一般の銀河面に適用したことにあると考えた。銀河面中の一般の分子雲は、周囲のさまざまな星がつくる輻射場につつまれているはずである。このため、従来の光解離領域モデルによる一次元構造の仮定、入射紫外光を遠紫外域に限る仮定は、ともに妥当でない。そこで、われわれは、BICEによる銀河面での[CII]輝線の観測結果を正しく解釈するために、 1)有限の大きさをもつ分子雲が等方的な星の光に包まれる 2)星からの光は紫外域から近赤外域におよぶ広い波長域をもつ の特徴をもつ新しい光解離領域モデルをつくることにした。 II.モデル モデル分子雲は球対称構造をもつとし、等方的な輻射場の中におかれていると仮定した。あらじめモデル雲内の密度分布を決定したうえで、雲内の各所においてガス中の化学平衡と熱収支を同時に解く。これら局所的な平衡は、輻射輸達によって、モデル雲内の他の場所での局所的な平衡と影響しあうことになる。化学平衡と熱収支を解くための基本的な過程は、従来のモデル(Hollenbach et al.1991)とほぼ同じである。ただし、われわれのモデル雲は三次元構造をもつため、局所的な平衡を解くために必要な輻射輸達は、立体角について積分して解く。 個々の分子雲は、入射紫外光強度G0(太陽近傍での値を単位とする)、質量M、平均密度<nH>の、3つのパラメタで特徴づけられる。銀河面での一般の分子雲を記述するため、これらパラメタは、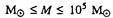 、 、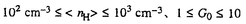 の範囲で計算を行った。 の範囲で計算を行った。 入射する光は、従来の光解離領域モデル中に含まれていた0.091 mから0.2 mから0.2 mまでの波長域の放射にくわえ、0.2 mまでの波長域の放射にくわえ、0.2 mから8 mから8 mまでの放射も考慮にいれた。パラメタG0は0.091 mまでの放射も考慮にいれた。パラメタG0は0.091 mから0.2 mから0.2 mの放射強度を表すために用いた。0.2 mの放射強度を表すために用いた。0.2 mから8 mから8 mまでの放射は、系外銀河の観測に基づき、 mまでの放射は、系外銀河の観測に基づき、 に比例する強度をもつと仮定した。 に比例する強度をもつと仮定した。 III.結果 星からの紫外光がモデル雲の表面に差し込むため、モデル雲表面付近のガス中の炭素は電離され、C+イオンとなる。紫外光は雲中のダストに吸収されて雲の内部しいくにしたがって弱くなるため、雲の内部では、ガス中の炭素はCO分子にとりこまれる。その結果、モデル雲は、内部にCOを多く含むガスでできた核(CO coreとよぶ)をもち、それをC+を多く含むガスが包む(C+envelopeとよぶ)構造をもつ。このC-1envelopeから[CII]輝線が放射される。CO輝線は光学的に厚いため、おもにCO coreの表面から放射される。 このように、われわれの球対称モデルでは、星からの紫外光がモデル雲を包みこみ、その表面全体を[CII]放射領域がおおうことになる。そのため、われわれのモデルは、同じ密度と入射紫外光強度をもつ従来の光解離領域と比較して、より大きな[CII]/CO輝線強度比をみせる。 質量Mと平均密度<nH>を固定してG0を大きくすると、モデル雲のより深い領域まで炭素が電離されるため、C-1envelopeの厚みが増える。これに伴い、モデル雲から放射される[CII]輝線の光度が増加し、[CII]/CO輝線強度比は大きくなる。このように、[CII]/CO輝線強度比はG0の増加関数なので、われわれのモデルは、ある[CII]/CO輝線強度比を再現するために、従来のモデルより小さな紫外光強度しか必要としないことになる。 図1に、質量Mと平均密度<nH>を固定したときにわれわれのモデルがつくる[CII]/CO輝線強度比を、分子雲質量の関数として示す。図中の実線がG0=1とG0=10のときにモデルがつくる輝線強度比を、破線がBICEによる観測値をあらわす。この図がしめすように、われわれのモデルは、<nH>=103cm-3のとき、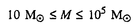 、1 、1 G0 G0 10の範囲で観測値を再現する。この紫外光強度は、従来のモデルが要求する強度と比較して一桁以上小さい。 10の範囲で観測値を再現する。この紫外光強度は、従来のモデルが要求する強度と比較して一桁以上小さい。 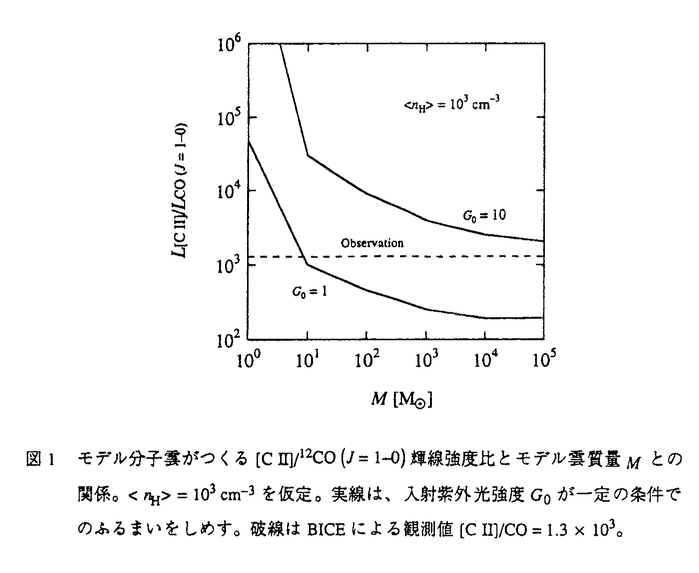 図1 モデル分子雲がつくる[CII]/12CO(J=1-0)輝線強度比とモデル雲質量Mとの関係。<nH>=103cm-3を仮定。実線は、入射紫外光強度G0が一定の条件でのふるまいをしめす。破線はBICEによる観測値[CII]/CO=1.3×103。IV.銀河面への適用 図1 モデル分子雲がつくる[CII]/12CO(J=1-0)輝線強度比とモデル雲質量Mとの関係。<nH>=103cm-3を仮定。実線は、入射紫外光強度G0が一定の条件でのふるまいをしめす。破線はBICEによる観測値[CII]/CO=1.3×103。IV.銀河面への適用 銀河系内の紫外光強度は、渦状腕上と渦状腕間で異なる。Scoville et al.(1968)は、銀河系内でのHII領域の分布から、渦状腕上での大質量星形成率を渦状腕間での値の9倍とみつもった。これにならい、われわれは、銀河系内の渦状腕上でG0=9、渦状腕間でG0=1とおく。分子雲の密度や質量は腕上と腕間で差がないと仮定し、典型的な値として<nH>=103cm-3、M=103 をとる。系外銀河について、分子ガスの1/4が腕上にあることを示す観測があるため、銀河系でも腕上分子雲(G0=9、<nH>=103cm-3、M=103 をとる。系外銀河について、分子ガスの1/4が腕上にあることを示す観測があるため、銀河系でも腕上分子雲(G0=9、<nH>=103cm-3、M=103 のモデル雲)が分子ガスの1/4をしめるとし、残りは腕間分子雲(G0=1、<nH>=103cm-3、M=103 のモデル雲)が分子ガスの1/4をしめるとし、残りは腕間分子雲(G0=1、<nH>=103cm-3、M=103 のモデル雲)であると考える。 のモデル雲)であると考える。 銀河面で観測されるスペクトルはこの2種の分子雲からのスペクトルの重ねあわせであるとすれば、われわれのモデルが予想する銀河面での典型的な[CII]/CO輝線強度比は1.4×103となる。これはBICEによる観測値1.3×103をよく再現している。すなわち、われわれのモデルは、BICEによって観測される[CII]放射が,銀河系内の一般の輻射場のもとで説明可能であることを明らかにした。 [CII]輝線/100 m連続波強度比についても、同様に銀河面の典型的な値をモデルから求めると、[CII]/100 m連続波強度比についても、同様に銀河面の典型的な値をモデルから求めると、[CII]/100 m=2.5×10-3となる。観測値は[CII]/100 m=2.5×10-3となる。観測値は[CII]/100 m=3.3×10-3であるから、この強度比もモデルでよく再現できる。[CII]輝線がガスの、遠赤外連続波がダストの、支配的な冷却放射であることを考えると、[CII]強度はガス、100 m=3.3×10-3であるから、この強度比もモデルでよく再現できる。[CII]輝線がガスの、遠赤外連続波がダストの、支配的な冷却放射であることを考えると、[CII]強度はガス、100 m強度はダストの加熱率の指標となる。光解離領域でのガス加熱は、紫外光がダストに吸収されたとき光電効果によりとび出した電子が、周囲のガス粒子にそのエネルギーを分配することによる(de Jong1977)。一方、このときダストに吸収された光子のエネルギーの多くはダストを加熱することになる。以上のことから、[CII]/100 m強度はダストの加熱率の指標となる。光解離領域でのガス加熱は、紫外光がダストに吸収されたとき光電効果によりとび出した電子が、周囲のガス粒子にそのエネルギーを分配することによる(de Jong1977)。一方、このときダストに吸収された光子のエネルギーの多くはダストを加熱することになる。以上のことから、[CII]/100 m強度比は、光電効果によるガス加熱の効率と考えることができる。 m強度比は、光電効果によるガス加熱の効率と考えることができる。 観測される小さな[CII]/100 m強度比を従来のモデルで説明するには、ダストが帯電するほどの強い(G0 m強度比を従来のモデルで説明するには、ダストが帯電するほどの強い(G0 100)紫外光強度で光電効果の効率を落とすことが要求された。これに対して、われわれのモデルは、6eV以下の、ガスは暖めないがダストを暖める入射光を考慮したため、弱い(G0 100)紫外光強度で光電効果の効率を落とすことが要求された。これに対して、われわれのモデルは、6eV以下の、ガスは暖めないがダストを暖める入射光を考慮したため、弱い(G0 100)紫外光のもとでも従来のモデルより小さな[CII]/100 100)紫外光のもとでも従来のモデルより小さな[CII]/100 m強度比をつくる。 m強度比をつくる。 すなわち、銀河面で観測される[CII]/CO強度比、[CII]/100 m強度比のいずれを解釈する際にも、大質量星形成領域のために作られた従来の光解離領域モデルは、紫外光強度を誤って一桁ほど大きくみつもっていたことになる。これに対し、われわれのモデルでは観測値を銀河系の一般の星間輻射場で説明できる。このような一般の星間輻射場が分子雲表面に形成する光解離領域こそが、銀河系内における[CII]輝線の起源の有力な候補である。 m強度比のいずれを解釈する際にも、大質量星形成領域のために作られた従来の光解離領域モデルは、紫外光強度を誤って一桁ほど大きくみつもっていたことになる。これに対し、われわれのモデルでは観測値を銀河系の一般の星間輻射場で説明できる。このような一般の星間輻射場が分子雲表面に形成する光解離領域こそが、銀河系内における[CII]輝線の起源の有力な候補である。 |