| 内容要旨 | | 超微小押込試験とは、負荷荷重を Nの精度で制御しながら圧子の変位を数nmの分解能で測定し、サブ・ミクロン領域の強度評価を行う動的硬さ試験法である。この方法では、従来の微小硬さ試験では測定が不可能であった厚さ1 Nの精度で制御しながら圧子の変位を数nmの分解能で測定し、サブ・ミクロン領域の強度評価を行う動的硬さ試験法である。この方法では、従来の微小硬さ試験では測定が不可能であった厚さ1 m以下の薄膜や層構造材、き裂が発生しやすい脆性材料に対しても測定が可能である。また、荷重と押込み深さを負荷・除荷の全過程に亘って連続的に記録することによって得られる荷重-変位曲線から、深さ方向の硬さ変化やヤング率を求めることもできる。 m以下の薄膜や層構造材、き裂が発生しやすい脆性材料に対しても測定が可能である。また、荷重と押込み深さを負荷・除荷の全過程に亘って連続的に記録することによって得られる荷重-変位曲線から、深さ方向の硬さ変化やヤング率を求めることもできる。 通常の金属材料では、一般的に硬さは引張り強さもしくは降伏応力にほぼ比例することが知られており[1,2]、圧痕の形成が転位の運動を素過程とする塑性変形によって担われているとされている。これに対しセラミックスや半導体は、結合特性の違いや結晶構造が複雑で対称性が低いことなどから一般に金属材料よりも高強度で異方性が強いため、複雑な変形を要する圧痕形成のメカニズムに関しては不明な点が多い。特にSiにおいては、圧縮試験によって求められる降伏応力は300℃〜600℃の温度範囲に亘って強い温度依存性を示すのに対し[3]、マイクロ・ビッカース硬さは500℃付近から低温域ではほとんど温度に依存しないことが知られている[4-6]。このことは通常の金属材料とは異なる機構によってSiの圧痕が形成されることを示唆する。これまでに静水圧縮応力による構造相転移が関与していることが指摘されている[6-11]が、詳細な圧痕形成のメカニズムは不明で、特異な硬さの温度依存性を説明するには至っていない。これらの挙動を明らかにするためには、き裂の発生などの不確定要素を除くことができる超微小押込試験による測定が有効であり、特に高温における正確な測定が必要である。しかし、Siのような硬度の高い材料の硬さを正確に測定するためには、圧子の押込過程における弾性変形の寄与を考慮に入れた評価法が必要で、さらに高温測定を行う上では正確な試料温度や測定系の熱膨張による誤差なども考慮しなければならない。 本研究では、超微小押込試験の高温測定法と脆性材料の硬さ算出法を提案し、これをSi単結晶に応用する。超微小押込試験は室温〜600℃の温度範囲で行い、荷重-変位曲線と圧痕の透過電子顕微鏡(TEM)および走査電子顕微鏡(SEM)観察から、試験温度や試料方位の違いによる圧痕形状や転位組織の差異を調べ、高圧下における構造解析の結果と比較することによってSiの圧痕形成メカニズムを明らかにすることを目的とする。 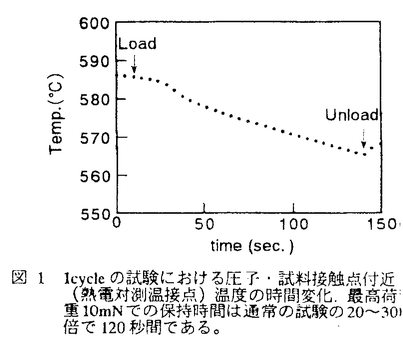 図1 1cycleの試験における圧子・試料接触点付近(熱電対測温接点)温度の時間変化.最高荷重10mNでの保持時間は通常の試験の20〜30倍で120秒間である。 図1 1cycleの試験における圧子・試料接触点付近(熱電対測温接点)温度の時間変化.最高荷重10mNでの保持時間は通常の試験の20〜30倍で120秒間である。 高温測定技術に関する課題の第一点は、試料温度の正確な測定である。一般に、圧子の温度は試料温度より低い状態から接触を開始するので、押込開始後、試料温度が大きく低下すると考えられている。本研究では、熱電対の測温接点を直接押し込んだときの温度変化を測定し、実際の試験における試料温度を見積もることを試みた。図1は初期温度約600℃における、1cycleの試験中の温度の時間変化を示したもので、total150秒間(最高荷重10mNでの保持時間120秒)の温度降下は20℃程度である。これに対し通常の試験は10秒程度で終わるためにこの間の温度降下は1〜2℃と見積もられ、十分無視できる範囲であることがわかる。 高温測定技術における第二の課題は、熱膨張による測定系の寸法変化である。圧子の押込み深さは圧子を支持する部材の変位から間接的に測定しているため、各支持部の熱膨張による寸法変化がそのまま押込み深さの誤差となる。試験中の熱膨張距離を見積もるため各荷重で一定に保持したときの変位を測定したところ、膨張速度は数秒間ほぼ一定で、図2に示すようにその値は保持する荷重に依存する。したがって荷重を連続的に変化させる実際の試験では、荷重の増減に伴ってdrift速度も変化すると考えられる。押込試験は負荷・除荷速度を一定の条件下で行うので、荷重とdrift速度の関係は、drift速度の時間変化に変換することができる。したがって、任意の時刻t=t1における膨張距離はt=0からの積分値として求められ、これによって押し込み深さを補正することができる。図3は補正前後の荷重-変位曲線で、補正後は室温試験と同様の曲線が得られる。 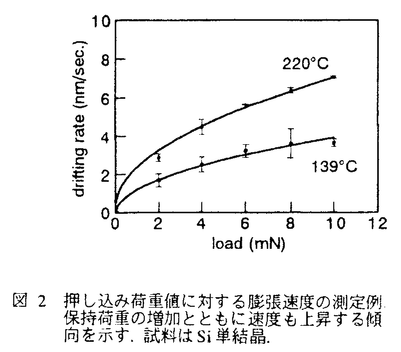 図2押し込み荷重値に対する膨張速度の測定例.保持荷重の増加とともに速度も上昇する傾向を示す.試料はSi単結晶. 図2押し込み荷重値に対する膨張速度の測定例.保持荷重の増加とともに速度も上昇する傾向を示す.試料はSi単結晶.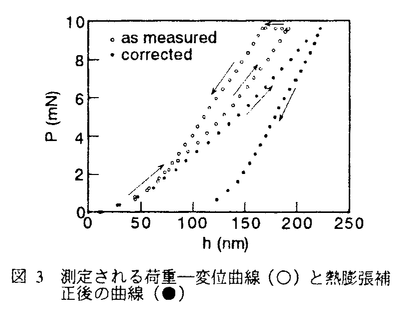 図3測定される荷重-変位曲線(○)と熱膨張補正後の曲線(●) 図3測定される荷重-変位曲線(○)と熱膨張補正後の曲線(●) 超微小押込試験によって得られる荷重-変位曲線は、試料の弾性および塑性変形の複合過程であるため、いかにしてそこからconventional hardnessを算出するかが課題となる。これに対して、硬さの算出法の一つとして次のような方法が提案されている[12]。荷重Pと押込み深さhがP=Bh2+Ch(B,Cはconst.)の関係に近似されることを利用し、P/h-hにプロットして得られる勾配Bが経験的にHvと比例関係にある(図4)ことからHvへの換算を行う方法である。しかし、この方法を適用できるのはHv=400程度よりも軟らかい材料に対してであり、それよりも硬い材料では弾性変形分が無視できなくなる。totalの押し込み深さに対する弾性変形分は、除荷曲線の解析によって求められるinitial unloading stiffness Sから求めることができる。しかし、その割合は圧子と試料の接触面積によって変化するので、あらかじめ実験的にhとSの関係を求めることが必要である。図5は各材料に対して求められたSとhの関係で、いずれもよい直線関係にある。これらのS、hとこれに対応するPからhc=h-P/Sを用いて負荷過程の全領域にわたって弾性変形分を補正することができる。この補正を行った荷重-変位曲線から算出される硬さは、図6に示すようにHv=1000程度までHvとよい比例関係にある。また電子顕微鏡で直接観察した圧痕の面積から硬さHを求めて比較すると、図7のように、B/Hの値は図6から求めた比例定数34.7によく一致する。 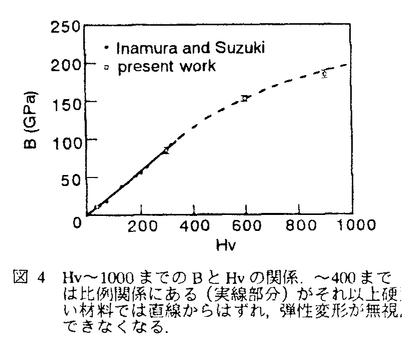 図4Hv〜1000までのBとHvの関係.〜400までは比例関係にある(実線部分)がそれ以上硬い材料では直線からはずれ,弾性変形が無視できなくなる. 図4Hv〜1000までのBとHvの関係.〜400までは比例関係にある(実線部分)がそれ以上硬い材料では直線からはずれ,弾性変形が無視できなくなる.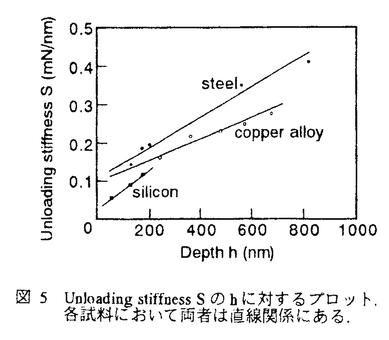 図5Unloading stiffness Sのhに対するプロット.各試料において両者は直線関係にある. 図5Unloading stiffness Sのhに対するプロット.各試料において両者は直線関係にある.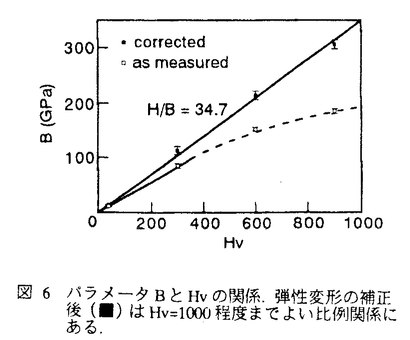 図6パラメータBとHvの関係.弾性変形の補正後(■)はHv=1000程度までよい比例関係にある. 図6パラメータBとHvの関係.弾性変形の補正後(■)はHv=1000程度までよい比例関係にある.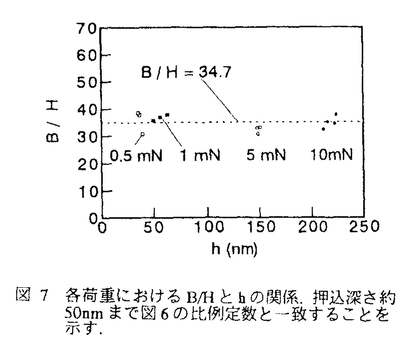 図7各荷重におけるB/Hとhの関係.押込深さ約50nmまで図6の比例定数と一致することを示す. 図7各荷重におけるB/Hとhの関係.押込深さ約50nmまで図6の比例定数と一致することを示す. 図8は上述の測定技術および解析方法を応用して得られたSiの荷重-変位曲線である。黒丸は弾性変形分の補正前、白丸は補正後をそれぞれ示している。室温の荷重-変位曲線では、除荷曲線上に回復速度が大きく変化する点(図中のR)が現れ、除荷後の圧痕の深さは最大押し込み深さの約1/3までに回復する。SEM観察の結果、室温の圧痕は錘面が膨れ上がって凸に湾曲しており、周囲にも堆積した部分が観察される。これに対して600℃では、除荷曲線は滑らかで圧痕形状も室温とは異なり金属材料に類似した平面的な錘面となる。補正後の曲線を解析して算出される硬さを温度に対してプロットしたものが図9である。超微小硬さの温度依存性はマイクロ・ビッカース硬さと同様の傾向を示し、室温から約500℃まではほぼ一定でそれよりも高い温度域では温度の上昇とともに硬さが急激に降下する。室温の硬さは12〜13GPaで、ダイヤモンド構造から -tin構造への相転移圧力にほぼ等しい。図10は各温度で試験を行った後の圧痕を透過電子顕微鏡(TEM)で観察したものである。室温で形成した圧痕の内部及び周辺部には転位は観察されない。また、圧痕内部の制限視野回折像はamorphousもしくは微細結晶を特徴づけるハロー・リングを形成する。300℃では、圧痕内部に転位が観察されるが外側には全く観察されず、回折図形はハロー・リングと回折斑点が重なった像となる。一方、硬さが温度に依存する高温度域では圧痕の外側にも多数の転位が観察され、それらは圧痕から外側に拡がる組織を形成する。また、回折図形にはハロー・リングは現れない。 -tin構造への相転移圧力にほぼ等しい。図10は各温度で試験を行った後の圧痕を透過電子顕微鏡(TEM)で観察したものである。室温で形成した圧痕の内部及び周辺部には転位は観察されない。また、圧痕内部の制限視野回折像はamorphousもしくは微細結晶を特徴づけるハロー・リングを形成する。300℃では、圧痕内部に転位が観察されるが外側には全く観察されず、回折図形はハロー・リングと回折斑点が重なった像となる。一方、硬さが温度に依存する高温度域では圧痕の外側にも多数の転位が観察され、それらは圧痕から外側に拡がる組織を形成する。また、回折図形にはハロー・リングは現れない。 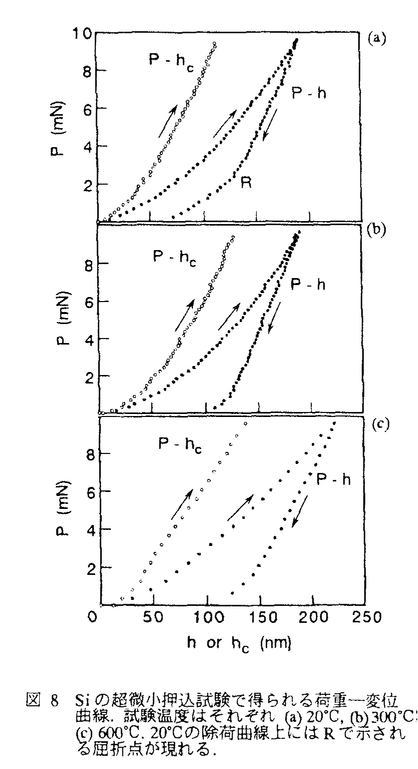 図8Siの超微小押込試験で得られる荷重-変位曲線.試験温度はそれぞれ(a)20℃,(b)300℃,(c)600℃.20℃の除荷曲線上にはRで示される屈折点が現れる. 図8Siの超微小押込試験で得られる荷重-変位曲線.試験温度はそれぞれ(a)20℃,(b)300℃,(c)600℃.20℃の除荷曲線上にはRで示される屈折点が現れる.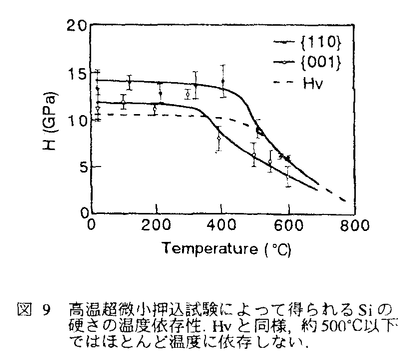 図9高温超微小押込試験によって得られるSiの硬さの温度依存性.Hvと同様,約500℃以下ではほとんど温度に依存しない. 図9高温超微小押込試験によって得られるSiの硬さの温度依存性.Hvと同様,約500℃以下ではほとんど温度に依存しない.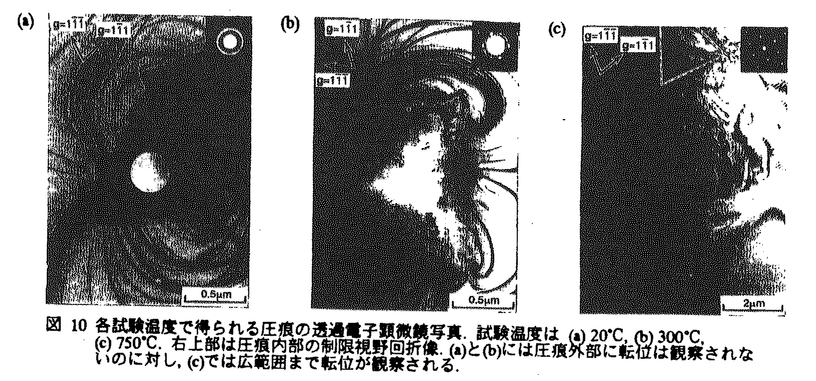 図10各試験温度で得られる圧痕の透過電子顕微鏡写真.試験温度は(a)20℃,(b)300℃,(c)750℃.右上部は圧痕内部の制限視野回折像.(a)と(b)には圧痕外部に転位は観察されないのに対し,(c)では広範囲まで転位が観察される. 図10各試験温度で得られる圧痕の透過電子顕微鏡写真.試験温度は(a)20℃,(b)300℃,(c)750℃.右上部は圧痕内部の制限視野回折像.(a)と(b)には圧痕外部に転位は観察されないのに対し,(c)では広範囲まで転位が観察される. 以上の結果を高圧下のSiの構造相転移に関する研究と照らし合わせると、圧痕の形成メカニズムは次のように説明される。500℃以下においては、負荷過程における圧痕の形成は、塑性変形が支配するのではなく、ダイヤモンド構造から -tin構造への相転移にともなう約20%の体積収縮によって担われる。室温付近では、除荷過程でこの -tin構造への相転移にともなう約20%の体積収縮によって担われる。室温付近では、除荷過程でこの -tin相はamorphous相または微小結晶に変化することにより体積が膨張し、圧痕の深さが回復する。その際、非平衡bcc構造(BC-8)を経由することも考えられる。300℃程度の中間温度域では、圧痕底部の転位源が働くものの、移動度が低いことや相転移によって応力場が緩和されるために長い距離を移動することができず、室温と同様に圧痕形成は相転移が支配するものと考えられる。図11はSiのtemperature-pressure diagramである[13]。これと照らし合わせると、500℃以下で硬さが一定であるのは、ダイヤモンド構造から -tin相はamorphous相または微小結晶に変化することにより体積が膨張し、圧痕の深さが回復する。その際、非平衡bcc構造(BC-8)を経由することも考えられる。300℃程度の中間温度域では、圧痕底部の転位源が働くものの、移動度が低いことや相転移によって応力場が緩和されるために長い距離を移動することができず、室温と同様に圧痕形成は相転移が支配するものと考えられる。図11はSiのtemperature-pressure diagramである[13]。これと照らし合わせると、500℃以下で硬さが一定であるのは、ダイヤモンド構造から -tin構造への相転移圧力が温度によらずほぼ一定であるためと結論づけられる。また、diagram上に破線で重ねた曲線はH=50 -tin構造への相転移圧力が温度によらずほぼ一定であるためと結論づけられる。また、diagram上に破線で重ねた曲線はH=50 cと見積もって硬さの軸と合わせた降伏応力の温度依存性である。diamond- cと見積もって硬さの軸と合わせた降伏応力の温度依存性である。diamond- -tin転移の線とは約500℃で交差している。つまり、500℃以上では、熱的に活性化された転位が長範囲を運動することが可能となり、塑性変形が相転移よりも優先的に変形を担うため、この温度域での硬さは降伏応力と同様に強い温度依存性を示す。 -tin転移の線とは約500℃で交差している。つまり、500℃以上では、熱的に活性化された転位が長範囲を運動することが可能となり、塑性変形が相転移よりも優先的に変形を担うため、この温度域での硬さは降伏応力と同様に強い温度依存性を示す。 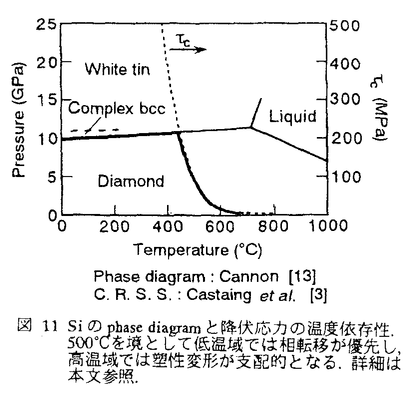 図11Siのphase diagramと降伏応力の温度依存性.500℃を境として低温域では相転移が優先し,高温域では塑性変形が支配的となる.詳細は本文参照. 図11Siのphase diagramと降伏応力の温度依存性.500℃を境として低温域では相転移が優先し,高温域では塑性変形が支配的となる.詳細は本文参照. 本研究では、高温測定の技術を確立し、また広い範囲の材料に適用可能な硬さの算出方法を提案した。また、これらを応用することにより、Siの圧痕形成機構と硬さの温度依存性の発現原因について明らかにした。半導体ではSiのほかにもGeやGaAsなどで、また、一部の酸化物系セラミックスにも同様の相転移が起こることが報告されている。今後は、これらの材料についても測定を行い、降伏応力や相転移圧の温度依存性と比較することによって、圧痕の形成機構に及ぼす相転移の影響をより詳細に知ることができると考えられる。さらに、金属材料に比べて圧痕の形成メカニズムがよく知られていないセラミックスなどの脆性材料に広く応用範囲を広げ、硬さ試験によってこれらの材料の本質的な特性を評価するための系統的研究が必要であろう。 参考文献[1]D.Tabor,Proc.Roy.Soc.London A 192,(1948)247.[2]D.Tabor,Hardness of Metals,Clarendon Press,Oxford,(1951).[3]J.Castaing,P.Veyssiere,L.P.Kubin and J.Rabier,Phil.Mag.A,44,(1981)1407.[4]Nikitenko,sited in Ref.5.[5]J.J.Gilman,J.Appl.Phys.,39,(1968)6086.[6]I.V.Gridneva,Yu.V.Milman and V.I.Trefilov,phys.stat.sol.(a),14(1972)177.[7]A.P.Gerk and D.Tabor,Nature,271(1978)732.[8]D.R.Clarke,M.C.Kroll,P.D.Kirchner,R.F.Cook and B.J.Hockey,Phys.Lev.Lett.,60(1988)2156.[9]G.M.Pharr,W.C.Oliver and D.R.Clarke,Scr.Metall.,23(1989)1949.[10]G.M.Pharr,W.C.Oliver and D.R.Clarke,J.Elec.Mater,19(1990)881.[11]T.F.Page,W.C.Oliver and C.J.McHargue,J.Mater.Res.,7(1992)450.[12]稲村元則,鈴木敬愛,生産研究,42(1990)257.[13]J.F.Cannon,J.Phys.Chem.Ref.Data,3(1974)781. |
| 審査要旨 | | 超微小押込試験は、ダイヤモンド圧子を1gf以下の低荷重で試料表面に押込みまた引抜く過程の荷重と変位の関係を測定し、材料表面のミクロな領域の力学特性を知る実験方法である。本論文は「高温超微小押込試験とsiliconの圧痕形成機構」と題し、超微小押込試験を高温で行うための技術的問題、高硬度材料に適用可能な解析方法、ならびに、その応用としてのSi単結晶の圧痕形成機構に関する研究の成果をまとめたもので、全5章からなる。 第一章序論では、超微小押込試験の方法と従来の研究について概観し、実験手法としての有用性は高温測定技術の確立に依存すること、セラミックスのような硬度の高い材料に応用できる解析方法を確立することの必要性を強調している。さらに、高温超微小押込試験の具体的な応用について考察し、Siの圧痕形成機構解明の可能性を指摘して研究の目的としている。 第二章は、超微小押込試験を高温で行うための技術的問題とその解決方法に関する記述である。まず、試料と圧子の温度差によって生ずる試料温度の変化を直接計測することを試み、10秒以下の短時間計測であれば温度の低下は数℃以内に止まることを確認している。次いで、試料と装置の熱膨張が変位計測にもたらすドリフトについて詳細な実験を行い、測定される圧子の押込変位から熱ドリフト分を差引いて補正する方法を提示している。これらの技術的問題の解決の結果、室温のみに限られていた超微小押込試験が大きく精度を損なうことなく600℃まで行えることとなった。 第三章は、超微小押込試験のデータ解析法に関する記述である。ビッカース硬度計と異なり、超微小押込試験では圧子の変位と荷重との関係が押込-除荷の全過程で連続記録される。その関係から通常の硬度や弾性定数を算出する方法は未だ確立しているとはいえない。特に、半導体材料やセラミックスのように硬度の大きい材料では、押込過程における圧子の侵入は材料の塑性変形のみでなく弾性変形の寄与とともに進行する。硬度の算定には、正味の塑性変形量を求める必要がある。それを行うに、圧子の引抜き過程における弾性回復を利用する。最大押込荷重を様々に変えることによって、押込みの全段階における塑性変形量を算出し、弾性変形分を含まない荷重-変位曲線を求めて硬度を算定する。こうして求めた硬度は、圧痕の面積を直接電子顕微鏡によって測ることによって得られる硬度とよく一致することが確かめられ、ビッカース硬度1000以上の硬い材料まで適用できる荷重-変位曲線の解析方法が確立したといえる。 第四章は、前二章の方法を応用したSiの圧痕形成機構に関する研究の記述である。Siの硬度は500℃以上では温度とともに減少するが、500℃以下ではほとんど温度に依存しない。き裂の生成や構造相転移の可能性が論じられてきたが、荷重の小さい超微小押込試験では、押込み過程でのき裂の発生を監視することができる。硬度の温度依存性の測定とともに、透過電子顕微鏡観察ならびに走査電子顕微鏡観察を行い、圧痕の構造と形状が温度とともにどのように変化するかを系統的に調べている。500℃以上では圧痕から多数の転位の放出が見られるのに対して、500℃以下では転位はほとんど観られず、電子線回折像は非晶質様の像を提する。500℃以下の硬度約1200がダイヤモンド構造から -錫構造への相転移圧にほぼ一致すること、 -錫構造への相転移圧にほぼ一致すること、 -錫構造は減圧過程で非晶質(あるいはダイヤモンド構造の微結晶)に転移すること等を考慮して、Siの圧痕形成機構を次のように結論している。500℃以下では -錫構造は減圧過程で非晶質(あるいはダイヤモンド構造の微結晶)に転移すること等を考慮して、Siの圧痕形成機構を次のように結論している。500℃以下では -錫構造への相転移による約20%の体積減少が圧痕形成を担うが、高温では構造相転移に優先して塑性変形が起こり、金属と同様に圧痕は形成される。この結論は、Siの硬度に関する長年の議論に終止符を打つものといえる。 -錫構造への相転移による約20%の体積減少が圧痕形成を担うが、高温では構造相転移に優先して塑性変形が起こり、金属と同様に圧痕は形成される。この結論は、Siの硬度に関する長年の議論に終止符を打つものといえる。 第五章は総括である。 以上を要するに、本論文は超微小押込試験を600℃の高温まで応用可能な技術として確立し、ビッカース硬度1000を越える高硬度材料にも適用可能な解析方法を提示した点において工学とりわけ材料科学の分野に寄与するところ大である。また、Siの圧痕形成機構を明らかにしたことは材料物性学の分野に新たな知見を加えたものである。 よって、本論文は博士(工学)の学位請求論文として合格と認められる。 |