AGSエネルギー領域(核子あたり10-20GeV/cでの)原子核・原子核衝突からの反陽子生成の研究は以下の点で非常に重要である。まず、このエネルギー領域は反陽子の生成閾値に近いため、核子-核子衝突でエネルギーを失った核子のほとんどは二度と反陽子を生成できない。従って、このエネルギー領域での原子核-原子核衝突での反陽子生成はハドロンの多段階励起過程やクォークグルーオンプラズマなどの協同課程の存在に敏感であると考えられる。一方Au+Auの中心衝突において、バリオン密度は通常の原子核密度の約10倍に達すると予測されているが、反陽子の核子による吸収効果はバリオン密度と密接な関係があるため、高バリオン密度を反陽子を用いて評価することが期待される。 重イオン衝突実験で観測される反陽子の収量は、反陽子の初期生成及び核子による吸収の競合の結果であるが、その二つの効果を抽出することは未解決の課題である。この論文では、以下のような観測を通じてそれらの探求を試みる。 1.反陽子の収量の衝突系の大きさや衝突径数への依存性。 2.横質量スペクトルの形の衝突径数への依存性。 3.ラピディティー分布の形の衝突径数への依存性。 現在までにAGSで行われた実験の結果、核子あたり14.6GeV/cでのp+A、Si+A衝突からの反陽子の収量は入射原子核中の「傷付いた」核子数(Nproj)にほぼ比例することがわかっている。 アメリカ合衆国のブルックヘブン国立研究所(BNL)のAlternative Gradient Synchrotron(AGS)で行われたE866実験は、核子あたり11.7GeV/cのAuビームとAu標的との衝突で生成した粒子の生成の研究を目的とした実験である。我々はE866実験において、Au+Au衝突で生成した反陽子を測定した。この反陽子測定はAGSエネルギー領域のAu+Au衝突の実験で、横質量の広い範囲に及ぶものとしては世界最初のものである。 図1はE866の実験装置を上方から見た図である。E866実験装置は、2つのスペクトロメーターからなる。我々はこのうち図の下方にある、前方スペクトロメーターで得られたデータを用いた。前方スペクトロメーターは、2つのダイポールマグネット(FM1、FM2)、2つの複合荷電粒子飛跡検出装置(FT1+TPC1+FT2、FT3+TPC2+FT4)、1台の飛行時間測定器(FTOF)からなる。 筆者は、E866実験において前方スペクトロメーターに設置されたTPC2の設計と製作、TPC1とTPC2のテスト、本実験においてはTPC1とTPC2のオペレーションを担当した。データー解析においては志垣賢太氏とともに前方スペクトロメーターにおける飛跡再構成のプログラムを開発した。またこの論文で使われた1500万イベントのデータについてTPCのパラメータの較正を行い、2ヶ月にわたるデータ解析の準備と総指揮を行った。 我々は1994年10-11月に行われた実験において、前方スペクトロメーターの角度が6-24度の範囲で、1500万個の事象を収集し、データ解析の結果、総計800個の反陽子を得た。我々はインクルーシブ事象において、またいくつかの衝突径数の範囲で区切った場合について反陽子の生成断面積を求めた。図2はインクルーシブ事象での反陽子の横質量スペクトルを示す。 求めたAu+Au衝突での断面積を様々な衝突系、セントラリティーについて系統的に比較した。第一に、反陽子の収量の入射原子核の「傷付いた」核子数(Nproj)に対する依存性を調べた。反陽子のビームエネルギー補正を加えたdN/dyはp+A、Si+A衝突についてほぼ比例し、原点を通る直線(破線)にのるが、Au+Au衝突でのdN/dyはその直線のわずか30-60%に過ぎない(図3参照)。 第二に、Au+Au衝突での各粒子のdN/dyの比、 / / -、p/ -、p/ -,K-/ -,K-/ -,K+/ -,K+/ -, -, +/ +/ -をNprojの関数として比較した。 -をNprojの関数として比較した。 / / -が減少するのに対し、p/ -が減少するのに対し、p/ -,K-/ -,K-/ -,K+/ -,K+/ -は増加し、 -は増加し、 +/ +/ -はほぼ一定である(図4参照)。 -はほぼ一定である(図4参照)。 これらの二つの観測結果はいずれも、AGSエネルギー領域においてAu+Au衝突系での反陽子の吸収効果がp+A、Si+A衝突系に比べて強いことを示唆するものである。 次にカスケード模型、RQMDの計算結果をデータと比較した。RQMDでは、反陽子は、ハドロンの多段階励起過程から初期生成され、その後自由N 消滅断面積により核子に吸収される。RQMDはp+A,Si+A,Au+Auまでの反陽子の収量の大局的な傾向を再現した。 消滅断面積により核子に吸収される。RQMDはp+A,Si+A,Au+Auまでの反陽子の収量の大局的な傾向を再現した。 最後に反陽子の収量からA+A衝突でのバリオン密度を「静的吸収長模型」を用いて探求した。この模型はRQMDの初期生成、自由N 消滅断面積を用いた吸収長を仮定する。まず、RQMDを用いて様々な衝突系におけるバリオン密度を計算した。Si+Al、Si+Auの中心衝突での最大バリオン密度は通常原子核の約5倍、Au+AU衝突では周辺衝突(セントラリティー50-100%)で約3倍、中心衝突(セントラリテイー0-10%)で約8倍であった。A+A衝突においては、相対運動量の違いにより、「反応参加核子(反応に関与した核子)」による吸収断面積は「傍観者核子(反応に関与しない核子)」による吸収断面積よりも約3倍大きい。したがって模型では反応参加核子による吸収のみを考慮した。反応参加核子の平均密度を 消滅断面積を用いた吸収長を仮定する。まず、RQMDを用いて様々な衝突系におけるバリオン密度を計算した。Si+Al、Si+Auの中心衝突での最大バリオン密度は通常原子核の約5倍、Au+AU衝突では周辺衝突(セントラリティー50-100%)で約3倍、中心衝突(セントラリテイー0-10%)で約8倍であった。A+A衝突においては、相対運動量の違いにより、「反応参加核子(反応に関与した核子)」による吸収断面積は「傍観者核子(反応に関与しない核子)」による吸収断面積よりも約3倍大きい。したがって模型では反応参加核子による吸収のみを考慮した。反応参加核子の平均密度を とし、体積は球を縦方向に とし、体積は球を縦方向に / / だけ圧縮した回転楕円体であると仮定する。反応参加核子による吸収長(通常原子核の密度において約0.65fm)は反応参加核子の大きさ(球と仮定したときAu+Auの中心衝突で約8fm)よりはるかに小さいので、静的吸収長模型は、反応参加核子の体積の表面付近で生成された反陽子のみが吸収されずに生き残るという描像を予言するが、これはRQMDの計算結果と一致する。RQMDの初期収量はNpart(反応参加核子数)に比例するが、それを取り入れた我々の模型は反陽子の最終収量が だけ圧縮した回転楕円体であると仮定する。反応参加核子による吸収長(通常原子核の密度において約0.65fm)は反応参加核子の大きさ(球と仮定したときAu+Auの中心衝突で約8fm)よりはるかに小さいので、静的吸収長模型は、反応参加核子の体積の表面付近で生成された反陽子のみが吸収されずに生き残るという描像を予言するが、これはRQMDの計算結果と一致する。RQMDの初期収量はNpart(反応参加核子数)に比例するが、それを取り入れた我々の模型は反陽子の最終収量が に比例するという実験結果を再現した。実験データとの比較を行った結果、反応参加核子の体積での平均のバリオン密度に対する表面付近でのバリオン密度の比が衝突系にかかわらず、3〜4の範囲で一定であるという結果が得られた。 に比例するという実験結果を再現した。実験データとの比較を行った結果、反応参加核子の体積での平均のバリオン密度に対する表面付近でのバリオン密度の比が衝突系にかかわらず、3〜4の範囲で一定であるという結果が得られた。 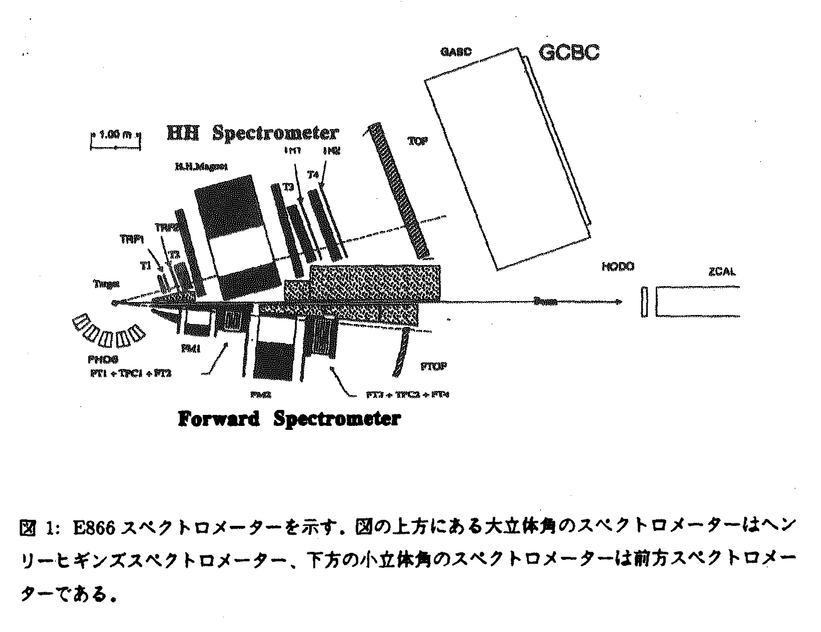 図1:E866スペクトロメーターを示す。図の上方にある大立体角のスペクトロメーターはヘンリーヒギンズスペクトロメーター、下方の小立体角のスペクトロメーターは前方スペクトロメーターである。 図1:E866スペクトロメーターを示す。図の上方にある大立体角のスペクトロメーターはヘンリーヒギンズスペクトロメーター、下方の小立体角のスペクトロメーターは前方スペクトロメーターである。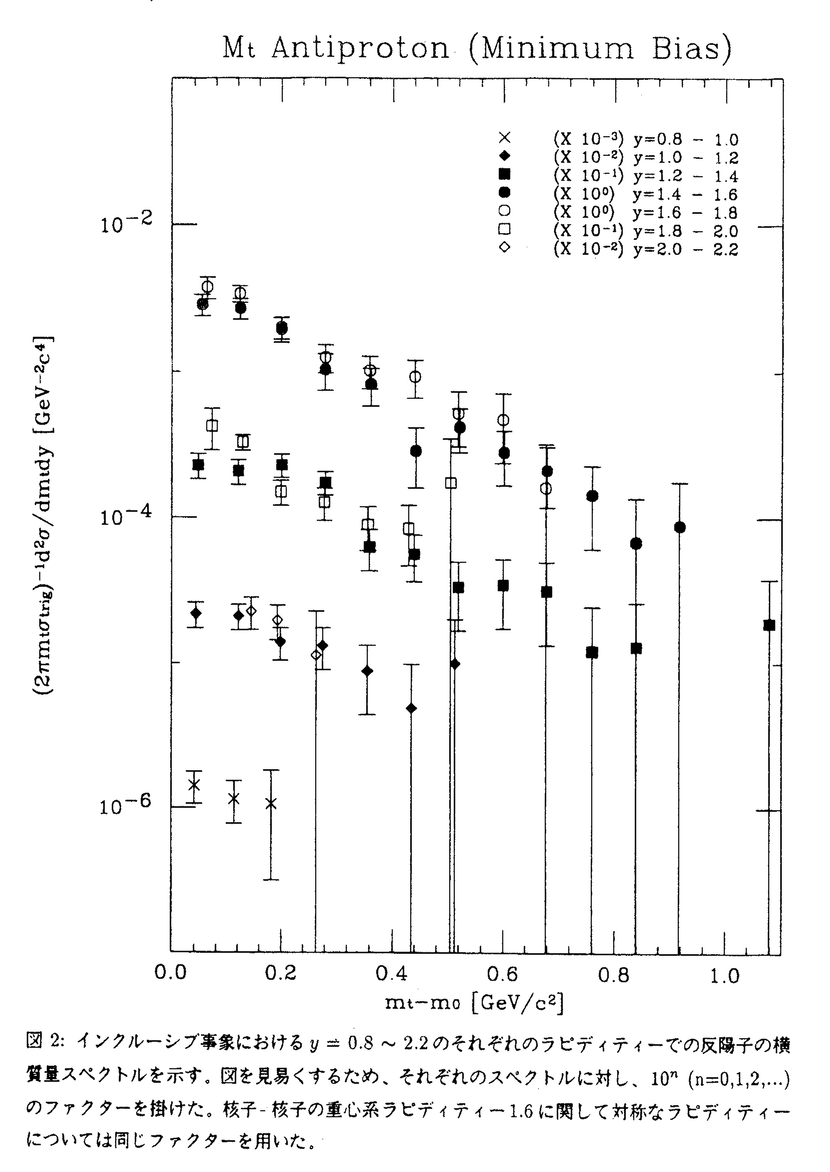 図2:インクルーシブ事象におけるy=0.8〜2.2のそれぞれのラピディティーでの反陽子の横質量スペクトルを示す。図を見易くするため、それぞれのスペクトルに対し、10n(n=0,1,2,...)のファクターを掛けた。核子-核子の重心系ラピディティー1.6に関して対称なラピディティーについては同じファクターを用いた。 図2:インクルーシブ事象におけるy=0.8〜2.2のそれぞれのラピディティーでの反陽子の横質量スペクトルを示す。図を見易くするため、それぞれのスペクトルに対し、10n(n=0,1,2,...)のファクターを掛けた。核子-核子の重心系ラピディティー1.6に関して対称なラピディティーについては同じファクターを用いた。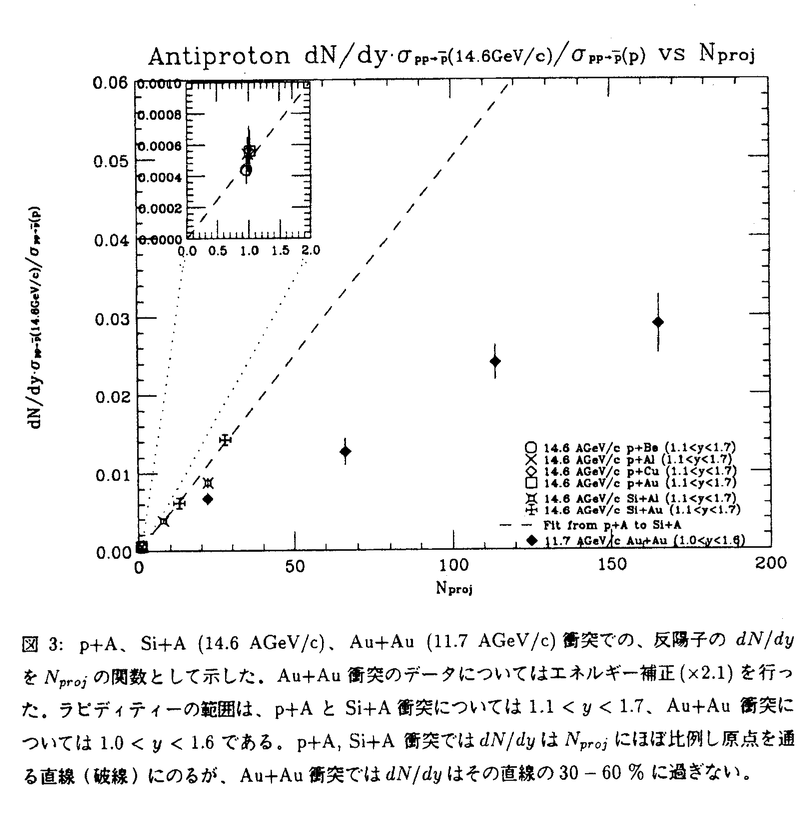 図3:p+A、Si+A(14.6AGeV/c)、Au+Au(11.7AGeV/c)衝突での、反陽子のdN/dyをNprojの関数として示した.Au+Au衝突のデータについてはエネルギー補正(×2.1)を行った。ラピディティーの範囲は、p+AとSi+A衝突については1.1<y<1.7、Au+Au衝突については1.0<y<1.6である。p+A,Si+A衝突ではdN/dyはNprojにほぼ比例し原点を通る直線(破線)にのるが、Au+Au衝突ではdN/dyはその直線の30-60%に過ぎない。 図3:p+A、Si+A(14.6AGeV/c)、Au+Au(11.7AGeV/c)衝突での、反陽子のdN/dyをNprojの関数として示した.Au+Au衝突のデータについてはエネルギー補正(×2.1)を行った。ラピディティーの範囲は、p+AとSi+A衝突については1.1<y<1.7、Au+Au衝突については1.0<y<1.6である。p+A,Si+A衝突ではdN/dyはNprojにほぼ比例し原点を通る直線(破線)にのるが、Au+Au衝突ではdN/dyはその直線の30-60%に過ぎない。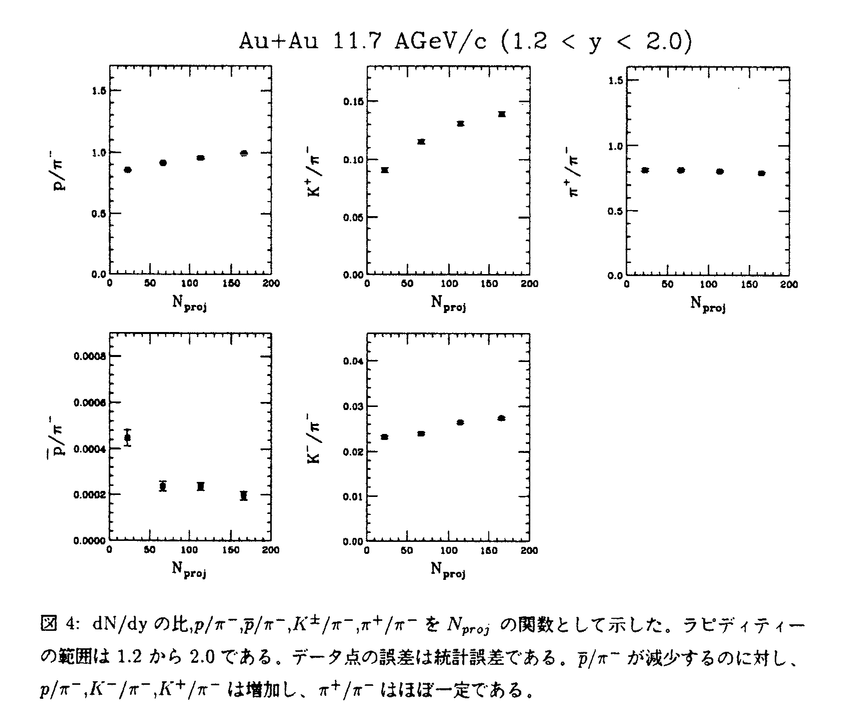 図4:dN/dyの比,p/ 図4:dN/dyの比,p/ -, -, / / -,K±/ -,K±/ -, -, +/ +/ -をNprojの関数として示した。ラピディティーの範囲は1.2から2.0である.データ点の誤差は統計誤差である。 -をNprojの関数として示した。ラピディティーの範囲は1.2から2.0である.データ点の誤差は統計誤差である。 / / -が減少するのに対し、p/ -が減少するのに対し、p/ -,K-/ -,K-/ -,K+/ -,K+/ -は増加し、 -は増加し、 +/ +/ -はほぼ一定である。 -はほぼ一定である。 |