トレーニングとは、一定水準以上の筋活動の継続を行うことにより、身体を鍛えることを意味する。人間の身体作業能力は、出生以来向上し続け、20歳代でのピークを過ぎると、加齢とともに低下していく。しかし、一生の間のある期間に限ってみれば、ほぼ一定の能力を保持しているようにみえる。そして、その水準は、トレーニングを行うことで増加し、日常生活での活動量の低下で減少する。現代の我々を取り巻く環境では、一般的に、疾病や障害がなくても、交通機関の発達や、各種施設でのエスカレーター・エレベーターの普及などにより、筋活動量は以前に比べ減少し、身体作業能力の水準がかなり低いところにある人の割合が、増加していると考えられる。そこでトレーニングの実施を推奨し、それにより身体作業能力の低下をくい止め、性・年齢に応じた一定水準の能力を保持・増大をはかろうとする試みが行われるようになった。これは、各個人の身体特性を調査したうえで、適切な運動量を提示し、その実行を促すもので、一般に、運動処方と呼ばれる。運動処方の中でも、酸素を取り込み、それを利用して運動のエネルギーを供給し、呼吸循環系機能を活発に活動させる有酸素性運動を用いたトレーニングに本論文は着目した。そして、その有酸素性トレーニングを対象として、トレーニングとトレーニングによる適応の過程を入出力関係とした数学的モデルを用い、ほぼ毎日の測定データから得たトレーニングの時系列データから、トレーニング経過に伴う各種生体反応の変化の予測を行うことを本論文の目的とする。 トレーニングによる適応現象の評価に用いたモデルは、以下のようなモデルである。 Calvertら(1976)らは、一回のトレーニング(w(t))の効果が、身体運動のパフォーマンスの伸び(p(t))に及ぼす影響を、以下のような1次の微分方程式で表した。 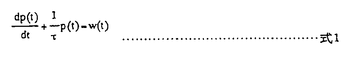 1式をラプラス変換すると、入力信号(トレーニング量)と出力信号(パフォーマンスの伸び)の間の伝達関数は以下のように表わされる。 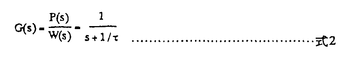 2式を逆ラプラス変換すれば容易に伝達関数(f(t))がexp(-t/tau)で表されることがわかる。 以上より、トレーニングを継続的に行った場合のパフォーマンスの伸びの経時的変化は、トレーニング量と伝達関数のたたみこみ積分として表現できる。 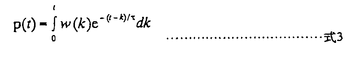 本研究では、パフォーマンスの伸びそのものがトレーニング効果のたたみこみ積分として表現されるのではなく、トレーニングがパフォーマンスの伸びに及ぼす影響をプラスの影響、マイナスの影響に分離し、そのおのおのが3式のように表されると仮定する(Mortonら1990)。ここでいうプラスの影響、マイナスの影響とは、パフォーマンスを表す指標の数値が、増加あるいは減少することへの影響を意味する。 すなわち、プラスの影響とマイナスの影響を表す時間関数をそれぞれ、g(t)、h(t)とすれば 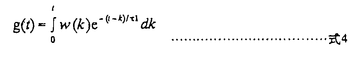 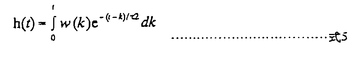 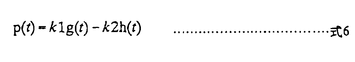 (k1:トレーニングのプラスの効果のための係数、k2:トレーニングのマイナスの効果のための係数、 1:プラスの効果の時定数、 1:プラスの効果の時定数、 2:マイナスの効果の時定数) 2:マイナスの効果の時定数) 式6を離散形に直すと以下の式になる。 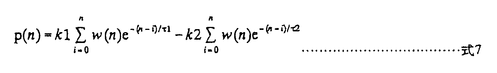 このモデルを用いて求めたパフォーマンスの予測値と実測値との残差の平方和が最小になるように、k1、k2、 1、 1、 2の4つのパラメーターを算出した。その際に、k1とk2の値が正になることと、 2の4つのパラメーターを算出した。その際に、k1とk2の値が正になることと、 1、 1、 2は整数値をとり、さらにトレーニング実施日数を越えないことを制約条件とした。 2は整数値をとり、さらにトレーニング実施日数を越えないことを制約条件とした。 予測に用いたデータは、換気性作業閾値を運動強度として12週間の有酸素性トレーニングを行った6名の健常な男女大学院生から得た。換気性作業閾値とは、疲労の蓄積を起こさずに長時間運動を行うことができる最も高い強度であり、漸増負荷運動中の換気応答の変局点から各個人で相対的に決定される運動強度である。トレーニングの強度の指標としても、トレーニング効果を表す指標としても広く用いられている。本論文では、身体作業能力の指標として、トレーニング刺激も含めてさまざまな要因によって、相対的に変化する性質をもつ換気性作業閾値の変化に着目した。トレーニング群6名は、週に5回1晩絶食ののち、午前中に研究室を訪れ、安静時の心拍変動および血圧変動の測定と、換気性作業閾値を決定するための漸増負荷運動テストを各々の最大酸素摂取量に合わせて8〜15分間行った。その他に形態計測(体重、皮脂厚など)や前日の睡眠時間、その日の体調なども記録した。そして午後に5分間のウォーミングアップの後、換気性作業閾値に相当する負荷での自転車こぎを30分間行った。日々の測定およびトレーニングは週に5日、計12週間行った。また6名中3名ではトレーニング中止の影響をみるため、午前中の測定のみをトレーニング終了後4週間継続した。図1に、トレーニング群6名全員のトレーニング経過に伴う換気性作業閾値の変化を示した。図中の実線は、単回帰モデルにより求めた予測式である。単回帰モデルから求めた相関係数により、6名中4名ではトレーニング経過に伴う有意な増加傾向が認められ、1名では変化がみられず、残りの1名ではトレーニング経過に伴う有意な減少傾向が認められた。このように、同じ強度のトレーニングを行った場合でも、被検者によっては、毎日測定した換気性作業能力は必ずしも一様な変化を示さなかった。適応現象に被検者間で差が生じたのは、他の測定項目についても同様であった。またトレーニングを行ったにもかかわらず、換気性作業閾値にトレーニング経過に伴う有意な減少傾向が認められた被検者では、体重が約10%減少し、こうした体重の急激な減少が換気性作業閾値の減少に影響した可能性も考えられる。 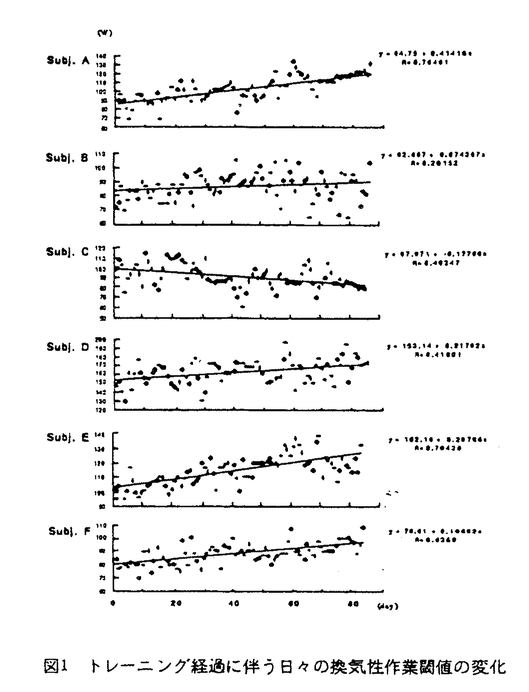 図1 トレーニング経過に伴う日々の換気性作業閾値の変化 図1 トレーニング経過に伴う日々の換気性作業閾値の変化 次に、前述のモデルを用いたトレーニングによる適応現象の予測を行った。入力信号はトレーニング量(トレーニング中の心拍数から安静時心拍数を減じた値)とし、出力信号である適応現象には、トレーニング群の測定結果から、換気性作業閾値、体脂肪率、心拍変動の周波数解析から求めた副交感神経活動指標、およびトレーニング中の心拍数の4つであった。これらは、トレーニングを行った結果生じる適応現象の指標として、多くの先行研究で用いられ、生理学的関連も報告されているものである。その結果、換気性作業閾値とトレーニング中の心拍数では全被検者でモデルによる予測値と実測値に正の相関がみられた。また体脂肪率と副交感神経活動指標では、それぞれ1名の被検者を除き同様に正の相関が確認された。また各被検者で同定されたモデルの係数は、さまざまな値を示した。換気性作業閾値の各被検者のモデルの係数を表1に示す。 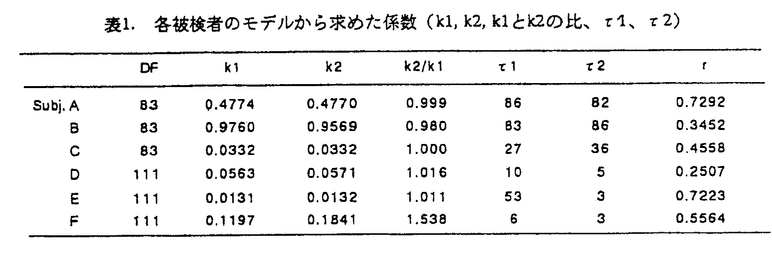 表1. 各被検者のモデルから求めた係数(k1,k2,k1とk2の比、 表1. 各被検者のモデルから求めた係数(k1,k2,k1とk2の比、 1、 1、 2) 2) 単回帰モデルの評価で、換気性作業閾値にトレーニング経過に伴う増加傾向がみられたSubj.A、D、E、Fの4名では、 1が 1が 2よりも大きな値を示した。また残りの2名は、単回帰モデルの評価で換気性作業閾値がトレーニング経過に伴い減少した、あるいは変化しなかった被検者で、 2よりも大きな値を示した。また残りの2名は、単回帰モデルの評価で換気性作業閾値がトレーニング経過に伴い減少した、あるいは変化しなかった被検者で、 1と 1と 2の大小関係が前述の4名と逆転していた。これは、 2の大小関係が前述の4名と逆転していた。これは、 1が 1が 2よりも大きい、すなわちトレーニングによる効果が消失する時間よりも、効果が残る時間が長かったモデルでは、換気性作業閾値が増加傾向にあり、逆に効果が残る時間より消失する時間のほうが短かったモデルでは、減少あるいは変わらない傾向にあったことを示す。これらの結果から、モデルによる予測の妥当性が確認されただけでなく、同定されたモデルの特性によって、適応現象の個人差が生じることも明らかになった。 2よりも大きい、すなわちトレーニングによる効果が消失する時間よりも、効果が残る時間が長かったモデルでは、換気性作業閾値が増加傾向にあり、逆に効果が残る時間より消失する時間のほうが短かったモデルでは、減少あるいは変わらない傾向にあったことを示す。これらの結果から、モデルによる予測の妥当性が確認されただけでなく、同定されたモデルの特性によって、適応現象の個人差が生じることも明らかになった。 最後に、換気性作業閾値でのトレーニングを行った被検者から同定された6つのモデル(表1)から実際の社会体育で実践された歩行トレーニングを想定して、身体作業能力の変化の予測を行った。このトレーニングは、定期的運動習慣をもたない30〜80歳代の一般成人467名を対象に12週間行われたもので、基本的に運動者の自由意志で行われた。トレーニング日誌の記録から週に1回以上、30分間以上歩いた場合を継続者とした。トレーニング前後の各測定項目の比較を行ったところ、母集団の平均値でみたさまざまなトレーニング効果が確認された。しかし、継続者を週に1回以上と設定したため、実際にこの467名が行った頻度は週に1〜7回の範囲にある。そして同じ週3回でも、連続して月曜日から水曜日までトレーニングを行う場合と、間にトレーニングを行わない日を入れてほぼ1日おきにトレーニングを行う場合では、適応現象に差が生じる可能性もある。そこで、トレーニングの入力を週に1〜7回まで、かつ週に2〜6回では連続してトレーニングを行う場合とそうでない場合も設定し、モデルによる適応現象の予測を行った。 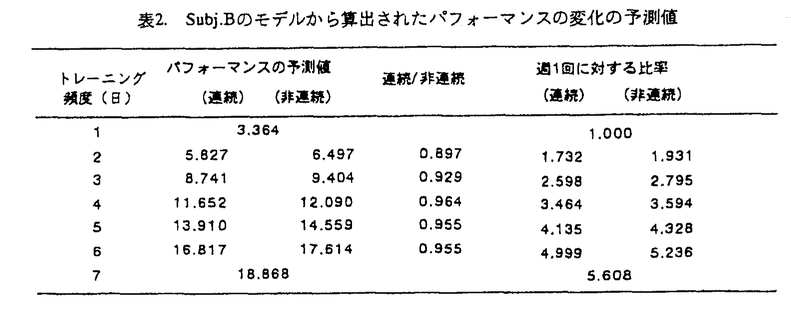 表2. Subj.Bのモデルから算出されたパフォーマンスの変化の予測値 表2. Subj.Bのモデルから算出されたパフォーマンスの変化の予測値 その結果、換気性作業閾値が減少傾向にあった被検者のモデルでは、すべての頻度で変化が負の値を示した。その他の被検者のモデルでは、頻度の増加に伴い、身体作業能力の変化もほぼ比例して増加した。また連続して行う場合とそうでない場合を比較すると、トレーニングによるマイナスの影響の時定数が比較的長い被検者のモデルでは、どの頻度においても、トレーニングを行わない日を間に入れたほうが変化が大きかった(表2)。またその他のモデルでも、週に4〜6回と頻度が多くなると、トレーニングを行わない日を間に入れたほうが変化が大きかった。歩行トレーニングの実測値の変化も負から正の値をとっていることを考慮すると、大きな母集団にみられる適応現象のばらつきも、モデルによって評価できる可能性が示唆された。またトレーニングを行うタイミングによってトレーニング効果が異なるといった結果から、トレーニングの画一的な量だけでなく、トレーニングのタイミングや各個人のトレーニング刺激に対する反応の特性といった、個別なトレーニングの質を見直す必要性も示唆された。 本論文の結果から、有酸素性トレーニングによって生じる適応過程は、トレーニングからのプラスの影響とマイナスの影響という拮抗する要素がその変化に影響し、日々のトレーニングという入力だけでなく、それによって生じる適応現象の変化の蓄積によって現れることが明らかになった。また実際にさまざまなタイミングでトレーニングを行った場合のパフォーマンスをモデルから算出した結果、トレーニングの量だけでなく、トレーニングを行うタイミングといった新たな要素の重要性も示された。本論文の結果は、トレーニングという入力刺激、適応現象という出力反応、両者を含むトレーニングに関連した入出力関係すべてが、時間経過に伴う過程を追って、評価されるべきものであることを明らかにした。 |