学位論文要旨
| No | 112396 | |
| 著者(漢字) | 佐貫,智行 | |
| 著者(英字) | Sanuki,Tomoyuki | |
| 著者(カナ) | サヌキ,トモユキ | |
| 標題(和) | 宇宙線陽子スペクトルの精密測定 | |
| 標題(洋) | A Precise Measurement of Cosmic Ray Proton Spectrum | |
| 報告番号 | 112396 | |
| 報告番号 | 甲12396 | |
| 学位授与日 | 1997.03.28 | |
| 学位種別 | 課程博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 博理第3176号 | |
| 研究科 | 理学系研究科 | |
| 専攻 | 物理学専攻 | |
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 宇宙から地球に降り注ぐ宇宙線の約90%は陽子が占めている。従って、宇宙線陽子の流束やエネルギースペクトルは、宇宙線物理学に於いて最も基礎的かつ重要な基本量である。エネルギースペクトルの形は、宇宙線の源の情報や伝搬過程の歴史を含んでいる。また、太陽活動の変動の影響を受けて変化する低エネルギーに於ける流束は、惑星間空間での宇宙線現象を理解するために不可欠となる情報である。 地下深くに建設された巨大なニュートリノ観測装置が、1980年代に入って観測を開始した。それらのうちの幾つかは、「大気ニュートリノ」の観測結果に異常があると報告している。測定が行なわれている数GeV以下の「大気ニュートリノ」では、ミューニュートリノと電子ニュートリノの比( ニュートリノ測定装置が設置されている地点に於ける大気ニュートリノのエネルギースペクトルは、宇宙から地球に降り注ぐ宇宙線のエネルギースペクトルを仮定した上で、この宇宙線が受ける地球磁気の影響や、地球大気の分子と起こす反応等をモンテカルロ・シミュレーションを用いて追跡し計算されている。モンテカルロ・シミュレーションによる計算は幾つかのグループによって行なわれているが、大気ニュートリノフラックスの計算結果の絶対値には30%程度の大きなばらつきが見られる。大気ニュートリノのエネルギースペクトルを正確に計算するためには、その出発点となる宇宙線のエネルギースペクトルを正しく知ることが大前提である。宇宙線の流束が決まらなければ、モンテカルロ・シミュレーションの手法が正しくても、大気ニュートリノに関しては正しい結果を決して得られない。このような状況であるために、「大気ニュートリノ問題」を議論する際には、ミューニュートリノと電子ニュートリノの比( 宇宙線陽子のエネルギースペクトルは、過去にもいくつかのグループによって測定されてきた。ところが、与えている流束の絶対値はグループによって差異が大きい。特に、神岡実験で観測されている1GeV程度の大気ニュートリノへの寄与が最も大きい10GeV程度の陽子のフラックスの測定結果のばらつきは、最大で2倍近くにも達する。大気ニュートリノ流束の絶対値を議論するためには、この宇宙陽子線のエネルギースペクトルを正確に決定することが必要不可欠である。 過去の測定で用いられた測定器は、宇宙線の飛跡を記録できる領域が狭く、測定点も少ないという弱点を持っていた。このために、測定器に入射した粒子が測定器中で相互作用を起こしてしまうと、解析の段階で見つけ出すことが難しく、大きな系統誤差を含んでいる恐れがある。 宇宙線中の荷電粒子を観測するために、大気の影響を受けない高空へ大型気球を用いて打ち上げることのできる超伝導ソレノイド型スペクトロメータBESS(Balloon-borne Experiments with Superconducting solenoidal magnet Spectrometer)を開発した。BESS測定器(図1)は、薄肉超伝導ソレノイドを使用することによってほぼ均一な強磁場を作りだし、その中に置かれたドリフト・チェンバーによって宇宙線粒子の磁気硬度(magnetic rigidity)を精密に測定することが可能である。BESS測定器の最大の特徴は、宇宙線の飛跡を記録できる領域が広いことと、飛跡を記録する点が最大で32点にも及ぶことである。この特徴を生かして、磁気硬度の絶対値を正確に測定することが可能である。また、チェンバー出力信号の記録には、出力波形を記録できるフラッシュ型ADCを用いているために、検出器内で宇宙粒子線が反応を引き起こし、複数の飛跡を残したとしても識別は容易である。また、同軸円筒状に配置した検出器は面積立体角を正確に見積もることが容易である。これらの特徴により、系統誤差を小さく押えることが出来る。さらに、大きな面積立体角は高速のデータ収集システムと相俟って、一日の飛翔実験で数百万事象もの膨大な情報を記録することを可能にし、統計誤差も小さくできる。 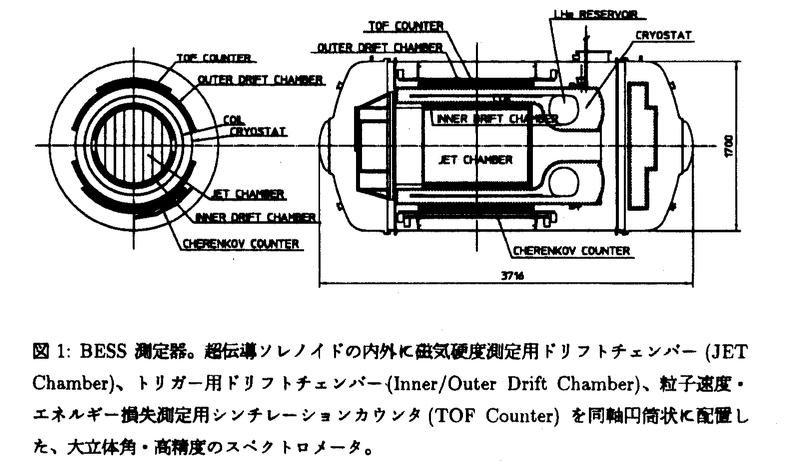 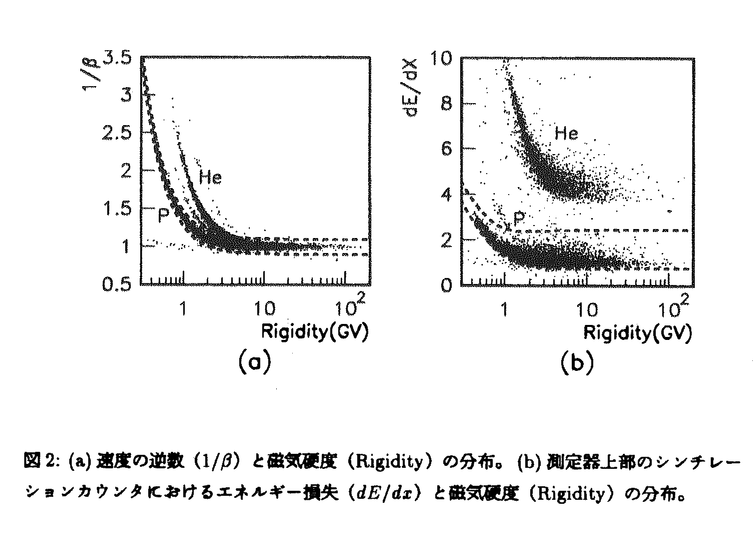  )と磁気硬度(Rigidity)の分布。(b)測定器上部のシンチレーションカウンタにおけるエネルギー損失(dE/dx)と磁気硬度(Rigidity)の分布。 )と磁気硬度(Rigidity)の分布。(b)測定器上部のシンチレーションカウンタにおけるエネルギー損失(dE/dx)と磁気硬度(Rigidity)の分布。1993年から95年の3年間に渡り、地磁気の影響の少ない北磁極に近いカナダ北部において3回の飛翔実験を行なった。浮遊高度は上空36kmに達し、測定器より上方に残存する大気は5g/cm2以下であった。3回の飛翔実験で記録した総事象数は、1.3×107にのぼった。 データの解析に当っては、入射粒子が測定器中の物質との相互作用によって散乱されたり、二次粒子を生成したりした場合に起こり得る粒子の誤認を防ぐため、いくつかの条件を課して事象を選別した。これらの事象については、200GVという高エネルギーの粒子まで、電荷の識別が可能であった。 条件を通過した事象について、粒子のシンチレーションカウンタ内に於けるエネルギー損失や粒子の速度と磁気硬度の分布は図2のようになる。図中に示した点線は、陽子を選び出すために施した選別条件を示している。 こうして求めた宇宙線陽子のエネルギースペクトルを図3に示す。低エネルギー領域では、太陽活動の変化の影響を受けて流束が変化する様子が見られる。一方、太陽活動の影響を受けにくい高エネルギー領域では、3年間に測定されたエネルギースペクトルは、統計誤差の範囲内で良く一致していることが分かる。 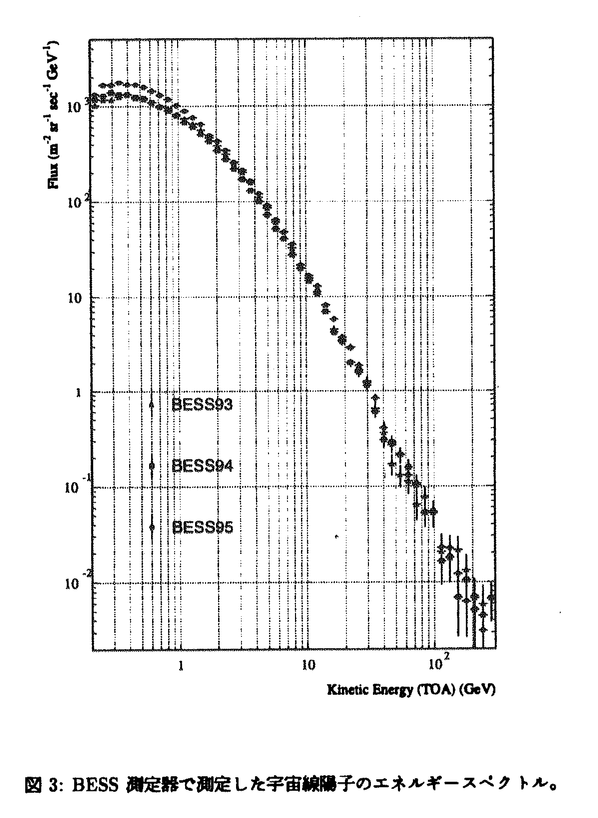 | |
| 審査要旨 | 本論文は6章からなり、第1章では宇宙線陽子スペクトルの精密測定の重要性が述べられている。第2章において測定に用いられた検出器システムが詳細に記述され、第3章で実際の気球実験の状況報告、第4章ではデータの解析方法が詳しく述べられている。次の第5章で解析結果がまとめられ、最後の第6章においては得られた結果について議論と考察が与えられている。 第1章に記されている研究の動機に関しては、その重要性は明らかである。地球に降り注ぐ宇宙線のほとんどは陽子であるが、その流束がこれまで正確には分かっていなかった。特に、素粒子物理において現在大きな問題となっている「大気ニュートリノ異常」の正しい理解の為には、陽子流束の絶対値を精度良く知る必要がある。そこで、素粒子物理実験で開発された検出器技術を用い、これまでの宇宙線測定における問題点を改善して精度の良い測定を行った本論文の意義は大きい。 第2章及び第3章では、研究に用いられた検出器の詳細、実験の実施方法、データの再構成について述べられている。これらはBESS実験グループ(研究代表責任者:折戸周治教授)による共同研究であるが、各段階において論文提出者の寄与が十分認められる。特に、流束の絶対値測定にとって重要な測定器の特性や環境変化の影響に関する較正において論文提出者の貢献が大きい。 第4章に記されているデータの解析は、主に論文提出者の独力によるものである。ここでは、宇宙線陽子と大気中および測定器中の物質との相互作用が与える影響についてモンテカルロ法等により詳しく計算を行ない、測定データから大気の上での流束を求めた。 流束の絶対値測定の為には系統誤差を正しく見積もる事が重要であるが、第6章において、実験および実験装置全体に対する深い理解に基づいて、十分な考察が行なわれている。また、太陽活動の影響を3年間のデータよりモデルを仮定して差し引き、太陽系外での流束を求めている。測定結果から明白な物理的結論を導き出すには至っていないが、本論文で行なわれた測定の重要性は、博士論文として十分値すると考えられる。 なお、本論文は、前述の通りBESS実験グループの研究者との共同研究であるが、論文提出者が主体となって解析を行ない、ほとんど独力で精度の良い結果を導き出したものであり、論文提出者の寄与が十分であると判断する。 よって、博士(理学)の学位を授与できると認める。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/54558 |
 +
+ )/(
)/( e+
e+ )は、約2となることが理論的に予測できる。ところが、水チェレンコフ測定装置による観測では、理論値に比べて40%も小さい値を与えているという。これがいわゆる「大気ニュートリノ問題」である。
)は、約2となることが理論的に予測できる。ところが、水チェレンコフ測定装置による観測では、理論値に比べて40%も小さい値を与えているという。これがいわゆる「大気ニュートリノ問題」である。