高温トーラスプラズマの研究当初から、粒子衝突から導出された新古典拡散で予想される輸送よりも観測される輸送が大きいことが知られていた。この現象を異常拡散という。異常拡散の物理の解明と異常輸送制御の物理は磁場閉じ込め核融合プラズマ物理の最大のトピックであり、これなくしては現実的なエネルギー源としての核融合は実現しえない。 現在、異常拡散のメカニズムと考えられているのは物理量の揺動による拡散である。揺動による粒子の輸送、 、は 、は  で記述される。ここで は電子密度の揺動成分であり、 は電子密度の揺動成分であり、 はプラズマの流れの揺動成分である。揺動の駆動源はプラズマの非一様性にあると考えられる。粒子拡散を考える場合の非一様性は密度勾配であると考えられ、これによって励起されるドリフト波不安定性のような静電揺動が はプラズマの流れの揺動成分である。揺動の駆動源はプラズマの非一様性にあると考えられる。粒子拡散を考える場合の非一様性は密度勾配であると考えられ、これによって励起されるドリフト波不安定性のような静電揺動が を決めていると考えられている。プラズマ周辺部においてはプローブによる実験結果がこれを示唆している。しかし、モードが特定できているわけではなく、また、主プラズマについての理解はまだ不十分である。 を決めていると考えられている。プラズマ周辺部においてはプローブによる実験結果がこれを示唆している。しかし、モードが特定できているわけではなく、また、主プラズマについての理解はまだ不十分である。 主プラズマにおける揺動は散乱計測によって調べられてきた。揺動は波数ベクトルが減るにしたがって増加し、小さなk⊥の揺動の主成分であることが知られている。しかし、通常の散乱計測は長波長の密度揺動に対して空間分解能が悪い。このような状況から主プラズマの長波長の揺動を空間分解能良く、時間分解能良く測ることのできる計測技術の確立が望まれている。 また、輸送の制御という観点から見ると、輸送が大きく変化する現象を観測することは重要である。1982年にドイツのASDEXトカマク装置の中性粒子入射加熱実験において、輸送が大きく閉じ込めの悪いプラズマから、輸送が減り閉じ込めの良いプラズマに突然遷移する現象が発見され、前者がL-mode、後者がH-modeと名付けられた。H-modeは国際協力による次期核融合プラズマ実験装置ITERの主たる運転領域であるが、LH遷移の物理が十分には理解されていないため、現在の設計は経験則による危険なものとなっており、LH遷移の物理の解明は重要である。 プローブによる実験結果によればH-mode時、プラズマ端に径方向負の向きの電場ができていることが確認されており、この領域で密度揺動が減少することが観測されている。 プラズマ中に径方向の電場があるとポロイダル方向に回転が引き起こされる。BiglariらはH-mode時における径方向の電場のシアによって引き起こされるポロイダル回転の速度のシアが、揺動を抑制するという理論を提示している。現在のところこのモデルの妥当性について決着はついていない。 径電場はプラズマ端の約1cm程度の領域で生じていると考えられている。プローブがプラズマに影響を与えたり、プラズマがプローブを破損させたりするため、プローブによって測定可能な領域はは高々この径方向電場が形成されている領域に制限される。H-mode時のdrasticな物理量の変化である径方向電場の変化が無い領域での揺動の計測は不十分である。 このようなことから主プラズマ領域での揺動測定は重要な研究課題である。反射計はこのような領域の測定が可能な測定器として近年注目されている。 反射計の測定原理はその名の通りプラズマからの反射を利用したものである。特定の周波数、f、の波をプラズマ中に入射したときの反射層はO-mode(Ei//B0:ここにはEi入射波の電場、B0は背景磁場でトカマク装置の場合トロイダル磁場と考えてよい)のとき密度によってのみ決まる。したがって、反射層から反射された波と参照波との位相差の時間変化は特定の密度層の動きを表わしている。この1次元の幾何光学的な見方から式1のような関係式が導出される。これまでの密度揺動の評価はこの式を使って行われてきた。 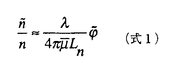 ここでは位相差の時間変化、 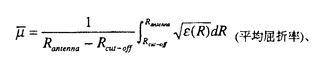 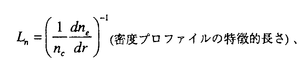 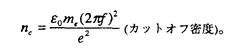 式1は、測定される位相の揺動が0の周辺で揺らぐことを意味している。しかし、本反射計では位相が単調に増える。このような現象はATF,JIPP-TIIU,W7AS,TFTRといった他の反射計でも報告されており、runaway phase現象と呼ばれている。本反射計もホモダイン検波、ヘテロダイン検波、周波数の変更などのシステムの変更を行ってきたがいずれの場合もrunaway phaseは見られ、いずれかのシステムに固有のものではない。 式1は1次元の幾何光学近似から導出された式である。runaway phaseが起きているとき1次元の幾何光学近似が適当でないことを意味している。Irbyらの2次元のsimulationでは入射波と垂直に伝播する密度揺動による散乱とアンテナのミスアライメントとによりrunaway phaseが起こることを指摘した。 本論文では、密度揺動と波の相互作用の考察から反射計の揺動測定を散乱波の計測として扱う。ただし散乱波が散乱を受けない波の大きさの3割程度未満であれば、この散乱の描像はこれまでの式1と結び付く。散乱の描像によるとrunaway phase現象は密度揺動が10%程度以上より大きくなると起こり、マイクロ波のアンテナが見込む立体角が主たる揺動の散乱角よりも大きい通常のセッティングでは、避けることが困難なものである。通常のセッティングのまま視線方向を変えるという意味でアンテナのアライメントを改良してもrunaway phaseは本質的に無くなるものではない。 runaway phaseが起きているときの反射計のデータの解析方法についてfringe jumpという見方以外では議論されてこなかった。この論文は散乱との関係を考察した上で、反射計のデータを散乱計測の手法で見直した最初のものである。解析には反射波が複素の情報を持った波 であることを考慮し、複素スペクトル、複素相関を利用し、散乱波の回転のイメージを見るために回転スペクトルも利用した。 であることを考慮し、複素スペクトル、複素相関を利用し、散乱波の回転のイメージを見るために回転スペクトルも利用した。 この解析法を用いて先に述べたLH遷移の計測を行い、runaway phaseを含んだ計測結果から密度揺動の情報を引き出すことに成功した。以下にその結果を示す。 (1)LH遷移時に100kHz程度未満の揺動の減少を確認した。また、この周波数領域で異なる反射層間での相関の減少が見られた。 (2)カットオフ密度が1.5×1019m-3以上の反射層の揺動はカットオフ密度1.5×1019m-3が以下の反射層の揺動に比べて揺動の減少に時間的な遅れが存在する。 (3)信号の低周波成分のみを用いるとプラズマの散乱の影響を抑えることができ、low pass filterを使用することで反射層の動きを測定することができた。 (4)(2)、(3)よりLH遷移による密度揺動の減少はプラズマ端に局在していることがわかった。 (5)スペクトルは約500kHzを境に異なった構造をもち、H-mode時に500kHz程度以上では揺動が増えているのが見られた。H-mode時には特定の波がたつことは報告されているがこのような500kHz以上のスペクトルの構造の変化は報告されていない。実験的にはこのようなスペクトルの構造はプラズマ中の不安定性の一つである鋸歯状振動が起きているときにも観測される。ただし、鋸歯状波の周波数は数kHz程度である。鋸歯状振動がH-modeをトリガーすることは良く知られており、この高周波成分がLH遷移のメカニズムと結び付いている可能性が期待される。 (6)H-mode後しばらくして100kHz付近にcoherentなモードが観測された。このモードはHL遷移直後に80kHz付近へ移動する。このcoherentなモードはプローブにおいても観測されている。 (1)(2)(4)の結果はBiglariらの理論の予想と矛盾しない。 (3)は反射計が密度分布測定に利用できることを示している。(5)、(6)は今後の解析によりL-mode、H-modeプラズマの物理に新たな知見を与えるものと期待される。 この論文では、まず、反射計におけるrunaway phaseという現象の散乱との関係を考察した。その結果runaway phaseが入射波の進行方向に垂直に伝播する密度揺動が10%程度あれば説明できることことがわかり、反射計のにおける密度揺動計測は散乱計測として行うことが妥当であることがわかった。この観点から散乱波計測の手法でrunaway phaseを含んだデータを解析し、密度揺動の情報を引き出すことに成功し、LH遷移における密度揺動の減少が100KHz程度未満の低周波によるもので、しかも、プラズマ端に局在したものであることがわかった。 |