原子核のスピン・アイソスピンに伴う諸性質、とりわけアイソベクトル型スピン応答関数の研究は、最近の原子核物理学の主要なテーマの1つである。 エネルギー移行が30-200MeV、運動量移行が1-2fm-1の領域では、準弾性散乱と呼ばれる散乱過程が支配的となる。この散乱過程は、入射核子と核内の核子との比較的自由な弾性散乱と考えられ、その反応機構の単純さから核内の情報をクリーンに引き出せると期待される。この運動量移行の領域では、核内でのパイ中間子の交換は引力のスピン縦相互作用を、ロー中間子の交換は斥力のスピン横相互作用をつくり出す。このような相関から、原子核のスピン縦応答関数はその強度が増大(エンハンス)しピークが低励起側にシフトする(ソフトニング)のに対し、スピン横応答関数は強度が減少(クエンチ)しピークが高励起側にシフトする(ハードニング)ことが理論的に示される。実験的には(p,p’)反応の偏極移行量測定からスピン応答関数の抽出が行なわれたが、結果はすべて理論の予想と相反するものであった。しかしながら(p,p’)反応はアイソスカラー励起を同時に励起するため、アイソベクトル型のみを励起する(p,n)反応での測定が望まれていた。 そこで本研究では2H,6Li,12C,40Ca,208Pbを標的とした(p,n)準弾性散乱の全偏極移行量測定から、純粋なアイソベクトル型スピン縦及び横応答関数の抽出を行なった。偏極移行量が核内の情報(スピン応答)を良く反映するためには、歪曲波の影響が小さい事が望まれる。そこで入射エネルギーとして346MeVを選択した。また過去の同種の実験の約10倍のデータ量を収集し、これまでにない精度でスピン応答関数を抽出することに成功した。実験的に抽出したスピン応答関数は、1粒子1空孔励起のみを考慮した乱雑位相近似(RPA)による応答関数と比較をした。12C及び40Caに対する実験結果及びRPAの理論計算との比較を図1に載せた。 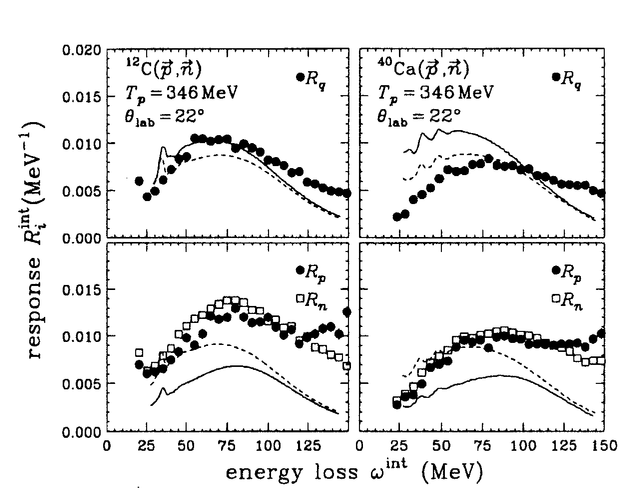 図1:(p,n)準弾性散乱の全偏極移行量から求めた、スピン縦(Rq)及びスピン横(Rp及びRn)応答関数。図中実線は1粒子1空孔のみを考慮したRPA計算で、破線は残留相互作用を0にした場合(無相関)の応答関数。 図1:(p,n)準弾性散乱の全偏極移行量から求めた、スピン縦(Rq)及びスピン横(Rp及びRn)応答関数。図中実線は1粒子1空孔のみを考慮したRPA計算で、破線は残留相互作用を0にした場合(無相関)の応答関数。 まずスピン縦応答関数の強度については、12CではRPAの理論計算とほぼ一致したが、40CaではRPA計算で予想されるエンハンスは認められなかった。RPAで予測されるエンハンスが認められないのは、 ( , , )反応が主に原子核の表面で起こる事が原因と考えられる。即ち、原子核表面では中心部に比べ核子密度が1/4-1/3と低いため、スピン応答に対する核内相関の効果が小さくなり、結果としてスピン縦応答関数に対して期待されるエンハンスが( )反応が主に原子核の表面で起こる事が原因と考えられる。即ち、原子核表面では中心部に比べ核子密度が1/4-1/3と低いため、スピン応答に対する核内相関の効果が小さくなり、結果としてスピン縦応答関数に対して期待されるエンハンスが( , , )反応では抑制されていると解釈される。実際、アイコナール近似における計算によると、12C( )反応では抑制されていると解釈される。実際、アイコナール近似における計算によると、12C( , , )では約43%の標的中の中性子が反応に寄与するのに対し、40Ca( )では約43%の標的中の中性子が反応に寄与するのに対し、40Ca( , , )では約28%の中性子しか反応に寄与しない。従って核表面で( )では約28%の中性子しか反応に寄与しない。従って核表面で( , , )反応が起こる事に起因するエンハンスの抑制の効果は、12Cより40Caの方が大きく、この事が40Caでエンハンスが認められない理由と考えられる。スピン縦応答関数のピークの位置に関しては、今回の実験では有意なソフトニングは認められなかった。しかしながら、理論的に予想されているソフトニングの効果が極めて小さいため、実験結果はスピン縦応答関数のソフトニングを否定するものではない。 )反応が起こる事に起因するエンハンスの抑制の効果は、12Cより40Caの方が大きく、この事が40Caでエンハンスが認められない理由と考えられる。スピン縦応答関数のピークの位置に関しては、今回の実験では有意なソフトニングは認められなかった。しかしながら、理論的に予想されているソフトニングの効果が極めて小さいため、実験結果はスピン縦応答関数のソフトニングを否定するものではない。 次にスピン横応答関数については、ハードニングについては予想通り認められたが、クエンチは認められなかった。スピン横応答関数は電子散乱からも導出することが可能である。(p,n)反応から引き出したスピン横応答関数の、(e,e’)反応から引き出したそれに対する比は、12Cで1.4、40Caで1.1となった。 12Cに関しては、準弾性散乱の場合に期待されるP=Ayの関係が準弾性散乱のピーク付近で成立していない。このことは準弾性散乱以外のアイソベクトル型励起モードの存在を示唆するものと考える事ができる。(p,n)反応から引き出したスピン横応答関数と(e,e’)反応から引き出したそれの不一致の原因としても、この励起モードの存在は有力な解釈の1つであるが、その存在の有無及びスピン応答関数に対する影響については今後の理論・実験両方からの研究が必要である。 電子散乱から得られたスピン横応答関数は、1粒子1空孔状態のみを考慮した理論計算からはその強度が再現されず、2粒子2空孔状態や中間子交換流といった高次効果を入れて初めて再現された。(p,n)反応から求めた応答関数について、その40Caでの強度が電子散乱のそれに比較的良く一致することから、(p,n)反応のスピン応答関数の解釈にも現在の理論計算に入っていない2粒子2空孔状態といった高次の効果が必要である事を強く示唆しており、今後の理論的解析が待たれる。 エネルギー移行 <20MeV、運動量移行q <20MeV、運動量移行q 0の領域では、スピン・アイソスピン依存の1粒子・1空孔間相互作用は強い斥力であり、このことがガモフ・テラー(GT)巨大共鳴に代表される集団励起状態を引き起こす。GT巨大共鳴を含むGT遷移強度に関しては、モデルに依存しない和則(池田の和則)が存在する。実験的にはGT遷移を(p,n)反応のような荷電交換反応で励起し、その0度での断面積と遷移強度の比例関係から種々の原子核について遷移強度和が調べられてきた。その結果、GT巨大共鳴までの領域に和則の約50%しか認められず、その原因について主に2つの理論モデルが提唱されてきた。一方はGT励起が2粒子2空孔状態のようなより複雑な配位と結び付き(配位混合)、巨大共鳴より高い励起状態にシフトするというものであり、他方は核子のクオーク自由度を考慮し、GT遷移強度が励起エネルギー300MeVのデルタ励起の領域にシフトするというものである。 0の領域では、スピン・アイソスピン依存の1粒子・1空孔間相互作用は強い斥力であり、このことがガモフ・テラー(GT)巨大共鳴に代表される集団励起状態を引き起こす。GT巨大共鳴を含むGT遷移強度に関しては、モデルに依存しない和則(池田の和則)が存在する。実験的にはGT遷移を(p,n)反応のような荷電交換反応で励起し、その0度での断面積と遷移強度の比例関係から種々の原子核について遷移強度和が調べられてきた。その結果、GT巨大共鳴までの領域に和則の約50%しか認められず、その原因について主に2つの理論モデルが提唱されてきた。一方はGT励起が2粒子2空孔状態のようなより複雑な配位と結び付き(配位混合)、巨大共鳴より高い励起状態にシフトするというものであり、他方は核子のクオーク自由度を考慮し、GT遷移強度が励起エネルギー300MeVのデルタ励起の領域にシフトするというものである。 本研究では、90Zr(p,n)反応を用いて90NbのGT遷移強度を励起エネルギー50MeVの高励起領域まで求めた。高励起状態では、角運動量移行が0のGT遷移以外にも種々の角運動量移行を持った状態が励起される。その中からGT励起のみを抽出するために多重極展開の手法を用い、断面積を角運動量移行が0から3の各成分に分解した。 角運動量移行が0の場合、スピン非反転のフェルミ励起とスピン反転のGT励起の2通りがあり、断面積のみを用いた多重極展開では両者を分離できない。本実験では入射エネルギーとしてGT励起が選択的に励起される295MeVで実験を行ない、且つ偏極移行量を測定し、スピン反転励起(GT励起)である事を直接確認した。またこのエネルギー領域では歪曲波の影響が最小となるため、核反応からGT遷移強度という核構造の情報を精度良く導き出す事が可能となる。 図2に最終的に得られたGT遷移強度分布を黒丸で示す。遷移強度和は励起エネルギー50MeVまでで28.0±1.6±5.4となった。ここで誤差±1.6は今回の多重極展開の誤差で、誤差±5.4は角運動量移行が0の成分をGT遷移強度に変換する際に用いるGT単位断面積の誤差からくる系統誤差である。これは和則値の(93±5±18)%に相当する。図中斜線で示されたグラフは、Bertsch and Hamamotoによる2粒子2空孔励起の効果を考慮した理論計算で、今回実験的に得られた高励起状態におけるGT遷移強度を良く再現している。また実験結果は、50MeV以上の高励起状態にもGT遷移強度が存在する可能性も示唆している。以上の事から、GT遷移強度は2粒子2空孔状態との配位混合の結果、約半分がGT巨大共鳴より高い励起エネルギーにシフトしている事、及び核内のクオーク自由度の影響が従来理論的に予測されてきた値よりも小さく、最大で10%程度である事が明らかにされた。 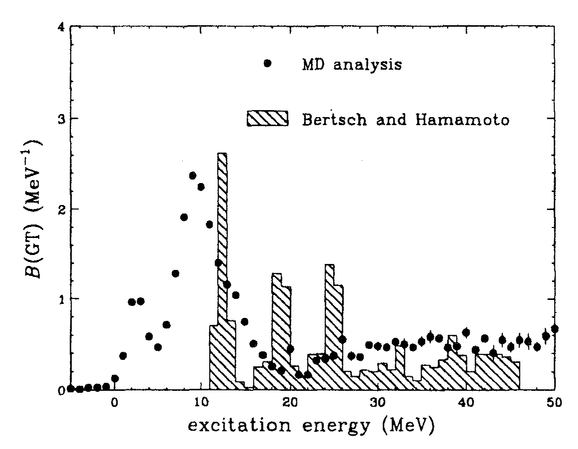 図2:マルチポール展開で求めた90Zr(p,n)反応の0度での角運動量移行0の成分から導き出された、90NbのGT遷移強度分布(黒丸)。斜線で示したヒストグラムは、Bertsch and Hamamotoによる2粒子2空孔励起の効果を考慮した理論計算。 図2:マルチポール展開で求めた90Zr(p,n)反応の0度での角運動量移行0の成分から導き出された、90NbのGT遷移強度分布(黒丸)。斜線で示したヒストグラムは、Bertsch and Hamamotoによる2粒子2空孔励起の効果を考慮した理論計算。 以上のように中間エネルギー(p,n)反応は、原子核のスピン応答を調べる上で非常に有益である。他方、原子核の構造が殻模型等で良く記述される場合には、偏極移行量は核子・核子間(NN)有効相互作用についての知見を与える。特に0度での偏極移行量DNN(0°)は、高運動量移行領域でのテンソル相互作用に敏感な観測量である。通常この領域でのテンソル相互作用は、高スピンの伸びきった状態の断面積から調べられてきた。偏極移行量による研究は、より高い運動量移行の領域が探査可能な事と、断面積のように絶対値が必要ではない為実験的に精度良くテンソル相互作用が調べられるという特徴を持つ。 本研究では、その構造が殻模型で良く記述されるp殻原子核を標的とした(p,n)反応のDNN(0°)測定から、テンソル相互作用に関する情報を引き出した。核反応の枠組として歪曲波インパルス近似を用い、NN相互作用としてFraney and Loveによる270MeV及び325MeVのデータセット(F.L.270MeV及びF.L.325MeV)を用い両者の比較を行なった。その結果、F.L.270MeVは実験結果を良く再現するものの、F.L.325MeVは実験値を再現しない事がわかった。両者のテンソル相互作用について比較を行なったところ、本研究で調べたq=3.4fm-1の高運動量移行領域ではF.L.325MeVのテンソル力が強すぎる事が明らかにされた(図3参照)。 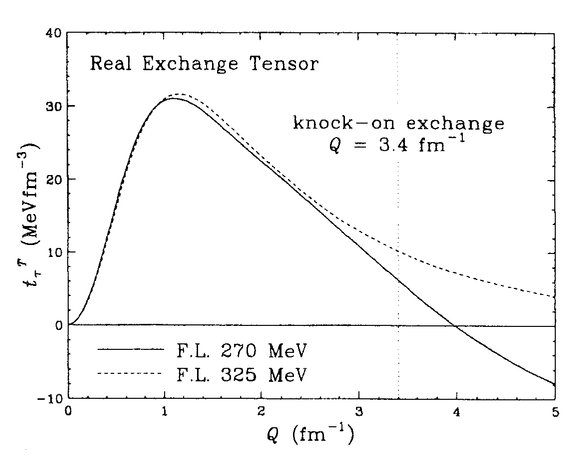 図3:F.L.270MeV(実線)及びF.L.325MeV(破線)のテンソル相互作用の実部の運動量依存性の比較。本研究では図中点線で示された運動量移行3.4fm-1の領域を調べた。この領域でF.L.325MeVのテンソル相互作用がF.L.270MeVのそれに比べて約60%大きい値となっている。 図3:F.L.270MeV(実線)及びF.L.325MeV(破線)のテンソル相互作用の実部の運動量依存性の比較。本研究では図中点線で示された運動量移行3.4fm-1の領域を調べた。この領域でF.L.325MeVのテンソル相互作用がF.L.270MeVのそれに比べて約60%大きい値となっている。 |