| 1研究の背景・動機 中・小質量星は進化の終末期おいて漸近巨星枝(asymptotic giant branch,AGB)と呼ばれる段階に達する。AGBにある星の内部ではコアをとりまくヘリウム殼とさらにその上の水素殼で核燃焼が起こっており、特に、ヘリウム殼における反応は熱的に不安定でパルス的に核反応が暴走し、ここでさまざまな元素合成が行なわれる。それらが対流によって汲み上げられ恒星表面の化学組成が変化すると考えられている。なかでも炭素星は大気中の炭素の組成が酸素よりも多いという特異な化学組成を示し、ヘリウム燃焼の熱的不安定によって合成された12Cが汲み上げられた結果と考えられている。しかし、現在の恒星内部構造理論では比較的質量の大きい星しか炭素星へと進化することができず、そのためにマゼラン雲における炭素星の光度関数を再現できないという困難に面している。 そこで、恒星表面の化学組成を観測的に決定することはAGB段階における内部核反応を理解するには重要な位置を占める。また、AGB星の大きな特徴の一つである質量放出のメカニズム解明には大気上層部及び星周エンベロープにおける物理・化学過程をダスト形成の素過程も含めて明らかにする必要がある。光球は星周エンベロープの境界条件に相当し、光球の化学組成は質量放出のメカニズムを研究する上で基本的情報である。また、AGB星は質量放出を通して核合成された物質を星間空間に還元するため、銀河内の物質の化学進化を解明する上でも大きな意味がある。 2炭素星における炭素同位体比の定量解析 炭素同位体比(12C/13C)はヘリウム燃焼で合成された12Cの汲み上げを直接反映するので、炭素星生成シナリオを観測的に制限を加えられる。そこで、N・SC・J型炭素星の100個を越えるサンプルに基づいて炭素同位体比を定量解析し、その頻度分布を求めた。観測は岡山天体物理観測所188cm望遠鏡のクーデ分光器にCCDを検出器として用いて行なわれた。観測波長域は7790〜8030Åで13CNと13CNの分子線から12C/13C比を定量解析した。波長分解能は約20,000、S/N比は典型的には100程度である。 炭素同位体比は12CNと13CNのラインからIso-intensity methodによって定量解析した。この方法は、強度が同じである12CNと13CNのラインから同位体比を求めることにより解析の精度を上げるところに特徴がある。また、各ラインの励起ポテンシャルの違いはモデル大気によって補正する。 解析の結果、62個のN型炭素星の炭素同位体比の平均値は12C/13C=27±11(標準偏差)で、実際サンプルの約85%が20〜30の炭素同位体比を持っていることが明らかになった。これと対照的なのが広く受け入れられてきたLambert et al.(1986)の結果で、炭素同位体比は50〜60に多く分布していることを示している。この食い違いは同じ星についても見られるために、なお深刻である。この食い違いの原因として彼らが解析に用いたモデル大気が我々のものよりも500Kも低温であることが考えられる。 15個のSC型炭素星の炭素同位体比の平均値は12C/13C=22±14(標準偏差)で、N型炭素星のものと大きな違いは見られない。SC型炭素星は従来の炭素星分類では13C過多、すなわち12C/13C<10と分類されてきたが、今回の定量解析の結果、ほとんどの星では炭素同位体比は10以上で、13C過多なものは3個だけであった。従来の炭素星分類は低分散分光に基づいて行なわれたため、原子か分子のブレンドのために13C過多という誤った分類が導かれた可能性がある。 最後にJ型炭素星の12C/13C比は26個のうち2つを除いてすべて10以下であり、12C/13C=2〜6にかけて比較的幅広く分布している。また、今回解析したサンプルの中には9.8 mのシリケイトのemissionが確認されているものがあるが、これらのいずれも他のJ型星と比べて特異な12C/13C比を示していない。「シリケイト炭素星は13C-richである」という従来の分類を定量的に確認するとともに、炭素同位体比に関する限りシリケイト炭素星は他のJ型炭素星と変わらないことが示された。 mのシリケイトのemissionが確認されているものがあるが、これらのいずれも他のJ型星と比べて特異な12C/13C比を示していない。「シリケイト炭素星は13C-richである」という従来の分類を定量的に確認するとともに、炭素同位体比に関する限りシリケイト炭素星は他のJ型炭素星と変わらないことが示された。 N・SC型炭素星について得られた炭素同位体比について、K・M型巨星における12C/13C比・C/O比と比較した結果、thermal pulseで生成された12Cが汲み上げによってK・M型巨星が炭素星に進化するというシナリオを支持していることがわかった。ただし、ここではN型炭素星のC/O比としてLambert et al.(1986)の解析結果の平均値C/O=1.1を仮定した。12C/13C比について上に述べたように彼らの結果と著しい食い違いが見い出されたということはC/O比についても再解析する必要があるため、このシナリオはC/O比解析の後、再検討する。 一方、J型炭素星への進化過程においてはCNサイクルの関与が考えられている。CNサイクルの平衡状態では3-4という非常に小さい12C/13C比が達成されるからである。今回の我々の結果はかなりの星で12C/13Cが3〜4であり、CNサイクルの関与を否定しない。しかし、我々のサンプルのうち少なからぬ数の星において12C/13C=1-2という極めて小さい値も見られ、このような小さい値は平衡状態のCNサイクルでは説明できない。 3球状モデル大気の構築 炭素星のモデル大気は化学組成解析に必要であるほか、今後大気上層部・星周エンベロープにおけるダスト形成や動力学構造をも含めた包括的な理論モデルを構築するのにも重要である。また、近赤外域においてもCOのlow excitation linesには光球上層部の情報が含まれていると考えられ、そこでの物理状態を引き出すためには現実的な光球モデルを構築する必要がある。 今回、多数の分子線吸収の影響をBand Model法によって考慮に入れた球状モデル大気コードを開発した。Band Model法は分子線吸収を平均の吸収係数と平均の線間隔で代表させる。その結果、与えられた温度・圧力・波長における吸収係数を簡単に計算できるという柔軟性がある。一方、現在の低温度星モデル大気ではOpacity Sampling法で多数の分子線データをそのままとりいれて計算するのがもっとも進んでいるとされている。しかし、今回Band Model法で計算したモデル大気とOpacity Sampling法で計算したJorgensen et al.(1992)のものでは温度構造が100K以内で一致することがわかり、Band Model法が低温度星モデル大気構築において柔軟かつ信頼のおける近似であることが示された。 また、球状モデル大気では平行平板大気に比べて表面近くの層では温度が著しく下がる。温度差は星のパラメータによるが、最大で500Kに達する。これは球状効果をとりいれることにより表面での輻射場が小さくなることで温度がさがり、さらにそれがC2H2やHCNの多原子分子の形成を促進する。よって球状効果は多原子分子の吸収線に顕著にあらわれると期待される。そこで、SS VirについてInfrared Space Observatory(ISO)によって得られた赤外スペクトルと比較を行なった。(図1)その結果、3 mのHCNとC2H2による吸収は球状モデル大気でよくフィットすることができた。ただし、同じHCNとC2H2の7 mのHCNとC2H2による吸収は球状モデル大気でよくフィットすることができた。ただし、同じHCNとC2H2の7 m及び14 m及び14 mの吸収はモデルから計算されるよりも弱く、星周エンベロープからの放射で埋まっていると考えられる。 mの吸収はモデルから計算されるよりも弱く、星周エンベロープからの放射で埋まっていると考えられる。 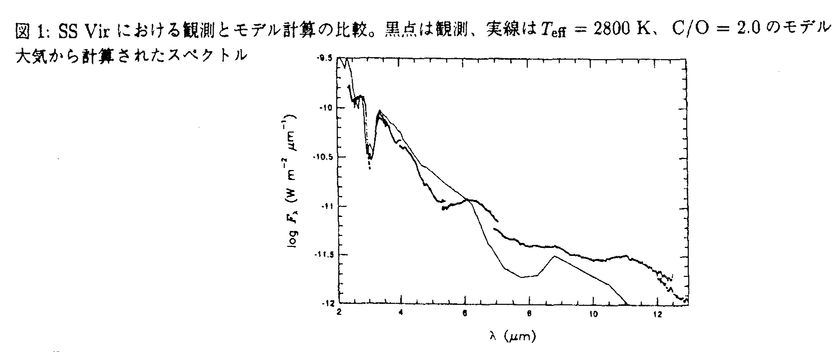 図1:SS Virにおける観測とモデル計算の比較。黒点は観測、実線はTeff=2800K、C/O=2.0のモデル大気から計算されたスペクトル4炭素・酸素元素組成解析 図1:SS Virにおける観測とモデル計算の比較。黒点は観測、実線はTeff=2800K、C/O=2.0のモデル大気から計算されたスペクトル4炭素・酸素元素組成解析 上に述べたように炭素星における炭素同位体比は我々の結果とLambert et al.(1986)で系統的に違っており、その原因を解明し、信頼のおける化学組成解析を行なう必要が指摘された。そこで、Lambertらが解析したデータをキットピーク天文台から入手し、我々のモデル大気を用いて解析を行なった。彼らのデータはHバンド及びKバンドの高分散スペクトルで、フーリエ分光器でとられた。波長分解能は約75,000、S/N比も100程度である。ここでは有効温度が異なる3つの星(TX Psc,BL Ori,V Aql)についてCO second overtone、C2 Phillips systemを用いて炭素組成及び酸素組成を解析した。 解析は酸素の元素組成とC/O比をパラメータとするモデル大気のグリッドを用いて行なう。これは求めようとしている酸素及び炭素の元素組成がモデル大気の入力パラメータで、しかも温度構造がそれらに大きく依存するためである。各グリッド点に対応するモデル大気でCO second overtoneのライン強度を計算し、観測値と比較することによって仮定した酸素の元素組成に対する補正を求める。この際、すべてのラインに対する補正が一致するように微小乱流速度を決定する。同じようにしてC2のラインから仮定した炭素組成に対する補正が各グリッド点で求められる。COとC2から求めた補正が同時に0になる点が求めるべき炭素及び酸素の元素組成で、内挿から求められる。全く同じ解析を球状モデル大気を用いても行ない、元素組成解析における球状効果を調べた。 酸素の元素組成は太陽系値とくらべて0.1-0.2dex少ないことがわかり、またLambertらの結果とも解析の誤差の範囲内で一致している。酸素の元素組成はCOのラインから求められるが、COは炭素星大気中で最も安定な分子の一つであるため、モデル大気の温度構造の違いからくる影響を受けにくいと考えられる。よってここで酸素の元素組成がLambertらの結果と一致することはごく自然なことである。 しかし、C/O比は彼らの結果と大きく食い違っている。表1にTX Psc、BL Ori、V Aqlにおける解析の結果を平行平板大気(PP)、球状大気(SS)の場合別に挙げる。またLambert et al.(1986)の結果も比較のために載せた。V Aqlにおいてはその食い違いは極めて顕著で、今回得たC/O比は彼らのものより2倍以上大きな値である。このようなC/O比の食い違いは解析に用いるモデル大気の温度構造の差を反映していると考えられる。また、LambertらはCO及びC2のラインの励起温度としてlog Ross=-1.4(RossはRossland mean opacityをあらわす)となる層の温度を一律に採用しており、このような励起温度の決め方は炭素星の複雑な大気構造においては必ずしも正当化されるものではない。今回解析に用いた球状モデル大気はSS Virの観測スペクトルを再現することができ、その妥当性が一部ながら支持されていることを考えると今回の元素組成解析の結果も信頼できるものであるということができよう。 Ross=-1.4(RossはRossland mean opacityをあらわす)となる層の温度を一律に採用しており、このような励起温度の決め方は炭素星の複雑な大気構造においては必ずしも正当化されるものではない。今回解析に用いた球状モデル大気はSS Virの観測スペクトルを再現することができ、その妥当性が一部ながら支持されていることを考えると今回の元素組成解析の結果も信頼できるものであるということができよう。 ここで求めたC/O比と先に求めた12C/13C比によって炭素星形成シナリオが矛盾なく説明できる。つまりK・M型巨星の大気に12Cが混入されると考える。K・M型巨星におけるC/O比・12C/13C比の解析はSmith&Lambert(1985,1990)によって行なわれており、平均としてC/O=0.45、12C/13C=14である。例えばV AqlにおいてはC/O比が5.3倍になっており、従って12C/13C比も14×5.3=75になると考えられ、これは前節の解析で求めた値12C/13C=66とよく一致する。TX Psc、BL OriのC/O比・12C/13C比についても同じように12Cの混入による炭素星形成シナリオでよく説明できることが示された。今後はさらに多くの炭素星について解析を行なうことが炭素星への進化を明らかにするうえで必要である。 5CO first overtone linesの解析 CO first overtoneのライン、とくに励起ポテンシャルの低いラインは飽和効果があらわれており、元素組成解析には適当ではない。しかし、これらのラインには光球上層の情報が含まれていると考えられる。上で求めた化学組成を入力パラメータとするモデル大気にもとづいてCO first ovetoneのライン強度を計算した結果、TX PscとV Aqlにおいてlow excitation linesはモデル大気で計算されるよりも観測値のほうがはるかに強いことが明らかになった。さらに、これらのラインのプロファイルを解析した結果、深さはモデル大気でほぼ説明できるが、半値巾はモデル計算よりも大きくなっていることがわかった。このようなlow excitation linesの強度異常を説明する仮説として、微小乱流速度が大気の深さに依存しているという説と光球よりも上層のextra componentが存在しているためとする説がある。 一般にlow excitation linesは光球上層部で形成されるため、微小乱流速度が上層部でのみ極めて大きくなっていると考えればCO second overtoneのライン強度には影響を与えることなくlow excitation linesの強度異常を説明できる。そこで、そのような深さ依存性を持たせた微小乱流速度にもとづいてライン強度を計算したところ、上層部にのみ10km s-1という大きな値を持たせるとlow excitation linesの強度異常を説明できることがわかった。しかし、同じ計算を(2,0)バンドヘッドについて同じ深さ依存性をもつ微小乱流速度でスペクトル合成を行なった結果、観測スペクトルを再現できないことが明らかになった。よってlow excitation linesの強度異常は深さ依存性をもつ微小乱流速度では説明できないことが明らかになった。 そこでlow excitation linesの強度異常の原因が光球にあるのか、もしくはさらに上層のextra componentにあるのかを調べるために、CO first overtone、second overtoneのラインの視線速度を測定した。その結果、強度異常が見られるlow excitation linesの視線速度はhigh excitation linesのものに比べて、1km s-1から3km s-1ずれていることがわかった。これはlow excitation linesの強度異常が光球ではなくその上層のextra componentに原因があることを示唆している。 上層のextra componentからの寄与は光球からの寄与を観測スペクトルからさしひくことによって分離することができる。具体的には観測スペクトルをモデル大気から計算されるスペクトルで割ることによってextra componentによる吸収を分離し、その強度(等価巾)を測定した。測定された等価巾から励起温度を求めたところ、900〜1500Kという値が得られた。また、COの柱密度は1020cm-2程度であった。よって光球の上層にquasi-staticでかつ暖かい分子の層が存在していることが示唆された。今後はさらに多くの星について解析を行ない、このようなextra componentの物理特性が星の有効温度とともにどのように変化するかを解析していく必要がある。 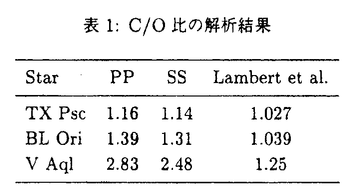 表1:C/O比の解析結果 表1:C/O比の解析結果 |