| 内容要旨 | | はじめに 地球の内核の構造がいかにして決まり、どのように進化してきたか、という疑問に答えるためには ・内核の構造進化に関与する素過程を組み合わせてフォワードモデリングにより観測可能な量を導く。 ・観測(地震、地磁気)よりモデルパラメータ(物性、内核の成長速度)を制約する。 という2つの方法を互いにフィードバックさせることが不可欠であるが、このようなアプローチは今まで殆んどなされていなかった。本論文ではこのように理論と観測を橋渡しする観点で地球の内核の構造進化を明らかにすることを目指した。 上の前者に対応するものとして、内核の諸構造がその成長様式(速度、異方性)によって決定されているという観点に立ち、中心核の冷却に伴う内核の構造進化を数値及び理論モデルより求めた。この際、特に地震波速度、振幅異常に関係が深いporosity構造と結晶選択配向構造を重視し、特に配向構造については対応する地震波の走時と振幅異常を求めた。後者に対応するものとして、モデリングの結果と観測とを比べ、モデルの検証を行ない、観測事実が説明されることを示した。またより詳しい検証をするための地震波の解析方法を提示した。さらに、地球の進化のタイムスケールでの内核の外核に対する影響を調べるために、地球磁場強度の変動を古地磁気学的な方法で実測した。以下行なった研究内容の概略について記す。 1.内核の堆積圧密モデル 地球の冷却に伴って、軽元素を含む外核から固化して成長する内核は、少なくとも内核外核境界では部分熔融状態を形成すると考えられる。この時、固体が液体より重いため固体が変形し液体を浸透流として絞り出す堆積圧密過程が生じると考えられるが、従来の研究は簡単のためこの過程を無視していた(Fearn et al.,1981)。この圧密過程とそれに伴う相変化により内核のporosity構造は決定されるが、この過程をモデリングすることにより、内核では堆積速度が小さいため、圧密が非常に効くことが分かった。これはICBが地震学的にシャープであることと整合的である。また、内核が自己重力球であり、成長速度が次第に遅くなることから内核表面直下に殻状の領域が形成されることが示された(図1)。これは地震学的には低速度層の存在に対応するものである。内核中のporosity構造の形成を詳しく理解するために、力学的な圧密過程の数値計算、及び理論的説明を行ない、その構造を決定するパラメータを明らかにした。そのことにより、圧密層の厚さから内核の粘性と成長速度が制約されること、また内核の浸透率が10-18m2より大きいと内核深部に液体が保持されないことが示された。さらに、内核の中の温度、組成構造を求め、内核中での熱対流が困難であること、組成構造はporosity構造と類似していることを明らかにした。 以上は大局的な核の熱史を解くことと平行して求まったものであるが、熱史に関しては、内核の成長速度が時間の平方根に比例することが分かり、また、CMB温度がペロブスカイトの融点以下(5000K)であること、内核が45億年より若いという制約を加えることにより、内核の年齢が26億以上であること、CMBにおける熱輸送が1012W以上、3×1012W以下であることが求められた。 2.内核の異方的成長モデル 内核には南北方向に伝わる地震波が速いという観測事実が知られている。これは内核を構成する六方晶鉄の結晶選択配向によると考えられているが、その原因は良く分かっていない。ここではそれを説明する為、以下のようなモデルを構築した。 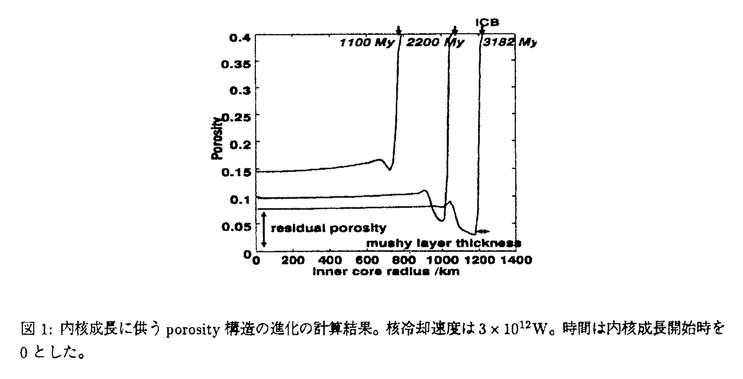 図1:内核成長に供うporosity構造の進化の計算結果。核冷却速度は3×1012W。時間は内核成長開始時を0とした。 図1:内核成長に供うporosity構造の進化の計算結果。核冷却速度は3×1012W。時間は内核成長開始時を0とした。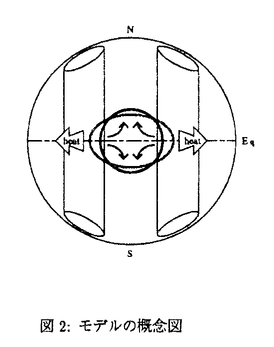 図2:モデルの概念図 図2:モデルの概念図 内核の成長は外核の自転軸に平行なロール状対流の影響を受けていることから赤道方向の成長が極方向のそれより卓越すると考えられる。その時、内核の内部に次数2の流れが粘性緩和過程により誘発され(図2)、それによって生じる差応力が選択配向の原因になると考えた。 次数2の成長速度の異方性を与えた下で内核の中で生ずる応力場を求めた。その応力場の下で、物質拡散による再結晶で生ずる結晶選択配向をKamb(1959)の理論(安定配向は歪みエネルギーが最小のもの)を適用した。内核での結晶サイズは動的再結晶により応力レベルにより決定されるする。その結果、内核の中では拡散クリープが主として起こり、粒径が数m、粘性が1022Pasとなり、Kambの理論を使うことが正当化される。再結晶メカニズムとしてはGrain Boundary Migration(GBM)、Pressure Solution(PS)、Pressure Solution and Compaction(PSC)の場合を考えた。ここで弾性定数はStixrude & Cohen(1995)の理論計算の結果を用いた。その結果、いずれの場合もICBより100km以深では南北配向、それより浅部では乱れた、もしくはMODEL PSCについては圧密領域では応力の主軸が半径方向になる為、半径方向の配向を示すことが示された(図3)。 3.モデルの検証 上で求まった各モデルに対応する走時異常を求め(図4)、特にICB直下で圧密が起きているとした場合(MODEL PSC)、観測より知られているICBより60km以浅では異方性がないという深さ依存性も良く説明することができた。しかし、上層部でランダムな配向でもこの観測事実は説明できる。そこで、波線が子午面となす角度が0度ではない場合について図4と同等なものを求めた。そうすることにより、波線の自転軸となす角度が同じでも子午面となす角度が異なると走時異常に違いが生じることにより、MODEL PSCが上層部がランダムなモデルと選別できることを示した。さらに、異方的媒質の効果を考慮して走時、振幅異常の震央距離、自転軸となす角度の違いに対する依存性を求めた。それにより、圧密層の厚さを速度及び振幅の震央距離依存から制約されることを示し、モデルの詳しい検証法を示した。またS波についても同様の計算することにより、子午面偏光のS波は自転軸と45度をなす方向に波線が収束し、この方向では検出が他方位より容易であることが判明した。 4.地球磁場強度変動の実測 地球磁場強度は中心核の活動の指標として重要であり、特に太古代以前のものは内核の情報を含んでいる可能性がある。3.5Gaまで遡る古地球磁場強度のデータは南アフリカ、バーバートンのコマチアイトを用いたCisowski(1981)とHale(1987)のものだけであるが、それらの結果は前者は現在の10倍程度、後者が現在のものよりも小さいというふうに矛盾している。ここでは、変質の程度が低い西オーストラリア、ピルバラ地塊の火山岩を用いて2.5〜3.5Gaの地球磁場強度変動を求めた。 信頼できる古地球磁場強度を求めるためには、残留磁化の少なくとも一部が単一成分の熱残留磁化であり、主磁性鉱物が単磁区磁鉄鉱であることが望まれるが、ピルバラの多くの火山岩について熱及び交流消磁、岩石磁気性質の測定によりこれが満たされていることが判明した。さらに、飽和磁化、帯磁率などの熱磁気的性質はキュリー点近くまで熱的に可逆であり、加熱による変質の程度が小さく、古地球磁場強度推定に適していることが分かった。 以上を確認した上で古地球磁場強度をテリエ法及びショウ法により求めた。その際、変質をlinearity、PTRM、ARM check、帯磁率の変化でモニターした。測定の結果、古地球磁場強度が2.7Ga以前では現在の約10倍以上であったことが判明した(図5)。この結果は岩石の種類によらず、また類似した岩石磁気的性質を持つ玄武岩でも、2.7Ga以前と以後では求まる古地球磁場強度が大きく異なることから、残留磁化の大きさは直接地球磁場強度を反映していると考えられる。 残留磁化の起源については海底起源の玄武岩については、磁鉄鉱は熱水活動などによるsilicate鉱物などの変質によって生じたものであり、残留磁気は化学残留磁化に熱残留磁化がoverprintしたものと解釈した。これはテリエ法により低温成分(TRM)と高温成分(CRM)の2成分が求まることと整合的である。大陸起源のものについては熱残留磁化と解釈した。 このような強地球磁場強度の原因であるが、エネルギー論的には10倍もの地球磁場強度を作るのが困難であることから、むしろダイナモの形態が異なり、太古代では(ボロイダル磁場/トロイダル磁場)比が内核の欠如により 効果が現在よりも卓越していたことによる可能性がある。 効果が現在よりも卓越していたことによる可能性がある。 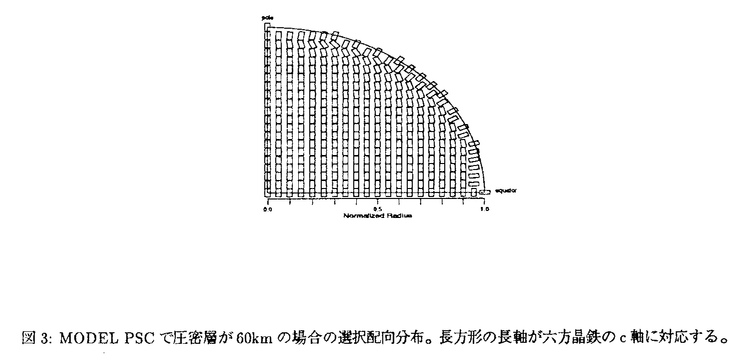 図3:MODEL PSCで圧密層が60kmの場合の選択配向分布。長方形の長軸が六方晶鉄のc軸に対応する。 図3:MODEL PSCで圧密層が60kmの場合の選択配向分布。長方形の長軸が六方晶鉄のc軸に対応する。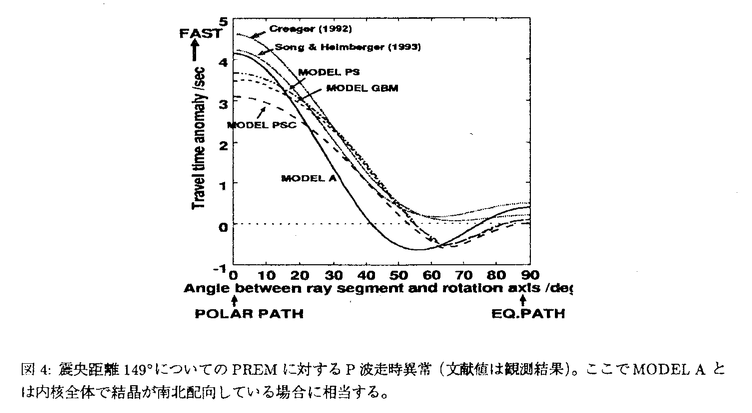 図4:震央距離149°についてのPREMに対するP波走時異常(文献値は観測結果)。ここでMODEL A とは内核全体で結晶が南北配向している場合に相当する。 図4:震央距離149°についてのPREMに対するP波走時異常(文献値は観測結果)。ここでMODEL A とは内核全体で結晶が南北配向している場合に相当する。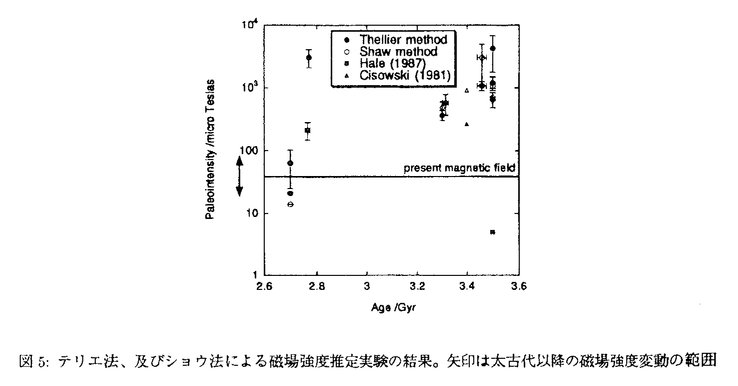 図5:テリエ法、及びショウ法による磁場強度推定実験の結果。矢印は太古代以降の磁場強度変動の範囲参考文献Cisowski,S.M.,Anomalous Magnetizations in 3.4 b.y.old Barberton Mountain Land Samples,Geophys.Res. Lett.,8,129-132,1981.Fearn,D.R.,Loper,D.E.and P.H.Roberts,Structure of the Earth’s inner core,Nature,292,232-233,1981.Hale,C.J.,The intensity of the geomagnetic field at 3.5Ga:paleointensity results from the Komati Formation, Barberton Mountain Land,South Africa,Earth Planet.Sci.Lett.,11,97-100,1984.Kamb,W.B.,Theory of preferred crystal orientation developed by crystallization under stress,J.Geol.,67,153-170,1959.Stixrude,L.and R.E.Cohen,High-Pressure elasticity of iron and anisotropy of Earth’s inner core, Science,367,1972-1975,1995. 図5:テリエ法、及びショウ法による磁場強度推定実験の結果。矢印は太古代以降の磁場強度変動の範囲参考文献Cisowski,S.M.,Anomalous Magnetizations in 3.4 b.y.old Barberton Mountain Land Samples,Geophys.Res. Lett.,8,129-132,1981.Fearn,D.R.,Loper,D.E.and P.H.Roberts,Structure of the Earth’s inner core,Nature,292,232-233,1981.Hale,C.J.,The intensity of the geomagnetic field at 3.5Ga:paleointensity results from the Komati Formation, Barberton Mountain Land,South Africa,Earth Planet.Sci.Lett.,11,97-100,1984.Kamb,W.B.,Theory of preferred crystal orientation developed by crystallization under stress,J.Geol.,67,153-170,1959.Stixrude,L.and R.E.Cohen,High-Pressure elasticity of iron and anisotropy of Earth’s inner core, Science,367,1972-1975,1995. |
| 審査要旨 | | 地球の中心核は液体の外核と固体の内核から成り立っている.地球物理学的観測によりこれらの中心核の化学組成は基本的には鉄・ニッケル合金であることが明らかになっているが、外核の密度は予測される値よりも小さく、鉄・ニッケル以外の第3成分の軽元素の存在を示している.内核はこのような状態の外核から地球の冷却に伴って高融点の鉄・ニッケル成分が析出、成長したものであると考えられている.中心核は最も観測の及ばないところであるために観測事実が乏しく、制約条件の少ない状態で定量的に検証可能な有効なモデルの提案も少ないのが従来の研究状況である.本論文では近年急速に進展した中心核の地震学的観測結果を参照にしつつ、内核の成長進化の物理的モデルを提案し、地震学的、地球電磁気学的考察を展開しており、極めてタイムリーな、かつ関連分野へのインパクトの大きな研究業績となっている. 本論文は6章より成り立っている.従来の研究のまとめの1、2章に引き続き、第3章においては地球の内核の成長進化を堆積圧密モデルに基づき定式化を行い、成長のタイムスケールやエネルギーバランス、予測される内部構造を明らかにした.此処に定量的に検討されているモデルでは、地球の形成初期の内部の高温状態は外部への熱の輸送により冷却が進み、温度の低下につれて内核成分の析出が生じ、自己重力場での必然的帰結として中心核の堆積圧密が生じたとするシナリオである. 第4章においては内核の圧密成長に伴う地震波速度異方性の形成メカニズムを示し、異方性の地震学的観測事実を説明した.内核を伝わる地震波は自転軸と平行な南北方向に伝搬するP波が早いという事実が知られている.自転の影響を受けた外核の対流構造、熱輸送構造を反映して、内核の析出・成長速度に異方性が生じ、それが応力場の異方性を引き起こし、更に六方晶鉄の結晶選択配向が生じた、とする異方性獲得のメカニズムを示し定量的に検討した. 第5章においては第4章の結果を敷延し、異方的構造進化モデルがどのような地震学的観測データによって検証され得るのか、観測可能な実体波のパスについてモデル計算に基づいた具体的な検証手法を提案している.極めて観測事実に乏しい中心核における研究状況においては、検証可能なモデルの構築/検証方法の提案は従来の研究スタンスを超えたものとして高く評価される. 第6章においては太古代の地球磁場強度をオーストラリア・ピルバラ地塊の火山岩を用いて推定し、現在の磁場強度と比較して極めて高い磁場が27億年以前には存在していた可能性を示した.内核の存在が磁場の形成、維持に重要な役割を果たしていることが指摘されており、初期地球での強い磁場の存在は形成初期の地球での内核の欠如とそれに引き続く急速な成長、という本論文の前半で示された内核成長のシナリオから理解されることを示した. 問題の取り組み方は第3章、第4章においてはフォーワード問題(モデルからの帰結)として扱い、第5章においては検証法の提案、第6章においてはインバース問題(データからの帰結)として内核の成長問題を取り上げるという幅広いスペクトルをもっている.このようなアプローチは十分なデータが不足している中心核研究においては有効で、今後の研究方向に新しい手法を示したと高く評価できる. 第3章は浜野洋三氏、熊沢峰夫氏、吉田茂夫氏との、また第4章は吉田茂夫氏、熊沢峰夫氏との共同研究であるが論文提出者が主体となってモデリング、計算を行ってきたものである. 以上述べてきたように本論文は高い到達度を示し、地球中心核研究に重要な貢献を行った.このことから審査員一同は申請者が博士(理学)の学位を授与されるに値すると認定する. |