学位論文要旨
| No | 112446 | |
| 著者(漢字) | 古屋,正人 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | フルヤ,マサト | |
| 標題(和) | 大気と太平洋の極運動への影響 | |
| 標題(洋) | The Effects of the Atmosphere and Pacific Ocean on the Earth’s Wobble | |
| 報告番号 | 112446 | |
| 報告番号 | 甲12446 | |
| 学位授与日 | 1997.03.28 | |
| 学位種別 | 課程博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 博理第3226号 | |
| 研究科 | 理学系研究科 | |
| 専攻 | 地球惑星物理学専攻 | |
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 地球の自転角速度ベクトルの変動を地球座標系でみたとき,大きさの変化が一日の長さの変化に,向きの変化が極運動に対応する.それぞれ極軸,赤道軸の回りの角運動量収支を反映し,一年周期以下の一日の長さの変化は大気だけで非常に良く説明されている.一方の極運動においては,年周極運動と14カ月周期のチャンドラー極運動の二成分が卓越している.14カ月という周期は地球の特性できまる固有周期と解釈されており,チャンドラー極運動は地球の自由振動である.その励起源が分かれば地球の特性の制約になる.しかし1891年のチャンドラー極運動の発見以来,その励起源は同定されてこなかった.ところがFuruya et al.[1996a,b]は,気象庁の客観解析データに基づきチャンドラー極運動励起への大気の寄与を解析し,風励起の重要性を初めて明かした. 極運動の観測によれば,年周とチャンドラー極運動の振幅は同程度であり,年周極運動の方が強く励起されていることを示す.したがって,チャンドラー極運動の励起が正確に解明されるためにも,年周極運動の励起源はより定量的に説明されている必要があるが,実は年周極運動の励起源は大気だけでは十分説明できていないことが知られている. 本研究では,米国NCEP(National Center for Environmental Prediction)の再解析プロジェクトによる大気データ,NCEPの海洋データ同化システムによる太平洋領域のデータを用いて,年周及びチャンドラー極運動への大気と太平洋の影響を調べた. 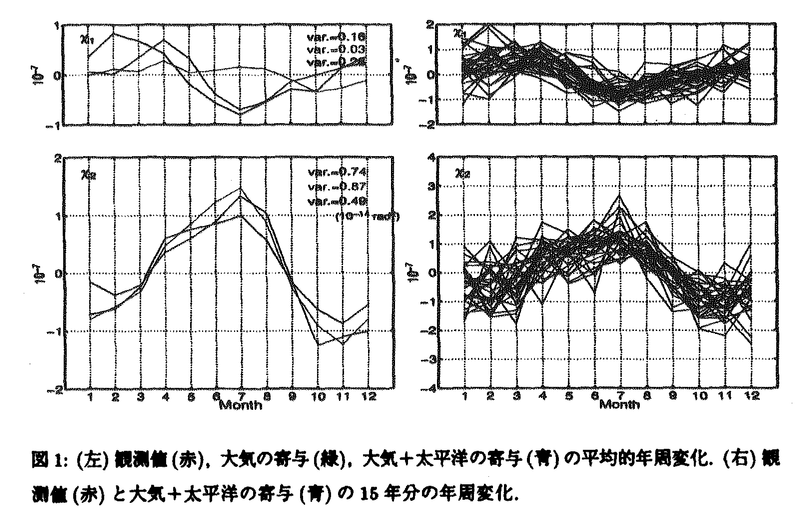 極運動データは,Gross[1996)]によるSPACE95である.1976年10月以降1996年2月迄の,daily dataであるが,大気と海洋データの利用可能期間に応じて切り出して月平均値に計算し直した.大気データには,NCEP再解析プロジェクトによる1979年から1995年迄の月平均値から,2.5°メッシュの地表気圧,鉛直17層の東西風と南北風を用いた.大気角運動量の計算はBarnes et al.[1983]の定式化に沿っている.海洋のデータには,NCEPの海洋データ同化システムによる1980年から1994年迄の月平均値から,東西流速,南北流速,温度,塩分濃度,海水面起伏を用いた.緯度方向1°経度方向1.5°メッシュのデータが太平洋領域について公開されている[e.g.,Ji et al.1995].角運動量の計算にあたり,慣性モーメント変化の寄与は,密度変化の効果と海水面変化の効果を分けて計算し,後で加える. 極運動は赤道軸の周りの角運動量収支を反映するので,トルクには二成分,経度90°方向成分( 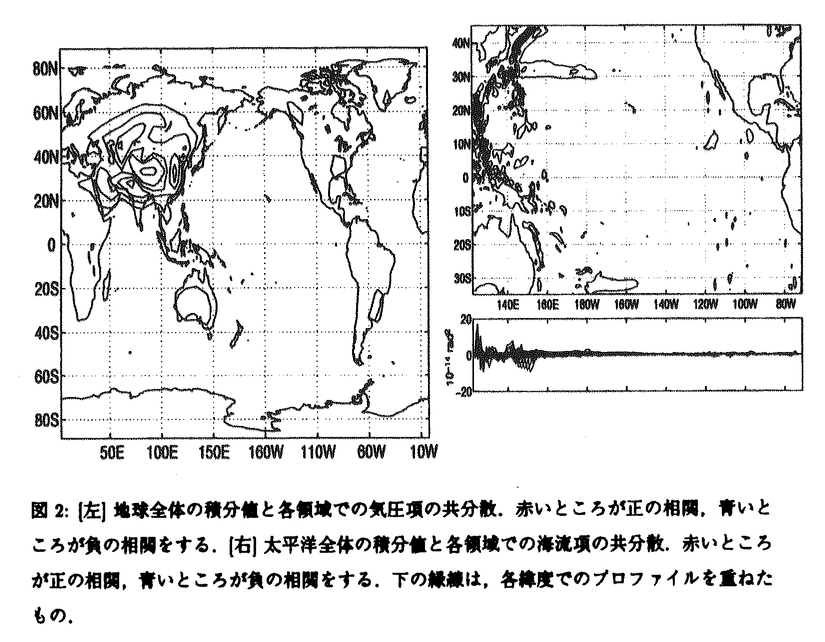 残された問題は 太平洋の寄与を加えた結果, 海流項の季節変動の大半は,海面に働く風応力トルクと内部摩擦トルクによるものである.海底山岳トルクは,一年以下の短周期変動と経年変動に寄与している. 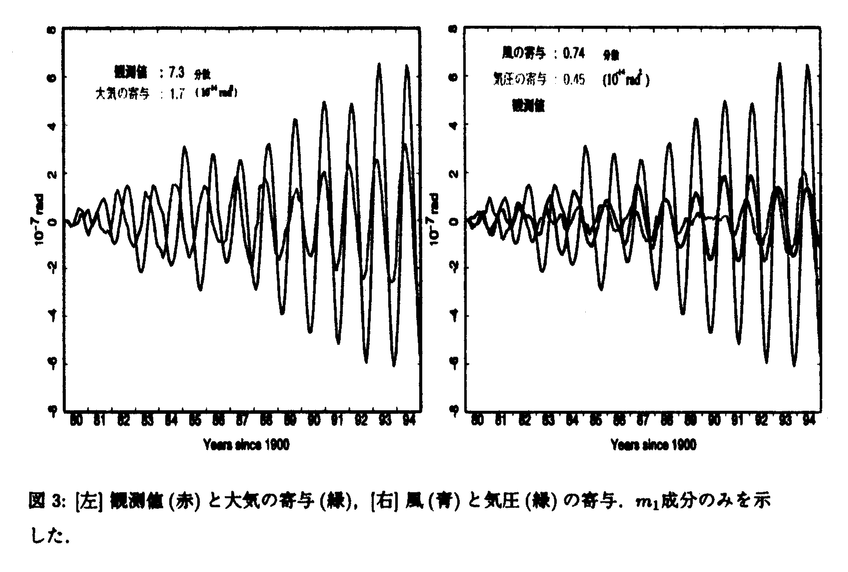 (i)Furuya et al.[1996a,b]による風励起説を,NCEPデータで検証すること,(ii)太平洋は励起するだろうか,という二点がこの解析の動機である. 極運動領域での解析によって,チャンドラー周波数付近の励起源の様子を調べる[Furuya et al.,1996b]. NCEPデータによるチャンドラー極運動は,観測値の振幅の半分程度になっているが(図3左),気圧項と風速項の寄与を比べると,風速項の寄与が大きい(図3右).JMAデータと比較した結果は,気圧項の寄与は一致するが,風速項は整合しない.この結果から気圧の寄与が小さく,風が重要なのは確定的となったが,風速項の精度には問題が残った. 太平洋の寄与を調べた結果,太平洋だけでも観測値に匹敵する振幅があることが判明した.現状では太平洋の寄与しか調べられなかったが,この結果は励起源としての海洋の潜在的重要性を示唆している. | |
| 審査要旨 | 本論文は3部からなり、第1部(1章〜2章)では地球回転全般に関する基礎理論の提示、第2部(3章〜4章)では年周極運動成分の励起源についての解析,また第3部(5章〜6章)ではチャンドラー極運動成分の励起源についての解析について述べられている.地球の自転角速度変動のうち,極運動の年周成分と14カ月周期(チャンドラー極運動)の二成分については,その励起源が同定されてこなかったので,その励起源を究明しようというのが本論文の目的である. 類似の従来の研究に比して,本論文では最先端のデータが積極的に駆使されている.そのことが,解析結果の信頼性を大きく高めるのにやくだっている.実際,極運動データとして,現在最新のSPACE95(Gross,1996)が用いられている.これは宇宙測地技術をもちいて得られたデータであるので,1980年代以前光学観測主流のデータに比して大幅な精度改善がなされている.この地球回転データをもちいた結果,固体地球に対してはたらく外部励起トルク2成分(経度90゜方向成分 (a)米国NCEP(National Center for Environmental Prediction)の大気データおよび (b)NCEPの海洋データ同化システムによる太平洋の海洋データ をいちはやく解析し,年周及びチャンドラー極運動への全地球大気と太平洋の影響を調べた. 大気の寄与については地表気圧,鉛直17層の東西風と南北風を用いて,大気角運動量の計算がなされている.海洋の寄与については,太平洋領域について公開されている東西流速,南北流速,温度,塩分濃度,海水面起伏データを用いて見積もっている.その結果,以下の結論を導いている. 太平洋の寄与を加えると, NCEPデータによって大気によるチャンドラー極運動をシミュレーションしてみると,観測値の振幅の半分程度になったが,気圧項と風速項の寄与を比べると,風速項の寄与が大きい.JMA(気象庁)大気データによる極運動と比較した結果は,気圧項の寄与は一致するが,風速項は整合しない.この結果から気圧の寄与が小さく,風が重要なのは確定的となったが,風速項の精度には問題が残った. 太平洋の寄与を調べた結果,太平洋だけでも観測値に匹敵する振幅があることが判明した.現状では太平洋の寄与しか調べられなかったが,この結果は励起源としての海洋の潜在的重要性を示唆している. 以上の結論は妥当なものであり,現時点で到達可能な最高水準の知見といえる.また固体地球物理学にとどまらず,気象学・海洋学的にみてもきわめて意味のある研究と認められる. なお参考論文第1章及び3章は濱野洋三・内藤勲夫と,第2章はBenjamin F.Chaoとの共同研究であるが,論文提出者が主体となって分析および検証を行ったもので,論文提出者の寄与が十分であると判断する. よって博士(理学)の学位を授与できると認める. | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/53951 |
 1)とグリニッジ方向成分(
1)とグリニッジ方向成分(