阪神大震災以降、極めて大きな地震動に対して構造物が重大な被害を引き起こさないための設計基準(第2段階の設計基準)の必要性がより一層高まっている。極めて大きな地震を受け、材料が降伏するような場合の粒状体斜面安定性評価においては、最終的にどの程度の変形が引き起こされるかで被害の大きさが変わってくることを考えれば、変形量の検討は避けて通れない。しかし、大きな歪みが生じる場合の斜面変形量においては、降伏点以降の粒状材料の力学特性に不明な点が多く、更に、構造の破壊モード、地震動特性の影響など関しても未だ明らかになっていないことから、現状では定量評価のレベルまで達していない。そこで本研究は、まず粒状体材料の力学特性を数値シミュレーションを用いて検討し、その知見を踏まえて、大きな地震動を受けて粒状体斜面が塑性変形を生じる場合の変形量を簡便に評価し、耐震設計に活かせる手法を提案することを目的としている。 粒状体材料の降伏点以降の力学特性は、歪みがせん断層と呼ばれる粒子10個から20個の狭い幅に集中することから、このせん断層内部の粒子間の相対運動や接触力のやり取りなどの相互作用に支配される。このミクロな挙動を要素試験などで検討することは多くの困難を伴う(1)。そこで本研究では、円形、正多角形、楕円形など、さまざまな形状の粒子を用いた個別要素法(DEM:Discrete Element Method)解析により、せん断層内の粒子間相互作用と、マクロな力学特性の関係を、粒子形状の影響を考慮しつつ検討した。そして、その結果を文献(1)の実験結果と比較し、定量的に意味のある、以下の知見を得た。 (1)せん断層内のダイレタンシーの低下率k(すなわち強度の低下率)はおよそ-0.35から-1.0の値をとり、初期密度が大きいものほど-1.0に近くなる。k=-1.0は、上の粒子が下の粒子を乗り越える、非常に単純なモデルでの値とほぼ等しい。また、peak強度から残留状態に達するまでのせん断歪みは0.5程度であり、これは粒子半径分のずれに相当する。 (2)異なったせん断歪みが生じている供試体の各部でほぼユニークな関係が得られた。従って、この関係を基に、連続体と仮定した解析が可能である。また、せん断層内の構成関係は、最も大きな歪みが生じている中央部で評価するのが良い。 (3)実際に目視されるせん断層の幅は、いくつかの極小せん断層から構成されている可能性がある。極小せん断層は粒子5個程度ではないかと推定される。 更に、地震波のように、大きな繰り返し歪みを受ける場合の構成関係を検討するために、繰り返し単純せん断試験のシミュレーションを行い、以下の知見を得た。 (4)peak強度を超える歪みを受けた場合でも、ヒステリシスは、静的な荷重変位曲線を骨格曲線とした、安定したループを描く。残留強度に至った後は、歪みの反転などによっても粒子骨格の質的な変化がなくなり、Masing則が成立する。 これらの知見を基に、非常に大きな地震動を受けて材料が降伏するような場合の、粒状体斜面の塑性変形解析過程の構成を試みた。既往のロックフィルダムの振動破壊実験結果(2)などを踏まえ、斜面の表層滑りを、剛な傾斜基盤上の1次元の柱の変形と理想化することで、比較的簡単な解析過程を構成できる。構成した解析法によって求めた斜面の残留変形量を図1に示す。入力地震波は兵庫県南部地震の地震波形で、加速度振幅をさまざまな大きさに変化させたものを用いた。1次元の柱の要素分割数を変化させることで、さまざまなせん断層の厚さを実現できるが、このせん断層厚さの違いが、生じる残留変形量に大きく影響を及ぼしていることが分かる。せん断層の厚さは粒径と関連が深いから、粒径が大きいほど残留変形量は小さい。すなわち、ロックフィルダムのような粗い粒子からなる構造は、粒径の小さなものより耐震性が高いということになる。この粒径の影響は、現在の設計基準では考慮されていない問題である。 この粒径依存性の原因は、せん断層内の歪み軟化と深い関わりがある。残留状態に達するまでに必要な歪みが0.5程度で粒径によらないとすると、変位量に直せば、せん断層の厚さが薄いほど、わずかな変位量で残留状態に達する。いわば、地震のエネルギーが小さい幅に集中するほど早く壊れる(残留状態に達する)のである。 図1によれば、塑性変形は、地震の最大加速度がある限界値(限界加速度 t)を超えると顕著に現れ、その後はほぼ直線的に増加している。斜面の耐震設計においては、この t)を超えると顕著に現れ、その後はほぼ直線的に増加している。斜面の耐震設計においては、この tが、安定性を示す指標になると考えられる。 tが、安定性を示す指標になると考えられる。 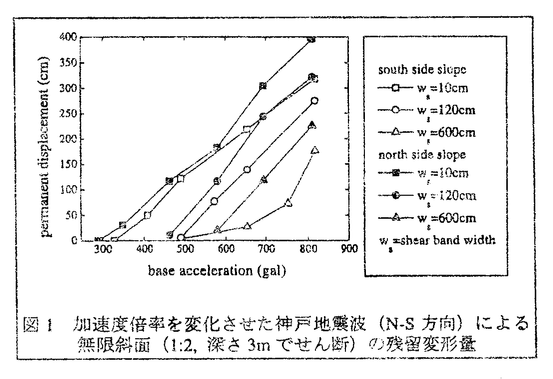 図1 加速度倍率を変化させた神戸地震波(N-S方向)による無限斜面(1:2,深さ3mでせん断)の残留変形量 図1 加速度倍率を変化させた神戸地震波(N-S方向)による無限斜面(1:2,深さ3mでせん断)の残留変形量 いくつかの解析例から、実地震波は、それに含まれる主要なパルスを独立に与えたと仮定して変形量を求めても、それほどおかしな結果にならないことが分かった。そこで、1つの矩形パルスに対する加速度-残留変位曲線を求めたものが図2である。やはり、せん断層厚さによって差が見られるが、ここで、斜面表層滑りを剛体ブロックの滑りと仮定したNewmarkのSliding Block法による基盤加速度amaxと残留変形量Dpの関係式  (ここに、aini=gtan( 0- 0- )(塑性変形の生じる限界の加速度)、 )(塑性変形の生じる限界の加速度)、 0はブロックと斜面の間の摩擦角、 0はブロックと斜面の間の摩擦角、 は斜面の傾斜角、t0は矩形波の継続時間) は斜面の傾斜角、t0は矩形波の継続時間) において、 0を、材料のpeak強度および残留強度にとった場合の関係を、それぞれp-line、r-lineとして図2に示すと、斜面の変形は、はじめp-lineに沿って進むが、ある加速度で急激に立ち上がり、r-lineに漸近してゆくことがわかる。この傾きの急変部は、材料が残留状態に達する点とほぼ一致しており、残留状態に達する条件が限界加速度に関係することが分かる。この結果を基に、限界加速度 0を、材料のpeak強度および残留強度にとった場合の関係を、それぞれp-line、r-lineとして図2に示すと、斜面の変形は、はじめp-lineに沿って進むが、ある加速度で急激に立ち上がり、r-lineに漸近してゆくことがわかる。この傾きの急変部は、材料が残留状態に達する点とほぼ一致しており、残留状態に達する条件が限界加速度に関係することが分かる。この結果を基に、限界加速度 tを簡便に評価する、以下の方法を検討した。 tを簡便に評価する、以下の方法を検討した。 まず、残留状態に達するまでに必要な変位量Dresは、残留到達せん断歪み res、せん断層の幅ws、せん断層内の変形モードを表す定数 res、せん断層の幅ws、せん断層内の変形モードを表す定数 より、以下のように表すことができる。 より、以下のように表すことができる。  ここに、 はせん断層内の変形モードを直線(歪み一様)とすると はせん断層内の変形モードを直線(歪み一様)とすると =1、二次曲線(歪みが直線分布) =1、二次曲線(歪みが直線分布) =0.5などとなる。 =0.5などとなる。  図2 矩形波加速度パルスを入力したときの斜面残留変形量 図2 矩形波加速度パルスを入力したときの斜面残留変形量 実際の地震波のパルスは、矩形波よりsine波に近いと考え、最大速度が等しくなるように円振動数 のsine波パルスを矩形波に置き換える等価継続時間を次のように定義する。 のsine波パルスを矩形波に置き換える等価継続時間を次のように定義する。  与えられた地震波の主要インパルス数をnpとする。主要なパルスによって生じる変形の和が残留状態に達するのに必要な変形量と等しくなる条件から実地震波の限界加速度が定まるとすると、1つのインパルスに対して必要な変位量はDres/npである。したがって、式(1)で、 0がpeak強度と残留強度の間の値をとるものとして、Dp=Dres/npを満たすような加速度amaxから限界加速度 0がpeak強度と残留強度の間の値をとるものとして、Dp=Dres/npを満たすような加速度amaxから限界加速度 tを近似的に評価できるとすると、式(0-2),(0-3)を用いて、 tを近似的に評価できるとすると、式(0-2),(0-3)を用いて、 tは以下のように表される。 tは以下のように表される。  この式を用いた結果と、先の兵庫県南部地震の応答結果から得られる tを比較したものが図3である。ここで、 tを比較したものが図3である。ここで、 0には、peak強度をとった。主要なインパルス数は、地震波形から4ないしは5波と推定されるが、その違いは余り顕著でなく、ここでは4波とした。地震動の卓越振動数fは1Hzから2Hzであり、神戸の結果は比較的よく合っている。図にはエルセントロの地震波形を用いた場合の結果も示した。エルセントロ地震波の卓越周波数も神戸地震波とほぼ同様であるが、神戸に比べて高周波成分を多く含んでいるため、勾配がf=3Hzの結果に近くなっていると思われる。 0には、peak強度をとった。主要なインパルス数は、地震波形から4ないしは5波と推定されるが、その違いは余り顕著でなく、ここでは4波とした。地震動の卓越振動数fは1Hzから2Hzであり、神戸の結果は比較的よく合っている。図にはエルセントロの地震波形を用いた場合の結果も示した。エルセントロ地震波の卓越周波数も神戸地震波とほぼ同様であるが、神戸に比べて高周波成分を多く含んでいるため、勾配がf=3Hzの結果に近くなっていると思われる。 なお、せん断層幅が小さい範囲で、数値解の結果と式(4)の結果が異なっているが、これは、せん断層が非常に薄い場合は、主要なインパルスの平均加速度ではなく、最大加速度を持つインパルス1つで残留状態に達してしまうため、その他のインパルスの影響がなくなるからである。そのためせん断層幅10cmの場合は、3つの地震波について、その波形に関わらず、最大加速度が静的な限界加速度(ここでは327gal)となるあたりで残留状態に達している。 以上の考察により、式(4)は、粒状体斜面の安定性を簡便に評価するのに有効であることが分かった。式(4)を用いるにあたって必要なパラメータは以下の通りである。 (1)斜面の材料の物性値として、(a)内部摩擦角、(b)残留摩擦角、(c)残留に至るまでに必要なせん断歪み(歪み軟化率より)、(d)せん断層厚さ(粒径などより)、(e)せん断層内の変形モード(2次式仮定など)、ただし(d)と(e)は構造の境界条件の影響を受ける可能性がある。 (2)斜面の振動特性値として、(f)最大加速度または主要なインパルスの平均加速度、(g)主要なインパルスの数、(h)卓越振動数 (3)構造の物性値として、(i)斜面勾配(または滑り面勾配)  図3 せん断層幅と限界加速度の関係(1)吉田 輝:砂の破壊に伴う歪みの局所化とせん断層の発生,東京大学博士論文,1994.(2)田村・岡本・加藤:ロックフィルダム模型の振動破壊実験-貯水のない場合-,土と基礎,Vol.20,No.7,pp.45-51,1972.(3)N.M.Newmark:Effect of Earthquake on Dams and Embankments,Geotechnique,Vol.15,No.2,pp.139-160,1965. 図3 せん断層幅と限界加速度の関係(1)吉田 輝:砂の破壊に伴う歪みの局所化とせん断層の発生,東京大学博士論文,1994.(2)田村・岡本・加藤:ロックフィルダム模型の振動破壊実験-貯水のない場合-,土と基礎,Vol.20,No.7,pp.45-51,1972.(3)N.M.Newmark:Effect of Earthquake on Dams and Embankments,Geotechnique,Vol.15,No.2,pp.139-160,1965. |