| 内容要旨 | | 近年、ある種のペロヴスカイト型Mn酸化物RE1-xAExMnO3(REは3価の希土類イオン、AEは2価のアルカリ土類イオン)において巨大磁気抵抗効果が発見された1)。この巨大磁気抵抗効果は金属人工格子におけるGiant Magneto-Resistance(GMR)と区別してColossal Magneto-Resistance(CMR)と呼ばれている。RE1-xAExMnO3においてはMnの3d軌道の中で局在したt2g軌道のスピンS=3/2と伝導を担うeg電子との間の強いHund結合に加えてeg電子間のCoulomb相互作用、さらには電子格子相互作用が働き、それらの競合によって多彩な物性が現れる。物理的面白さに応用上の興味も加わり、現在この系に関する研究は精力的に行われている。さらにRE1-xAExMnO3の中で特にegバンドのバンド幅Wが小さい系では、隣接サイト間のCoulomb相互作用Vによって電荷整列(CO)現象が起こる2)。CO相は絶縁体相であり、t2gスピンはCE型の反強磁性配列をとる。COはFe3O4のVerwey転移3)等で知られた現象であるが、Mn酸化物のCOでは磁場によるWの変化でW>Vを達成し、COを崩壊させられる点が特徴的である。 COの磁場による崩壊はPr0.50Sr0.50MnO3等で報告4)されており、転移磁場は低温ほど高くなる傾向がある。Pr1-xCaxMnO3では0.3 x x 0.5の広範囲の組成でCOが出現する5)。このCOが整合でないx 0.5の広範囲の組成でCOが出現する5)。このCOが整合でないx 0.40においては転移磁場は逆に低温で減少する傾向を示すが、この相図の振る舞いがCOの整合性に起因するものであるのか、またはPrCa化合物に固有の性質であるのかは不明である。 0.40においては転移磁場は逆に低温で減少する傾向を示すが、この相図の振る舞いがCOの整合性に起因するものであるのか、またはPrCa化合物に固有の性質であるのかは不明である。 Jirakらが行った粉末試料に対する零磁場下での中性子線回折によると6)、Pr0.50Ca0.50MnO3はCOと同時に構造相転移を起こす。室温での結晶構造は立方晶に近い、CO相ではc軸長が減少して擬正方晶になる。この構造相転移によってeg軌道の二重縮退が解けて軌道の配列が起こる。この軌道の配列が二重交換相互作用(DE)の作用する方向を特定し、MnスピンのCE型の反強磁性秩序を決定していると考えられている。 本研究の対象とした試料はRE1-xCaxMnO3で表される物質群でJRCAT十倉グループの富岡氏によって作成された。RE=Pr,Nd,Sm,Yに対し、x=0.50付近の組成の試料を使用した。RE=Pr,Nd,Smに関してはフローティングゾーン法によって成長した単結晶試料を測定に用いた。これらのegバンド幅の狭い系においてはCOを破壊するために強磁場を要する。本研究ではパルスマグネットを用いて発生された強磁場下において物性測定を行った。40Tまでの長時間パルス磁場下では、同軸型ピックアップコイルを用いた誘導法による磁化測定、直流四端子法による縦磁気抵抗測定及びキャパシタンス法による磁場方向の磁歪測定を行った。また、100Tまでの超強磁場下における磁化測定には並列型ピックアップコイルを使用した。 まず、典型的な例としてPr0.55Ca0.45MnO3に対して行った磁化、磁気抵抗及び磁歪測定の実験結果を示す(図1)。この温度領域ではPr0.55Ca0.45MnO3は零磁場で電荷整列した反強磁性体である。磁場に比例して磁化が増大した後、強磁性的状態へ一次の相転移を起こす。この磁気相転移は図1(b)に見られる様に、低温では測定系のダイナミックレンジを越える4桁以上に及ぶCMRを伴う。また同時に磁場方向に10-3のオーダーに達する試料の伸びが観測される。この磁歪はCO相で縮んだc軸長を回復する構造相転移が起こっているものと考えられる。この構造層転移は縮退の解けていたeg軌道を再び縮退させることになる。本研究において転移磁場の定義は磁化の飽和磁場で統一して議論を進める。 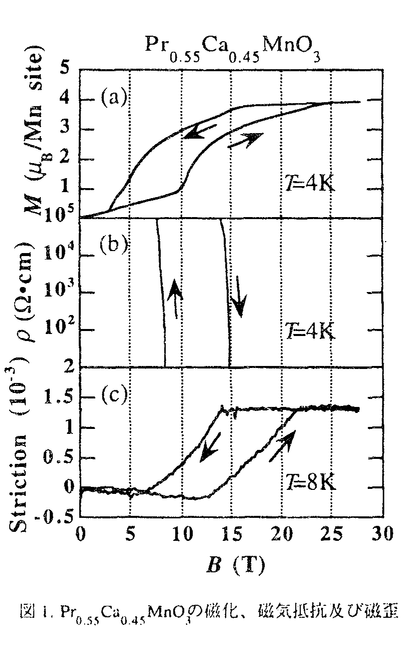 図1.Pr0.55Ca0.45MnO3の磁化、磁気抵抗及び磁歪 図1.Pr0.55Ca0.45MnO3の磁化、磁気抵抗及び磁歪 図2.超強磁場下における磁化測定結果。 図2.超強磁場下における磁化測定結果。 RE=Pr,Nd,Sm,Yのx=0.50の組成の各試料に対して磁化測定を行った。このうちRE=Sm,Yに関しては40Tまでの測定では低温領域で転移が起こらなかった。この二つの試料に対して、100Tまでの超強磁場下で磁化測定を行った(図2)。図の縦軸はピックアップコイルに誘導された起電力Vで、磁化の時間微分に比例した量である。Sm化合物では温度18Kにおいて磁化の飛びに対応して50T付近にピークをもつ構造が現れる。一方Y化合物に関しては40Tまでの磁化測定でMn3dのモーメントが80T付近で飽和することが予想されており、転移磁場は80T以下であることが期待されていたが、実験では95Tに至るまで磁化の飛びに相当するような構造は現れなかった。 RE=Prのx=0.50,0.45及びRE=Ndのx=0.50,0.45,0.40の組成の試料に対して、磁化の飽和磁場で定義した転移磁場の温度依存性を図3にまとめた。x=0.50におけるCO相図は温度-磁場平面においてPr0.50Sr0.50MnO3と同様の振る舞いを示す。また、転移磁場の温度依存性はPr化合物とNd化合物の間に顕著な差はなく、キャリア濃度xで決定されていることが明らかとなった。  図3.RE=Pr及びRE=Nd化合物のx=0.50,0.45,0.40の相図。 図3.RE=Pr及びRE=Nd化合物のx=0.50,0.45,0.40の相図。 以上の実験結果を元に、まず転移磁場の温度依存性の起源について考察した。一連の相図を比較すると転移磁場の温度依存性は希土類の種類よりも、キャリア濃度xで決定されている。これは定性的には熱力学的に次のように説明できる。系のHelmholtzの自由エネルギーFはF=U-TSで与えられる。x=0.50のとき、整合なCOが起こるためにCO相のエントロピーSは電荷の整列しない(CDO)相に比べて小さい。そのためCO相とCDO相との自由エネルギーの差は温度上昇に伴って減小し、転移磁場が低下する。一方xが0.50からずれるとCO相では反強磁性配列が一通りに決まらないため強磁性的CDO相よりもSが大きく、転移磁場が温度上昇とともに増加すると考えられる。 続いて転移の機構について考える。反強磁性CO相に磁場を印加したとき、低磁場での磁場に比例した磁化過程では反強磁性配列したt2gスピンのキャンティングが進む。この過程でバンド幅が増大し、W>Vが達成されたところでeg電子によるDEが強く働き、磁気構造が崩壊する。磁気構造の崩壊に伴いeg軌道の縮退が解けることによるエネルギーの利得が減少し、構造相転移が起こり軌道の配列が崩壊する。  図4.tolerance factorとHC。 図4.tolerance factorとHC。 最後にREサイトの影響について述べる。ペロヴスカイト型Mn酸化物ではRE及びAEサイトの平均イオン半径を変化させることにより、Mn-O-Mnボンドアングルを調整しeg軌道の作るバンドの幅を調整する事が可能である。そのためREサイトの種類を変えた試料に対する磁化測定結果を通じて、バンド幅の変化がCO現象に及ぼす影響を議論した。低温極限における磁場上昇時と下降時の転移磁場の平均で定義した熱力学的転移磁場HCOをMn-O-Mnの歪みの度合いを示すtolerance factorに対して表すと図4の様な関係になる。一般的な傾向としてMn-O-Mnのボンドアングルが減小しtが小さくなるにつれて転移磁場が増大する傾向が明らかになった。なお、Y化合物はt=0.946であるが、100Tまでの磁化測定では転移が見られなかった。これは零磁場におけるバンド幅がある程度以上小さくなると、局在スピンが完全に整列しても電荷移動のギャップがつぶれないことを反映した結果であると思われる。 参考文献1). A.Urushibara,et al.,Phys.Rev.B5114103(1995).2). E.O.Wollan,et al.,Phys.Rev 100,545(1955).3). E.J.W.Verwey,et al.,J.Chem.Phys.,15,181(1947).4). Y.Tomioka,et al.,Phys.Rev Lett 745108(1995).5). Y.Tomioka,et al.,J.Phys.Soc.Jpn.,643626(1995).6). Z.Jirak,et al.,J.Magn.Magn.Mat.53,153(1985). |
| 審査要旨 | | REMnO3(REは希土類元素)という化学式で表される一連のペロヴスカイト型化合物は、反強磁性のMott絶縁体であるが、3価のREイオンを2価のアルカリ土類(AE)イオンで置換することにより、キャリアをドープして金属絶縁体転移を引き起こすことが可能である。ドープした系は、適当な温度、組成範囲で2重交換相互作用による強磁性、巨大な負の磁気抵抗効果(Colossal Magnetoresistance,CMR)、構造相転移、電荷整列状態を示し、キャリア系、スピン系、格子系が相互に関連しあった相転移を起こす物質として関心を集めており、またそのCMRは、応用上の観点からも注目されている。 本論文は、「ペロヴスカイト型Mn酸化物の強磁場物性」と題し、これらの物質の強磁場下での物性を詳細に調べ、特に磁場誘起相転移の機構を明らかにすることを目的として行った研究をまとめたものである。 第1章「序論」では、研究の目的、意義、論文の概要などが述べられている。 第2章「RE1-xAExMnO3の物性」では、RE1-xAExMnO3の結晶構造と電子配置、巨大磁気抵効果、磁場誘起構造相転移、電荷整列現象など、この物質に関する従来の実験的研究とそれらを説明する既存の理論が要約されており、本研究の背景が述べられている。 第3章「実験」では、本研究で使用した種々の実験技術が述べられている。本研究では、主として非破壊型パルスマグネットによる40Tに及ぶ長時間パルス磁場下で、磁化、磁歪、磁気抵抗の測定の実験が行われ、またさらに強い磁場が必要な場合には、一巻きコイル法による100Tにおよぶ超強磁場の下での磁化測定も行われたが、これらの実験に必要な諸技術が述べられている。 第4章「実験結果」では、種々のCa濃度をもつRE1-xCaxMnO3(RE=Pr,Nd,Sm,Y)における実験結果とその解析が述べられており、第5章と並んで本論文の中心部分を成している。Pr化合物では、強磁場における磁化、磁歪、磁気抵抗の測定によって、磁場による電荷整列の崩壊に伴う電荷整列・絶縁体相から強磁性・高伝導度相への相転移を観測し、これまでx≦0.4の試料で調べられていた温度磁場平面における電荷整列相の相境界を、電荷整列が格子と整合する濃度(x=0.5)に至るまで調べた。その結果から、濃度が整合条件からはずれるにしたがって相図が変化していく様子を明らかにした。種々のxをもつNd化合物についても同様に相図を決定し、相境界の形状の定性的特徴が、これら2つの物質では、REの種類によらずxで支配されることを明らかにした。さらに磁歪の測定においても相転移を巨大な磁歪の変化として観測し、磁場による電荷整列の崩壊は、巨大磁気抵抗を伴う磁気相転移だけでなく構造相転移を伴っていることを示した。Sm化合物では、一巻きコイル法による超強磁場下測定をも含めた実験から相図を決定した。Y化合物(x=0.50)では100Tに至るまで、相転移に対応する磁化のとびが起こらないことを確認した。これらの実験は、パルス磁場による強磁場領城ではじめて可能になったものである。 第5章「考察」では、本研究で得られた実験結果の考察が詳しく議論されている。反強磁性と強磁性の相転移の一般論を基礎として、これに電荷秩序相転移を導入した考察を行った。これにより、キャリア濃度によって金属-絶縁体転移の起こる相境界の温度-磁場依存性が異なること、相転移が反強磁性相から起こる場合と常磁性相から起こる場合とで、相境界が異なる傾きを示すことを説明し、相図の定性的な形状を理論的に再現することに成功した。さらにREイオンの種類を変えた実験の結果から、REイオン半径が小さくなってキャリアのバンド幅が減少するにしたがって、電荷整列崩壊を引き起こす磁場が増大することを示した。 第6章「電子スピン共鳴」では、ミリ波領域における電子スピン共鳴の実験結果が述べられている。Nd1-xCaxMnO3では、高温の常磁性状態では強い電子格子相互作用を反映した常磁性共鳴が観測されるが、低温になると、反強磁性共鳴が観測されることが確認された。 以上を要するに、本研究は最高100Tにおよぶ強磁場下で、磁化測定、磁歪測定、磁気抵抗測定、電子スピン共鳴を手段として、RE1-xCaxMnO3(RE=Pr,Nd,Sm,Y)の磁場誘起相転移の研究を行い、強磁場で起こる磁気相転移について多くの新しい知見を見出したものであり、物性物理学、物理工学の発展に寄与するところがきわめて大きい。 よって本論文は博士(工学)の学位請求論文として合格と認められる。 |