| 【研究目的】 X線磁気円二色性(X-ray Magnetic Circular Dichroism)は磁性を研究する新しい手段である。軟X線領域では始状態・終状態ともに局在しており実験的解析が行い易くまた理論的解釈もかなり明らかにされてきた。しかし硬X線領域に属する3d遷移金属のK-吸収端は始状態であるls軌道にはスピン軌道相互作用が存在しないこと、終状態である4pがバンドを形成しており非局在であること、の2つの理由でXMCDスペクトルの解釈が困難となっている。したがって本研究では3d遷移金属のK-吸収端のMCDスペクトルを理解し、3d遷移金属合金における磁性電子の振る舞いを明らかにすることを目的とした。そのためには系統的な測定と第一原理からの理論計算との比較が必要不可欠である。 【実験方法】 XMCD測定は高エネルギー物理学研究所のPF-28Bにて透過法を用いて行った。XMCD測定の装置のレイアウトは通常のX線吸収測定とほぼ同様である。XMCDの強度  tはX線の波数ベクトルと磁化ベクトルが反平行の場合の吸収強度 tはX線の波数ベクトルと磁化ベクトルが反平行の場合の吸収強度 +tからX線の波数ベクトルと磁化ベクトルが平行の場合の吸収強度 +tからX線の波数ベクトルと磁化ベクトルが平行の場合の吸収強度 -tを差し引くことによって得る。同一エネルギーで磁場を反転することによりX線の波数ベクトルと磁化ベクトルの平行または反平行の相関を作る。全吸収量 -tを差し引くことによって得る。同一エネルギーで磁場を反転することによりX線の波数ベクトルと磁化ベクトルの平行または反平行の相関を作る。全吸収量 tは tは +tと +tと -tとの平均として定義した。ここで -tとの平均として定義した。ここで は吸収係数、tは試料の実効厚みである。 は吸収係数、tは試料の実効厚みである。 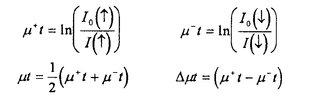 ここで式の右辺の↑はX線の波数ベクトルと試料の磁化ベクトルが反平行の場合を示し、一方↓は平行の場合を示す。I0,Iはそれぞれ入射X線強度と透過X線強度である。エネルギーのスキャン範囲は吸収端近傍の50〜60eVでエネルギーステップの幅はleVである。そのスキャン範囲を数回測定して結果を足しあわせることで統計精度の向上を図った。またX線吸収量 をX線のエネルギーの関数とした場合の第一変曲点をフェルミレベルと仮定し、0eVとした。 をX線のエネルギーの関数とした場合の第一変曲点をフェルミレベルと仮定し、0eVとした。 【実験結果】 3d遷移金属のK-吸収端におけるMCDとXANESを測定した。MCDスペクトルを図1-1に示す。図1-1において横軸は光子の運動エネルギーであり、縦軸はMCDの強度で、任意単位である。 XANESスペクトルは吸収端付近で肩をもち、なだらかに吸収強度が上昇しWhite-Lineと呼ばれる比較的強いピークを形成する。さらに高エネルギー側ではそれぞれの結晶系に固有な振動スペクトルを描く。このエネルギー領域の振動構造はEXAFSと呼ばれている。すべてのスペクトルは金属の特徴であるなめらかな吸収曲線を示した。  図1-1 MCDスペクトル 図1-1 MCDスペクトル MCDスペクトルは全体的に複雑なスペクトルを形成している。MCD領域における主要なピークは、吸収端付近のピークAとそれより高エネルギーに存在するピークB、Cの3つが存在する。ピークCは純金属には見られないが合金および化合物系には存在するものである。ピークAは3d電子の占有数が増えるとピークが正から負へ変化していくピークであり、フェルミレベル付近の3d電子の構造を強く反映したスペクトルである。これはスピン分極を考慮したバンド計算結果と比較することにより明確となった。MCDスペクトルの吸収端付近のプロファイルとup-spinの非占有状態密度からdown-spinの非占有状態密度を引いたものの比較を行うと、吸収端付近ではMCDスペクトルと非占有状態密度の差のプロファイルがよく似ていることがわかる。例えばFeにおいて比較したものを図1-2に示す。またこの傾向は他の化合物であるFeB,MnBおよびFe4Nにおいても同様であった。  図1-2 FeのMCDスペクトルとバンド構造 図1-2 FeのMCDスペクトルとバンド構造 一方B,Cなどのピークはより非局在の特徴の強い4p電子の影響が優位に効いている領域になる。これは結晶構造・磁気構造ともに同一であるFeB,MnBにおいてスペクトルを比較することにより明らかになった。図1-3にFeB,MnBのMCDスペクトルを示す。吸収端より10eV以上高エネルギー領域でMCDのスペクトルの振動構造がFeB,MnBで良く似ていた。この領域ではXANESにおいてもスペクトルの振動構造は非常に似ている。これは両化合物で結晶構造のみならず磁気構造が類似しており、磁性原子(この場合Fe、Mn)の存在するサイトでの交換ポテンシャルの配置が同様であることを反映している。またこのエネルギー領域では交換ポテンシャルが支配的に効いている。これはFeB,MnBの磁気モーメントとMCD強度が正の相関を持っていることより明らかとなった。  図1-3 FeBとMnBのMCDスペクトル 図1-3 FeBとMnBのMCDスペクトル 以上の考察によりK-吸収端のスペクトルは2つの領域に分けることが出来、次のような特徴を持っていることが明らかになった。 低エネルギー(吸収端付近) 終状態である4pより内殻に位置する3dバンドの影響を強く受けている領域でMCDの強度も相対的に強い。またスピン・軌道相互作用のポテンシャルも比較的強い領域である。しかし交換ポテンシャルの方が断然強いことが理論計算から示された。 高エネルギー p対称を持つ光電子が隣接原子の交換相互作用のポテンシャルにより散乱されることによってMCDが観測されるので、結晶構造・磁気構造に強く依存する領域となる。 【理論計算】 実験結果を考察・解析するために多重散乱理論の枠内で作成した理論計算を行った。多重散乱理論を用いたMCD計算のプログラムは千葉大学理学部化学科藤川研究室で開発されたXANESの理論計算プログラムを基にしてK-吸収端用に開発したものである。本研究においてMCD計算用に付加された点は次の2点である。 第一に位相シフトをup-spinの光電子とdown-spinの光電子とそれぞれに対して別々に求めた。本研究においては磁性体を対象としているが3d遷移金属合金磁性体中では基底状態において3dバンドに大きな交換分裂が存在する。この交換分裂のためにup-spinの光電子が感じるポテンシャルとdown-spinの光電子が感じるポテンシャルが異なったものとなる。したがってこの状況を考慮に入れるために3d電子及び4s,4p電子は交換分極が存在するとしてup-spinに対する位相シフト およびdown-spinに対する位相シフト およびdown-spinに対する位相シフト を別々に求めた。 を別々に求めた。 第二にはXMCDの多重散乱理論を展開する上において光電子が感じるポテンシャルをクーロン相互作用、交換相互作用およびスピン・軌道相互作用の3つを考える必要がある。本計算において交換相互作用に比べてスピン・軌道相互作用は非常に小さいという仮定をおいた。この仮定をおくことによって計算に用いるGreen関数を対角化する基底状態として位相シフトを求めるときに用いた波動関数と同じ波動関数を適用することができる。このような仮定を用いて導出したMCDの強度はup-spinに関するX線吸収強度からdown-spinに関する吸収強度をひくことにより求められることになる。 【計算結果】 3d遷移金属の代表的な強磁性体であるFe,Co,およびNiについてMCDスペクトルの計算を行った。Feは体心立方格子をとるとし、電子構造はバンド計算の値を用いた。その場合の結果を図1-4に示す。実線が計算結果で黒丸が実験結果である。横軸はXANESスペクトルのピーク位置があうようにずらしてある。このエネルギー原点の任意性はフェルミレベルの位置の不定性によるものである。一方、縦軸は前節で述べたように規格化を実験値に合うように決めた。 計算結果は実験結果に極めてよく一致している。特徴的なピークは位置・形状ともによく合っている。しかし18eVのところのピークが計算ではあらわれないピークである。このピークは計算においてスピン・軌道相互作用を完全には取り入れていないために生じたと考えられる。またCo,Niについても実験結果と極めてよい一致を得た。以上の結果により多重散乱理論を用いたこの理論計算の妥当性が示された。またこの計算で用いた仮定すなわち、各原子サイトにおいてスピン軌道相互作用が交換相互作用に比べて非常に小さいとしたことおよびMuffin-tin近似を用いたことが妥当であることが示されたことになる。  図1-4計算によるMCDスペクトル 図1-4計算によるMCDスペクトル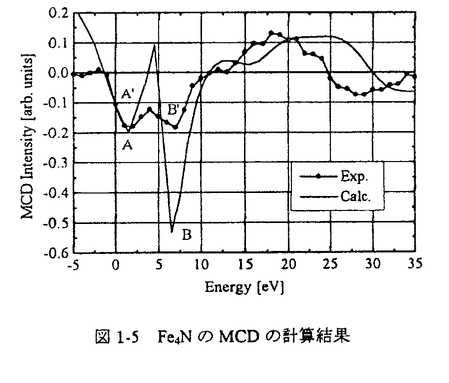 図1-5 Fe4NのMCDの計算結果 図1-5 Fe4NのMCDの計算結果 さらに純金属にのみならず3d遷移金属化合物(Fe4N,FeB,MnB)に対しても計算を行った。例としてFe4NのMCDスペクトルの計算結果を図1-5に示す。Fe4NはNに近い面心サイトを占めるFeとNから遠いコーナーサイトを占めるFeに2つのサイトが存在するので、それぞれのサイトでMCDスペクトルを計算した。そのサイトの存在比はcorner-site:face-center-site=1:3である。したがって存在比で重みをつけて吸収強度を重ね合わせた。それぞれのサイトで用いたFeおよびNの電子構造はバンド計算の結果を用いた。計算結果は定性的には実験結果を再現している。計算スペクトルにおける分裂しているピークA,Bはそれぞれ実験スペクトルのA’,B’に対応している。この計算により今まで不明であったFe4Nにおける吸収端付近で分裂したピークA’,B’の起源を初めて明らかにした。サイト別に計算させたMCDスペクトルを図1-6に示す。破線がコーナーサイト(corner)を実線が面心サイト(center)を表す。図中のBは破線・実線ともに負のピークとして存在する。一方Aは破線の方は正にピークを形成しているが実線の方は負にピークを形成している。つまりこの面心サイトにおけるピークAの絶対値のコーナーサイトのものよりも大きいことが分裂ピークA’,B’の起源である。  図1-6 Fe4Nのサイト別のMCD 図1-6 Fe4Nのサイト別のMCD またFe4NにおけるN原子の果たす役割を考えるためにN原子が存在しないFe4N0のMCDスペクトルを計算した。Fe4N0はFe4Nの体心サイトに存在するN原子を取り去り、そのほかの物理量は保存したものとして考える。すなわちFeが面心立方格子組んだときのMCDスペクトルに対応する。kの場合のMCDスペクトルはCoのMCDスペクトルに酷似している。またサイト別のスペクトルは吸収端以降のエネルギーでほとんど差がなくなる。したがってN原子の存在が面心サイトのFe原子のピークの分裂構造の起源であることが明らかになった。さらにFe4N0とFe4Nの結果の比較から面心サイトのFe原子の4s,4pおよび3d電子がN原子の2sや2p電子と混成軌道を形成し、Fe原子からN原子へ電子が移動していることが明らかになった。これはSakumaのバンド計算結果を支持するものとなっている。 【結言】 3d遷移金属合金のK-吸収端MCD測定を結晶対称性や磁気構造に着目して行った。同時に多重散乱理論の枠内で理論計算を行った。測定プロファイルを解析した結果MCDスペクトルはエネルギー領域により反映している情報が異なってくることが明らかにされた。すなわち吸収端付近では3d電子の影響を強く受ける領域であり、それより高エネルギーにおいては4p軌道における交換ポテンシャルを強く反映した領域となることを明らかになった。さらに理論計算を行った結果、3d遷移金属のK-吸収端のMCDスペクトルの理解は劇的な進歩を遂げた。純金属においては広範囲なエネルギー領域にわたって計算結果は実験結果を再現した。これにより交換相互作用がスピン軌道相互作用より大きな影響を光電子に与えていることが示された。またFe4Nにおいては吸収端付近のピークの分裂構造はFeのサイトが2つ存在することに起因することと、Nの2s,2p軌道と面心サイトのFeの3d,4s,4p軌道が混成軌道を形成しFeからNへ電子が移動していることを明らかにした。NdFeB,FeB,MnBに対しても磁性電子に関する挙動を反映した知見が得られた。このように本研究によってFe4Nをはじめとする3d遷移金属合金における磁性電子の挙動に関する有用な情報を得るとともにK-吸収端MCD測定は電子構造を決定する強力な手段とたりうる存在となった。 |