最近、重イオン加速器や不安定核ビーム生成技術の進展によって、安定線から離れた不安定原子核が原子核物理学の新たな対象となってきた。なかでも、中性子の束縛限界に位置する中性子ドリップライン近傍核の研究からは、中性子ハロー構造に代表されるようなこれまでの原子核物理の枠組を逸脱した興味深い現象が見つかっている。これまでの原子核構造の基本となっていた殻模型も、中性子過剰領域では変更を受けることが明らかになりつつある。例えば、中性子過剰核32Mgは、N=20の魔法数をもつ原子核にもかかわらず、非常に変形していることが近年の研究で分かった。11Beにおいても、通常の殻模型では数MeV離れているp軌道とsd軌道の準位がほぼ縮退していることが古くから知られているが、近年になって11Liなどの近傍の中性子過剰核においてもやはりp軌道とsd軌道が強く混合している、すなわち中性子数N=8の魔法数が消失していることが分かってきた。魔法数とは安定線近傍核の構造研究における基本的な概念で、その中性子過剰領域における振舞いは中性子超過剰核の構造の特異性を議論する上で極めて重要な意味合いを持つといえる。 本研究は、N=8近傍にフェルミ面を持った中性子ドリップライン核である14Beおよび11Liの 崩壊の崩壊様式を実験的に決定することにより、中性子過剰領域におけるN=8の殻構造の振舞いを研究することを目的とする。 崩壊の崩壊様式を実験的に決定することにより、中性子過剰領域におけるN=8の殻構造の振舞いを研究することを目的とする。 崩壊の機構は理論的に良く理解されており、崩壊の半減期と分岐比から特定の状態に対する行列要素をより明確に求めることができるため、安定線近傍核では構造研究のプローブとして古くから用いられてきた。しかし、中性子超過剰核の 崩壊の機構は理論的に良く理解されており、崩壊の半減期と分岐比から特定の状態に対する行列要素をより明確に求めることができるため、安定線近傍核では構造研究のプローブとして古くから用いられてきた。しかし、中性子超過剰核の 崩壊様式は、以下に述べるように安定線近傍核のそれとは異なる特徴を持つため、従来の実験手法を直接適応するのでは不十分である。すなわち、中性子超過剰核の 崩壊様式は、以下に述べるように安定線近傍核のそれとは異なる特徴を持つため、従来の実験手法を直接適応するのでは不十分である。すなわち、中性子超過剰核の 崩壊では 崩壊では が10〜20MeVと大きく、それに比較して娘核の中性子分離エネルギーSnが数MeV以下と非常に小さいため遷移後の状態がほとんど非束縛状態となるが、崩壊様式を決定するためにはこの時に放出される遅発粒子の測定が必要になるということである。これまでの遅発中性子核分光法では、 が10〜20MeVと大きく、それに比較して娘核の中性子分離エネルギーSnが数MeV以下と非常に小さいため遷移後の状態がほとんど非束縛状態となるが、崩壊様式を決定するためにはこの時に放出される遅発粒子の測定が必要になるということである。これまでの遅発中性子核分光法では、 -n二重同時計測による -n二重同時計測による 核分光がほとんどだったが、それでは残留原子核の準位が起状態の場合はさらに 核分光がほとんどだったが、それでは残留原子核の準位が起状態の場合はさらに 線を放出するため、崩壊様式の決定に曖昧さが残った。本研究では、 線を放出するため、崩壊様式の決定に曖昧さが残った。本研究では、 -n二重測定に加えて残留核の放出する -n二重測定に加えて残留核の放出する 線を測定する三重同時計測により、11Liと14Beの崩壊様式の確定に初めて成功した。 線を測定する三重同時計測により、11Liと14Beの崩壊様式の確定に初めて成功した。 14Beは半減期4.35±17msで娘核14Bへ 崩壊する。 崩壊する。 は16.22±0.11MeV、14Bの1中性子分離エネルギーはわずか970±21keVであり、上に述べた中性子超過剰核に特有な は16.22±0.11MeV、14Bの1中性子分離エネルギーはわずか970±21keVであり、上に述べた中性子超過剰核に特有な 崩壊といえる。これまでの研究から、遅発中性子がi個放出される分岐比Pinは、P0n=14±3%、P1n=81±4%、P2n=5±2%であることがわかっており、1中性子崩壊の分岐が大部分を占めていることを示している。最近我々が行なった研究で、エネルギー287keVのエネルギーに分岐比は40%〜100%の遅発中性子ピークが測定された。しかしこの測定では、低エネルギー中性子の測定の困難さから分岐比に大きな誤差が残り、また、 崩壊といえる。これまでの研究から、遅発中性子がi個放出される分岐比Pinは、P0n=14±3%、P1n=81±4%、P2n=5±2%であることがわかっており、1中性子崩壊の分岐が大部分を占めていることを示している。最近我々が行なった研究で、エネルギー287keVのエネルギーに分岐比は40%〜100%の遅発中性子ピークが測定された。しかしこの測定では、低エネルギー中性子の測定の困難さから分岐比に大きな誤差が残り、また、 線との同時計測を行なわなかったことから崩壊様式も決定されなかった。 線との同時計測を行なわなかったことから崩壊様式も決定されなかった。 一方、11Liは半減期8.5±0.2msで娘核11Beへ 崩壊する。 崩壊する。 は20.61±0.04MeV、11Beの中性子分離エネルギーSnは504±6keVである。これまでの研究で、i-中性子分岐比Pin(中性子がi個放出される分岐比)がそれぞれP0n=9.2±0.7%、P1n=85±1%、P2n=4.1±0.4%、P3n=1.9±0.2%でることが分かつており、14Beと同様、遅発1中性子放出の分岐が大部分となっている。さらに遅発 は20.61±0.04MeV、11Beの中性子分離エネルギーSnは504±6keVである。これまでの研究で、i-中性子分岐比Pin(中性子がi個放出される分岐比)がそれぞれP0n=9.2±0.7%、P1n=85±1%、P2n=4.1±0.4%、P3n=1.9±0.2%でることが分かつており、14Beと同様、遅発1中性子放出の分岐が大部分となっている。さらに遅発 線のスペクトルには1中性子放出の場合の娘核である10Beの 線のスペクトルには1中性子放出の場合の娘核である10Beの 線が測定されており、11Liの 線が測定されており、11Liの 崩壊様式が非常に複雑なものであることを伺わせる。この複雑さのために11Liの 崩壊様式が非常に複雑なものであることを伺わせる。この複雑さのために11Liの 崩壊様式については、その具体的内容が1中性子放出分岐についてさえほとんどわかっていなかった。 崩壊様式については、その具体的内容が1中性子放出分岐についてさえほとんどわかっていなかった。 以上を踏まえ、本研究では14Beと11Liの 崩壊の崩壊様式の決定すべく、新たに開発した低エネルギー中性子測定用の検出器と高検出効率の 崩壊の崩壊様式の決定すべく、新たに開発した低エネルギー中性子測定用の検出器と高検出効率の 線検出器と組合せた 線検出器と組合せた -n- -n- 三重同時計測を行なった。 三重同時計測を行なった。 実験は理化学研究所の加速器施設に敷設された不安定核ビームラインRIPSを利用して行なった。RIPSはリングサイクロトロンによって加速された重イオンビームの入射核破砕反応により生成された不安定核を2次ビームとしてとりだすことができ、そのビーム強度は世界の他の施設の10〜100倍を誇る。14Beおよび11Liの不安定核ビームは核子当たり100MeVの18OビームをBe標的に衝突させることにより生成され、それぞれ一秒あたり約3×102個、1×103個の強度で実験を行なった。 不安定核ビームはビーム光学系により最終焦点面に導き、減衰板で減速した後にSi検出器のストッパーに停止させる。静止後に放出される 線は、ストッパー上下に設置した 線は、ストッパー上下に設置した E- E- E-E型のプラスチックシンチレーターテレスコープで測定した。検出効率は4MeV以上の E-E型のプラスチックシンチレーターテレスコープで測定した。検出効率は4MeV以上の 線に対し40%であった。遅発 線に対し40%であった。遅発 線はClover型のGe検出器で測定し、その検出効率は1.3MeVの 線はClover型のGe検出器で測定し、その検出効率は1.3MeVの 線に対し0.3%であった。 線に対し0.3%であった。 遅発中性子はプラスチックシンチレータで構成される中性子検出器で検出し、そのエネルギーは 線と中性子検出の時間差から得られる飛行時間から求めた。広範囲のエネルギーにわたる中性子測定に対応するため、2種の異なる中性子検出器を用いている。第一の中性子検出器(高エネルギー中性子検出器と呼ぶ)は1MeV以上の中性子検出用で、6台のシンチレータからなる。1台の大きさは、高さ160cm、幅40cm、厚さ2cmで、中心で放出された中性子の飛行距離が検出位置によらないように曲率半径1.5mの球殻の一部をなすような形状を持つ。シンチレーション光は両端の光電子増倍管で読まれ、検出時間の平均から飛行時間が決定される。この検出器は飛行距離が十分長いため、よいエネルギー分解能が得られている(2MeVの中性子に対し、約50keVの分解能)。また、4 線と中性子検出の時間差から得られる飛行時間から求めた。広範囲のエネルギーにわたる中性子測定に対応するため、2種の異なる中性子検出器を用いている。第一の中性子検出器(高エネルギー中性子検出器と呼ぶ)は1MeV以上の中性子検出用で、6台のシンチレータからなる。1台の大きさは、高さ160cm、幅40cm、厚さ2cmで、中心で放出された中性子の飛行距離が検出位置によらないように曲率半径1.5mの球殻の一部をなすような形状を持つ。シンチレーション光は両端の光電子増倍管で読まれ、検出時間の平均から飛行時間が決定される。この検出器は飛行距離が十分長いため、よいエネルギー分解能が得られている(2MeVの中性子に対し、約50keVの分解能)。また、4 の約10%に達する立体角を持ち、1MeVから5MeVの中性子に対する検出効率は約20から30%程度となっている。一方の低エネルギー中性子検出器は30keVから1MeVの範囲の低エネルギー中性子の測定に用いられた。高さ30cm、幅4.5cm、厚さ2.5cmのプラスティックシンチレータの両端に光電子増倍管を接着したもの9台からなる。中性子のエネルギーが数100keVと低くなってくると光量不足のため検出効率が急激に低くなるため、低エネルギー中性子検出器では、短いシンチレータを用いることにより生成された光子が光電子増倍管に届く割合を上げることで光電子数を増やし、低エネルギーでも十分な検出効率を得られるよう工夫した。中性子のエネルギー閾値として約30keVを達成し、100keVの中性子に対し約40%、300keVの中性子に対し約80%の検出効率があった。 の約10%に達する立体角を持ち、1MeVから5MeVの中性子に対する検出効率は約20から30%程度となっている。一方の低エネルギー中性子検出器は30keVから1MeVの範囲の低エネルギー中性子の測定に用いられた。高さ30cm、幅4.5cm、厚さ2.5cmのプラスティックシンチレータの両端に光電子増倍管を接着したもの9台からなる。中性子のエネルギーが数100keVと低くなってくると光量不足のため検出効率が急激に低くなるため、低エネルギー中性子検出器では、短いシンチレータを用いることにより生成された光子が光電子増倍管に届く割合を上げることで光電子数を増やし、低エネルギーでも十分な検出効率を得られるよう工夫した。中性子のエネルギー閾値として約30keVを達成し、100keVの中性子に対し約40%、300keVの中性子に対し約80%の検出効率があった。 図1に低エネルギー中性子検出器で測定された14Beの飛行時間スペクトルを示す。この中に現われた強いピークが先の実験で測定されたピークに対応し、エネルギーが288±8keV、幅は49±2keVであった。この中性子ピークと 線との同時計測の解析から、中性子放出に続いて 線との同時計測の解析から、中性子放出に続いて 線が放出されないことが分かった。これに加えて13Bの第一励起状態からの 線が放出されないことが分かった。これに加えて13Bの第一励起状態からの 崩壊も測定され、以上をまとめると、14Beは図2に示すような崩壊様式を持つことが分かった。288keVの中性子崩壊を伴う 崩壊も測定され、以上をまとめると、14Beは図2に示すような崩壊様式を持つことが分かった。288keVの中性子崩壊を伴う 崩壊の崩壊先の14Bの励起準位の励起エネルギーは1.280±0.021MeVで、これまでに知られていないものであった。この分岐の分岐比は91±9%であり、対応するlog ft値は3.68±0.05と非常に小さくGamow-Teller遷移であることを示している。スピン・パリティは、従って、1+と決定した。 崩壊の崩壊先の14Bの励起準位の励起エネルギーは1.280±0.021MeVで、これまでに知られていないものであった。この分岐の分岐比は91±9%であり、対応するlog ft値は3.68±0.05と非常に小さくGamow-Teller遷移であることを示している。スピン・パリティは、従って、1+と決定した。  図1:低エネルギー中性子検出器によって測定された14Beの 図1:低エネルギー中性子検出器によって測定された14Beの 遅発中性子の飛行時間スペクトル。 遅発中性子の飛行時間スペクトル。 図2:288keVの中性子ピークに対応する14Beの崩壊過程。14Bの1.28MeVの励起準位は本研究で初めて同定された。各準位の右端に励起エネルギー(MeV)を示す。 図2:288keVの中性子ピークに対応する14Beの崩壊過程。14Bの1.28MeVの励起準位は本研究で初めて同定された。各準位の右端に励起エネルギー(MeV)を示す。 この14Bの準位が基底状態と異なるパリティをもついわゆる非正常状態(non-normal parity state)であることは興味深い。非正常状態は、基底状態に対して1h 異なる殻への励起に対応するため、大きいな殻間隔エネルギーを反映して高い励起状態に現われるのが普通である。1+状態は中性子の(P1/2)軌道から(S1/2)軌道への励起に対応しており、そのエネルギー差は近傍の15Cでは約3MeVであるのに対して、14Bにおいては励起エネルギー1.28MeVという小さい値であり、14BにおいてN=8の殻間隔エネルギーが小さくなっていることを示唆していると言える。また、13Bが中性子閉核で、中性子がsd殻へ励起していないとすると、14Bの1+状態からの中性子放出は強く抑制される。しかし、測定された中性子ピークの幅は独立粒子模型で求めた値の約19%もありこれもまた13BでのN=8の殻間隔エネルギーの減少を示唆するものであった。 異なる殻への励起に対応するため、大きいな殻間隔エネルギーを反映して高い励起状態に現われるのが普通である。1+状態は中性子の(P1/2)軌道から(S1/2)軌道への励起に対応しており、そのエネルギー差は近傍の15Cでは約3MeVであるのに対して、14Bにおいては励起エネルギー1.28MeVという小さい値であり、14BにおいてN=8の殻間隔エネルギーが小さくなっていることを示唆していると言える。また、13Bが中性子閉核で、中性子がsd殻へ励起していないとすると、14Bの1+状態からの中性子放出は強く抑制される。しかし、測定された中性子ピークの幅は独立粒子模型で求めた値の約19%もありこれもまた13BでのN=8の殻間隔エネルギーの減少を示唆するものであった。 次に、11Liの 崩壊の結果得られた中性子の飛行時間(TOF)スペクトルを図3に示す。主図は高エネルギー中性子検出器で測定された飛行時間スペクトル、インセットの図は低エネルギー中性子検出器で測定された同スペクトルである。一方、 崩壊の結果得られた中性子の飛行時間(TOF)スペクトルを図3に示す。主図は高エネルギー中性子検出器で測定された飛行時間スペクトル、インセットの図は低エネルギー中性子検出器で測定された同スペクトルである。一方、 線のエネルギースペクトル中には、娘核11Beの 線のエネルギースペクトル中には、娘核11Beの 線1つと遅発中性子放出後に10Beから放出された 線1つと遅発中性子放出後に10Beから放出された 線4本が測定された。中性子の飛行時間スペクトルと 線4本が測定された。中性子の飛行時間スペクトルと 線の各ピークとの同時計測関係解析から高エネルギー検出器によるスペクトル中に6種類のピークが、低エネルギー検出器によるものにはさらにもう1つのピークが同定され、11Liの1中性子放出に関する 線の各ピークとの同時計測関係解析から高エネルギー検出器によるスペクトル中に6種類のピークが、低エネルギー検出器によるものにはさらにもう1つのピークが同定され、11Liの1中性子放出に関する 崩壊様式を図4に示すように決定することができた。この中で、11Beの8.04(5)MeVの準位は今回の実験で初めて同定された準位である。この図からわかるように、11Liの 崩壊様式を図4に示すように決定することができた。この中で、11Beの8.04(5)MeVの準位は今回の実験で初めて同定された準位である。この図からわかるように、11Liの 崩壊様式は4分岐あり、それぞれの分岐比からlog ft値が決められる。遅発中性子放出を伴う3分岐のlog ft値は4.4から5.0にわたっており、これらすべての遷移がGamow-Teller遷移であることを示している。このことから、娘核のそれぞれの準位のスピン・パリティを図に示したように決定した。 崩壊様式は4分岐あり、それぞれの分岐比からlog ft値が決められる。遅発中性子放出を伴う3分岐のlog ft値は4.4から5.0にわたっており、これらすべての遷移がGamow-Teller遷移であることを示している。このことから、娘核のそれぞれの準位のスピン・パリティを図に示したように決定した。 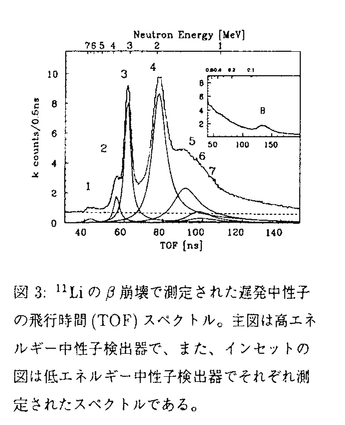 図3:11Liの 図3:11Liの 崩壊で測定された遅発中性子の飛行時間(TOF)スペクトル。主図は高エネルギー中性子検出器で、また、インセットの図は低エネルギー中性子検出器でそれぞれ測定されたスペクトルである。 崩壊で測定された遅発中性子の飛行時間(TOF)スペクトル。主図は高エネルギー中性子検出器で、また、インセットの図は低エネルギー中性子検出器でそれぞれ測定されたスペクトルである。 図4:三重同時計測により決定した11Liの崩壊様式。11Beの8.04MeVの励起準位は我々が新たに同定した準位。各準位の右端に励起エネルギー(MeV)を示す。 図4:三重同時計測により決定した11Liの崩壊様式。11Beの8.04MeVの励起準位は我々が新たに同定した準位。各準位の右端に励起エネルギー(MeV)を示す。 11Beの第一励起状態のスピン・パリティは1/2-であり、11Liからはガモフ・テラー遷移で結ばれるが、この遷移のlog ft値、5.64はGamow-Teller遷移としては非常に大きな、従って遷移強度としては弱いものであったが、これは親核11Liのハロー中性子の波動関数にp殻に加えてsd殻の成分が多く混合しているためであると考えられ、鈴木、大塚による殻模型計算によると、我々の実験値は、11Liの2個のハロー中性子の波動関数を、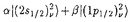 と表したときに、| と表したときに、| |2=55に対応する。s状態とp状態は異なるシェルに属するため、通常の殻模型では大きなシェルギャップを反映して |2=55に対応する。s状態とp状態は異なるシェルに属するため、通常の殻模型では大きなシェルギャップを反映して 〜100%、 〜100%、 〜0%となるが、| 〜0%となるが、| |2=51%と大きな値を取るということは、11Liにおいて、p殻とsd殻がほぼ縮退していること、すなわち殻構造が破れていることを示唆している。 |2=51%と大きな値を取るということは、11Liにおいて、p殻とsd殻がほぼ縮退していること、すなわち殻構造が破れていることを示唆している。 以上のように、中性子過剰領域の多くの原子核で、N=8の殻間エネルギーが安定線近傍核の場合と比較して減少していることが分かった。 |