| 導入  粒子は 粒子は 中間子と共にカイラル対称性の線形表現を成す粒子である。対称性の破れに伴ってクォークに構成子質量を与える役割をし、その重要性は色々な観点から強調されてきた。しかし 中間子と共にカイラル対称性の線形表現を成す粒子である。対称性の破れに伴ってクォークに構成子質量を与える役割をし、その重要性は色々な観点から強調されてきた。しかし の存在は1974年のCERN-MunichグループによるI=0、S波の の存在は1974年のCERN-MunichグループによるI=0、S波の  散乱位相差 散乱位相差 の精密測定によって一般には否定されてきた。それによると の精密測定によって一般には否定されてきた。それによると は は =1300MeVで270°にしかならない。巾の狭いf0(980)共鳴の180°の寄与を除くと90°しか残らず、質量500〜600MeVの =1300MeVで270°にしかならない。巾の狭いf0(980)共鳴の180°の寄与を除くと90°しか残らず、質量500〜600MeVの 粒子が存在する余地はない。 粒子が存在する余地はない。 一方、近年pp中心衝突過程(pp→pp 0 0 0)で 0)で の500〜600MeVの領域に巨大な事象の集中が観測された。これは単純にバックグラウンドとして解釈するには余りに大きく、実際1GeV以下の質量スペクトルは の500〜600MeVの領域に巨大な事象の集中が観測された。これは単純にバックグラウンドとして解釈するには余りに大きく、実際1GeV以下の質量スペクトルは とf0の2つのBreit-Wigner共鳴公式によって記述できることが示された。しかしこの結果はいわゆる「 とf0の2つのBreit-Wigner共鳴公式によって記述できることが示された。しかしこの結果はいわゆる「  散乱振幅のユニバーサリティ」の議論によって否定された。 散乱振幅のユニバーサリティ」の議論によって否定された。 共鳴は 共鳴は  散乱振幅で観測されないのだから 散乱振幅で観測されないのだから  生成振幅でも観測されるはずがないとするものである。 生成振幅でも観測されるはずがないとするものである。  粒子の現象論的観測 粒子の現象論的観測 近年筆者とその協力者は の再解析を行い、 の再解析を行い、 粒子存在の強い証拠を見出した。従来の解析と同じ 粒子存在の強い証拠を見出した。従来の解析と同じ を用いながら異なる結果を得た原因は、技術的には振幅干渉法(IA)と呼ばれる新しい解析法を用いた事にあり、物理的には負のバックグラウンド位相 を用いながら異なる結果を得た原因は、技術的には振幅干渉法(IA)と呼ばれる新しい解析法を用いた事にあり、物理的には負のバックグラウンド位相 BGを導入した事にある。IAはユニタリティを満足するS行列の記述法であり、散乱振幅 BGを導入した事にある。IAはユニタリティを満足するS行列の記述法であり、散乱振幅 がBreit-Wigner共鳴公式を通じて各粒子の質量と結合定数で直接記述されていることに特徴がある。 がBreit-Wigner共鳴公式を通じて各粒子の質量と結合定数で直接記述されていることに特徴がある。 BGは現象論的に斥力芯型, BGは現象論的に斥力芯型, BG(s)=-|P1|rc,にとる。解析の結果を図1(a)に示す。表1は我々の結果と従来の結果の本質的な点を比較したものである。我々の解析ではrc〜3GeV-1(0.60fm:ほぼ BG(s)=-|P1|rc,にとる。解析の結果を図1(a)に示す。表1は我々の結果と従来の結果の本質的な点を比較したものである。我々の解析ではrc〜3GeV-1(0.60fm:ほぼ 中間子の電磁半径と同じ大きさ)の半径を持つ 中間子の電磁半径と同じ大きさ)の半径を持つ BGの導入が BGの導入が (600)粒子の存在に決定的な役割を果たす。 (600)粒子の存在に決定的な役割を果たす。 (600)共鳴に由来する引力による大きな正の (600)共鳴に由来する引力による大きな正の  (600)と負の (600)と負の BG和が小さな正の BG和が小さな正の を与えるが、従来の解析ではこれが正のバックグラウンド位相 を与えるが、従来の解析ではこれが正のバックグラウンド位相 (あるいは非常に巾の広い (あるいは非常に巾の広い (900)粒子)として扱われてきた。我々の解析は、rc=0の場合" (900)粒子)として扱われてきた。我々の解析は、rc=0の場合" "に対応する粒子の質量と巾が "に対応する粒子の質量と巾が (900)のそれと近くなり、従来の解析と本質的に等価であることが分かる。この場合、図1(a)から分かるように500〜600MeVの領域のこぶの様な構造が再現できず、 (900)のそれと近くなり、従来の解析と本質的に等価であることが分かる。この場合、図1(a)から分かるように500〜600MeVの領域のこぶの様な構造が再現できず、 2の値163.4はrc≠0の場合のbest fitに比べて140も悪くなっている。この事実は 2の値163.4はrc≠0の場合のbest fitに比べて140も悪くなっている。この事実は の存在を強く示唆している。 の存在を強く示唆している。  図1:散乱、生成過程での 図1:散乱、生成過程での 粒子の現象論的観測。(a)I=0 粒子の現象論的観測。(a)I=0  散乱位相差,(b)pp中心衝突(GAMSNA12/2)での 散乱位相差,(b)pp中心衝突(GAMSNA12/2)での 0 0 0質量分布,(c)J/ 0質量分布,(c)J/ → →   崩壊(DM2)での 崩壊(DM2)での  質量分布 質量分布 表1: 表1:  位相差解析:rc≠0のフィットとrc=0のフィットの比較。後者は従来の解析に対応。 位相差解析:rc≠0のフィットとrc=0のフィットの比較。後者は従来の解析に対応。 GAMSグループによるpp中心衝突実験とDM2によるJ/ → →   崩壊実験での 崩壊実験での  質量分布の解析結果をそれぞれ図1(b)と(c)に示す。ここでは 質量分布の解析結果をそれぞれ図1(b)と(c)に示す。ここでは  生成振幅に先述の 生成振幅に先述の =500〜600MeVの巨大な事象の集中に対応する" =500〜600MeVの巨大な事象の集中に対応する" "とf0の、位相因子をもつBreit-Wigner振幅の和の形(VMW法)が用いられており、この形で、図示している質量分布のみならず特徴的な角分布まで説明する事ができる。 "とf0の、位相因子をもつBreit-Wigner振幅の和の形(VMW法)が用いられており、この形で、図示している質量分布のみならず特徴的な角分布まで説明する事ができる。 散乱振幅と生成振幅の関係 散乱振幅 と生成振輻 と生成振輻 を扱う場合、2つの一般的な問題を考慮せねばならない。 を扱う場合、2つの一般的な問題を考慮せねばならない。 はユニタリティ条件 はユニタリティ条件 を満たさねばならず、また を満たさねばならず、また は、始状態が強い相互作用に起因する位相を持たない場合には、 は、始状態が強い相互作用に起因する位相を持たない場合には、 と同じ位相を持たねばならない: と同じ位相を持たねばならない: (終状態相互作用定理(FSI))。従来 (終状態相互作用定理(FSI))。従来 にはより厳しい関係式として「 にはより厳しい関係式として「 のユニバーサリティ」、 のユニバーサリティ」、 (a(s)は変化の緩い実関数)、が要請されてきた。これまで (a(s)は変化の緩い実関数)、が要請されてきた。これまで 共鳴が 共鳴が で観測されなかったことから、本論文のVMWによる で観測されなかったことから、本論文のVMWによる に に 共鳴があるとする解析は強く批判された。この批判の中心的な根拠は上述の我々の 共鳴があるとする解析は強く批判された。この批判の中心的な根拠は上述の我々の の再解析の結果によって既に失われているが、VMWがFSIと無矛盾であるかどうかという一般的な問題は検討されねばならない。 の再解析の結果によって既に失われているが、VMWがFSIと無矛盾であるかどうかという一般的な問題は検討されねばならない。 まず第1にFSI定理が厳密に成り立つ場合について と と の関係を考察する。その為に簡単な場の理論的模型を用いる。 の関係を考察する。その為に簡単な場の理論的模型を用いる。 中間子と共鳴粒子である 中間子と共鳴粒子である (600)やf0(980)は等しくカラー1重項のq (600)やf0(980)は等しくカラー1重項のq 束縛状態であり、巾0の安定粒子として導入される。これらのいわば「クォーク力学的状態(bare状態:以下 束縛状態であり、巾0の安定粒子として導入される。これらのいわば「クォーク力学的状態(bare状態:以下 として記す)」,(と生成チャンネル"P")は構造を持っている為、強く相互作用をする: として記す)」,(と生成チャンネル"P")は構造を持っている為、強く相互作用をする: ,その結果bare状態は有限の巾を持つ物理的状態(| ,その結果bare状態は有限の巾を持つ物理的状態(| 〉=| 〉=| 〉,| 〉,| 〉,|f〉として記す)に変わる。以下ではまず共鳴状態が支配的な場合を考え、 〉,|f〉として記す)に変わる。以下ではまず共鳴状態が支配的な場合を考え、  のバックグラウンドの効果を無視する( のバックグラウンドの効果を無視する( )。強い相互作用としては )。強い相互作用としては  ループの繰り返しの効果のみを考える。 ループの繰り返しの効果のみを考える。 共鳴粒子を記述する状態には3つの型、bare状態 ,"K行列"状態 ,"K行列"状態 ,物理的状態| ,物理的状態| 〉、がある。最初に2つの状態 〉、がある。最初に2つの状態 のみが散乱に寄与する場合を考える。Tは のみが散乱に寄与する場合を考える。Tは と伝搬関数行列 と伝搬関数行列 を用いて を用いて  と表される。式(1)はユニタリティを満たすことが容易に示される。 を直交変換によって対角化することで"K行列"状態 を直交変換によって対角化することで"K行列"状態 が得られさらに が得られさらに を複素直交変換によって対角化することで物理的状態| を複素直交変換によって対角化することで物理的状態| 〉が得られる。これに対応して散乱振幅 〉が得られる。これに対応して散乱振幅 Resにも3つの表示がある。(bare状態表示の)式1は物理的状態表示を用いる事によって Resにも3つの表示がある。(bare状態表示の)式1は物理的状態表示を用いる事によって  と書き直される。ここで は物理的状態の質量自乗, は物理的状態の質量自乗, は実の結合因子である。これらは は実の結合因子である。これらは , , ,と ,と  状熊密度 状熊密度 ( ( )で書く事ができ、 )で書く事ができ、  しきい値領域以外では殆どsに依存せず、式(2)はIA法による散乱振幅そのものであることが分かる。 しきい値領域以外では殆どsに依存せず、式(2)はIA法による散乱振幅そのものであることが分かる。 FSI定理を満たす生成振幅 は、式(1)の最初の は、式(1)の最初の  結合定数 結合定数 生成結合定数 生成結合定数 に代える事によって得られる。この に代える事によって得られる。この は物理的状態表示で は物理的状態表示で  と書かれる は物理的状態表示による は物理的状態表示による  結合(生成結合)因子で一般に複素数)。 結合(生成結合)因子で一般に複素数)。 は は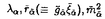 によって表すことができるので によって表すことができるので  しきい値領域以外では殆どsに依存せず、式(3)はVMWによる生成振幅そのものである事が分かる。しかしVMWでは散乱と無関係な、本質的に3つのパラメター、 しきい値領域以外では殆どsに依存せず、式(3)はVMWによる生成振幅そのものである事が分かる。しかしVMWでは散乱と無関係な、本質的に3つのパラメター、 と相対位相 と相対位相 、を含むが、これらは2つの生成結合定数、 、を含むが、これらは2つの生成結合定数、 と と (あるいは (あるいは と と )、によって表される為、 )、によって表される為、 について拘束がある。以上の議論は直接2 について拘束がある。以上の議論は直接2 を生成するバックグラウンドがある場合にも拡張する事ができ、その効果が共鳴の効果に比べ弱い場合には同様の結論を得る。一般に強い相互作用によるあらゆる過程は始状態に位相 を生成するバックグラウンドがある場合にも拡張する事ができ、その効果が共鳴の効果に比べ弱い場合には同様の結論を得る。一般に強い相互作用によるあらゆる過程は始状態に位相 を持ち、これを評価する手掛かりが殆どない現状では、対応する を持ち、これを評価する手掛かりが殆どない現状では、対応する をフリーとして扱わざるを得ない。本論文のpp中心衝突実験とJ/ をフリーとして扱わざるを得ない。本論文のpp中心衝突実験とJ/ 崩壊実験の解析はこの立場から成されたものである。 崩壊実験の解析はこの立場から成されたものである。 関連する諸問題 位相差解析で決定的な役割を果たした斥力芯型の BGは線形 BGは線形 模型の 模型の  4相互作用と強い関係を持つ。SU(2)線形 4相互作用と強い関係を持つ。SU(2)線形 模型では 模型では  散乱のA(s,t,u)振幅は 散乱のA(s,t,u)振幅は と書かれる。第1項と第2項は関係式 と書かれる。第1項と第2項は関係式 に従って強く相殺する。 に従って強く相殺する。  式(4)第1項の友沢-Weinberg振幅は南部ゴールドストーン粒子である 中間子の微分結合性に基づくもので低エネルギーでは小さい値を与える。この意味で 中間子の微分結合性に基づくもので低エネルギーでは小さい値を与える。この意味で  4相互作用はカイラル対称性に基づき 4相互作用はカイラル対称性に基づき の存在と共に要請される相補的な斥力相互作用であるとみなせる。式(4)は位相差解析での の存在と共に要請される相補的な斥力相互作用であるとみなせる。式(4)は位相差解析での と と BGの相殺に対応する。従来多くの解析で BGの相殺に対応する。従来多くの解析で の存在が否定されたのはこの機構の見落としに原因がある。 の存在が否定されたのはこの機構の見落としに原因がある。 I=1/2K 散乱位相差を 散乱位相差を  系と同様の方法を用いて解析する事で 系と同様の方法を用いて解析する事で (900)の存在が示唆される。 (900)の存在が示唆される。 (600)と (600)と (900)、及び既に観測されている (900)、及び既に観測されている 0(980)とf0(980)は、SU(3)線形 0(980)とf0(980)は、SU(3)線形 模型に現れる 模型に現れる 九重項とほぼ無矛盾な性質を持つ。ベクトル、擬ベクトル九重項を含む模型でも同様の結果が得られる。このことはカイラル対称性が、非線形表現から導かれる低エネルギー定理としてのみならず、線形表現を通じて〜1GeV以下の全ての中間子の質量スペクトルと反応を記述する際、大きな役割を果たす事を示している。 九重項とほぼ無矛盾な性質を持つ。ベクトル、擬ベクトル九重項を含む模型でも同様の結果が得られる。このことはカイラル対称性が、非線形表現から導かれる低エネルギー定理としてのみならず、線形表現を通じて〜1GeV以下の全ての中間子の質量スペクトルと反応を記述する際、大きな役割を果たす事を示している。 |