時間反転対称性の破れの探索は二つの点で極めて重要である。一つには、時間反転対称性は基本対称性の一つであり、これの妥当性の検証は現代物理の発展の上で欠かせないものである。もう一点として、CPT対称性を前提とすれば、CP対称性の破れが中性K中間子の崩壊において観測されている以上、時間反転対称性の破れの探索は、CP対称性の起源の問題と密接に絡み付いているという点である。このCP対称性の起源については、現在までの所、クォーク世代間の混合における小林益川行列の位相により説明するという標準理論の枠内で議論され、実験もその位相の測定を対象として進められてきた。中性K中間子での ’/ ’/ の測定や、まもなく始まるBファクトリーでの実験はこれに含まれる。しかしながら、宇宙のバリオン数の非対称度は標準理論のCP対称性の破れのみでは説明出来ないため、標準理論以外のCP非保存の機構の探索は現在極めて重要な問題となっている。 の測定や、まもなく始まるBファクトリーでの実験はこれに含まれる。しかしながら、宇宙のバリオン数の非対称度は標準理論のCP対称性の破れのみでは説明出来ないため、標準理論以外のCP非保存の機構の探索は現在極めて重要な問題となっている。 このような動機から、時間反転対称性の破れの探索が、例えば、中性子の電気双極子能率の測定等を通じてなされてきたが、未だ決定的な証拠を見つけ出すには至っていない。この様な試みの一つとしてK+→ 0 0 + + ( ( )崩壊における崩壊平面に対して横方向のミュオンの偏極 )崩壊における崩壊平面に対して横方向のミュオンの偏極  の測定があげられる。ここで はそれぞれ はそれぞれ +の偏極, +の偏極, 0及び 0及び +の運動量である。この量に対して、現在までに +の運動量である。この量に対して、現在までに  という実験からの制限が得られている。ここでIm( )は )は 崩壊の二つの形状因子f+,f-の比の虚数部分( 崩壊の二つの形状因子f+,f-の比の虚数部分( ≡f-/f+)であり、PTの測定において物理の内容に直接関わる量である。本論文の主題であるKEK PS E246はPTを10-3の精度で測定する事を目標にした実験である。私はこの実験に学部四年以来参加し、測定器の開発,実験全体の運営、実験データの解析など実験全体に関与してきた。特にミュオンの運動量測定に用いられるカソード読み出しのMWPCについては、設計、開発、試験、及び実際の実験での運用の全てを担当してきた。 ≡f-/f+)であり、PTの測定において物理の内容に直接関わる量である。本論文の主題であるKEK PS E246はPTを10-3の精度で測定する事を目標にした実験である。私はこの実験に学部四年以来参加し、測定器の開発,実験全体の運営、実験データの解析など実験全体に関与してきた。特にミュオンの運動量測定に用いられるカソード読み出しのMWPCについては、設計、開発、試験、及び実際の実験での運用の全てを担当してきた。 このMWPCの解析については従来この方式のMWPCに使われてきた方法に比べ、三つ新しい点がある。一つはADCのpedestal情報を用いたアンプのゲイン補正である。これにより従来に比べ、格段に効率良く、しかも実験装置に据え付けられた状態のままでアンプのゲインを補正することが可能になった。二つ目は新しいカソード上の電荷分布の式の導入である。従来用いられてきた電荷分布の式はアノードカソード間の距離をパラメーターとして調整してやる必要があった。これに対し、私の提案した式ではパラメーターの調整が不要になり、実際の設計値のみで電荷の分布を説明することができるようになった。最後は大角度入射への対応である。我々の実験で予想される最大40度の入射角での粒子の位置測定を可能にするための大角度入射の粒子に対する電荷分布の補正を試み、大角度の入射粒子に対し従来の方法に比べて2倍程度の位置分解能の改善を達成することができた。 本実験は1996年4月から本格的なデータ収集を開始し、現在までに配分された実験期間の約1/3に当たるデータの収集が終了している。本論文は現時点までに収集されたデータを元に解析を行いその結果をまとめたものである。 K+→ 0 0 + + 崩壊におけるPTの主な特徴として二点挙げられる。まず、標準理論からのPTに対する寄与が10-6程度と無視できる程度しか無いという点は強調すべきであろう。もし我々の測定でPTに対して有限な値を検出できたなら、それは直ちに標準理論を超える物理からの寄与であると結論できるのである。通常のCP非保存の探索実験においては、標準理論の寄与が無視できない為、標準理論の枠組みを超える様なCP非保存の機構に対しての感度が鈍る傾向にある。これに対して、PTの測定は初めから標準理論を超える物理にのみ照準を絞っている為、他のCP非保存の実験では代替出来ないユニークな探索手段になっているのである。二番目の特徴としては、K+→ 崩壊におけるPTの主な特徴として二点挙げられる。まず、標準理論からのPTに対する寄与が10-6程度と無視できる程度しか無いという点は強調すべきであろう。もし我々の測定でPTに対して有限な値を検出できたなら、それは直ちに標準理論を超える物理からの寄与であると結論できるのである。通常のCP非保存の探索実験においては、標準理論の寄与が無視できない為、標準理論の枠組みを超える様なCP非保存の機構に対しての感度が鈍る傾向にある。これに対して、PTの測定は初めから標準理論を超える物理にのみ照準を絞っている為、他のCP非保存の実験では代替出来ないユニークな探索手段になっているのである。二番目の特徴としては、K+→ 0 0 + + においては終状態において荷電粒子が一つしかないため、電磁相互作用による終状態の擾乱に起因する偽のPTの寄与が無視出来る程小さいという事が挙げられる。仮にKL→ においては終状態において荷電粒子が一つしかないため、電磁相互作用による終状態の擾乱に起因する偽のPTの寄与が無視出来る程小さいという事が挙げられる。仮にKL→ - - + + 崩壊を使った場合、この終状態の擾乱の寄与が10-3程度と測定精度と同程度にまでなってしまい、実験の精度を下げてしまうのでる。以上の様な特徴により、標準理論以外の物理のみに敏感で、物理的なバックグラウンドの少ない測定が可能になるのである。 崩壊を使った場合、この終状態の擾乱の寄与が10-3程度と測定精度と同程度にまでなってしまい、実験の精度を下げてしまうのでる。以上の様な特徴により、標準理論以外の物理のみに敏感で、物理的なバックグラウンドの少ない測定が可能になるのである。 この実験は高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究所の陽子シンクロトロンを用いて、生成されたK+粒子を測定器近辺に静止させて測定を行うという手法を採用している。実験装置を図1に示す。後ろからの図に示されている様に実験装置はビームに対して軸対称に配列されており、これにより系統誤差を打ち消す事が可能である。また、静止K+を使っでPTを測定するのは世界で初めての試みであり、これにより、系統誤差をさらに大幅に減らす事が可能になっている。  Figure1:実験装置の概略図(詳しい内容については本論文参照) Figure1:実験装置の概略図(詳しい内容については本論文参照) この実験の解析において特に重要な点として二点挙げることが出来る。一つは、この実験では系統誤差を減らすために、軸対称に配置された12組のミュオン偏極計を用いるが、これらの特性、つまり実際の実験環境における各々の応答を理解すること、二つ目としては、実験の系統誤差を正確に見積もる事、以上の二点である。 まず、一番目の重要項目であるミュオン偏極計の応答の理解については、二つの側面から確認した。一つとしては無偏極のデータに対して、偏極が零という事を確認するという方法である。これについては 0の方向を特定しない 0の方向を特定しない のデータを用いて統計誤差の範囲内で零であるということが確認された。二つめとして、12個の偏極計それぞれの無偏極のデータに対する非対称度の分布、及び、PTの分布を実験データ、及び、実験セットアップについての情報から説明することである。これについては、K+の分布、及び、偏極計の位置のばらつきにより説明することに成功した。図2にその典型的な例を示す。これは12個の偏極計それぞれに対するPTの分布を示したもので、黒丸が、実際のデータのPTの分布、白丸がK+の分布等、位置のばらつきから予想される各々の偏極計に対するオフセットであり、互いに極めて良く一致している事がわかる。この様に12組の偏極計の応答は空間的なばらつきから説明出来る事が確かめられた。この様なばらつきの系統誤差への寄与は我々の実験方法では打ち消す事が可能であるため、最終的な結果に影響は与えない。 のデータを用いて統計誤差の範囲内で零であるということが確認された。二つめとして、12個の偏極計それぞれの無偏極のデータに対する非対称度の分布、及び、PTの分布を実験データ、及び、実験セットアップについての情報から説明することである。これについては、K+の分布、及び、偏極計の位置のばらつきにより説明することに成功した。図2にその典型的な例を示す。これは12個の偏極計それぞれに対するPTの分布を示したもので、黒丸が、実際のデータのPTの分布、白丸がK+の分布等、位置のばらつきから予想される各々の偏極計に対するオフセットであり、互いに極めて良く一致している事がわかる。この様に12組の偏極計の応答は空間的なばらつきから説明出来る事が確かめられた。この様なばらつきの系統誤差への寄与は我々の実験方法では打ち消す事が可能であるため、最終的な結果に影響は与えない。 二番目の重要項目である系統誤差の見積もりについて簡単にまとめたい。系統誤差の要因としては大きく分けて三つのものが挙げられる。一つは偏極計の位置、及び、偏極計内の磁場分布に起因する系統誤差で、これらについては、実際に測定された位置、及び磁場分布のばらつきをモンテカルロシミュレーションの結果と組み合わせて評価した。次に偏極計以外の検出器に起因する系統誤差が挙げられる。これらは最終的な解析に使われるデータの分布に影響を与える為、 の崩壊平面の偏極計に対する回転の度合いを実際のデータを用いて測定することによって見積もられる。ビームから来るバックグラウンドの影響についても、この方法を用いて見積もられた。最後の一つは上の二つのどれにも属さないものである。例えば、我々の実験では偏極計の外部の影響を抑制するためにveto counterを設置しているが、これの性能のばらつきも系統誤差に影響する。これについては、veto counterを使用した時としない時でのPTの値の変化自身から評価した。K+のdecay-in-flight、及びミュオンのスペクトロメーター等での散乱の影響は同様にして見積もられた。以上のようにして系統誤差の評価を行った結果、この実験においては統計誤差からの寄与が実験誤差の大半を占めている事がわかった。 の崩壊平面の偏極計に対する回転の度合いを実際のデータを用いて測定することによって見積もられる。ビームから来るバックグラウンドの影響についても、この方法を用いて見積もられた。最後の一つは上の二つのどれにも属さないものである。例えば、我々の実験では偏極計の外部の影響を抑制するためにveto counterを設置しているが、これの性能のばらつきも系統誤差に影響する。これについては、veto counterを使用した時としない時でのPTの値の変化自身から評価した。K+のdecay-in-flight、及びミュオンのスペクトロメーター等での散乱の影響は同様にして見積もられた。以上のようにして系統誤差の評価を行った結果、この実験においては統計誤差からの寄与が実験誤差の大半を占めている事がわかった。  Figure2:各偏極計でのPTの分布。黒丸は実際のデータからのPT、白丸はK+の分布などから予想されるオフセットに各々対応する。 Figure2:各偏極計でのPTの分布。黒丸は実際のデータからのPT、白丸はK+の分布などから予想されるオフセットに各々対応する。 上記の様な解析の結果、現時点で、 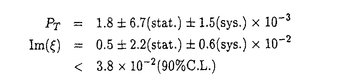 の値を得ることができた。これによりIm( )に対して過去の実験に比べ約20%程度厳しい制限を与えることに成功した。実験終了の時点では、統計として現在の3倍程度に増えると思われるので、最終的には前回の実験の2倍程度の精度の改善が期待できる。 )に対して過去の実験に比べ約20%程度厳しい制限を与えることに成功した。実験終了の時点では、統計として現在の3倍程度に増えると思われるので、最終的には前回の実験の2倍程度の精度の改善が期待できる。 |