流れの数値解析手法として、一般的には現象式を時間空間で離散化して解く差分法などが用いられるが、物理現象を表現する巨視的な支配方程式が明確に記述できることを必要とするため、複雑流れの模擬では適用範囲が限定されている。一方で近年、流体の連続体近似によらない手法が生まれている。格子ガスオートマトン(Lattice Gas Automata;LGA)はその一つで、微視的な疑似粒子を時間空間で離散化された場に用い、衝突・並進ルールを適用して時間発展を計算し、それを巨視的に観察することでマクロな振る舞いを捉える手法である。この手法は現象式を明示する必要がなく簡単なオートマトンルールのみで現象が記述されるため、複雑流れへの適用が比較的容易であると考えられる。従来の数値計算手法では一般性のあるシミュレーションに適しない複雑流れの代表として、相界面や相間に働く相互作用のモデル化が困難である二相流があげられる。LGAでも二相への適用について研究が行われているが、相分離シミュレーションが中心で流動現象を対象とした研究はあまり行われていない。これまでにさまざまな拡張で成果を挙げているImmiscible Lattice Gas(ILG)モデルは二相流の模擬にも有効であると考えられるが、密度の同じ二相しか扱えないという制限がある。しかし、気液二相流などの大きな密度差を持つ二相流では密度差に起因するダイナミクスを持っている可能性があり、ILGモデルをそのまま適用することは問題があると考えられる。そこで本論文では密度の大きく異なる二相の流動現象を扱うことのできるLGAモデルを開発し、それにより二相流動現象を解明することを目的とした。 まずはじめに、これまでに提案された相分離モデルのILGモデル、Liquid Lattice Gas(LLG)モデルについて説明し、流動現象への適用を試みて可能性と問題点を探る。 ILGモデルは1988年にD.H.Rothman等によって提案された二種類の色付き粒子を用いて異なる相を表現する相分離モデルである。ILGモデルでは二次元LGA基本モデルであるFHPモデルの衝突則に局所的なカラー場を導入して赤粒子は赤粒子の多い方向に青粒子は青粒子の多い方向にそれぞれ行きやすいというルールを加え、相界面に働く表面張力を表現している。このモデルを拡張して二相流への適用を試みた。適用例として粘性の異なる二流体を扱えるように拡張して平行平板間流動シミュレーションを行ったところ、図1の結果が得られた。これはLubricated pipeliningと呼ばれる現象で、密度に差のない場合粘性の低い相は速度勾配の大きいところに集まるという性質を表している。このようにILGモデルは密度にほとんど差のない非混和二流体の流動解析には有効であるが、モデルの性質上異なる密度を持つ二相を扱うモデルとしては適していないことがわかった。 LLGモデルは1990年にC.Appert等によって提案された、離れた距離の粒子間に働く力を導入して生じる粒子分布に密度差で二相を表現するモデルである。非局所粒子間相互作用過程を導入することで粒子の凝集を起こし、その結果できる密度の高い相と低い相を二相とする。このモデルについても相分離シミュレーション及び流れシミュレーションへの適用を試みた。その結果、LLGモデルは密度の大きく異なる二相を表現することができることは確認できたが、流れが入ると二相の界面や密度の低い部分は不安定になり、流動現象にそのまま適用することは難しいことがわかった。 このようにこれまでに提案された相分離モデルを気液二相流などの密度差に起因するようなダイナミクスを持つ二相流に適用することは難しい。そこで、本論文では密度差のある二相流を表現できるようなLGAモデルを提案する。このモデルでは単位質量と単位速度を持つ二種類の色付き粒子を用いる。FHPモデルでは衝突過程と並進過程の繰り返しで時間発展が行われているが、今回開発したモデルでは密度差を表現するために離れた格子点の粒子間に働く非局所粒子間相互作用過程を、相界面を安定に表現するために局所的カラー場を用い、それに従って各々の色の粒子を配置する粒子再配置過程を新たに導入した。 非局所粒子間相互作用過程では、相互作用距離をあらかじめ設定しておき、それで決められた格子点ペアでの粒子の状態が、相互作用条件に合致するときに両格子点の粒子の状態はルールに従って変更される。図2は粒子間相互作用の一例である。ここで距離5離れた両端の格子点で実線方向の運動量を持つ粒子が共に存在し破線方向の運動量を持つ粒子が共に存在しないときに、粒子の運動量を実線方向から破線方向に変える。相互作用条件としてはこれに加えて格子点に存在する各色の粒子数を用いる。ここでは青粒子が密度の低い相を赤粒子が密度の高い相を表すことを考えて引力と斥力が働く条件が設定されている。この過程により色付き粒子で表される二相の粒子密度に差を生じさせることが可能となる。 粒子再配置過程では局所的カラー場と先に求めた粒子の持つ運動量に従って計数されている数だけ各々の色の粒子を配置することが行われる。このときに用いられる局所的カラー場は隣接する6格子点の二色の粒子の状態から決定され、格子点近傍で最も赤粒子の存在確率が高い方向を表している。従ってこのベクトルとなす角が最も小さい運動量を持つ粒子から順に赤粒子が割り振られる。この過程により各色の粒子がどの運動量を持つか決定される。 こうして提案したモデルを用いて実際に適用性を確かめた。まず、体系480x480格子で周囲は全て周期境界条件、初期配置粒子密度を赤粒子密度0.4、青粒子密度0.1として一様に配置して相分離シミュレーションを行った結果をそれぞれ図3、図4に示す。図3で示す密度分布では色の濃い部分ほど密度が高く、図4の色分布では赤粒子の占める部分は赤く青粒子の占める部分は青く表示されている。これらから時間発展に従って赤相と青相の二相に分離し、赤相と密度の高い部分、青相と密度の低い部分がよく一致していることがわかる。ここで、初期配置密度や相互作用の作用条件などのパラメータを変更することで各相の性質や密度を柔軟に変えられることも確認した。また、表面張力と界面の測定ではLLGモデルに較べ薄い界面が実現できていることを示した。 次に泡の成長率について測定を行いその変化を調べた。泡径の測定では泡は全て円形であるという仮定をして各泡の径を求め、それぞれの径の平均値をそのタイムステップでの代表径とした。時間と泡の径の関係を図5に示す。この結果から気泡径がある程度の大きさになる前後で泡の成長率が変化することが分かる。この結果は他のLGA二相分離モデルや格子ボルツマン法、分子動力学法等で得られている結果とよく一致している。泡の成長率が途中で変わるのは径が小さいときには主に泡の成長はブラウン運動に支配されているのに対して径が大きくなると主に慣性力に支配されるためである。ここでの結果は提案したモデルがこのような二つの異なるスケールを持つダイナミクスを自然に内包していることを示している。 このように、提案したモデルは流れのない系では密度差のある二相を表現できることが示せた。そこで、次に流動現象への適用を考え浮力を導入したシミュレーションを行った。体系は320x960格子、周囲は全て周期境界として、初期配置で二種類の粒子を一様に配置し、密度の低い青相に浮力をかけて計算を行った。このときの計算結果を図6に示す。この結果では泡が合体・成長しながら上昇していく様子が観察できる。また、流動現象でも密度分布と色分布が一致し界面が安定していることがわかる。この結果から流動現象に対しても密度の異なる二相流動をうまく表現できる可能性を示せた。また、泡径の大きさと上昇速度の関係を調べた結果泡径が大きくなるにつれて上昇速度も上がるが、径が大きくなっていくと泡が上下方向につぶれるという変形を起こし、その結果抵抗が大きくなって上昇速度の伸びが鈍ることが確認できた。これは実際の物理現象と同じような結果である。 最後に壁境界条件を検討し、平行平板間流れのシミュレーションを試みた。壁境界付近の格子点では、そのままでは非局所相互作用ができないので壁近傍での粒子分布をもとに壁内部にも粒子分布をとり、それとの相互作用を起こすようにした。このような壁境界条件を用いて平行平板間流れのシミュレーションを行った。体系を160x800格子、左右をここで設定した壁境界条件、上下を周期境界条件として初期配置で二種類の粒子を一様に分布させ計算を行った。その結果図7に示すように密度の小さい泡が中央部によりつつ合体・成長してスラグ流のような流れを形成する様子が観察できた。また、このときの泡の成長率を測定したところ図8のようになった。これから流れを伴う系では泡系がごく小さい段階から慣性力が泡の成長に対して支配的であることがわかる。また、流速やボイド率などを変化させると気泡流のような流れから環状流のような流れまで気液二相流でみられるようなフローパターンが観察できた。このようなパターンはILGモデルを用いた場合にはみられないことから、ここで提案したモデルが密度差に起因するダイナミクスを表現できていると考えられる。 これらのシミュレーション結果より本論文で提案したモデルは密度差に起因する流体のダイナミクスを表現でき、密度の異なる二相の流動現象を表現できることを示した。  図1 異なる粘性を持つ二流体シミュレーション 図1 異なる粘性を持つ二流体シミュレーション 図2 粒子間相互作用の例 図2 粒子間相互作用の例 図3 相分離シミュレーション(密度分布) 図3 相分離シミュレーション(密度分布) 図4 相分離シミュレーション(色分布) 図4 相分離シミュレーション(色分布)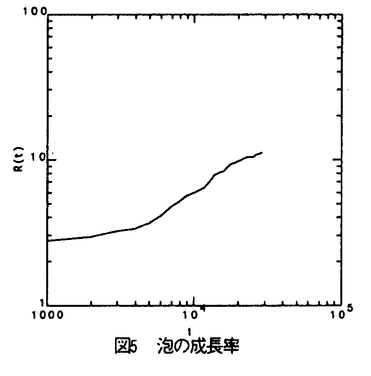 図5 泡の成長率 図5 泡の成長率 図6 浮力による泡の上昇シミュレーション 図6 浮力による泡の上昇シミュレーション 図7 平行平板間流れの時間発展 図7 平行平板間流れの時間発展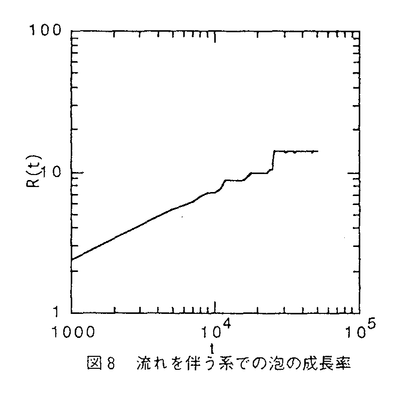 図8 流れを伴う系での泡の成長率 図8 流れを伴う系での泡の成長率 |