学位論文要旨
| No | 113698 | |
| 著者(漢字) | 古武,弥一郎 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | コタケ,ヤイチロウ | |
| 標題(和) | パーキンソン病関連新規内在性脳内アミン1BnTIQに関する神経化学的研究 | |
| 標題(洋) | ||
| 報告番号 | 113698 | |
| 報告番号 | 甲13698 | |
| 学位授与日 | 1998.03.30 | |
| 学位種別 | 課程博士 | |
| 学位種類 | 博士(薬学) | |
| 学位記番号 | 博薬第817号 | |
| 研究科 | 薬学系研究科 | |
| 専攻 | ||
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | パーキンソニズムを引き起こす外因性物質1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine(MPTP)が発見されて以来、パーキンソン病をはじめとする種々の神経変性疾患において、MPTP類似の内在性低分子化合物が注目されてきた。その中でも特にtetrahydroisoquinoline(TIQ)類はこれまでの当教室の研究から、生体内で様々な生理活性を示すことが知られ、脳内のTIQ量と1-methyl-TIQ(1MeTIQ)量のバランスが、パーキンソン病発症と関連していることなどから、TIQ、1MeTIQはそれぞれパーキンソン病発症物質候補、防御物質候補と考えられている(Fig.1)。そこで私は、新規内在性脳内アミンとして1-benzyl-TIQ(1BnTIQ)(Fig.1)を分子設計し、標品を合成した。1BnTIQは、フェネチルアミンが自身の代謝物であるフェニルアセトアルデヒドと環化縮合して生成することが予想され、有力な内在性パーキンソン病発症物質候補の一つであると考えられる。そこで、1BnTIQのパーキンソン病態に於ける量的変動に着目し、パーキンソン病と1BnTIQの関係を明らかにする目的で以下の研究を行った。  C57BLマウス脳内及びヒト脳脊髄液から塩基性画分を抽出し、ヘプタフルオロ酪酸無水物で誘導化して、陰イオン化学イオン化法によるGC-SIM法で1BnTIQの検出を試みたところ、3本のフラグメントピーク比並びに保持時間が標品と一致し、1BnTIQが検出された。また、ヒト脳脊髄液のサンプルに関しては、高分解能GC-SIM法によっても1BnTIQの存在が確認された。次に、ヒト脳脊髄液中1BnTIQの定量を陽イオン電子衝撃法にて行い、パーキンソン病患者と他の神経疾患の患者で比較した結果、パーキンソン病患者の1BnTIQ量は1.17±0.35ng/ml(mean±SEM,n=18)、他の神経疾患の患者の1BnTIQ量は0.40±0.10ng/ml(mean±SEM,n=11)であり、前者の平均は後者の平均に比べて約3倍と高い傾向にあった(Fig.2)。自然発症のパーキンソン病は多因子性の疾患であるといわれており、その一因が1BnTIQである可能性が考えられる。  パーキンソン病治療薬として用いられているMAO-B阻害剤デプレニルの、脳内1BnTIQ量に対する影響を調べるため、まず、フェネチルアミンを基質とした1BnTIQのin vitro生合成におけるデプレニルの効果について調べた。C57BLマウスより調製したプレインホモジネートを酵素源としてフェネチルアミンと共にインキュベーションし、1BnTIQの生成を調べたところ、デプレニルにより阻害された。次に、in vivoでもデプレニルにより1BnTIQが減少している可能性を調べるため、C57BLマウスにデプレニル5mg/kgを1日2回計4回連投し、最終投与2時間後の脳内1BnTIQ量を定量した。その結果、1BnTIQは有意に減少しており、1BnTIQの1MeTIQに対する量比も顕著な減少がみられた(Fig.3)。これらの結果より、デプレニルによるパーキンソン病治療効果に、脳内の1BnTIQ/1MeTIQ存在比の減少が関与する可能性が示唆された。 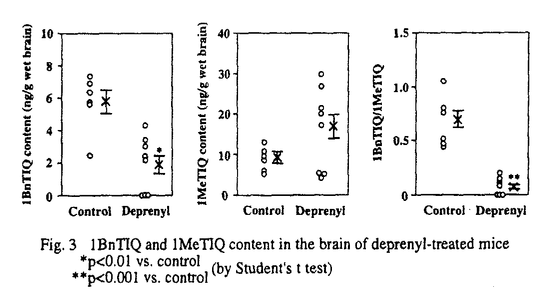 1BnTIQがMPTPと同じ作用機構により神経毒性を発現している可能性を探るため、MPTPの作用点と考えられているミトコンドリア呼吸鎖阻害について検討を加えた。その結果、凍結融解したミトコンドリア膜を使用したときにIC50値が52.6 培養細胞を用いて1BnTIQの神経毒性を検討しようと考え、in vivoにより近い培養系と考えられる中脳線条体切片共培養系を用いた。Wistar系ラットの胎生16日齢から得られた中脳腹側部と、生後1日齢から得られた線条体を多孔質膜上にて約500 培養約10日目から培養液中に1BnTIQを添加し、一定時間後の培養切片中のドーパミンを定量した。100  中脳線条体共培養系、線条体単独、大脳新皮質、海馬、小脳をそれぞれ同様に多孔質膜上にて培養し、300 100 培養切片の一部を固定し、20 1BnTIQはまずドーパミン量を低下させ、細胞体の萎縮を経てドーパミン神経を細胞死に至らしめる可能性が示唆された。また、1BnTIQが濃度依存的かつ時間依存的にドーパミン量を減少させることから、低い濃度の1BnTIQが長期間で、ドーパミン量低下、細胞体萎縮、細胞死という過程を経て毒性を発現する可能性が示唆された。これは老人性疾患であるパーキンソン病態を考える上で興味深いと思われる。 最後に、パーキンソン病患者の脳脊髄液で増加傾向にあり、中脳ドーパミン神経系に選択毒性を有する1BnTIQの神経毒性を調べるため、C57BLマウスを用いてパーキンソン病の症状に特徴的な運動緩徐の指標となるポールテストを行った。ポールテストはマウスを棒の最上部に上向きに掴まらせ、マウスが動き始めてから、回転して下に向くまでの時間をTturn、下に降りるまでの時間をTLAとし、時間が多くかかるほど運動緩徐が強く発現しているとする行動薬理試験である。1BnTIQ 80mg/kgを1日2回計5日間連投した群ではTturn、TLAが有意に延長され、1BnTIQが、パーキンソン病に特徴的な症状のひとつである運動緩徐を誘発し、パーキンソン病治療薬であるL-DOPAの作用により回復することが示された(Fig.5)。また、1MeTIQの前投与は、1BnTIQの神経毒性を抑制することがわかり、これは1MeTIQのパーキンソニズム防御機構を考える上で興味深い知見であると思われる。  1BnTIQはヒト脳脊髄液中に存在し、パーキンソン病態に於いて増加する傾向を持つ化合物であることが示された。また、パーキンソニズム発症作用を有し、中脳ドーパミン神経に選択毒性を持つことから、パーキンソン病と深い関連があり、パーキンソン病発症物質群のひとつであることが示唆される。 | |
| 審査要旨 | パーキンソニズムを引き起こす外因性化合物1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine(MPTP)が発見されて以来、パーキンソン病をはじめとする種々の神経変性疾患において、MPTP類似の内在性低分子化合物が注目されてきた。その中でも特にtetrahydroisoquinoline(TIQ)類はこれまでの当教室の研究から、生体内で様々な生理活性を示すことが知られている。本研究では、新規内在性脳内アミンとして1-benzyl-TIQ(1BnTIQ)を分子設計し、まず標品を合成している。1BnTIQは、フェネチルアミンが自身の代謝物であるフェニルアセトアルデヒドと環化縮合して生成することが予想され、有力な内在性パーキンソン病発症物質候補の一つであると考えられる。そこで、1BnTIQのパーキンソン病態に於ける量的変動に着目し、パーキンソン病と1BnTIQの関係を以下のように明らかにした。 C57BLマウス脳内及びヒト脳脊髄液からGC-SIM法で1BnTIQの検出を試みたところ、3本のフラグメントピーク比並びに保持時間が標品と一致し、1BnTIQが検出された。次に、ヒト脳脊髄液中1BnTIQの定量を行い、パーキンソン病患者と他の神経疾患の患者で比較した結果、パーキンソン病患者の1BnTIQ量が他の神経疾患の患者のそれと比較して約3倍高い傾向にあることを示した。 パーキンソン病治療薬として用いられているMAO-B阻害剤デプレニルの脳内1BnTIQ量に対する影響を調べたところ、デプレニルにより1BnTIQが有意に減少し、デプレニルによるパーキンソン病治療効果に脳内1BnTIQの減少が関与する可能性が示唆された。 MPTPの作用点と考えられているミトコンドリア呼吸鎖阻害について検討を加えたところ、1BnTIQは低濃度でComplex Iを阻害した。 In vivoにより近い培養系と考えられる中脳線条体切片共培養系を用いて、1BnTIQの神経毒性を検討した。その結果、1BnTIQは中脳、線条体のそれぞれの部位において、濃度依存的かつ時間依存的にドーパミン量を減少させた。100 1BnTIQはまずドーパミン量を低下させ、細胞体の萎縮を経てドーパミン神経を細胞死に至らしめる可能性が示唆された。また、1BnTIQが濃度依存的かつ時間依存的にドーパミン量を減少させることから、低い濃度の1BnTIQが長期間で、ドーパミン量低下、細胞体萎縮、細胞死という過程を経て毒性を発現する可能性が示唆された。これは老人性疾患であるパーキンソン病態を考える上で興味深いと思われる。 最後に1BnTIQのin vivoにおける生理活性を調べるため、C57BLマウスを用いてパーキンソン病の症状に特徴的な運動緩徐の指標となるポールテストを行った。1BnTIQ 80mg/kgを1日2回計5日間連投した群では、パーキンソン病に特徴的な症状のひとつである運動緩徐を誘発し、パーキンソン病治療薬であるL-DOPAの作用により回復することが示された。 以上より1BnTIQはヒト脳脊髄液中に存在し、パーキンソン病態に於いて増加する傾向を持つ化合物であることが示された。また、パーキンソニズム発症作用を有し、中脳ドーパミン神経に選択毒性を持つことから、パーキンソン病と深い関連があり、パーキンソン病発症物質群のひとつであることが示唆される。上記の内因性神経毒に関する研究は神経化学の分野に重要な知見をもたらし、老人性神経疾患の病因に迫るものと考えられ、博士(薬学)の学位に充分値するものと認定した。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/54021 |
 Mと、MPP+と比較して極めて低濃度でComplex Iを阻害した。
Mと、MPP+と比較して極めて低濃度でComplex Iを阻害した。