| 内容要旨 | | 縄文時代の終焉とともに本州以南では稲作を基盤とする農耕経済に移行する.しかし北海道では明治時代にいたるまで本格的な農耕経済への転換はおこらず,基本的に狩猟・採集・漁労を主体とする生業が継続した.たとえば,噴火湾沿岸では冬期に回遊するオットセイを対象とした狩猟活動が縄文時代以来,近世アイヌ期まで連綿と維持されたとが出土遺物の構成から知られる.一方では,生業に占める狩猟活動の意味は本州和人との交易が開始される13世紀以降変化したのではないかとの指摘もなされている.本研究は,考古学上不明な点の残る北海道先史時代における動物資源の利用形態の時代変遷を遺跡から出土する動物骨の分析から明らかにしようとするものである. 遺跡から出土する動物骨は先史時代の生業活動を復元するうえで最も基本的な資料である.ただし,資料生成のプロセスで生じる崩壊,変質を常に被っており,本来資料に反映された文化的情報量は減少し,かわって堆積過程でくわわる自然要因に置換されていくと考えられる.近年,こうした資料の形成過程が強く意識されるようになり,アフリカの初期人類遺跡における研究を筆頭に,遺跡に伴なう動物骨資料に対してタフォノミー的分析が盛んに推進されている.しかし,日本の先史時代遺跡から出土した動物骨資料についてはほとんど研究例をみない.これは,動物骨が遺跡に主体的に伴なうのは縄文時代以降であり,その出土状況から基本的にそれらを人類の食料残滓として扱うことが出来るとの前提がなされるからであろう.とはいえ埋蔵資料を扱う以上,資料には一定のバイアスがかかることを免れず,タフォノミー的分析の推進が必要である. 本研究では,動物骨資料の部位別出現頻度を骨の大きさ,骨密度,イヌによる骨の消費など,骨の残存に影響すると考えられる要素との関係から検討することで,出土動物骨資料に影響を与えた自然要因を特定し,その影響度の評価を行った.これにより資料の生成過程に生じたバイアスが同一と仮定できない,異なる堆積環境下に形成され複数の遺跡間の比較が可能になる. 資料としたのは,縄文時代前期(約5000年前)の北黄金貝塚遺跡,続縄文時代(約2000年前)の南有珠6遺跡,擦文時代(約800年前)の南有珠7遺跡,近世アイヌ文化期(約200年前)の有珠オヤコツ遺跡および向有珠2遺跡の,4期5遺跡から出土した動物骨資料5000点である.資料にしめる動物種の構成比は向有珠2遺跡を除きオットセイが一貫して約80%を占めた. 部位別出現頻度の分析 図1は4遺跡で最優占種となったオットセイの,各遺跡資料における骨格部位別出現頻度を,現生骨格の計測から得られた各部位それぞれの最大長と骨密度に対して3次元に散布したものである.いずれの資料にも,出現頻度が極端に低い1群が存在する.4遺跡資料共通して,これらは脊椎骨,手根・足根骨以遠の骨格要素であった.サイズが小さく,骨密度の低い部位が一貫して低頻度であることから,骨格部位の出現頻度に骨の強度と大きさが強く影響を与えているることが示される.そこで出現頻度の高い群についても,一律に骨の強度と大きさが影響を与えているのかが問題となる.これを検討するために,出現頻度とサイズ,および骨密度との順位相関を調べた.その結果,すべての資料で,いずれの組み合わせにおいても有意な相関は得られなかった.このことから,相対的に出現頻度の高かった骨格要素,具体的には頭部と四肢骨の出現頻度における遺跡間のばらつきは当時の動物消費行動の相違を反映するものと考えられる.  図1骨格要素の最大長,骨密度と出現頻度MAU部位別出現頻度,SIZE最大長,BMD骨密度 図1骨格要素の最大長,骨密度と出現頻度MAU部位別出現頻度,SIZE最大長,BMD骨密度 図2は主要部位の出現頻度を遺跡間で比較したものである.縄文時代の資料では極端な部位の偏りが認められないが,続縄文時代と擦文時代の資料では前肢の出現頻度が高くなる.部位別出現頻度の遺跡間の相違をカイ2乗検定によって検定した結果,続縄文時代と擦文時代の遺跡の組み合わせを除いて有意差が認められた. 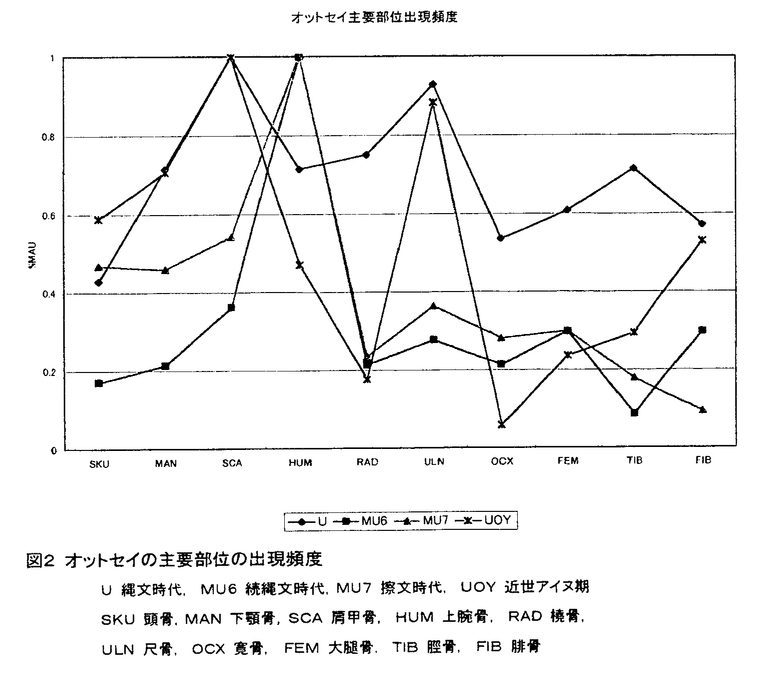 図2オットセイの主要部位の出現頻度U縄文時代,MU6続縄文時代,MU7擦文時代,UOY近世アイヌ期SKU頭骨,MAN下顎骨,SCA肩甲骨,HUM上腕骨,RAD橈骨,ULN尺骨,OCX寛骨,FEM大腿骨,TIB脛骨,FIB腓骨 図2オットセイの主要部位の出現頻度U縄文時代,MU6続縄文時代,MU7擦文時代,UOY近世アイヌ期SKU頭骨,MAN下顎骨,SCA肩甲骨,HUM上腕骨,RAD橈骨,ULN尺骨,OCX寛骨,FEM大腿骨,TIB脛骨,FIB腓骨 特定の部位が頻出,もしくは欠損する場合,動物の身体が1ヶ所で解体・消費されず一部が運搬されたことを示唆する.民族調査から導かれたビンフォードのモデルにしたがって解釈すれば,続縄文時代および擦文時代の資料は,仕留めた獲物を現地でまず解体し,高価値な部位のみを選択的に持ち帰ったsettlement assemblageに対応する.縄文時代の資料は,高価な名部位が頻出する点でsettlement assemblage的特徴を示すが,部位間の出現頻度の偏りが小さい点を考慮すると,オットセイの水揚げから解体・消費までを行った,kill siteとsettlement siteの両方の性格を備えた遺跡に伴なう資料であったとみることが出来る.アイヌ期の資料に関しては,通常,解体時にひとつの単位として扱われる傾向が強い橈骨と尺骨の出現頻度に大きな差が見られるなど,一般化されたモデルでは説明が難しい傾向をしめしている. 骨損傷の分析 動物の解体,消費のプロセスをより詳細に理解することで明らかにするため,骨の残存状態,骨表面に観察される解体痕の分布を調べた.その結果,以下の点が明らかになった. 1.解体痕の種類,分布は,擦文時代を境に大きくかわる.損傷の形態から,この時機に石器にかわって鉄器が動物解体に本格的に導入された. 2.体幹部,四肢骨の分断単位が続縄文時代以降,順じ細かくなっていく. 3.擦文時代を境に完形で残存する骨の頻度が下がり,人為的な破砕の痕跡が明確になる.縄文時代には行われた痕跡のない骨油脂の利用が行われたと解釈できる. これらの知見を総合すると,獲物の全身を遺跡に持ち込み,解体から消費までを行っていた縄文時代のオットセイ利用が,続縄文時代以降,遺跡外で解体され,身体各部が分断されたうえで選択的に搬入されるようになったことが指摘できる.獲物の細分化は,捕獲するオットセイの個体数が減少するのにあわせ,1頭あたりの利用効率を増していく行為であったと考えられる. |