金属間化合物Mn3GaCはペロブスカイト型の立方晶結晶構造である。Gaは基本の立方格子を組み、Cは体心に、磁性原子のMnは面心に位置している。このような対称性の高い単純な結晶構造をしているのにも関わらず、この物質は非常に多彩な磁性を示す。磁気秩序状態では(111)面上にあるMn磁気モーメントが強磁性的に揃っている。この強磁性面が[111]方向に交互に反転しながら積み重なる反強磁性状態(AF)が、基底状態と考えられている。このときのMn磁気モーメントの大きさは1.8 B(T=4.2K)と報告されている。温度を上昇させると、 B(T=4.2K)と報告されている。温度を上昇させると、 程度で急激な体積の収縮 程度で急激な体積の収縮 を伴って、強磁性(F)への1次転移を起こす。F状態でのMn磁気モーメントの大きさは1.2 を伴って、強磁性(F)への1次転移を起こす。F状態でのMn磁気モーメントの大きさは1.2 B(T=170K)で、AF状態でのそれよりも小さくなっている。キュリー温度は B(T=170K)で、AF状態でのそれよりも小さくなっている。キュリー温度は である。加圧によりキュリー温度Tcは増大し、TAF-Fが減少する。すなわち、圧力を加えることでF状態の温度領域が広がる。また、0.3GPa以上の圧力でAF相とF相の間の温度領域に、これらと異なる中間的な磁気相(I)が現れるという。更に加圧を続けて行くと、AF相とI相の間の転移温度TAF-Iと、I相とF相の間の転移温度TI-Fは、両方とも減少してゆく。また、Gaを外殻電子数が同じAlで少量の置換を行うことにより立方格子間隔を収縮させることが出来、直接的に圧力を加えたときと同様の効果が得られるという。 である。加圧によりキュリー温度Tcは増大し、TAF-Fが減少する。すなわち、圧力を加えることでF状態の温度領域が広がる。また、0.3GPa以上の圧力でAF相とF相の間の温度領域に、これらと異なる中間的な磁気相(I)が現れるという。更に加圧を続けて行くと、AF相とI相の間の転移温度TAF-Iと、I相とF相の間の転移温度TI-Fは、両方とも減少してゆく。また、Gaを外殻電子数が同じAlで少量の置換を行うことにより立方格子間隔を収縮させることが出来、直接的に圧力を加えたときと同様の効果が得られるという。 AF-F 1次相転移の起源については、いくつかのモデルや理論が提唱されている。局在描像に基づくKittelの交換反転モデル、スピン揺らぎの理論に基づく守谷・宇佐美モデルなどである。3d遷移金属化合物・合金で実際にAF-F 1次相転移を示す物質として他に、FeRh合金やCe(Fe1-xCox)2などが挙げられる。前者は守谷・宇佐美モデルを改訂した磁気転移モデルで定性的に説明可能だとされている。また、後者についてはバンド描像に基づく電子比熱の違いが、転移の際のエントロピー変化に主要な寄与をしているという考察がされている。このような考察がMn3GaCには適用可能なのであろうか?。本研究では、Mn3GaCおよびその混晶系Mn3Ga1-xAlxCの磁気特性を実験的に明らかにし、考察を行った。以下に結果を述べる。 1)磁化測定・中性子回折 常圧で決定した磁気相図を(図-A)に示す。基底状態のAF状態は、I状態との1次転移相境界で囲まれている。交流帯磁率測定の報告だと圧力0.3GPaでI状態が突然に現れるが、これは不自然な話で、むしろ常圧で弱磁場だとI相の温度領域が狭いから判別できなかっただけのようである。我々の測定では、常圧・零磁場での転移温度を磁場外挿によりTAF-I[0]=160.1K,TI-F[0]=163.9Kと決定した。I相も、F相との2次転移相境界で囲まれていると考えられるが、低温での境界を定めるには磁場が足りない様子である。アロットプロットによる推定キュリー温度は245.8Kである。 この系に直接加圧すると、TAF-Iは敏感に下がり、TI-Fはゆるやかに下がる。TCは上昇する。これは、交流帯磁率測定と同様の傾向である。F相温度領域で加圧で磁化が増大する。また、圧力が1.25GPaになると、AF状態温度領域全域にわたって一様な自発磁化が発現する。GaサイトをAlで微少量(1〜2%)置換して格子間隔を収縮させた試料について高圧下磁化測定を行うと、より低い圧力で同じ現象が観測され、圧力誘起のAF-I転移が起きることが確認された。温度-圧力-組成磁気相図を(図-B)に示す。以上の磁気秩序-秩序転移は、これまで報告されているような単純な磁気転移モデルでは説明できない。 Mn3Ga1-xAlxC(x=0.02)の中性子回折により、Alを置換した試料でもAF相とF相の磁気構造は、過去に報告された純粋な試料のそれと同様であることを確認した。また、x=0.05組成試料のI状態の中性子回折により、I状態の(温度領域のうちの1点で)磁気モーメントを 1)強磁性成分:約1.2 B。方向は不明。 B。方向は不明。 2)反強磁性成分:約0.6 B。方向[111]方向。( B。方向[111]方向。(   )周期構造。 )周期構造。 ということを推定した。AF成分は温度上昇と共に消失していくものと思われる。これを見ると、I状態はF状態とAF状態の2相共存状態ではないかと疑われるが、磁化の温度依存性がヒステリシスを見せないことや、X線回折の温度依存性(AF相とF相は格子定数が違うため、違う角度にブラッグピークが現れる)から、I状態は単相な状態であると考えられる。また、最近NMRのI状態での温度依存性が報告されている。それより、Mn核周囲の内部磁場について考察すると、上の中性子回折で定めた磁気モーメントのAF成分とF成分は垂直になっている(すなわち、canted ferro)磁気構造の可能性が示唆される。 2)比熱測定 いづれの測定でも、C/T-T2プロット中に上に凸の折れ曲がりが存在する。折れ曲がり点より低温側、高温側、いづれの温度領域でも直線性が良い。その起源が磁気比熱か格子比熱かは分からないが、本質的な電子比熱係数として採用すべきなのは、低温側の直線外挿で得られた値と考えられる。各温度領域で直線外挿を行って、切片から仮想的に電子比熱係数を、傾きからデバイ温度を求めると次のテーブルのようになる。 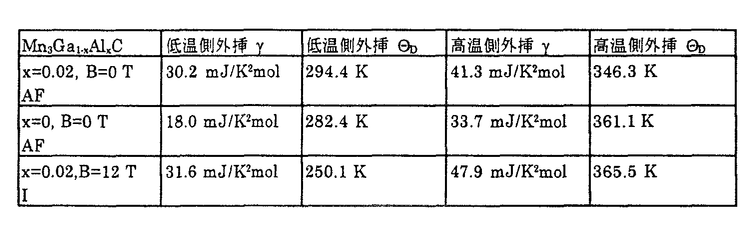 図表 図表 試料の組成によって、同じAF状態であるにも関わらず電子比熱係数が違って観測されたのは、x=0.02の試料では圧力誘起のAF-I転移境界に極めて近い状態であるため、磁気比熱の寄与がバックグラウンドとして働いているせいだと解釈できる。 I状態の比熱でも磁気比熱の寄与はあるかも知れない。しかし、零磁場・低温でI状態が安定な他の組成の試料の電子比熱係数と大差ないことから、I状態では磁気比熱の「組成依存性」はそれほど重要ではないものと考えられる。比熱の温度依存性には強磁性マグノン的な寄与が働き、I状態のC/T-T2プロットが低温で急勾配になり、低温の外挿でデバイ温度が下がっているのかも知れない。低温外挿で決定した値で、デバイ温度には磁気比熱の寄与があると思われるが、電子比熱係数にバックグラウンドとしての磁気比熱の影響はさほど現れていないものと考えられる。 比熱測定に用いた試料でパルス磁場中磁化測定を行い、AF-I転移磁場の温度依存性を求め、熱力学的考察により総エントロピー変化を算出した。それより、AF-I 1次転移にともなう総エントロピー変化は、磁気比熱の寄与がメインであると考えられるが、バンド構造の変化に伴う電子比熱係数の変化も無視できない程度の大きさで寄与しているものと考えられる。 3)伝導現象 パルス強磁場中での磁気抵抗測定により、低温で磁場誘起のAF-I1次転移を起こすと8割近い抵抗の減少(巨大磁気抵抗効果)が観測された。これほどの大きな変化は、磁気モーメントの配列の仕方に基づく磁気散乱のみでは説明するのは難しいと思われる。従って、AF状態とI状態のフェルミ面付近での電子帯構造は極めて大きく変化していると推測できる。一方、常磁性(P)〜Tc近傍での磁気抵抗は、磁気散乱の寄与を緩和時間に入れ伝導電子の濃度と独立に考えたde Gennes & Friedelのシンプルな磁気散乱モデルに基づく考察により良く説明される。 またホール係数から、AF状態とF状態とでキャリア濃度が、大きく異なることを明らかにした。このキャリア濃度の逆数の大きさの比率は、低温でのAF-I転移の磁気抵抗の比と大体同じになっている。Tc近傍の議論と同じように考えると、低温の巨大磁気抵抗効果は磁気散乱よりもキャリア濃度の変化が露に現れていると解釈できる。F状態とI状態とで、キャリア濃度は同程度なのであろう。以上のことは、AF状態とI,F状態の電子状態の構造の違いを反映していると思われる。 しかし、現状のバンド計算結果からは、上記の伝導に寄与する電子の濃度変化や電子比熱係数をうまく説明できない。実験結果は一貫していると思われるので、今後の理論の進展に期待したい。  (図-A) (図-A)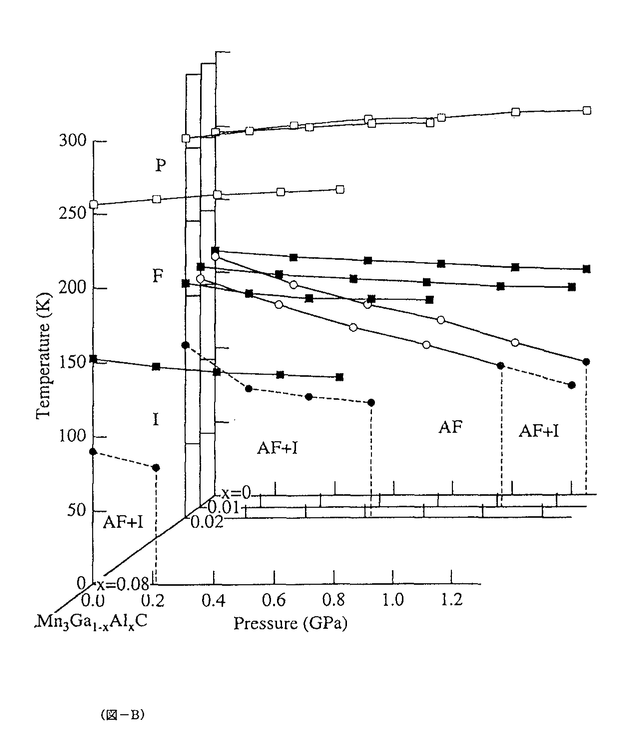 (図-B) (図-B) |