分子による電子の散乱現象を理解することは、大気科学、放射線化学、プラズマプロセッシング等の様々な分野において重要である。特に電子衝突による分子の振動励起は、入射電子のエネルギー損失過程の一つとして非常に重要であり、その詳細な理解が必要とされている。そのため、電子衝突による分子の振動励起断面積を精度良く求める試みが実験、理論の両面から行なわれてきているが、そのデータの蓄積は、ごく少数の分子に対する狭い入射エネルギー領域に限られており、応用分野の要求を満たすには不十分であり、包括的とは言えないのが現状である。 特に理論的側面からの試みは、実験に比べても非常に立ち後れている。その理由は、分子は振動、回転の自由度を持つので取り扱うべきチャネルの数が膨大になるため、そして入射電子が感じる相互作用ポテンシャルは一般に非球対称になるので、その取り扱いが困難なためである。振動モードが一つに限られている二原子分子を標的とした研究は、これまでに比較的多く報告されており、その振動励起断面積も高精度で求められるようになってきたが、3N-6(直線分子においては3N-5:Nは原子数)の振動モードを持つ多原子分子を標的とした研究は、ほとんど報告がないのが現状である。しかし、応用上の必要性からだけでなく、基礎科学的な見地からも、電子衝突による多原子分子の振動励起過程を理論的に研究し、各振動モードにおける励起断面積の違い、また特定の振動モードにおける励起断面積の入射エネルギー及び散乱角依存性等を詳細に解明することは重要である。実験では、前方(0度近辺)及び後方(180度近辺)散乱領域において断面積を測定する手法は未だ発展途上であり、また励起エネルギーが小さい過程を扱う場合、分解能に限界があるためエネルギー損失スペクトルの解析が困難になる。このような理由から、実験的研究を補完する意味でも理論的研究は不可欠である。そこで本研究では、最も簡単な多原子分子の一つであり、実験データが比較的多く報告されている二酸化炭素(CO2)分子を標的とし、各基準振動モード別に電子衝突による振動励起断面積の計算を行なった。そして同時に、振動励起断面積に対する入射粒子の電荷の正負依存性にも興味が持たれるので、電子の反粒子である陽電子を入射粒子とした場合の振動励起断面積の計算も行なった。 CO2分子は、対称伸縮(振動量子数をn1で表す)、変角(同n2)、逆対称伸縮(同n3)の3つの基準振動モードを持ち、そのうち変角振動モードは二重縮退している。本研究では、基底状態(n1n2n3)=(000)から第一励起状態(nk=1:k=1,2or3)への遷移のみに着目する。また、入射粒子が衝突している間、標的分子の分子軸方向は変化しないとして計算を行なった。本研究の入射粒子のエネルギー領域は、電子については2.0〜50.0eV、陽電子については2.0〜6.0eVであり、これは基底状態におけるCO2の回転定数より十分大きいため、この近似は妥当であると考えられる。また標的分子の振動運動は調和振動として取り扱い、各基準振動モード毎に基底状態と第一励起状態を考慮して、入射粒子の波動関数の動径成分が満たす2状態緊密結合方程式を導いた。この緊密結合方程式を適当な境界条件を課して解き、振動遷移についての散乱行列を求め、微分及び積分断面積を計算した。 入射粒子と標的分子の相互作用としては、静電、交換(電子衝突の場合のみ)及び相関分極の効果を取り入れた。静電ポテンシャルは分子軌道計算プログラムを用いてSCFレベルで決定し、交換及び相関分極効果は局所的モデルポテンシャルで近似した。そして振動運動による平衡配置からのずれの効果は、相互作用ポテンシャルを平衡配置のまわりで振動の基準座標によって展開し、その展開項を1次まで取ることで取り入れた。 図1〜3に、それぞれ電子衝突による対称伸縮、変角そして逆対称伸縮の振動励起積分断面積の結果を実験値と共に示す。図1及び2では、5.0eV付近に非常に強いピークが見られる。これは、入射電子が標的分子のポテンシャルに一時的に捕らえられる形状共鳴を示しており、その対称性はIIuであることが明らかになっている。このピークの位置は、実験によって与えられている位置(3.8eV)よりやや高いが、筆者が修士過程において扱った弾性散乱の断面積においても同様な傾向が現れていることから、これは本研究において構築したポテンシャルの特性によるものと思われる。しかし、ピーク強度は実験値とよく一致している。ピークの位置について精緻な議論を行なうためには、局所的モデルポテンシャルとして取り入れた交換効果や相関分極効果の精度をより向上させる、もしくはそれらの効果をモデルではなく厳密に取り扱う必要があると思われる。また図1のE 10.0eVにおいて、Nakamuraによる実験値は急激に減少しているが、理論値は大きな断面積を持つという違いが見られる。特に理論値では、14.0eV及び32.0eV付近に実験値には見られない2つのピークが現れている。これらはそれぞれ 10.0eVにおいて、Nakamuraによる実験値は急激に減少しているが、理論値は大きな断面積を持つという違いが見られる。特に理論値では、14.0eV及び32.0eV付近に実験値には見られない2つのピークが現れている。これらはそれぞれ g及び g及び u対称性を持つ形状共鳴によるピークであることが本研究によって示された。 u対称性を持つ形状共鳴によるピークであることが本研究によって示された。 図2の変角振動モードの結果においても、対称伸縮振動モードの場合と同様に、8.0eV以上のエネルギー領域でNakamuraによる実験値が急激に減少しているのに対し、理論値は小さくない断面積を与えており、また30.0eV付近では形状共鳴と思われるピークの存在を示唆している。このピークは図1の32.0eV付近に見られるピークと同様なダイナミクスに起因するものと考えられる。これらのピークは、散乱ダイナミクスを議論する際非常に興味深い対象であり、今後一層の解析が必要と思われる。 図3に示した逆対称伸縮振動モードの結果は、全エネルギー領域に渡って定量的に実験値と非常に良い一致を示している。Registerらによる実験値は、入射エネルギーが増加するに従い、本研究における理論値及びNakamuraによる実験値との差が大きくなる。これは、装置の性質上測定できない散乱角領域においてRegisterらが外挿して求めた微分断面積が、過小評価されているためである。Registerらのデータにおいて、外挿値の代わりに理論値を用いて積分断面積を計算すれば、各入射エネルギーでNakamuraの実験値に誤差の範囲で一致することが本研究で確認された。  図1 電子衝突によるCO2分子の対称伸縮振動励起積分断面積 図1 電子衝突によるCO2分子の対称伸縮振動励起積分断面積 図2 電子衝突によるCO2分子の変角振動励起積分断面積 図2 電子衝突によるCO2分子の変角振動励起積分断面積 図3 電子衝突によるCO2分子の逆対称伸縮振動励起積分断面積 図3 電子衝突によるCO2分子の逆対称伸縮振動励起積分断面積 図4に、入射エネルギー20.0eVにおける変角振動励起の微分断面積の結果を実験値と共に示す。0度付近では、散乱角が小さくなるにつれて断面積が著しく大きくなる傾向が見られる。これは入射電子が、標的分子の振動励起により生じる双極子相互作用を受けるためである。本計算結果は、前方及び中間散乱領域では実験値と非常に良い一致を示しているが、120度以上の後方ではやや差が見られる。特に140度以上の散乱角におけるRegisterらの外挿値は、理論値よりかなり大きい。中間及び後方散乱領域における断面積については、散乱のダイナミクスが非常に複雑であるために、一概に議論することが出来ない。しかし、実験で行なわれる微分断面積の外挿の方法は決して確立されているとは言えず、本研究結果は、実験において微分断面積の外挿を行なう際に、一つの指針を与えることが出来る。 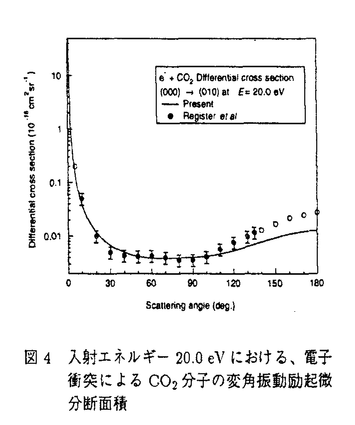 図4 入射エネルギー20.0eVにおける、電子衝突によるCO2分子の変角振動励起微分断面積 図4 入射エネルギー20.0eVにおける、電子衝突によるCO2分子の変角振動励起微分断面積 表1は、入射エネルギー2.0,5.0そして6.0eVにおける電子及び陽電子衝突の振動励起断面積及びその比を振動モード別にまとめたものである。この表から、他のモードの場合に比べて(000)→(100)の断面積比が特に大きくなっていることが分かる。このモードの電子衝突の断面積が増大しているのは、IIu共鳴の影響によるものとして理解出来るが、一方で陽電子衝突の断面積が著しく小さくなっている点にも注意しなければならない。  表1電子及び陽電子衝突における二酸化炭素分子の振動励起断面積(10-16cm2)。表記A(-B)は、A×10-Bを表す。 表1電子及び陽電子衝突における二酸化炭素分子の振動励起断面積(10-16cm2)。表記A(-B)は、A×10-Bを表す。 この現象は、以下のように説明付けられる。(100)モードの場合、遠方の相互作用は四極子相互作用及び分極効果であるため、それらは が大きくなると急激に小さくなる。陽電子は、核による斥力によって分子の内側まで近付けないために、その感じる相互作用は小さい。そのため断面積が小さくなる。一方電子は分子のかなり内側まで入れるために、感じる相互作用は大きく、従って大きな断面積を持つことになる。また(010)及び(001)モードの場合、遠方の相互作用は双極子相互作用であり、 が大きくなると急激に小さくなる。陽電子は、核による斥力によって分子の内側まで近付けないために、その感じる相互作用は小さい。そのため断面積が小さくなる。一方電子は分子のかなり内側まで入れるために、感じる相互作用は大きく、従って大きな断面積を持つことになる。また(010)及び(001)モードの場合、遠方の相互作用は双極子相互作用であり、 が大きくなってもその相互作用はある程度の大きさを保ったままゆっくり減衰していくため、斥力ポテンシャルによって弾き返される距離においても、陽電子はある程度大きな相互作用を感じる。そのため陽電子衝突の場合においても、電子衝突の場合とそれほど大きな差のない絶対値の断面積を与えることになる。 が大きくなってもその相互作用はある程度の大きさを保ったままゆっくり減衰していくため、斥力ポテンシャルによって弾き返される距離においても、陽電子はある程度大きな相互作用を感じる。そのため陽電子衝突の場合においても、電子衝突の場合とそれほど大きな差のない絶対値の断面積を与えることになる。 またこの表の電子衝突断面積と陽電子衝突断面積の比較において、(100),(010)モードにおいては常に電子衝突断面積の方が大きいのに対し、(001)モードにおいては常に陽電子衝突断面積の方が大きくなっていることが分かる。この興味深い振動モード依存性の違いについては定性的な解釈はまだ行なわれておらず、より詳細な解析が必要と思われる。 |