海洋中には生物活動によって生成されたデトライタスが蓄積され、陸上の植物、土壌の腐食と並んで、地球上の有機炭素の大きなストックとなっている。またその80%以上が孔径約1 mのフィルターを通過する、いわゆる溶存有機物と呼ばれるものである。これらの溶存有機物の内、懸濁態有機炭素(POC>1 mのフィルターを通過する、いわゆる溶存有機物と呼ばれるものである。これらの溶存有機物の内、懸濁態有機炭素(POC>1 m)との境界付近の大きさを持つ、コロイド有機炭素(COC:1-1000nm)は、海洋生態系の中で従来の捕食食物連鎖を補完するシステムとして注目されている微生物食物網における、代謝基質としての重要性が指摘されている。Koikeら(1990)は、これらのコロイド有機物のうち上限サイズ(球体換算直径0.4-1 m)との境界付近の大きさを持つ、コロイド有機炭素(COC:1-1000nm)は、海洋生態系の中で従来の捕食食物連鎖を補完するシステムとして注目されている微生物食物網における、代謝基質としての重要性が指摘されている。Koikeら(1990)は、これらのコロイド有機物のうち上限サイズ(球体換算直径0.4-1 m)のもの(サブミクロン粒子;SMP)が外洋表層に多量に存在し、ほぼ同じサイズである細菌よりも一桁数が多い事を見出だした。これらの大型コロイド粒子の存在は、海洋中の有機物のサイズ分布の連続性を証明するとともに、デトライタスと生物との相互作用に新しい関係をもたらすものとなった。しかし、これまでSMPの海洋での時空間的分布や粒径分布等についての研究例は乏しく、生物活動との関係についても、細菌、鞭毛虫やウイルスといった微生物群集との相互作用が個別に示唆されているだけである。更に生物活動の盛んな沿岸域での研究がほとんど無かった為、現場での生成過程など、その動態についての解明が遅れていた。本研究では、北西太平洋沿岸域の海水を用いて、まずSMPのいくつかの物理化学的特性を調査した後、沿岸域での現場観測と沿岸試水を使った実験によって、生物量、特に植物プランクトンの増加と相関してSMPが増加し、それと共に、SMPの粒径分布に特徴的なピークが出現することを始めて見出した。更に培養実験におけるSMPの粒径分布の経時的変化から、SMPは植物プランクトンのブルーム時に生成された溶存有機物の凝集により形成されると推測した。サイズ分画した有機炭素の測定の結果もこの推測を支持していた。 m)のもの(サブミクロン粒子;SMP)が外洋表層に多量に存在し、ほぼ同じサイズである細菌よりも一桁数が多い事を見出だした。これらの大型コロイド粒子の存在は、海洋中の有機物のサイズ分布の連続性を証明するとともに、デトライタスと生物との相互作用に新しい関係をもたらすものとなった。しかし、これまでSMPの海洋での時空間的分布や粒径分布等についての研究例は乏しく、生物活動との関係についても、細菌、鞭毛虫やウイルスといった微生物群集との相互作用が個別に示唆されているだけである。更に生物活動の盛んな沿岸域での研究がほとんど無かった為、現場での生成過程など、その動態についての解明が遅れていた。本研究では、北西太平洋沿岸域の海水を用いて、まずSMPのいくつかの物理化学的特性を調査した後、沿岸域での現場観測と沿岸試水を使った実験によって、生物量、特に植物プランクトンの増加と相関してSMPが増加し、それと共に、SMPの粒径分布に特徴的なピークが出現することを始めて見出した。更に培養実験におけるSMPの粒径分布の経時的変化から、SMPは植物プランクトンのブルーム時に生成された溶存有機物の凝集により形成されると推測した。サイズ分画した有機炭素の測定の結果もこの推測を支持していた。 SMP(0.45-1 m)の数と粒径は、電気パルス抵抗法による粒子計測装置で計測した。沿岸試水を熱や超音波等で処理したところ、試水中のSMP数は著しく減少し、SMPが物理化学的衝撃に弱い構造を持つ事が確認された。しかし加水分解酵素に対してはSMP数がほとんど変化せず、特に冬期の現場海水中のSMPは、単独の酵素のみでは分解されにくい事が示された。 m)の数と粒径は、電気パルス抵抗法による粒子計測装置で計測した。沿岸試水を熱や超音波等で処理したところ、試水中のSMP数は著しく減少し、SMPが物理化学的衝撃に弱い構造を持つ事が確認された。しかし加水分解酵素に対してはSMP数がほとんど変化せず、特に冬期の現場海水中のSMPは、単独の酵素のみでは分解されにくい事が示された。 外洋におけるこれまでの観測結果と同様、相模湾・伊豆七島近海などの沿岸域においても、SMPは表層に多く存在し(約107particles ml-1)深さ約200m以深では約104-105particles ml-1でほぼ一定となった。SMPは水深100-200mまでで急速に減少するが、同様にクロロフィルa濃度や細菌数などの生物指標も表層で高い鉛直分布を示した。更に表層のSMP量を水平的に比較すると、相模湾から沖合への測線において、クロロフィルa濃度の高い、岸よりの測点(3x107particles ml-1)の方が沖合いの測点(1x107particles ml-1)より多かった。また、季節変化を調べた大槌湾と江ノ島の測点においては、春から夏にかけて、高いクロロフィルa濃度と同時にSMP量の増加が見られた。このようにSMP量とクロロフィルaなどの生物指標との間には、空間的にも季節的にも正の相関があり(図1)、また培養実験で確認された経時的変化からも、沿岸域では生物活動に伴ってSMPが生されていることが示唆された。 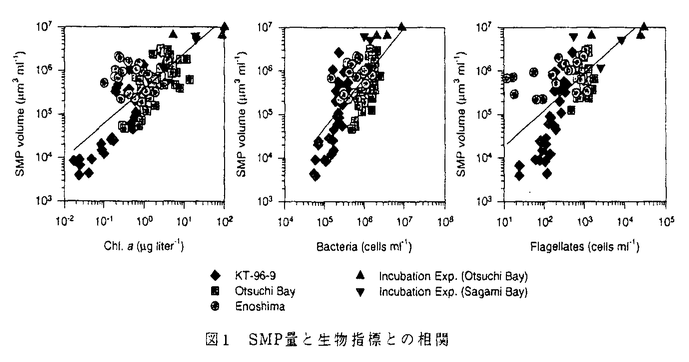 図1 SMP量と生物指標との相関 図1 SMP量と生物指標との相関 一般に海洋の非生物粒子の数は、凝集や解離などの物理過程に依って制御され、粒径の減少に伴って指数的に増加すると考えられ、SMPも外洋域ではこのような粒径分布を示す。しかし相模湾(Sta.D)の0m層においては、直径0.6 m付近の粒子が明らかにピークを形成していた(図2)。またこのピークは、深くなるにつれ、右下がりの粒径分布に移行した。更に、生物量の少ない沖合い(Sta.B)に向かうにつれ、0mでも右下がりの粒径分布に移行することが分かった(図2)。このように生物活動が盛んな水塊でSMPのピークが出現する傾向は大槌湾や江ノ島でも観察され、春から夏にかけての植物プランクトンのブルーム期に、ピークのある粒径分布が見られた。またクロロフィルa濃度が高い試水ほど、粒径の大きな方にピークがある傾向が見られた。これらのピークは、計数の比較あるいは超音波処理による減少パターンから、細菌群集によるものではないことが確認された。 m付近の粒子が明らかにピークを形成していた(図2)。またこのピークは、深くなるにつれ、右下がりの粒径分布に移行した。更に、生物量の少ない沖合い(Sta.B)に向かうにつれ、0mでも右下がりの粒径分布に移行することが分かった(図2)。このように生物活動が盛んな水塊でSMPのピークが出現する傾向は大槌湾や江ノ島でも観察され、春から夏にかけての植物プランクトンのブルーム期に、ピークのある粒径分布が見られた。またクロロフィルa濃度が高い試水ほど、粒径の大きな方にピークがある傾向が見られた。これらのピークは、計数の比較あるいは超音波処理による減少パターンから、細菌群集によるものではないことが確認された。 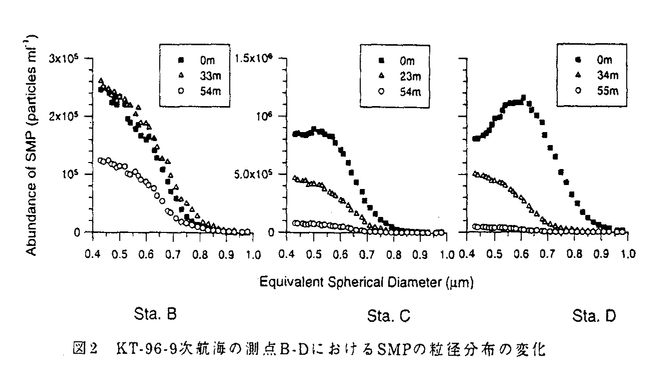 図2 KT-96-9次航海の測点B-DにおけるSMPの粒径分布の変化 図2 KT-96-9次航海の測点B-DにおけるSMPの粒径分布の変化 現場海水中での生物群集によるSMPの生成と粒径分布上のピークの生成過程を解析するため、相模湾の海水を用いて、光条件を変えた培養実験を行った。光を照射した系では、クロロフィルa濃度は96時間まで急速に増加したが、栄養塩の枯渇によってその後減少した。また暗条件では、クロロフィルa濃度は始めから減少したが、細菌や鞭毛虫の数の変化は光を照射した系と大きな違いは無かった。一方、SMP数は、光を照射した系においては培養開始時から150時間後まで増加しており、その後はほぼ定常となった。しかし暗条件では逆に減少し、SMPの生成には植物プランクトンの増殖が大きく影響することが示された。更に、光を照射した系では、培養の進行にともなってSMP数が増加すると同時にピークが形成され、クロロフィルa濃度が減少を始めた後もSMP量は少しずつ増加し、ピークは徐々に大きい方へと移行した。同様の結果が、大槌湾の海水を用いて栄養条件を変えて行った実験でも得られた。この時、クロロフィルa濃度が大きく増加し、SMPの増加も大きな培養系ほど、ピークが最終的に到達した粒径が大きくなる傾向が見られた。このように、沿岸域における観測と培養実験を通して、ピークの粒径とクロロフィルa濃度との間には、正の相関(r=0.776)が有る(図3a)ことが明らかになった。更に、ピークの粒径とSMPの総体積の間にも、非常に強い正の相関(r=0.966)が見られ(図3b)、SMPの粒径は、SMPの総量、ひいては生物によって生産された有機物の量によって制御されていることが示唆された。  図3 SMPのピーク粒径と(a)クロロフィルa濃度及び"(b)SMPの総体積との相関 図3 SMPのピーク粒径と(a)クロロフィルa濃度及び"(b)SMPの総体積との相関 このような粒径分布上のピークが生じる理由としては、1)生成されるSMPのサイズ分布は均等であるが、ある大きさのSMPだけが何らかの理由で生物的な分解や物理的凝集による除去を受けにくく、蓄積した場合、2)生物作用により、あるサイズのSMPが集中して生成された場合、3)活発な生物活動により継続的に多量に生産された溶存有機物が、雪ダルマ式に凝集してSMPを形成し、その速度が粒径分布の平坦化の速度を上回っていた場合、等が考えられる。培養実験における経時的変化からは3)の仮説が強く支持される。即ち、植物プランクトンにより生産される有機物がSMPの重要な起源であり、それらが連続的に供給されるブルーム時には、溶存有機物の凝集によるSMPの生成速度が大きく、粒径分布にピークが形成されると考えられる。また、この仮説は、別に行われたシミュレーション(A.Burd,personal communication)の計算結果からも支持された。 江の島で採取した試水をGF/Cフィルター(孔径約1 m)とAnoporeフィルター(孔径0.2 m)とAnoporeフィルター(孔径0.2 m)でろ過し、粒径0.2 m)でろ過し、粒径0.2 m以下の溶存、0.2-1 m以下の溶存、0.2-1 mの大型コロイド、および1 mの大型コロイド、および1 m以上の懸濁態の、各画分に含まれる有機炭素・窒素濃度およびそれらの比(C/N比)の季節変化を測定した。年間平均では、大型コロイド(COC)および懸濁態(POC)の有機炭素が、それぞれ全有機炭素(TOC)の9%を占めていた。このような海洋の大型コロイドの有機炭素・窒素量を測定した例はほとんどなく、しかもその大部分は細菌の菌体であると考えられていた。しかし細菌量も同時に推定したこの研究では、沿岸域においては、COCへの細菌の寄与は年間平均で27%にすぎないことが示された。COC、POCの濃度は生物量の増加する春から夏にかけて高く、またTOCに対する比率も、COC、POCとも春から夏にかけて高かった。これらの結果は、COCが生物活動によって生産されることを示唆しており、これまでの粒子計数による結論を支持している。またコロイド有機物のC/N比は、溶存および懸濁態有機物のほぼ中間にあることが分かった。更に相模湾の海水を用いた培養実験において、クロロフィルa濃度およびSMPの増加した系のみで、DOCの増加に伴ってCOCが増加したことから、植物プランクトン由来のDOCが凝集してSMPが形成されるという仮説が支持された。またCOCは、江ノ島のサンプルでも培養実験のサンプルでもそれぞれ、SMPの総体積と正の相関が有ることが初めて明らかになった。 m以上の懸濁態の、各画分に含まれる有機炭素・窒素濃度およびそれらの比(C/N比)の季節変化を測定した。年間平均では、大型コロイド(COC)および懸濁態(POC)の有機炭素が、それぞれ全有機炭素(TOC)の9%を占めていた。このような海洋の大型コロイドの有機炭素・窒素量を測定した例はほとんどなく、しかもその大部分は細菌の菌体であると考えられていた。しかし細菌量も同時に推定したこの研究では、沿岸域においては、COCへの細菌の寄与は年間平均で27%にすぎないことが示された。COC、POCの濃度は生物量の増加する春から夏にかけて高く、またTOCに対する比率も、COC、POCとも春から夏にかけて高かった。これらの結果は、COCが生物活動によって生産されることを示唆しており、これまでの粒子計数による結論を支持している。またコロイド有機物のC/N比は、溶存および懸濁態有機物のほぼ中間にあることが分かった。更に相模湾の海水を用いた培養実験において、クロロフィルa濃度およびSMPの増加した系のみで、DOCの増加に伴ってCOCが増加したことから、植物プランクトン由来のDOCが凝集してSMPが形成されるという仮説が支持された。またCOCは、江ノ島のサンプルでも培養実験のサンプルでもそれぞれ、SMPの総体積と正の相関が有ることが初めて明らかになった。 以上の結果から、沿岸域においては、植物プランクトンのブルーム時に新たに生産された、比較的反応性に富んだ有機物の凝集によってSMPが形成される事が示唆された。海洋の有機物の大部分を占める溶存有機物の半分以上が難分解性であることが既に示されているのに対し、沿岸域のSMPは、比較的生物群集によって利用されやすいと推定されることから、様々なサイズの生物と非生物を含めた海洋の有機物フラックスにおいて、重要な役割を果たしていると考えられる。 |