| 内容要旨 | | [はじめに] 堆積物中に含まれる浮遊性有孔虫化石及びプランクトンネットで採取した浮遊性有孔虫の殻と無機的に合成した炭酸カルシウム(CaCO3)の結晶について,電子スピン共鳴(Electron Spin Resonance:ESR)測定を行なうと,これらすべてに共通して,2価のマンガンに起因する典型的な6本のMn(II)の信号が観察される(図1).X線回折による分析では浮遊性有孔虫化石も無機的に合成した炭酸カルシウムもカルサイトであることが確認された.したがって,ESRで検出できるMn(II)はカルサイトの結晶中に存在することになる.しかし,その含有量について明確な値を示した研究例はない. 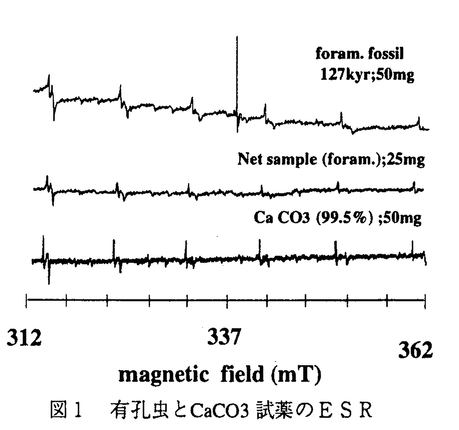 図1 有孔虫とCaCO3試薬のESR 図1 有孔虫とCaCO3試薬のESR その理由としてマンガンの反応性の高さが上げられる.マンガンは非常に多くの酸化状態を示す元素であり,海洋においては,+II,+III,+IVの酸化状態で存在していることがよく知られている.そのなかで,理論的にESRにより検出が可能なのは,Mn(II)だけであり,Mn(III)及びMn(IV)の検出は不可能だから,全マンガン量には対応しない. そこで純度の高い炭酸カルシウム試薬(メルク:99.9%,和光:99.5%)について, ESR測定とICP-AESによる全マンガン量の測定を行なった.さらに,ESR測定を行った有孔虫化石のいくつかについて,CL-method(化学発光分析)により全マンガン量を求めた.純度99.9%の試薬では両測定ともに検出ることはできなかったが,99.5%の試薬ではESR信号強度が53という値に対し,マンガン含有量が,0.25 g/gという値が得られた.一方,堆積物中に含まれる有孔虫のESR信号強度は純度99.5%試薬の1〜3倍程度であるにもかかわらず,全マンガン量は150〜400 g/gという値が得られた.一方,堆積物中に含まれる有孔虫のESR信号強度は純度99.5%試薬の1〜3倍程度であるにもかかわらず,全マンガン量は150〜400 g/gと非常に大きな値を示している.このことは,有孔虫化石に含まれるマンガンのほとんどが,Mn(III)もしくはMn(IV)の化合物の形で存在していることを示している.さらに,現在海水中に生息しているプランクトンについてのMartin等の分析値(3〜10 g/gと非常に大きな値を示している.このことは,有孔虫化石に含まれるマンガンのほとんどが,Mn(III)もしくはMn(IV)の化合物の形で存在していることを示している.さらに,現在海水中に生息しているプランクトンについてのMartin等の分析値(3〜10 g/g)と比べても非常に大きい値であることから,全マンガン量は海底で初期の続成作用の影響を受けた値であることを示唆している.にもかかわらず,プランクトンネットで海洋表層から採取された有孔虫と有孔虫化石のESR信号強度は,ほとんど同じ値である.これは,ESR測定により有孔虫化石に観察されるMn(II)の信号は,過去の海洋表層の情報を意味し,それが現在まで保存されていることが予想できる.この情報として海洋表層の溶存マンガン濃度が上げられる. g/g)と比べても非常に大きい値であることから,全マンガン量は海底で初期の続成作用の影響を受けた値であることを示唆している.にもかかわらず,プランクトンネットで海洋表層から採取された有孔虫と有孔虫化石のESR信号強度は,ほとんど同じ値である.これは,ESR測定により有孔虫化石に観察されるMn(II)の信号は,過去の海洋表層の情報を意味し,それが現在まで保存されていることが予想できる.この情報として海洋表層の溶存マンガン濃度が上げられる. 本研究の目的は,『浮遊性有孔虫が炭酸カルシウムの殻を生成する際,海水中のMn濃度に比例してMn(II)が取り込まれている』という仮説を証明することと,すでに堆積年代が与えられている有孔虫試料についてESR測定を行なうことで過去の海洋表層におけるマンガン濃度を復元し,その時系列変動と気候変動と関係を調べることにある. [方法] 仮説を証明する手段として無機的な炭酸カルシウムを合成実験を採用した.溶液中の濃度が,0〜100nMとなるようにMnC12を添加した0.1M(mol/l)CaCl2水溶液(pH=7.8):200mlに,0.4MのNa2CO3の水溶液(pH=11):50mlを滴下させ,炭酸カルシウムの結晶を合成した.実験により,生成された炭酸カルシウムの結晶内に取り込まれるMn(II)と最初溶液に添加したMnCl2濃度との関係をESR測定で明らかにする. [堆積物試料] 東京大学海洋研究所白鳳丸KH90-3,KH94-4,KH96-3の各航海及び淡青丸KT92-17の航海で得られた深海底堆積物中に含まれる浮遊性有孔虫をESR測定用の試料とした.各航海で採取された海域は,それぞれ,KH90-3;オントンジャワ(OJ)海台,KH94-4;タスマン海台(TSP),KH96-3;シャツキー(SKY)海台,KT92-17;四国海盆(SHB)であり,酸素同位体比による堆積年代がOkada(1992),Ikehara(1997),Yamane and Oba(1998)MS,Ahagon(1996)によって与えられている.オントンジャワとタスマン海台の堆積物は,おもに円石藻と有孔虫からなる石灰質軟泥である.四国海盆とシャツキー海台の堆積物は,数枚の火山灰層を挟んだ半遠洋性堆積物である. ESR測定用の試料は,粒子サイズが250〜350 mの浮遊性有孔虫の殻50mgである.Mn(II)に起因する信号の内,左端の信号を測定の対象とした(図1).測定条件は,;マイクロ波:9.5GHz,1mW;測定磁場幅:310±5mT;変調磁場:100kHz,0.05mT;増幅:2000;掃引時間:8min;応答時間:0.3secと設定した. mの浮遊性有孔虫の殻50mgである.Mn(II)に起因する信号の内,左端の信号を測定の対象とした(図1).測定条件は,;マイクロ波:9.5GHz,1mW;測定磁場幅:310±5mT;変調磁場:100kHz,0.05mT;増幅:2000;掃引時間:8min;応答時間:0.3secと設定した. 1993年8月から測定し続けている有孔虫化石試料(OJ:127kyr)を標準<Mn(II)=116.5>とし,一つの試料に対して3回の測定を行い,その平均値を標準思量を用いて補正した値をESR信号強度と定義した. [結果と考察] 炭酸カルシウムの合成実験の結果は,添加したMn量に対して結晶中にESRで観察されるMn(II)の量が増加傾向を示すが,比例関係ではない.この理由として,高pHかつ低Mn濃度の水溶液中において,Mn(II)はすぐに酸化されて水溶液中から除去されてしまう(Wilson,1980).実際,水溶液中に存在するMn(II)は,実験が進行するにしたがって,添加したMn量よりもかなり少なくなっていると解釈される. したがってCa(OH)2を用いた実験はかなりの量が酸化されてしまったことになる. CL-methodによる分析では,添加したMn量が10nMのとき,結晶中に取り込まれた全Mn量は1.04 g/gという試薬に近い値を示し,さらにESR信号強度は,58.3とほぼ試薬と同じ値である.このことは,合成実験で生成された炭酸カルシウムには酸化によるの吸着が含まれていると考察できる. g/gという試薬に近い値を示し,さらにESR信号強度は,58.3とほぼ試薬と同じ値である.このことは,合成実験で生成された炭酸カルシウムには酸化によるの吸着が含まれていると考察できる. ここで和光の特級試薬(0.25 g/g,ESR=53)中に観察されるMn(II)が,酸化による吸着を含んでいないとしたら,その濃度(C: g/g,ESR=53)中に観察されるMn(II)が,酸化による吸着を含んでいないとしたら,その濃度(C: g/g)は, g/g)は,  と求めることができる. 図2にオントンジャワ海台の堆積物中に含まれる浮遊性有孔虫のESR測定の結果の一例を示した.横軸は酸素同位体比の変動曲線から求められた堆積年代である(Okada,1992).太線は有孔虫に観察されたMn(II)のESR信号強度の変動を示し,細線は気候変動のよい環境指標となる酸素同位体比の変動曲線である.グラフ中のグレーの部分は氷期,白い部分は間氷期にそれぞれ対応している.Mn(II)の信号は氷期に強くなる傾向が顕著に見られる.この理由として氷期には,赤道域と極域の温度較差が大きくなり,大気中から外洋域に運ばれるエアロゾルの量が増加して,それに伴って運ばれてくるMnの量が増えたと解釈することができる.近年,Shiller(1997)は,大西洋の海洋表層Mn濃度分布がダストフラックスの分布とよく似ていることを示している. 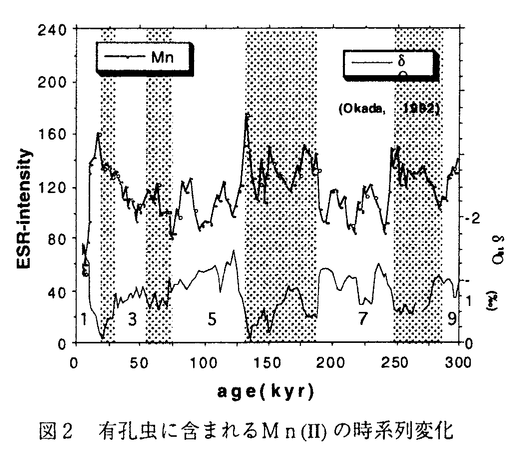 図2 有孔虫に含まれるMn(II)の時系列変化 図2 有孔虫に含まれるMn(II)の時系列変化 各海域の表層堆積物中に含まれる有孔虫のMn(II)は,オントンジャワ海台[0.9]:60,タスマン海台[1.0]:70,シャツキー[2.0]:340,四国海盆[2.2]:350となる.[]内の数値は,Klinkhammer and bennder(1980)によって示された海洋表層Mnの濃度から推定した各海域の海洋表層のMn濃度を推定した値である.わずか4サイトではあるが,有孔虫のMn(II)と海洋表層Mn濃度は非常によく,一致している. [まとめ] 浮遊性有孔虫化石に含まれるマンガンは,海底で初期に続成作用により表面に吸着したものである.炭酸カルシウム試薬に観察されるMn(II)は,CaCO3中のMn濃度を反映しているとするとESR信号強度=100が観察される有孔虫の殻に取り込まれたMn量は,0.5 g/gと求めることができる. g/gと求めることができる. ラフではあるが海洋表層マンガンの濃度と,表層堆積物中に含まれる有効虫の殻のMn(II)との間には,比例関係に近い正の相関がある. 堆積物中に含まれる浮遊性有孔虫のESR測定により,過去の海洋表層のMn濃度を求めることができる可能性を示すことができた.さらに |