| 内容要旨 | | はじめに 1985年に発見された球殻状炭素分子フラーレンは,超伝導,半導体特性を示す新素材として工学的応用が期待されている.原子状態となった炭素が見事な対称性をもつ構造を自発的に形成するメカニズムについて,これまでに様々なモデルが提案されているが,いずれが現実的であるかは未だ明らかとなっていない.このような理論的興味と同時に,高効率生成法の開発のためにも生成機構の解明は重要課題である. 著者は,フラーレン生成機構の探求を目的とし,比較的長時間に渡る構造形成過程を計算可能な分子動力学法を用いて,クラスター成長過程のシミュレーションを行った.更に金属原子をケージ構造内に含む金属内包フラーレンに問題を拡張し,炭素クラスター成長過程における金属原子の効果について詳細に検討した. 中空フラーレン系のシミュレーション 炭素原子間相互作用に関してはBrennerのポテンシャルを用い,温度制御法については,系内のクラスターの運動を並進,回転,振動の運動エネルギーに分離し,各平均温度に対して0.1ps毎に制御温度Tcとの差を60%に縮小するよう独立にスケーリングを施す方法を用いた. 全方向に周期境界条件を科した一辺342Åの立方体のセルに,500個の炭素原子をランダムに配置し,制御温度Tc=3000Kでシミュレーションを行った.計算開始から2500ps後に実現されたケージ状のC70クラスターについて,成長履歴の概略を図1に表現した.例えば,約1900〜2000psの間では独立に存在していたC60とC8が約2000psで合体してC68になったという過程が示されている.C20以下の前駆体は,鎖状,単環状の極めて単純な構造をとっており,C30程度に成長する段階で三次元的な構造に変化する.その後C40以上に成長しケージ構造を模索するが,歪みの小さい閉じた構造を形成するには炭素原子数が足りず大きな孔が残る.C50程度で初めて閉じたフラーレンに近い構造となり,さらに成長を続ける. また,図中C60,C70が比較的長時間に渡ってその大きさを維持していることが分かるが,これはケージ構造にアニールすることで,衝突断面積が大幅に減少し,他のクラスターとの衝突確率が大きく低下するためである.一旦ケージ構造をとると,非衝突の時間帯が長くなり,より安定な構造にアニールすることが可能となる. 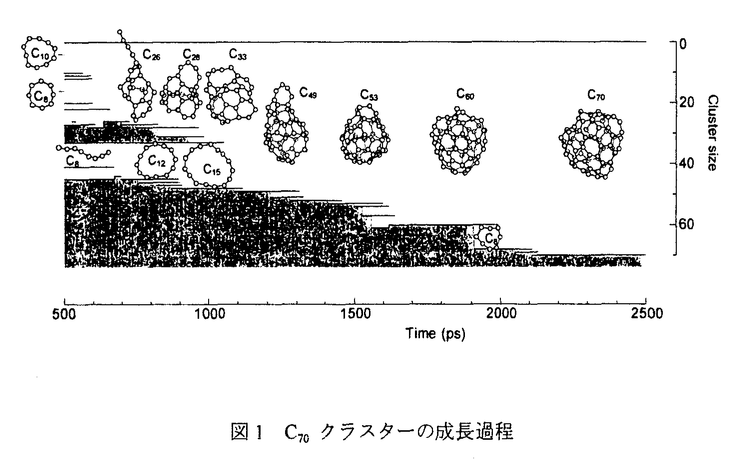 図1 C70クラスターの成長過程 図1 C70クラスターの成長過程 実験的にはフラーレン生成に要する時間は数10〜100 s以上と見積もられるが,図1の計算では,実際の生成環境と比較して3桁程度高い炭素原子密度を仮定して衝突頻度を増加させ,その分急速に冷却することで成長を促進している.このため,比較的長期間孤立していたケージ構造のC60でさえ構造のアニールは十分ではない.そこで,図1のシミュレーションで得られたケージ構造のC60を独立に取り出し高温に保つことで仮想的にアニール時間を与え,その効果を見積もった.図2に初期構造と215ns以降の構造変化を示す.初期的には,ダングリングボンドを持つ原子,七,八員環,隣接する五員環群(影付き)を含み,完全なフラーレン構造とはかけはなれたものであったが,アニールによる構造変換を経て,215ns以降,五員環を移動し,221.7nsで切頭二十面体構造の完全なフラーレン構造C60に至った.この間,クラスター中では主にStone-Wales変換と呼ばれる系統的な構造変化が観察されたが,この変換反応速度に関してArrehenius型の温度依存性が成り立つとすると,シミュレーションの2500K,50nsというアニール条件は,現実の実験条件と比較して矛盾しないことが分かった.更に,図1中のC70構造に関しても,同様なアニールにより完全なフラーレン構造へと変換されることが確認された. s以上と見積もられるが,図1の計算では,実際の生成環境と比較して3桁程度高い炭素原子密度を仮定して衝突頻度を増加させ,その分急速に冷却することで成長を促進している.このため,比較的長期間孤立していたケージ構造のC60でさえ構造のアニールは十分ではない.そこで,図1のシミュレーションで得られたケージ構造のC60を独立に取り出し高温に保つことで仮想的にアニール時間を与え,その効果を見積もった.図2に初期構造と215ns以降の構造変化を示す.初期的には,ダングリングボンドを持つ原子,七,八員環,隣接する五員環群(影付き)を含み,完全なフラーレン構造とはかけはなれたものであったが,アニールによる構造変換を経て,215ns以降,五員環を移動し,221.7nsで切頭二十面体構造の完全なフラーレン構造C60に至った.この間,クラスター中では主にStone-Wales変換と呼ばれる系統的な構造変化が観察されたが,この変換反応速度に関してArrehenius型の温度依存性が成り立つとすると,シミュレーションの2500K,50nsというアニール条件は,現実の実験条件と比較して矛盾しないことが分かった.更に,図1中のC70構造に関しても,同様なアニールにより完全なフラーレン構造へと変換されることが確認された. 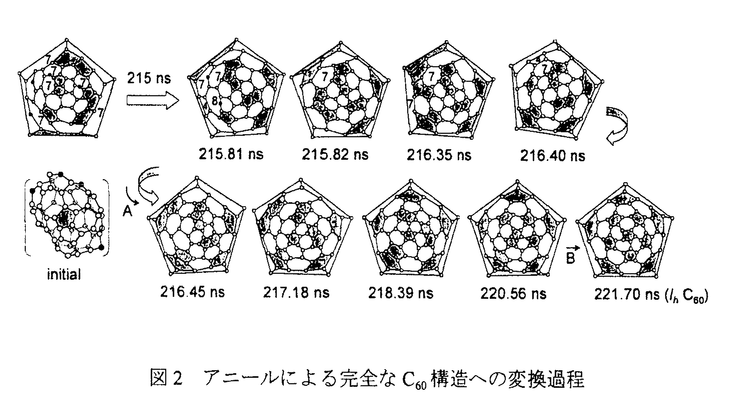 図2アニールによる完全なC60構造への変換過程 図2アニールによる完全なC60構造への変換過程 ここまでで,ある特定の温度条件においてフラーレン構造の生成が可能であることがシミュレートされたが,一つの大きな疑問点は,他のグラファイトやダイヤモンド構造に対してフラーレン構造が選択される条件があるかということである.そこで,同様の初期条件を用い,制御温度Tc=1000〜6000Kの範囲でシミュレーションを行った際の,成長するクラスター形状と制御温度の関係を図3にまとめた.制御温度Tc<2500Kの低温環境下ではグラファイト的平面構造を,2500K<Tc<3500K程度では,フラーレン的ケージ構造,更にTc>3500Kの高温環境下では,三次元的なランダム構造をとる.  図3クラスター構造に対する制御温度の影響 図3クラスター構造に対する制御温度の影響 以上の結果に加え,温度,時間スケールに関して検討し構築したフラーレン生成モデルを図4に示す.クラスターが成長する際,C10程度までは鎖状,C20程度までは環状構造をとり,その後,C30程度までは平面的構造が大半となるが,少しずつ三次元的な構造が増え,およそC30を境に三次元的な構造が平面的なものを凌駕し不完全ケージ構造を好むようになる.ここで,系の温度が低い場合には三次元的な形とならずに平面的なまま順次成長して最終的にグラファイトとなり,逆に高温の場合には三次元的なランダムな形状になりこれを解きほぐすことが困難となる.この中間の適当な温度条件で不完全なケージ状となるが,C50程度の大きさまでは原子数が足りないため閉じることができず大穴が残る.ここに小さなクラスターが加わり,ほぼ閉じたケージ構造といえる形でさらに成長しながら5/6面体を目指したアニールが進み,ちょうどC60となると初めてIPR(Isolated Pentagon Rule)を満たすフラーレン構造をとりうる.十分にアニーリングが可能な温度で比較的小さなクラスターの付加反応が頻繁に起こると考えると,ほとんどのクラスターがC60まで成長してそれ以上の付加反応を拒否する.ちょうどC60とならなかった場合には更に反応が進み,次にIPRを満たすC70まで成長し,これも失敗すると高次フラーレンとなる.  図4フラーレン生成機構モデル炭素金属混合系のシミュレーション 図4フラーレン生成機構モデル炭素金属混合系のシミュレーション ランタンなどの遷移金属原子を炭素ケージ内に含む金属内包フラーレンは,単層炭素ナノチューブと並んで広く注目を集めており,実験・理論,両面からのアプローチにより,その構造,電子状態などが明らかになりつつあるが,絶対的な生成量が少なく未知な点が多い.ここでは,金属内包フラーレン生成メカニズムの解明に先立ち,金属元素としてLa,Sc,Niを取り上げ同様のシミュレーションを行い,クラスタリング過程における金属原子の効果について詳細に検討した. 炭素-炭素原子間相互作用ポテンシャルに関しては前述と同様である.一方,金属-炭素,金属-金属間ポテンシャルに関しては,シミュレーションの前段階として,小型のクラスターMCn(M:La,Sc,Ni)について密度汎関数法により計算を行い,様々な形状で結合エネルギー,電荷分布を求めた.これらの結果に基づき,金属原子周辺の炭素原子数(配位数)として表現し,金属原子から炭素系への電荷移動によるクーロン相互作用を考慮した多体ポテンシャル関数を構築した.図5に配位数ごとの金属-炭素間ポテンシャルEb,クーロン力項Vc,および金属二量体間のポテンシャルの形状を示す.これらはVcの値により定性的に,クーロン力が強い場合(La),弱い場合(Sc),無視できる場合(Ni)として分類できる. 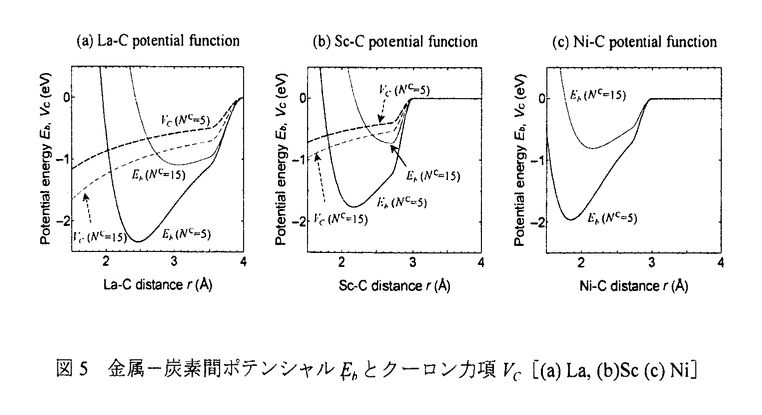 図5金属-炭素間ポテンシャルEbとクーロン力項Vc[(a)La,(b)Sc(c)Ni] 図5金属-炭素間ポテンシャルEbとクーロン力項Vc[(a)La,(b)Sc(c)Ni] 中空の系と同様に一辺342Åの立方体のセルに,500個の炭素原子と5個のLa原子をランダムに配置し,制御温度Tc=3000Kで計算を行った.図6(a)に示すようにLaC4以下の前駆体は,鎖状の炭素クラスターがLa原子を取り巻く構造(fan-type)LaC5以上のサイズでは,炭素クラスター自体は環状の構造をとるようになり,La原子は環の上部の位置に付着する.更にLaC18程度以降は炭素クラスターが多重環構造に変形するが,この際,各炭素原子との間にクーロン力による引力が働くため,炭素クラスターに曲率が生じ,この半球殻状の構造(open-cap)を保ちながらランタン原子を包み込むように成長する.その後,LaC35〜42程度でちょうど半球程度になり,LaC60程度のサイズで概ね閉じたケージ構造をとることになる. 一方,金属原子としてScを用いた場合,図6(b)に示すようにLa系と比較してクーロン力が小さいため,ScCn(20<n<40)の領域において,Sc原子が炭素クラスターの構造には大きく影響していないことが分かる.ScC43程度で三次元的open-cage構造にアニールするが,このサイズではSc原子はケージ構造の開端部に付着し,その後,Sc@C54程度でケージを閉じる直前に,内部にすべり込むかたちで内包される. また,金属原子として現在のところ実験的にはフラーレンケージに内包されないと考えられているNiを用いた場合,図6(c)に示すようにSc系と非常に類似したクラスター成長過程をとる.しかし,最終段階でSc原子がケージ構造に内包されたのに対し,クーロン相互作用の無いNi原子の場合には七員環,八員環といったケージ構造の欠陥部に付着し,その内外を行き来しする様子がみられ,内部に安定に留まることはなかった.  図6金属炭素混合クラスターの成長過程[(a)La,(b)Sc(c)Ni] 図6金属炭素混合クラスターの成長過程[(a)La,(b)Sc(c)Ni] |
| 審査要旨 | | 本論文は「フラーレン生成機構に関する分子動力学シミュレーション」と題し,新しい球殻状炭素分子フラーレンに関して,一旦は原子状態となった炭素が高い対称性をもつフラーレン構造や金属原子を内包したフラーレン構造を自己形成するメカニズムを,分子動力学法シミュレーションを用いて理論的に研究したものであり,論文は全4章よりなっている. 第1章は,「序論」であり,本研究と関連して,フラーレンの工学的応用,従来の研究,従来提案されているフラーレン生成機構モデルと分子シミュレーションによる研究の目的について述べている. 第2章は,「中空フラーレン系のシミュレーション」であり,純粋な炭素のクラスタリング過程をシミュレートし,フラーレン構造が生成する機構について述べている.分子動力学法シミュレーションに用いるポテンシャルの選択と独特の時間圧縮手法によるシミュレーション手法を記述し,孤立炭素原子状態からのクラスタリング過程のシミュレーションにおける中間体の構造を詳細に検討している.3000K程度の高温条件下においては,C20以下で鎖状,単環状の極めて単純な構造をとりC30程度で三次元的な構造に変化,その後C40以上で開いたケージ構造,C50程度で初めて閉じたフラーレンに近い構造を経てC60程度のサイズのケージ構造が自発的に形成されることを示している.また,計算時間圧縮のため課した高密度条件を考慮し,途中段階で生成するC60のケージ構造を独立に取り出し仮想的に非衝突時間を与えることで,アニールの効果を見積もっている.この過程において,初期的には,七,八員環,隣接する五員環群を含み,完全なフラーレンとはかけはなれたC60クラスターが,アニールによる構造変換を経て,約200ns後に切頭二十面体構造の完全なフラーレン構造C60に至ることを実証している.また,この過程における主要な結合変換過程であるStone-Wales変換についてアレニウス的な反応速度を見積もり,シミュレーションと実験的温度,時間スケールとの相関について考察している.同様にC70についても完全なフラーレン構造の形成を再現している.さらに,成長するクラスター形状と制御温度の関係について整理し,制御温度Tc<2500Kの低温環境下ではグラファイト的平面構造を,2500K<Tc<3500K程度では,フラーレン的ケージ構造,更にTc>3500Kの高温環境下では,三次元的なランダム構造をとり,更に高温では熱エネルギーによる解離のため,C20以下の鎖状,単環状構造程度までしか成長しないことが示されている.最後に,クラスター成長過程の中間体構造に対する温度の影響を踏まえ,シミュレーション結果に基づくフラーレン生成機構の新しいモデルを提案し,既存のモデル,過去の実験結果と比較検討がなされている. 第3章は,「炭素金属混合系のシミュレーション」であり,金属元素としてLa,Sc,Niを取り上げ,これらの金属を内包するフラーレンが生成される過程に関する分子動力学法シミュレーションについて述べている.シミュレーションの前段階として,炭素-金属,金属-金属間ポテンシャル関数の定式化が試みられている.具体的には,様々な形状の小型のクラスターMCn(M:La,Sc,Ni)について密度汎関数法により求めた結合エネルギー,電荷分布をもとに,金属原子から炭素系への電荷移動によるクーロン相互作用を考慮した多体ポテンシャル関数が構築されている.これらのポテンシャルを用い,実験と同様に炭素原子のみの系に1%の金属原子を加えた条件で分子動力学シミュレーションが行われている.金属原子としてLaを用いた場合,強いクーロン相互作用により,炭素クラスターがLaを包む開いたキャップ構造を拡張しながら球殻構造を形成していく様子が示されている.一方,金属原子としてScを用いた場合,La系と比較してクーロン力が小さいため,ScCn(n<40)の領域において,Sc原子が炭素クラスターの構造には大きく影響せず中空の場合と同様な成長過程を辿り,Sc@C50-60程度でケージ構造を閉じる直前に内部にすべり込むかたちで内包されている.また,クーロン相互作用のないNi原子の場合には,Sc混合系と同様の成長プロセスを辿るものの,最終段階でもケージ構造に内包されることなく七員環,八員環といったケージ構造の欠陥部に付着し,ケージの内外を行き来する様子がみられ,内部に安定に留まることがないことを明らかとした. 第4章は「結論」であり,上記の研究結果をまとめたものである. 以上要するに,本論文は分子動力学法シミュレーションによりフラーレン類の生成機構に関する重要な知見を与えており,分子熱工学の発展に寄与するものと考えられる.よって本論文は博士(工学)の学位請求論文として合格と認められる. |