1.緒言 ウランの地球化学的挙動を知るには、U(VI)イオンの吸着挙動を定性的かつ定量的に把握することが必要となる。表面錯体モデルに対するフィッティングでは、U(VI)イオンは6価のままの形で吸着し、さらに加水分解や炭酸錯体を形成したU(VI)イオンは配位子を伴ったまま吸着するものであるとされている。しかし、鉱物表面に吸着したU(VI)イオンが4価に還元される現象なども報告されている。
固液界面において実際に元素の酸化数が変化したか否か、あるいは配位子が離脱したか否かを決定するのは一般には極めて困難であるが、赤外線吸収分光法、ラマン散乱分光法はいずれも振動分光法の一種であり、試料の形状を問わずin situに固液界面の分子の振動を観測することがきる手法として、吸着メカニズムの解明への応用が期待されている。
本研究においては、ラマン分光法により金属コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのO=U=O対称伸縮振動(v1)波数を観測し、そのpH依存性などより吸着メカニズムの解明を行うことを試みたほか、同位体効果や偏光特性を利用してラマンスペクトル中のピークの帰属を試みた。さらに、金属の種類により違いが観られる吸着メカニズムを、量子化学的手法により解明することを試みた。
2.ラマン分光法による金属コロイド表面へのウランの吸着挙動の解明 目的 金属コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのラマンスペクトルを測定し、U(VI)イオンの吸着のメカニズムを解明することを目的とした。
実験 実験はすべて大気開放系で行った。容積15mlのパイレックスチューブに、コロイド分散溶液(銀コロイド、金コロイド)を5ml入れ、その上に硝酸ウラニル溶液(U:1.0×10-1M)を30 l加え、次にpH調整のための硝酸溶液または水酸化ナトリウム水溶液を加えた。このパイレックスチューブを恒温振盪器に入れ、温度を25℃に保ちながら15〜48時間振盪した。振盪後、沈殿を分離するために遠心分離を行った後、チューブ中の分散溶液のpHを測定した。pH測定後、分散溶液約4mlを全面透明無蛍光石英セルに採取し、そのラマンスペクトルの測定を行った。
l加え、次にpH調整のための硝酸溶液または水酸化ナトリウム水溶液を加えた。このパイレックスチューブを恒温振盪器に入れ、温度を25℃に保ちながら15〜48時間振盪した。振盪後、沈殿を分離するために遠心分離を行った後、チューブ中の分散溶液のpHを測定した。pH測定後、分散溶液約4mlを全面透明無蛍光石英セルに採取し、そのラマンスペクトルの測定を行った。
銀コロイド表面への吸着試験 pH2.75においてU(VI)イオンを吸着させた銀コロイド分散溶液のラマンスペクトルを波数範囲200〜1200cm-1について測定した。その結果、798cm-1、1050cm-1および1650cm-1にピークが観測された。しかし、1050cm-1のピークは硝酸イオンに、1650cm-1のピークは水分子に帰属されるため、798cm-1のピークが吸着したU(VI)イオンに帰属すると考えられる。pH2.75の溶液中においてU(VI)イオンはUO22+イオンとして存在し、そのラマン活性な振動はO=U=O対称伸縮振動(v1)のみであり、この振動は溶存イオンの場合は870cm-1に観測される。銀コロイド表面への吸着によって、これが798cm-1に大きくシフトしたことがわかる。このような大きなシフトは、U(VI)イオンの銀コロイド表面への吸着が、イオン交換などではなく、吸着物質からU(VI)イオンへの電子密度の移動に伴う強い相互作用に基づいたものであることを示唆している。
図1に種々のpHにおける実験で観測されたラマンスペクトルを示す。pHが4〜5付近においては、785cm-1付近と830cm-1付近にほぼ同じ高さのピークが2つ見られる。この2つのピークはpHの変化に伴い若干シフトはするものの殆ど位置は変わらないが、pHが高くなるにつれて785cm-1付近のピークの相対的な強度が強くなる。pHが10付近になると、830cm-1付近のピークは殆ど見えなくなり代わって870cm-1付近に新しいピークが現れるほか、785cm-1のピークが765cm-1付近に大きくシフトする。さらにpHが高くなると765cm-1のピークが751cm-1付近までシフトする。
 図1:銀コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのラマンスペクトルのpH変化
図1:銀コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのラマンスペクトルのpH変化 pHを細かく変化させてピークの位置の変化を調べた結果を図2に示す。pHの変化全体を通して恒に750〜800cm-1の間に出現するピークがv1に帰属されると考えられる。このピークはpHの変化によって離散的に値を変えており、その変化は次のように分類できると考えられる。pH2付近〜pH4付近(798cm-1)、pH5付近〜pH8付近(785cm-1)、pH8付近〜pH10付近(765cm-1)、pH10付近〜pH12付近(751cm-1)。上記のような4つの領域に分けて考え、それぞれの領域中においてはpHの上昇に伴いラマン波数が微妙に小さくなるpH依存性はあるものの、全体としてラマン波数は4つの値を取るものだと考えられる。
 図2:銀コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのラマン波数のpH依存性
図2:銀コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのラマン波数のpH依存性 上記のラマン波数の変化は、pHの変化によるU(VI)イオンの溶存種の変化と対応づけて考えることができる。すなわち、U(VI)イオンの溶存種はpHの変化に伴い変化するが、溶存種の変化にともなって銀コロイド表面に吸着したU(VI)イオンの化学形が変化するため、ラマン波数の位置も変化するものと考えられる。図3に大気開放系(炭酸ガス圧10-3.5atm)、U(VI)初期濃度6.0×10-4M(実験初期濃度)におけるU(VI)イオン化学形を、OECDデータバンクのデータを利用して計算した結果を示す。
 図3:実験条件下でのU(VI)イオン化学形と溶解度のpH変化
図3:実験条件下でのU(VI)イオン化学形と溶解度のpH変化 この図より、U(VI)イオンの化学形はpHにより、pH4以下(UO22+)、pH5付近〜pH8付近(UO2(OH)2)0、PH8付近〜pH10付近(UO2(CO3)2)2-、pH10以上(UO2(CO3)3)4-と分類することができ、これは750〜800cm-1に観測されるv1のラマン波数の位置により分類した前述のpHの分類と対応していることがわかる。もしU(VI)イオンがpHに関係なく常に同じ化学形で銀コロイド表面に吸着しているとすれば(たとえば常に配位子を解放してUO22+の形で吸着するなど)、ラマン波数がpHの変化によって離散的に値を変えることは考えられない。したがって、加水分解反応や炭酸錯体を形成したU(VI)イオンは銀コロイド表面に吸着する際に、配位子を伴ったまま吸着していると考えられる。
次にスペクトル中に見られる他のピークについて考える。図2において、pHが4〜5付近においては、780cm-1付近と830cm-1付近にほぼ同じ高さのピークが2つ見られ、pHが高くなるにつれて780cm-1付近のピークの相対的な強度が高くなり、830cm-1付近のピークは次第に弱くなることは本節最初の記述の通りである。この830cm-1付近のピークであるが、その帰属についてはいくつかの可能性が指摘され、(1)O=U=Oの非対称伸縮振動(v2)や変角振動(v3)(いずれも本来ラマン禁制である)(2)Uの配位子内の振動、Uと配位子間の振動(U-Oeq振動)(3)溶解できていないUの沈殿による振動、などが挙げられる。
しかし、このpH域での実験では同じ試料溶液のラマンスペクトルを続けて数回測ると、780cm-1付近のピークは殆ど変化がないのに対し830cm-1付近のピークは次第に強度が弱くなる。830cm-1のピークが仮に上記の(1)や(2)に因るものであるとすれば、このピークと780cm-1のピークの強度比は恒に一定の値を示すはずである。したがって、この830cm-1のピークは(3)の銀コロイド表面に吸着したU(VI)の沈殿を観測している可能性が高く、この沈殿は単に物理的な力で銀コロイド表面に吸着しているためレーザー光照射により乖離すると考えられる。一方、化学吸着して銀コロイド表面に強く吸着しているU(VI)イオンはレーザー光を照射しても容易には乖離しないと考えられる。
次に、さらにpHが高いときに観られる870cm-1付近のピークについても考える。このピークは同じ試料溶液を数回続けて測っても大きな変化は見られず、レーザー光照射に対して比較的安定性が高いと考えられる。したがってこのピークは(3)の可能性は低く、(1)か(2)のいずれかであると考えられる。しかし、O=U=Oの直線型構造が配位子の配位によって曲がることはなく、したがって直線型では本来ラマン不活性なV2やV3が、たとえ銀コロイド表面に吸着したU(VI)イオンにおいてでも観測されうる可能性は殆どない。このことから(1)の可能性は否定されたといえる。また、このピークはU(VI)イオンが炭酸錯体を形成し始めるpH域より現れ始めることからも、U(VI)イオンの炭酸錯体形成が関係した振動である可能性が高い。以上の理由から870cm-1付近に見られるピークは炭酸配位子内の振動、もしくはUとequatorial面で配位結合している炭酸配位子のOとの間の振動(U-Oeq振動)を見ている可能性が高いと考えられるが、U-Oeq振動はU-Oax2振動に較べると極めて弱い振動であるため、そのピークは200cm-1付近に現れるものであると考えられ、従ってこのピークは炭酸配位子内の振動であると見られる。しかし、炭酸配位子内の具体的にどの振動に帰属されるかは、以上の実験結果のみからでは明確ではない。
金コロイドへの吸着試験 様々なpHにおいて、金コロイドにU(VI)イオンを吸着させた場合のラマンスペクトルを、図4に示す。これらの結果はすべて一様に798cm-1にピークを示しており、金コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのラマン波数がpHに依らないことを示している。
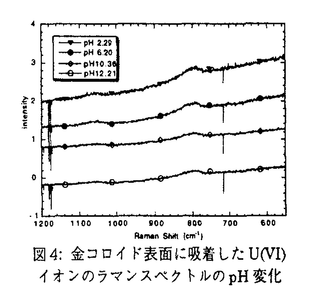 図4:金コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのラマンスペクトルのpH変化
図4:金コロイド表面に吸着したU(VI)イオンのラマンスペクトルのpH変化 金コロイドについても、吸着によってラマン波数が大きく短波数側にシフトしたことから、金コロイドとU(VI)イオンの間の強い相互作用によって、吸着がおきているのがわかる。金コロイドと銀コロイドとの大きな違いは、金コロイドではpH2からpH12の幅広い範囲のpHに対して、同じ798cm-1ラマン波数を示していることであり、U(VI)イオンは金コロイドに対して、分散溶液のpHに関係なく同じ吸着構造をしていることがわかる。pH4付近以上の溶液中では、U(VI)イオンは加水分解種あるいは炭酸錯体を形成していることから、金コロイドに対する吸着では、吸着にともないすべての配位子が解放されていることがわかる。金コロイドにおいて観測された798cm-1という値が、銀コロイドの場合の低pH(pH4以下)での吸着の際のU(VI)イオンの波数と同じ値である点も、注目すべきであると考えられる。すなわち、U(VI)イオンの銀コロイドに対する低pH領域における吸着と、金コロイドに対する全pH域における吸着構造が同じである可能性が高いことが示唆される。
3.ウランの吸着挙動の解明に対する量子化学計算の適用可能性 目的 金属コロイドの種類により違いが見られるU(VI)イオンの吸着挙動を解明するために、量子化学計算の適用可能性を検討することを目的とした。
計算 計算には、量子化学計算コードMulliken2.0を使用し、abinitio Hartree Fock(HF)計算を行った。基底関数には6-31Gを使用し、Uの計算には有効内殻ポテンシャル(ECP)近似を用いた。
計算内容 HF法により、いくつかのU(VI)錯体のv1波数の計算を行った。第一水和水の存在を考慮した計算などもおこない、実測値との比較から、両者の相関性などについて検討を行った。
結果 まず、U(VI)錯体のV1波数の計算結果を実測値と併せて表1に示す。計算値の右に小さく記した値は、実測値より波数が何%高く計算されたかを示す。
 表1 v1波数の実測値と計算値の比較
表1 v1波数の実測値と計算値の比較 HF計算では電子相関が考慮されていないため、結合が実際より強く計算される。このため結合長が短くなり、全体的に波数が実測値より高く計算される傾向を示す。まず、水和水を考慮した計算では、水和水の存在を無視した計算に比べて、波数が実測値に大きく近づいていることがわかる。これは、水和水の存在を無視した場合、U=O結合が実際より短く見積もられてしまうことに因る。次に、水和水を考慮しない計算においては、配位子の数が増すと、計算値と実測値のずれが小さくなる傾向が見られる。これは、配位子の数が増加していくとUに配位する水和水の数が減少していくため、結果として計算上「無視」される水和水の数が減少していくため、実測値に近づいていくと考えられる。さらに、水和水を考慮しない計算において、例えば配位子の数が同じ1個であるUO2(OH)+、UO2Cl0、UO2F0の計算値と実測値のずれを比較するといずれも28〜29%と近い値を示しており、これは水和水を考慮しない計算でも、配位子の数が同じであれば実測値とのずれは配位子の種類に依らずに同じ程度であることを示している。この結果は、計算上水和水の存在を無視することが、波数の値に結果的にどの程度の数値的な影響を及ぼすかが、おおむね予測可能であり、そのためにはまずいろいろな系での実測値と計算値の相関性を調べることが必要であることを示唆するものである。
本研究の結果は、量子化学計算による構造最適化、ラマン波数計算、によって得られるラマン波数の値はやや高い値ではあるものの、実測値と一定の相関性が見いだされることを明らかにした。このことは、例えば実測値によって得られたラマン波数から逆に吸着構造をおおまかに予測することも可能であることを示唆するものであり、銀コロイドおよび金コロイドに対するU(VI)イオンの吸着構造、および両コロイドで異なると見られる吸着メカニズムの解明に量子化学的手法が有効であることが実証された。