学位論文要旨
| No | 114726 | |
| 著者(漢字) | 久保田,尚之 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | クボタ,ヒサユキ | |
| 標題(和) | 熱帯海洋上の対流活動の日変化 | |
| 標題(洋) | ||
| 報告番号 | 114726 | |
| 報告番号 | 甲14726 | |
| 学位授与日 | 1999.09.30 | |
| 学位種別 | 課程博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 博理第3663号 | |
| 研究科 | 理学系研究科 | |
| 専攻 | 地球惑星物理学専攻 | |
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 熱帯の雲活動は潜熱の放出や放射との相互作用を通じて大気大循環と気候において重要な役割を果たしている。熱帯では雲は多くの積雲を含んだ雲集団に組織化されて、対流活動を形成している。このような積雲対流活動は波動や渦と結び付きながら、様々な時間・空間スケールで変動している。その中ではっきりした外的要因のある唯一の周期変動が日変化であり、熱帯対流活動の様々な時間変動と関連して、重要な位置を占めている可能性が考えられる。ただ、熱帯海洋上では詳細な観測が少ないため、対流活動の日変化とそれに伴う循環の鉛直構造などが明らかとなっていないのが現状である。また、これらの観測結果をもとにした系統的な数値実験も十分に行なわれていない。 本研究では、まずこれまではっきりと示されていない対流活動の日変化の鉛直構造を、熱帯西部太平洋で行なわれたTOGA-COAREの集中観測の詳細なデータを用いて解析することにより明らかにする。また、海洋上の対流活動の日変化のメカニズムを明らかにするため、集中観測の結果をもとに、領域大気モデルを用いた数値実験を行なう。そこでは、これまでに示された日変化のメカニズムを系統的な比較実験を行ない検討し、その結果から、妥当と思われる日変化のメカニズムを指摘する。さらに、以上のような結果に基づいて対流活動の発達する過程について詳しく考察する。 TOGA-COARE(1992年11月-1993年2月)の集中観測データのうちレーダデータ(2.0S,156.0E)を降水量に換算して用いた。IFA(Intensive Flux Array)領域の5地点の1日4回の高層観測データ、1時間間隔の海洋ブイデータ(2.0S,156.0E)を用いた。また、静止気象衛星「ひまわり」のTBBデータを1°×1°で5K間隔で平均したヒストグラムデータを用いた。さらに海洋地球観測船「みらい」の1998年6月16-23日に(0-5N,156.0E)で得られた3時間間隔の高層観測データを用いた。 本研究で用いた領域大気モデルRAMS(Pielke et al.,1992)は圧縮性非静力学方程式系からなり、氷を含んだ雲物理過程(Walko et al.,1995)を入れ、放射コード(Nakajima et al.,1995)はk-distribution法に基づいて計算を行なった。領域は東西400km,鉛直30kmの2次元cyclicモデルで、格子間隔は水平2km,鉛直に41層である。TOGA-COAREのIFA領域の1992年12月平均の温度と水蒸気の鉛直分布を東西一様な初期値とした。大規模収束と12月平均の東西風の鉛直分布を東西一様に与えている。(case studyでは鉛直67層,1998年6月21日00Zの温度と水蒸気を初期値とし、大規模収束は入れていない)。下の境界条件は海面としSST=302.5Kで固定した。 対流活動の日変化は海洋大陸域の陸上で夕方から夜にピークが現れた。それに対して、島周辺海域や熱帯西部太平洋の収束帯では、高い雲頂高度でみた場合には午前中から昼頃にピークが現れ、雲頂高度の低い雲の活動のピークとなる時間は、高い雲頂温度の雲とは異なることが明らかとなった。TOGA-COARE観測域では、降水量は0時過ぎに最大となり、午前中に減少し、昼頃に最小となる。強い降水が観測された期間により顕著な日変化が現れた。対流活動は0-3時頃にTBB190K付近まで発達し、この最も低いTBBのピークとなる時刻は、降水量のピークの時刻ととほぼ一致する。この対流活動が活発となる20時から6時頃にかけては、750hPaより上層でIFA領域で平均した上昇流が観測されている。降水量の朝から昼頃にかけての減少に対応して、低いTBBをもつ雲の活動度が徐々に弱くなった。発達の初期の16時頃には下層1km以下で水蒸気が増加している。この時期には、下層雲が多く観測され、また下層で平均上昇流が現れている。この夕方の下層での水蒸気の増加が、夜間に発達に何らかの役割を果たしていることが推測される。 TOGA-COAREの観測をもとに標準実験(STND)を行ない、3時頃に降水量が最大となり、日中は少ない日変化が再現された。標準実験(STND)の雲による放射冷却の日変化をみると、上層雲だけでなく、下層の500m付近に境界層雲とみられる雲による放射冷却が夜間に強く現れることがわかった。 過去に示された日変化のメカニズムを系統的に検討し、対流活動の日変化を引き起こすメカニズムを調べた。まずGray and Jacobson(1977)の主張する夜間に雲域とその周辺域での水平方向の放射冷却の違いが、対流活動の日変化を引き起こす仮説を検討し、一様雲水量実験(UNICLD)を行なった。この結果、夜間に降水が最大となる日変化が再現され、日変化を引き起こす主要因ではないことが考えられる。それに対してRandall et al.(1991)は上層雲の放射冷却による不安定化が重要であると主張している。雲放射冷却除去実験(NOCLDR)では日変化が再現されず、彼らの示す雲の放射冷却の効果と整合的である。だが、一様雲水量実験(UNICLD)では夜間の雲による放射冷却が対流圏上層だけでなく、境界層雲の存在のために境界層上端でも大きくなっていた。そこで、境界層上端での放射冷却を取り去り、上層雲による放射加熱・冷却を与えた実験(境界層上端放射冷却除去実験;NOPBLR)を行なった。その結果、一様雲水量実験(UNICLD)と比べて日変化の振幅は小さくなり、雲にともなう上層の放射冷却で不安定化するメカニズムに関して、その効果は弱いということを示している。もう1つの説としてSui et al.(1998)は夜間に相対湿度が増加することにより夜に対流活動が活発になると推測している。そこで標準実験(STND)に対応した温度の日変化を与える気温強制日変化実験(TEMFRC)を行なった。その結果、降水量の日変化は再現されなかった。 これらの結果から対流活動の日変化を引き起こす要因として重要なのは、境界層上端付近での強い放射冷却であることが示唆された。 数値実験で再現された日変化を引き起こすのに重要な役割を果たしている下層雲、特に境界層雲が熱帯西部太平洋の対流活発域において実際に存在するのかを調べた。観測船「みらい」の観測から500m付近に夜間に相対湿度の高い層が現れ、2000m付近までの高湿度層が拡大することがわかった。これが数値実験で現れた境界層雲とその発達する対流雲に対応する可能性が考えられる。観測船「みらい」の観測をもとに数値実験で再現し、対流の発達過程を見ると、境界層雲が現れた18時頃は熱的に不安定にも関わらず深い対流へと発達せず、0時以降の同じような条件において発達している。その間2km付近までの温度が低下し、水蒸気が増加することにより、相対湿度が増加していた。下層の水蒸気を増加させる役割として、境界層雲の放射冷却により乱流が強まり、境界層からの水蒸気が上に輸送されることが考えられる。つまり、熱的に不安定となるだけでなく、2km付近の高度までの相対湿度が高いことが深い対流へと発達するには重要であることが示唆された。 熱帯西部太平洋で行なわれたTOGA-COAREの集中観測から、夕方に下層雲が現れ、夜半頃に最も活発となる対流活動の日変化が明らかとなった。この観測結果をもとに数値実験から対流活動の日変化を再現した。また、これまで示された日変化のメカニズムを数値実験で検討した。Gray and Jacobson(1977)の主張する雲域と周辺域での夜間の放射冷却の違いによる効果、Randall et al.(1991)の主張する雲に伴う対流圏上層の放射冷却による鉛直不安定化、Sui et al.(1998)が主張する放射冷却で夜間気温が下がり相対湿度が増加する効果は、いずれも日変化を引こ起こすメカニズムの決定的な原因としては弱いことが示された。本研究では日変化のメカニズムを明らかにするため、対流活動の発達過程に着目した。その結果、夜間に境界層雲が発生し、その放射冷却により乱流が強められる。乱流によって水蒸気が境界層雲より上へ運ばれ、下層が湿ることが重要となる(図1)。つまり、熱的に不安定となるだけでなく、2km付近の高度までの相対湿度が大きいことが深い対流へと発達するには重要であると示唆された。さらに、日変化を引き起こす環境場として大規模収束により大気が不安定化し、蒸発が多く、このため下層の水蒸気が多くなり不安定化することが重要であることがわかった。 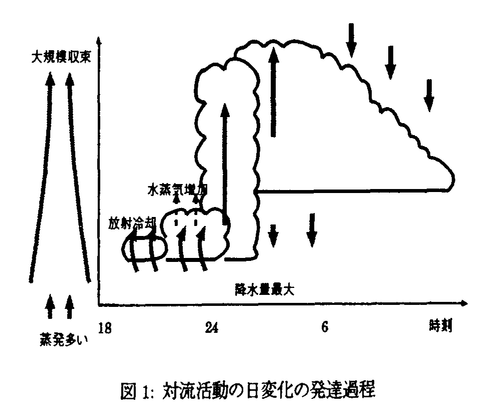 | |
| 審査要旨 | 降水を伴う対流活動が日変化を示すことは,陸上に関しては,午後から夕方に降雨が最大となることや日射が地面を暖めることなど、そのメカニズムも含めて比較的よく知られている.しかし,海洋上での日変化については,その存在自体は以前から知られていたものの,密な観測も少なく,その鉛直構造などについては,あまりよくわかっていなかった.また日変化のメカニズムについても,過去にいくつかの研究はあるものの,広く受け入れられるような説明はなされていないのが現状である. 本研究は,熱帯海洋上のTOGA COARE集中観測データ(1992年11月-93年2月)や海洋地球観測船「みらい」からのデータ(1998年6月)を解析し,対流活動の日変化の実態,特にその鉛直構造を明らかにすると共に,数値モデルを用いて日変化を再現し,日変化に対する境界層付近の雲の放射冷却の重要性と,それが日変化を引き起こすメカニズムを明らかにした優れた研究である.また,これまでの研究で示唆されていたメカニズムはいづれも不十分(または不適切)であることも,系統的な比較実験によって明らかにしている. 本論文は3部から構成されている.まず第2章では,熱帯西部太平洋で行われたTOGA COARE観測で得られた高層ゾンデ,レーダ,海上ブイ等のデータと気象衛星のデータとを解析し,日変化の実態を明らかにしている.まず、日変化が,海洋大陸域だけでなく島周辺の海域や熱帯収束帯,南太平洋収束帯などでもみられることを気象衛星データから確認した。さらに、これまでの研究では、対流活動や降雨は早朝から午前中にかけて最も活発であることが知られていたが、TOGA COARE観測領域では,やや早い時刻(真夜中すぎ)に対流が活発になり降水もピークをもっことを指摘した.次に,気象衛星による放射黒体温度のヒストグラムデータによる雲頂温度の頻度の日変化の解析から,従来の研究でははっきりしなかった日変化に伴う対流活動の鉛直構造に関する知見を得た.さらに,高層ゾンデ観測のコンポジット解析により,気温,水蒸気,鉛直流などの鉛直分布の日変化を明らかにした.それらの結果から,夕方ころに下層2km以下で水蒸気が増加することをきっかけとして下層雲が生じ、これが夜の背の高い対流や降雨に重要な役割を果たしていることを示した. 第3章では,数値モデルを用いて,TOGA COAREのデータをもとに2次元の数値実験を行い,対流活動の日変化を再現することに成功した.さらに、過去の研究で示唆されたいくつかのメカニズムを検討するために系統的な比較実験を行い,その妥当性を調べた.すなわち,放射冷却が雲の内外で異なるための水平温度傾度の重要性,上層の放射冷却による不安定化の重要性,温度の日変化に伴い相対湿度が夜間に高くなることの重要性など、過去の研究で論じられたこれらのメカニズムはいずれも日変化を引き起こす主な原因ではないことを示した.さらに,大きなスケールの収束に伴う冷却と加湿が対流活動域に存在することや、海上風が強く海面からの蒸発が多い状況であることが、日変化の再現に重要であることを示した.これらの効果を考慮しないと対流が不活発となり,日変化がはっきりとは現われなくなるが,これは観測結果とも整合的である. 第4章では,3章で示した境界層雲に伴う放射冷却の重要性,また,実際に境界層雲が存在するのかを明らかにするために,「みらい」からのデータと数値モデルを用いて議論している.観測データによれば,夕方ころに境界層内の高度500m付近に相対湿度の高い層が現われ,夜間に拡大して高度1.5kmまでに及ぶ.この観測データは境界層での雲が夕方から夜間にかけて多いことを示唆しており,3章の数値実験の結果をサポートする.次に、この観測された状況を数値実験で再現し,境界層雲が対流活動に与える影響について詳しく調べた.夕方18時頃に境界層雲が形成されたが,大きな潜在不安定(対流有効位置エネルギー,CAPE)の存在にもかかわらず,このときには背の高い対流には成長しなかった.背の高い対流へと成長したのは,その後高度2km程度まで相対湿度が大きくなった真夜中(0時)以降であり,2時すぎに降水の最大をひきおこした.この数値実験の結果から,大きな潜在不安定だけではなく,高度2km程度までの大気の湿潤化が対流の成長の重要な要因であることを示唆すると共に,この湿潤化のメカニズムとして,境界層雲ができること、そして夜間にその境界層雲上部での放射冷却により乱流が強化され,それによって水蒸気が上方に輸送される過程の重要性を明らかにした.日中は太陽放射の吸収がありこのメカニズムが働かないことが,対流活動の日変化をひきおこす原因であることを示唆している. 以上のように,本研究は熱帯海洋上での対流活動の日変化に関し,新たな知見を与える優れた研究である.本研究は,日変化そのものの理解を大きく前進させたばかりでなく,対流活動の発達のプロセスに関する示唆も含み,さらに近年注目されている対流活動の2日周期の変動や季節内振動の解明の基礎としても大きな意義をもつものである. なお,本研究の一部(第2章)は故新田勍氏との共同研究であるが,論文提出者が主体となって分析および検証を行ったもので,論文提出者の寄与が十分であると判断される. したがって,博士(理学)を授与できると認める. | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/54110 |