| 内容要旨 | | 序文 近年,様々な物質系において「光誘起相転移」とよばれる現象が実験的に見出されている.この現象の舞台となるのは,一次相転移の転移温度,転移圧力近傍のように,幾つかの相が(準)安定に存在するような系である.具体的には, 共役ポリマー(ポリジアセチレン)の主鎖構造転移,スピンクロスオーバー錯体の低スピン高スピン転移,電荷移動錯体(TTF-CA)の中性イオン性転移などである.このような系に励起状態を光注入すると,光励起前のもとの相と光により注入される新しい相とがエネルギー的にほぼ縮退しているため,僅かな量の光励起によって大域的な相変化を引き起こし得る.これは,通常の絶縁体や半導体のように,基底状態と励起状態との区別が明瞭な系における光励起では見られない独特の現象である.これらの現象は,注入された相の寿命が長い場合(永続的相転移)と有限の寿命でもとの相に戻る場合(過渡的ドメイン注入)とに大別されるが,これらをまとめて「光誘起相転移」と称している.このように,平衡状態の統計力学で用いられているのとはやや異なった意味合いで「相転移」という言葉が用いられていることに注意が必要である. 共役ポリマー(ポリジアセチレン)の主鎖構造転移,スピンクロスオーバー錯体の低スピン高スピン転移,電荷移動錯体(TTF-CA)の中性イオン性転移などである.このような系に励起状態を光注入すると,光励起前のもとの相と光により注入される新しい相とがエネルギー的にほぼ縮退しているため,僅かな量の光励起によって大域的な相変化を引き起こし得る.これは,通常の絶縁体や半導体のように,基底状態と励起状態との区別が明瞭な系における光励起では見られない独特の現象である.これらの現象は,注入された相の寿命が長い場合(永続的相転移)と有限の寿命でもとの相に戻る場合(過渡的ドメイン注入)とに大別されるが,これらをまとめて「光誘起相転移」と称している.このように,平衡状態の統計力学で用いられているのとはやや異なった意味合いで「相転移」という言葉が用いられていることに注意が必要である. これらの物質においては,多重安定性の原因や協力現象を誘起する相互作用が全く異なっているが,この現象に共通して見られる特徴が幾つか存在する.(i)一つのフォトン当たりの変換効率が大きい.光誘起中性イオン性転移の例では,一つのフォトン当たり310個のドナー・アクセプター対を中性からイオン性に変換すると見積もられている.(ii)注入励起量に対する応答が非線型であり,ドメイン注入に必要なしきい値が存在する.つまり,しきい値以下の励起量ではドメイン注入を起こせず,それ以上の励起があった場合にのみドメインを注入し得る.(iii)ドメイン注入の前に潜伏時間が存在し,潜伏時間の後に急に新しい相の注入が進行して行く.以上の特徴は,物質を構成している各サイト間の相互作用の重要性を反映している. 先程,各々の物質において,多重安定性の原因や協力現象を誘起する相互作用が異なっていると記した.具体的には, 共役ポリマーではパイエルス転移によって二通りの安定な主鎖構造がもたらされており,電子-格子相互作用が協力現象の源になっていると捉えることができる.また,スピンクロスオーバー錯体においては,低スピン状態と高スピン状態における錯体の体積の違いによる弾性的相互作用が錯体間相互作用を担っている.一方,電荷移動錯体においては,(中性相から見て)イオン化することによるイオン化エネルギーの損とマーデルングエネルギーの得との拮抗が多重安定性の原因となっており,電子相関が協力現象の主因であると考えることができる.但し,この物質は電荷移動に関して一次元的であること,かつイオン性相では各サイトにスピンの自由度があることのために二量体化に対する不安定性もあり(スピンパイエルス転移),複雑な転移である. 共役ポリマーではパイエルス転移によって二通りの安定な主鎖構造がもたらされており,電子-格子相互作用が協力現象の源になっていると捉えることができる.また,スピンクロスオーバー錯体においては,低スピン状態と高スピン状態における錯体の体積の違いによる弾性的相互作用が錯体間相互作用を担っている.一方,電荷移動錯体においては,(中性相から見て)イオン化することによるイオン化エネルギーの損とマーデルングエネルギーの得との拮抗が多重安定性の原因となっており,電子相関が協力現象の主因であると考えることができる.但し,この物質は電荷移動に関して一次元的であること,かつイオン性相では各サイトにスピンの自由度があることのために二量体化に対する不安定性もあり(スピンパイエルス転移),複雑な転移である. このように,光誘起相転移の舞台は多様であるために,これらの現象を統一的な視点から理論的に理解するのは難しく各物質に基づいて理論的研究がなされている.現時点で最も良く理解が進んでいるのは一次元電子-格子系である.そこでは電子相関の無い電子-格子系のモデル(SSHモデル)によって,基底状態や光注入された電子正孔対の緩和経路などが断熱ポテンシャルを用いて解析され,電子正孔対がソリトン対に緩和する様子などが議論された.更に,このモデルに電子相関をとり込むことにより,白金錯体などの系も議論されている.ところが,電子相関によって駆動される系に関しては,現時点では理論的に解明されていない.そこで本研究では,電子相関によって多重安定性がもたらされている系における光誘起ダイナミクスを議論し,先に述べた特徴が如何に記述されるかという点を明らかにすることを目的とする.具体的な系としては,電荷移動錯体TTF-CAの中性イオン性転移を対象とする. モデル 電荷移動錯体TTF-CAは,スタック軸方向にドナー分子(TTF)とアクセプタ分子(CA)とが交互に積層しており,電子の移動はスタック軸方向に限られた擬一次元系である.以下では,ドナーのHOMO軌道とアクセプタのLUMO軌道にある電子のみに注目し,次のmodified Hubbard Hamiltonianを出発点として用いる.  但し奇数サイトはドナー(D)サイトのHOMO軌道,偶数サイトはアクセプタ(A)サイトのLUMO軌道に対応し, , , , , はj番めのサイトの はj番めのサイトの ( ( 又は 又は )スピンの電子に対する消滅,生成,個数演算子である.qjは,奇数のjに対しては2-nj,偶数のjに対しては-njと定義され,j番めの錯体の電荷を表している.電子の数はサイトの数に等しく,これをNで表す.各パラメータの意味は次の通りである. )スピンの電子に対する消滅,生成,個数演算子である.qjは,奇数のjに対しては2-nj,偶数のjに対しては-njと定義され,j番めの錯体の電荷を表している.電子の数はサイトの数に等しく,これをNで表す.各パラメータの意味は次の通りである. :ドナー軌道とアクセプタ軌道とのエネルギー差,U:オンサイトクーロン力,V|i-j|:サイト間クーロン力,T:重なり積分.このモデルは,適当なパラメータの選択の下で,中性(N)相とイオン性(I)相とを安定状態としてもっており(図1参照),電子相関により多重安定性がもたらされている様子を良く記述できる.(I相に関してはスピン自由度に由来する縮退があり,低エネルギーの振る舞いは反強磁性ハイゼンベルグモデルで記述される.本研究では,錯体結晶のスタック間相互作用に由来する異方性があるものと仮定し,I相をネール状態で記述する.) :ドナー軌道とアクセプタ軌道とのエネルギー差,U:オンサイトクーロン力,V|i-j|:サイト間クーロン力,T:重なり積分.このモデルは,適当なパラメータの選択の下で,中性(N)相とイオン性(I)相とを安定状態としてもっており(図1参照),電子相関により多重安定性がもたらされている様子を良く記述できる.(I相に関してはスピン自由度に由来する縮退があり,低エネルギーの振る舞いは反強磁性ハイゼンベルグモデルで記述される.本研究では,錯体結晶のスタック間相互作用に由来する異方性があるものと仮定し,I相をネール状態で記述する.)  図1:N相,1相における電子配置.奇数サイトがドナー,偶数サイトがアクセプターに対応する. 図1:N相,1相における電子配置.奇数サイトがドナー,偶数サイトがアクセプターに対応する. 実際のサイト間クーロン力は距離に依存した複雑な形をしているが,本研究では,以下の二つの相補的極限を扱う.一つは最近接サイト間だけを考える短距離極限(V|i-j|=V |i-j|,1)であり,これを |i-j|,1)であり,これを UVTモデルとよぶ.これによって,励起状態増殖の局所的機構が明らかになる.もう一つは,マーデルング定数M=(V1+V-1)-(V2+V-2)+…を保ったまま距離を無限大にする長距離極限(V1=V3=… UVTモデルとよぶ.これによって,励起状態増殖の局所的機構が明らかになる.もう一つは,マーデルング定数M=(V1+V-1)-(V2+V-2)+…を保ったまま距離を無限大にする長距離極限(V1=V3=… ,V2=V4=… ,V2=V4=… ;但し ;但し =M)であり,これを =M)であり,これを UMTモデルとよぶ.これによって,系の中の電子全体による平均場的な効果が明らかにされる. UMTモデルとよぶ.これによって,系の中の電子全体による平均場的な効果が明らかにされる.  UVTモデルでのダイナミクス UVTモデルでのダイナミクス まず UVTそデルにおける光誘起ダイナミクスについて考察する.但し,最も典型的な場合として,N相とI相がエネルギー的に縮退している状況( UVTそデルにおける光誘起ダイナミクスについて考察する.但し,最も典型的な場合として,N相とI相がエネルギー的に縮退している状況( -U=2V)を考える.この場合,T=0とした古典的極限をとればすぐにわかるように,電荷移動励起子の数よりもNI相境界の数の方が系の励起状態を指定するのに適していることがわかる.つまり,この系における基本的素励起はNI相境界である.相境界に励起エネルギーが局在しているという点では,この励起状態はポリマー中でのソリトン励起と類似している.T≠0の場合には,この相境界がバンド運動をするが,それをTに関する一次の摂動で取り扱う.初期条件として,N相又はI相中に一つの電荷移動励起子が注入された状態を用い,この状態からのコヒーレントな時間発展を調べる.以下の議論が成立する時間領域は -U=2V)を考える.この場合,T=0とした古典的極限をとればすぐにわかるように,電荷移動励起子の数よりもNI相境界の数の方が系の励起状態を指定するのに適していることがわかる.つまり,この系における基本的素励起はNI相境界である.相境界に励起エネルギーが局在しているという点では,この励起状態はポリマー中でのソリトン励起と類似している.T≠0の場合には,この相境界がバンド運動をするが,それをTに関する一次の摂動で取り扱う.初期条件として,N相又はI相中に一つの電荷移動励起子が注入された状態を用い,この状態からのコヒーレントな時間発展を調べる.以下の議論が成立する時間領域は である.その結果得られる物理的描像は以下の通りである(図2参照). である.その結果得られる物理的描像は以下の通りである(図2参照).  図2: 図2: UVTモデルにおける,電荷移動励起子注入後のダイナミクス.(a)N相から,(b)I相から. UVTモデルにおける,電荷移動励起子注入後のダイナミクス.(a)N相から,(b)I相から. (i)N相からの時間発展:一つの電荷移動(D→A)励起子注入に伴って,ドミノ倒し的にドナーサイトからアクセプタサイトへの電荷移動が誘起される.その際,移動される電子のスピンはランダムに選択される.また,I相領域は定速(-サイト当たり大体 )で広がってゆき,一つの電荷移動により大きなI相ドメインの注入がなされる. )で広がってゆき,一つの電荷移動により大きなI相ドメインの注入がなされる. (ii)I相からの時間発展:一つの電荷移動(A→D)励起子注入に伴って,平均して2〜3個のA→Dへの電荷移動と1〜2個のD→Aへの電荷移動が誘起される.つまり、N相領域は局所的にしか広がらない. 以上が UVTそデルより得られる励起状態の自己増殖の局所的機構である. UVTそデルより得られる励起状態の自己増殖の局所的機構である.  UMTモデルでのダイナミクス UMTモデルでのダイナミクス 次に UMTモデルにおける光誘起ダイナミクスについて考察する.T=0とした古典的極限での考察から,この系での基本的素励起は電子正孔対であることが分かる.この点を考慮して,このHamiltonianを波数表示( UMTモデルにおける光誘起ダイナミクスについて考察する.T=0とした古典的極限での考察から,この系での基本的素励起は電子正孔対であることが分かる.この点を考慮して,このHamiltonianを波数表示( )で書き換え,Unrestricted Hartree-Fock近似を行い電子間相互作用を一粒子状態のエネルギーに繰り込むことにより,次の有効Hamiltonianを得る. )で書き換え,Unrestricted Hartree-Fock近似を行い電子間相互作用を一粒子状態のエネルギーに繰り込むことにより,次の有効Hamiltonianを得る.  但し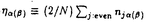 は は ( ( )スピン電子の電荷移動度(アクセプタサイトにある割合)であり,一粒子状態のエネルギーは )スピン電子の電荷移動度(アクセプタサイトにある割合)であり,一粒子状態のエネルギーは で与えられる.N相とI相とが多重安定に存在するようなパラメータの下では, で与えられる.N相とI相とが多重安定に存在するようなパラメータの下では, と と で表される一粒子状態のエネルギーの逆転が電荷移動度 で表される一粒子状態のエネルギーの逆転が電荷移動度 に依存して二次元的に起こっている.このような系では,両者のエネルギー差が重なり積分T程度に小さくなる領域において,励起状態の自己増殖が起こることが簡単に示すことができる.例として,時刻r=0に, に依存して二次元的に起こっている.このような系では,両者のエネルギー差が重なり積分T程度に小さくなる領域において,励起状態の自己増殖が起こることが簡単に示すことができる.例として,時刻r=0に, スピンの電子正孔対を スピンの電子正孔対を , , スピンの電子正孔対を スピンの電子正孔対を だけN相又はI相中に光注入した,という理想的な初期条件の場合をとりあげ,それによって誘起されるダイナミクスを以下にまとめる だけN相又はI相中に光注入した,という理想的な初期条件の場合をとりあげ,それによって誘起されるダイナミクスを以下にまとめる (i)I相からの時間発展:励起量( )が小さい時には( )が小さい時には( )の小さな振動しか誘起されない,つまり電荷移動は殆ど起こらない.ところが, )の小さな振動しか誘起されない,つまり電荷移動は殆ど起こらない.ところが, 又は 又は があるしきい値を超えると,I相からN相への巨視的電荷移動が誘起される. があるしきい値を超えると,I相からN相への巨視的電荷移動が誘起される. スピン励起と スピン励起と スピン励起は相反転の誘起に建設的に働く. スピン励起は相反転の誘起に建設的に働く. (ii)N相からの時間発展:励起量( )が小さい時にはやはり電荷移動は殆ど起こらない.しかし, )が小さい時にはやはり電荷移動は殆ど起こらない.しかし, と と の差があるしきい値を超えると,N相からI相への巨視的電荷移動が誘起される. の差があるしきい値を超えると,N相からI相への巨視的電荷移動が誘起される. スピン励起と スピン励起と スピン励起は相反転の誘起に非建設的に働く. スピン励起は相反転の誘起に非建設的に働く.  図3: 図3: UMTモデルにおける,励起量と相反転との関係.(a)N相から,(b)I相から. UMTモデルにおける,励起量と相反転との関係.(a)N相から,(b)I相から. 以上のように,系全体の電子の平均場的な相互作用により,光注入された励起量に対して誘起される電荷移動量が非線型に応答し,しきい値的振る舞いを生み出すとうことが UMTモデルにより明らかにされた. UMTモデルにより明らかにされた. 結論 結論として,光による励起状態注入後に、系に内在する電荷移動相互作用Tを介して電荷移動が進行する二つの機構を示した.一つは UVTモデルにより記述される局所的機構であり,もう一つは UVTモデルにより記述される局所的機構であり,もう一つは UMTモデルにより記述される平均場的機構である.これら二つの機構から,電荷移動錯体中の光誘起ダイナミクスに関して,以下に述べるような描倣を得た.N相中に光注入された電荷移動励起子は,局所的機構によりドミノ倒し的に広がり,大きなI相領域に成長する. UMTモデルにより記述される平均場的機構である.これら二つの機構から,電荷移動錯体中の光誘起ダイナミクスに関して,以下に述べるような描倣を得た.N相中に光注入された電荷移動励起子は,局所的機構によりドミノ倒し的に広がり,大きなI相領域に成長する. スピン電子と スピン電子と スピン電子の電荷移動度の差が大きい場合には,平均場的効果によって,電荷移動度の大きい方のスピンの電子の電荷移動が助長され,I相への相反転に至る.一方,I相中に光注入された電荷移動励起子は,局所的機構によってはあまり増殖しない.しかし,平均場的効果としては,それらは全てN相への相反転に建設的に働き,あるしきい値を超えると相反転に至る.このように,電子相関のみによって多重安定性がもたらされている系においても,序文のなかで示したような光誘起相転移の一般的な特徴が現れることが示された.但し,TTF-CAのような-次元系においては電子(スピン)-格子相互作用も重要であり,電子相関のみの効果は高次元の系でより顕著になると期待される. スピン電子の電荷移動度の差が大きい場合には,平均場的効果によって,電荷移動度の大きい方のスピンの電子の電荷移動が助長され,I相への相反転に至る.一方,I相中に光注入された電荷移動励起子は,局所的機構によってはあまり増殖しない.しかし,平均場的効果としては,それらは全てN相への相反転に建設的に働き,あるしきい値を超えると相反転に至る.このように,電子相関のみによって多重安定性がもたらされている系においても,序文のなかで示したような光誘起相転移の一般的な特徴が現れることが示された.但し,TTF-CAのような-次元系においては電子(スピン)-格子相互作用も重要であり,電子相関のみの効果は高次元の系でより顕著になると期待される. 今後の課題は多岐にわたるが.現実の物質(TTF-CA)ではI相においてスピン揺らぎによる二量体化が生じており,I→N転移の初期段階として逆スピンパイエルス機構が働いていると考えられることから,電子格子相互作用の導入が特に重要である.また,位相緩和やエネルギー散逸の効果も考慮されるべきである. |