擬2次元有機導体(ET)2X(ET=BEDT-TTF)は多様な電子状態をとることが知られている。閉殻なX-の層に挟まれたET層は平均価数が1/2+であり全てのET分子が等価ならば1/4充填の バンドをもつ。ET分子は面内で非常に多様な配列をとり(この配列の違いはpolytypeと呼ばれ バンドをもつ。ET分子は面内で非常に多様な配列をとり(この配列の違いはpolytypeと呼ばれ 、 、 、 、 、 、 等のギリシャ文字で分類される)、それに起因する分子間遷移積分の異方性における多様性と、さらに強い電子間クーロン相互作用によりこの系は様々な基底状態を示す。この物質群のうち、最近電荷整列を起こすものが2つ見つかった: 等のギリシャ文字で分類される)、それに起因する分子間遷移積分の異方性における多様性と、さらに強い電子間クーロン相互作用によりこの系は様々な基底状態を示す。この物質群のうち、最近電荷整列を起こすものが2つ見つかった: -(ET)2I3と -(ET)2I3と -(ET)2RbZn(SCN)4である。 -(ET)2RbZn(SCN)4である。 電子相関による1/4充填系の絶縁状態には二つの極限が考えられる。一つは遷移積分の二量体化が大きい時にサイト上クーロン斥力Uの働きによるモット絶縁体であり、この時各二量体に一つずつキャリアが局在する。この場合二量体化により実際バンドは1/2充填となっている。もう一つはサイト間クーロン斥力Vi,jの効果によるウィグナー結晶的な電荷整列である。これらの状態の1次元系での研究は進んでおり、例えば(TMTTF)2XにおいてはTMTTF鎖上の二量体化およびU、Vi,jの競合により両者のの共存状態が提案され、実験的にも最近その存在が確かめられた。 木野・福山は2次元ET系における二量化とUの効果を拡張ヒュッケル法によるET分子間の遷移積分を導入しUを平均場近似で取り扱うことによって系統的に調べる方法を確立し、二量体化が強い 型塩の構造を調べた結果モット絶縁体と解釈できる二量体間の反強磁性絶縁状態がUの値が大きい時に安定化することを示した。さらに上記の 型塩の構造を調べた結果モット絶縁体と解釈できる二量体間の反強磁性絶縁状態がUの値が大きい時に安定化することを示した。さらに上記の -(ET)2I3の構造(図1(a))に対するハバード模型の計算でも電荷整列の傾向をもつことが示されたが、上記の様に電荷整列の研究にはVi,jが重要であり、実際遷移金属酸化物NaV2O5の電荷整列現象の研究においてもVi,jの2次元系での重要性が認識された。よってVi,jをも含めた研究が(ET)2Xにおける電荷整列を理解する上では不可欠となる。そこで本論文では上記の -(ET)2I3の構造(図1(a))に対するハバード模型の計算でも電荷整列の傾向をもつことが示されたが、上記の様に電荷整列の研究にはVi,jが重要であり、実際遷移金属酸化物NaV2O5の電荷整列現象の研究においてもVi,jの2次元系での重要性が認識された。よってVi,jをも含めた研究が(ET)2Xにおける電荷整列を理解する上では不可欠となる。そこで本論文では上記の 型、 型、 型のET系の物性を、木野・福山の枠組みにサイト間クーロン斥力を含めて拡張し、基底状態を調べることにより実験事実の解明を目指す。さらに 型のET系の物性を、木野・福山の枠組みにサイト間クーロン斥力を含めて拡張し、基底状態を調べることにより実験事実の解明を目指す。さらに 型塩も含めて(ET)2X系の統一的理解を得たい。 型塩も含めて(ET)2X系の統一的理解を得たい。  -(ET)2I3はTMI=135Kで金属絶縁体転移を起こし、TMI直下から磁化率は急激に落ちこみスピンギャップの存在が示唆されており最近の13C-NMRの実験でTMI以下で電荷整列が直接観測された。木野・福山の計算による電荷整列のパターンは図1(a)のII鎖上にホールが多いものであったが、この物質の金属絶縁体転移の起源および電荷整列状態における電荷分布のパターンは明らかにされていない。電荷整列が観測されたもうひとつの物質 -(ET)2I3はTMI=135Kで金属絶縁体転移を起こし、TMI直下から磁化率は急激に落ちこみスピンギャップの存在が示唆されており最近の13C-NMRの実験でTMI以下で電荷整列が直接観測された。木野・福山の計算による電荷整列のパターンは図1(a)のII鎖上にホールが多いものであったが、この物質の金属絶縁体転移の起源および電荷整列状態における電荷分布のパターンは明らかにされていない。電荷整列が観測されたもうひとつの物質 -(ET)2RbZn(SCN)4は、一連の -(ET)2RbZn(SCN)4は、一連の 型塩、 型塩、 -(ET)2MM’(SCN)4(以後MM’塩と省略する)の一員である。 -(ET)2MM’(SCN)4(以後MM’塩と省略する)の一員である。 -(ET)2Xは物質によって図2に示すようにいわゆる -(ET)2Xは物質によって図2に示すようにいわゆる 型と呼ばれている構造(b)とET分子の積層方向に二量化を起こした構造(c)(ここではこれを 型と呼ばれている構造(b)とET分子の積層方向に二量化を起こした構造(c)(ここではこれを d型構造と呼ぶ)を持つ二種類の錯体が存在し、それぞれの物性は相異なる。 d型構造と呼ぶ)を持つ二種類の錯体が存在し、それぞれの物性は相異なる。 相では、温度50K〜100Kで電気抵抗が最小値をとり低温では絶縁体的な振る舞いを見せ、磁化率もその温度付近から低温に向かってCurie則的に増加していく。一方 相では、温度50K〜100Kで電気抵抗が最小値をとり低温では絶縁体的な振る舞いを見せ、磁化率もその温度付近から低温に向かってCurie則的に増加していく。一方 d相では、絶縁体的な電気抵抗を示し、磁化率はBonner-Fisher曲線に従うが10K付近以下でスピンギャップ的振る舞いを見せる。電荷整列が発見されたRbZn塩では290Kで d相では、絶縁体的な電気抵抗を示し、磁化率はBonner-Fisher曲線に従うが10K付近以下でスピンギャップ的振る舞いを見せる。電荷整列が発見されたRbZn塩では290Kで 型から 型から d型に構造相転移を起こし、それとともに電荷の不均衡が、すなわち電荷整列がET分子間で起きていることが13C-NMR実験によって明らかにされた。 d型に構造相転移を起こし、それとともに電荷の不均衡が、すなわち電荷整列がET分子間で起きていることが13C-NMR実験によって明らかにされた。  図1: 図1: 型(a)、 型(a)、 型(b)、 型(b)、 d型(c)の(ET)2XにおけるET面内の模式的な構造。楕円と矢印はET分子と遷移積分をそれぞれ表している。(d)は簡易化された(ET)2Xの模型。 d型(c)の(ET)2XにおけるET面内の模式的な構造。楕円と矢印はET分子と遷移積分をそれぞれ表している。(d)は簡易化された(ET)2Xの模型。 ここでは、それぞれの物質の遷移積分の異方性を取り入れた2次元拡張ハバード模型を考え、UおよびVi,jを平均場近似によって取り扱う。サイト間クーロン斥力Vi,jとしては隣接分子間のものを考慮し、得られた解のエネルギーを比較することにより基底状態を決定する。その結果ET系に適切なU=0.7eV、Vi,j=0.15〜0.35eVにおいてストライプ状の電荷整列状態が安定化することが示され、上記の物質の電気抵抗の絶縁体的振る舞いはこの状態の出現によると考えられる。またその電荷分布のパターンは模型のパラメータ、すなわち遷移積分の異方性とVi,jの値に敏感に依ることがわかった。以下にそれぞれの構造すなわち 、 、 d、 d、 型における平均場計算の結果を示し、またそれに基き平均場近似において取り入れられていなかった磁気的量子効果をスピン1/2ハイゼンベルグ模型に電荷整列状態をマップすることにより考慮することにより実際の物質中で実現している電荷パターンを議論する。この際局在スピン間の交換相互作用の大きさJi,jを遷移積分ti,jを用いて関係式Ji,j〜 型における平均場計算の結果を示し、またそれに基き平均場近似において取り入れられていなかった磁気的量子効果をスピン1/2ハイゼンベルグ模型に電荷整列状態をマップすることにより考慮することにより実際の物質中で実現している電荷パターンを議論する。この際局在スピン間の交換相互作用の大きさJi,jを遷移積分ti,jを用いて関係式Ji,j〜 /Uで見積もる。 /Uで見積もる。  型の構造に対する計算結果では、傾向としてVi,jが小さい領域では図2(a)に示すverticalストライプ型の電荷整列状態が、またVi,jが大きい領域では図2(b)に示すdiagonalストライプ型の電荷整列状態が安定化した。実験で観測された磁化率の局在スピン的振る舞いは前者のverticalストライプ型の電荷整列状態の実現に起因していると考えられる。すなわち、1次元ハイゼンベルグ模型を与えるこのストライプ上での交換相互作用の大きさは,Jc〜 型の構造に対する計算結果では、傾向としてVi,jが小さい領域では図2(a)に示すverticalストライプ型の電荷整列状態が、またVi,jが大きい領域では図2(b)に示すdiagonalストライプ型の電荷整列状態が安定化した。実験で観測された磁化率の局在スピン的振る舞いは前者のverticalストライプ型の電荷整列状態の実現に起因していると考えられる。すなわち、1次元ハイゼンベルグ模型を与えるこのストライプ上での交換相互作用の大きさは,Jc〜 /U=10K程度と見積もられ、この小さい値がCurie的な磁化率の原因であると推測できる。さらにこの振る舞いの一因としてNMRの実験より示唆されている大きい電荷揺らぎも考えられる。また光学伝導度の測定もverticalストライプ型の電荷パターンの実現を支持している。 /U=10K程度と見積もられ、この小さい値がCurie的な磁化率の原因であると推測できる。さらにこの振る舞いの一因としてNMRの実験より示唆されている大きい電荷揺らぎも考えられる。また光学伝導度の測定もverticalストライプ型の電荷パターンの実現を支持している。  d型の構造ではVi,jが等方的な場合図2(c)に示すverticalストライプ型の電荷整列状態が安定化する。しかしVi,jの異方性を数%導入すると図2(d)に示すdiagonalストライプ型や図2(e)に示す遷移積分tp4に沿ったhorizontalストライプ型の電荷整列状態のエネルギーがより低くなる。この最後の状態はスピン間の交換相互作用がJp4〜 d型の構造ではVi,jが等方的な場合図2(c)に示すverticalストライプ型の電荷整列状態が安定化する。しかしVi,jの異方性を数%導入すると図2(d)に示すdiagonalストライプ型や図2(e)に示す遷移積分tp4に沿ったhorizontalストライプ型の電荷整列状態のエネルギーがより低くなる。この最後の状態はスピン間の交換相互作用がJp4〜 /U=450Kで与えられる1次元ハイゼンベルグ模型にマップでき、磁化率のBonner-Fisher的振る舞いと合致するので、このtp4に沿ったhorizontalストライプ型の電荷パターンが /U=450Kで与えられる1次元ハイゼンベルグ模型にマップでき、磁化率のBonner-Fisher的振る舞いと合致するので、このtp4に沿ったhorizontalストライプ型の電荷パターンが d相では実現していると演繹できる。13C-NMR実験の解析および光学伝導度の測定もこの電荷パターンを示唆している。すると、10K以下で観測されているスピンギャップはこの1次元ハイゼンベルグ鎖上でのスピンパイエルス転移と理解できる。 d相では実現していると演繹できる。13C-NMR実験の解析および光学伝導度の測定もこの電荷パターンを示唆している。すると、10K以下で観測されているスピンギャップはこの1次元ハイゼンベルグ鎖上でのスピンパイエルス転移と理解できる。  -(ET)2I3の構造に対する計算結果では、Vi,jを増加させていくと図2(f)に示すカラムII上のverticalストライプ型の電荷整列状態から図2(g)に示すカラムI上のverticalストライプ型の電荷整列状態へと基底状態は変化し、さらに図2(h)に示す遷移積分tp2とtp3に沿ったhorizontalストライプ型の電荷パターンの状態が最も低いエネルギーを持つ。このhorizontalストライプ型の電荷整列状態をハイゼンベルグ模型にマップすると、上記の -(ET)2I3の構造に対する計算結果では、Vi,jを増加させていくと図2(f)に示すカラムII上のverticalストライプ型の電荷整列状態から図2(g)に示すカラムI上のverticalストライプ型の電荷整列状態へと基底状態は変化し、さらに図2(h)に示す遷移積分tp2とtp3に沿ったhorizontalストライプ型の電荷パターンの状態が最も低いエネルギーを持つ。このhorizontalストライプ型の電荷整列状態をハイゼンベルグ模型にマップすると、上記の 相や 相や d相と異なり、1次元鎖上の交換相互作用においてJp2〜 d相と異なり、1次元鎖上の交換相互作用においてJp2〜 /U=1100KとJp3〜 /U=1100KとJp3〜 /U=220Kの交替が存在する。 /U=220Kの交替が存在する。 -(ET)2I3の磁化率のTMI直下からのスピンギャップ的振る舞いはこの交換相互作用の交替により理解できる。 -(ET)2I3の磁化率のTMI直下からのスピンギャップ的振る舞いはこの交換相互作用の交替により理解できる。 さらに、これらET系の統一的理解の為、図2(d)に示す構造をもつ模型を調べた。この模型はtp1とtp4を変化させることにより二量体化とバンド間の重なりの度合いをそれぞれ変化させることができ、(ET)2Xの簡易な有効模型として木野・福山が導入したものである。前者によって二量体化が強い 型と弱い 型と弱い d型の間を、後者によってバンド間の重なりが小さい d型の間を、後者によってバンド間の重なりが小さい -(ET)2I3と大きい -(ET)2I3と大きい -(ET)2MHg(SCN)4の間の関係が調べられる。 -(ET)2MHg(SCN)4の間の関係が調べられる。 型はtp=tp1=tp4の場合に当る。この模型の計算においてもVi,jの導入によってストライプ型の電荷整列相が安定化した。V/U=0.25に保ち、U、tp1、tp4を変化させて得られた結果を基にそれぞれの物質の位置を示した相図が図3である。tp1もtp4も小さいほど電荷整列相がより安定となることが明らかとなった。 型はtp=tp1=tp4の場合に当る。この模型の計算においてもVi,jの導入によってストライプ型の電荷整列相が安定化した。V/U=0.25に保ち、U、tp1、tp4を変化させて得られた結果を基にそれぞれの物質の位置を示した相図が図3である。tp1もtp4も小さいほど電荷整列相がより安定となることが明らかとなった。 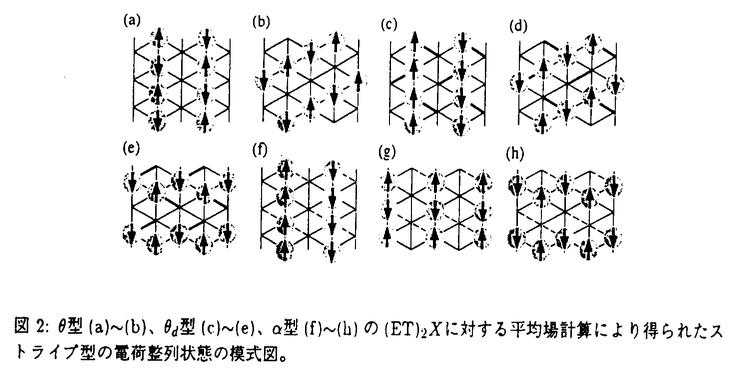 図2: 図2: 型(a)〜(b)、 型(a)〜(b)、 d型(c)〜(e)、 d型(c)〜(e)、 型(f)〜(h)の(ET)2Xに対する平均場計算により得られたストライプ型の電荷整列状態の模式図。 型(f)〜(h)の(ET)2Xに対する平均場計算により得られたストライプ型の電荷整列状態の模式図。 図3:(ET)2Xの統一的相図。PM、dimerAF、COはそれぞれ常磁性金属相、二量体間反強磁性相、電荷整列相を表している。圧力効果も矢印で示されている。 図3:(ET)2Xの統一的相図。PM、dimerAF、COはそれぞれ常磁性金属相、二量体間反強磁性相、電荷整列相を表している。圧力効果も矢印で示されている。 以上、擬2次元有機導体(ET)2Xにおける電荷整列現象をサイト上クーロン斥力Uおよびサイト間クーロン斥力Vi,jを平均場近似によって取り扱い調べた。実際の 型、 型、 d型、 d型、 型物質における遷移積分の異方性を取り入れて計算した結果Vi,jが電荷整列を引き起こすことがわかった。その電荷パターンは遷移積分およびVi,jの異方性によって変化し、 型物質における遷移積分の異方性を取り入れて計算した結果Vi,jが電荷整列を引き起こすことがわかった。その電荷パターンは遷移積分およびVi,jの異方性によって変化し、 型塩ではverticalストライプ状の、 型塩ではverticalストライプ状の、 d型塩ではtp4に沿ったhorizontalストライプ状の、 d型塩ではtp4に沿ったhorizontalストライプ状の、 -(ET)2I3ではtp2とtp3に沿ったhorizontalストライプ状の電荷整列が実現していると提案した。これらの結果をもとに量子効果を適切なS=1/2ハイゼンベルグ模型に移行して考慮することにより実験結果を理解できた。 -(ET)2I3ではtp2とtp3に沿ったhorizontalストライプ状の電荷整列が実現していると提案した。これらの結果をもとに量子効果を適切なS=1/2ハイゼンベルグ模型に移行して考慮することにより実験結果を理解できた。 |