 ハイパー核は、通常の原子核に ハイパー核は、通常の原子核に 粒子を1個含む自然には存在しない新しい特徴的なバリオン多体系を形成する。その分光学的研究は、原子核の深部を探る有効な手段の一つである。通常の原子核では、深い空孔状態を作っても、その状態は非常に不安定で原子核の深部に関する分光学的情報を実験的に得ることは難しい。一方、 粒子を1個含む自然には存在しない新しい特徴的なバリオン多体系を形成する。その分光学的研究は、原子核の深部を探る有効な手段の一つである。通常の原子核では、深い空孔状態を作っても、その状態は非常に不安定で原子核の深部に関する分光学的情報を実験的に得ることは難しい。一方、 ハイパー核では、原子核中の ハイパー核では、原子核中の 粒子は核子からのパウリ原理の効果を受けないので、原子核中を自由に動くことができ、安定した束縛状態を形成する。その基底状態は、弱い相互作用によって崩壊し、その状態幅は非常に狭い。 粒子は核子からのパウリ原理の効果を受けないので、原子核中を自由に動くことができ、安定した束縛状態を形成する。その基底状態は、弱い相互作用によって崩壊し、その状態幅は非常に狭い。 -核子相互作用は、核子-核子相互作用に比べて弱いことが知られているので、励起状態でさえも、その状態幅は100keV以下と見積もられる。 -核子相互作用は、核子-核子相互作用に比べて弱いことが知られているので、励起状態でさえも、その状態幅は100keV以下と見積もられる。 一方、 ハイパー核分光のもう一つの側面としては、その構造研究から ハイパー核分光のもう一つの側面としては、その構造研究から -核子間の2体の相互作用の特徴を導き出すという点が挙げられる。原子核を構成する核子間に働く核力は、中心力、スピン-スピン力、スピン-軌道力、テンソル力などから成る。しかし、その起源に関しては、強い相互作用を記述する量子色力学を基に説明されるに至っていないのが現状である。 -核子間の2体の相互作用の特徴を導き出すという点が挙げられる。原子核を構成する核子間に働く核力は、中心力、スピン-スピン力、スピン-軌道力、テンソル力などから成る。しかし、その起源に関しては、強い相互作用を記述する量子色力学を基に説明されるに至っていないのが現状である。 -核子相互作用の研究は、この核力の問題をSU(3)に拡張したバリオン-バリオン相互作用として扱い直し、新たな核力の描像を確立するための一歩となるものである。 -核子相互作用の研究は、この核力の問題をSU(3)に拡張したバリオン-バリオン相互作用として扱い直し、新たな核力の描像を確立するための一歩となるものである。 軽い質量領域の ハイパー核では、2体の ハイパー核では、2体の -核子相互作用の中で、 -核子相互作用の中で、 粒子のスピンに依存した、スピン-スピン力、スピン-軌道力、テンソル力等が微細なレベル構造に反映される。即ち、それらのスピン依存力によって引き起こされるレベル分離を測定することにより、 粒子のスピンに依存した、スピン-スピン力、スピン-軌道力、テンソル力等が微細なレベル構造に反映される。即ち、それらのスピン依存力によって引き起こされるレベル分離を測定することにより、 -核子相互作用を定量的に議論することが可能である。しかしながら、 -核子相互作用を定量的に議論することが可能である。しかしながら、 -核子相互作用のスピン依存部分は、核子-核子相互作用と比べて非常に小さいことがわかってきており、そのレベル分離を測定するには、数百keV以下のエネルギー分解能が必要とされている。これに関しては、現在、ガンマ線分光の手法を取り入れることにより数keV〜数百keVの高エネルギー分解能での測定が行われつつある。 -核子相互作用のスピン依存部分は、核子-核子相互作用と比べて非常に小さいことがわかってきており、そのレベル分離を測定するには、数百keV以下のエネルギー分解能が必要とされている。これに関しては、現在、ガンマ線分光の手法を取り入れることにより数keV〜数百keVの高エネルギー分解能での測定が行われつつある。 一方、重い ハイパー核では、スピン-スピン力等は平均化され、 ハイパー核では、スピン-スピン力等は平均化され、 ハイパー核の構造にはあまり反映されず、核中の ハイパー核の構造にはあまり反映されず、核中の 粒子の振舞は一体場で近似される。重い 粒子の振舞は一体場で近似される。重い ハイパー核ほど高い角運動量を持つ ハイパー核ほど高い角運動量を持つ 軌道が束縛されるので、スピン-軌道力の存在は、そのレベル構造に強く反映されるはずである。これは、スピン軌道分離の大きさが、通常核の場合と同様に(2l+1)A-2/3に比例することが予想されるからである。Woods-Saxon型ポテンシャルを用いた計算によれば、丁度、 軌道が束縛されるので、スピン-軌道力の存在は、そのレベル構造に強く反映されるはずである。これは、スピン軌道分離の大きさが、通常核の場合と同様に(2l+1)A-2/3に比例することが予想されるからである。Woods-Saxon型ポテンシャルを用いた計算によれば、丁度、 の の -軌道での分離が、 -軌道での分離が、 までの束縛状態の中で最大となることが期待される。たとえ、p殻 までの束縛状態の中で最大となることが期待される。たとえ、p殻 ハイパー核のスピン軌道分離が1MeV以下であっても、 ハイパー核のスピン軌道分離が1MeV以下であっても、 の の -軌道では1.5MeV以上の分離が予想され、十分観測にかかるような大きさになる可能性がある。また、重い -軌道では1.5MeV以上の分離が予想され、十分観測にかかるような大きさになる可能性がある。また、重い ハイパー核ほど深い束縛状態を形成するので、核物質中でのハイペロンの振舞を研究する上で有効である。特に最近では、中性子星中心付近における高密度核物質中に混在するハイペロンが、中性子星の最大質量や超新星爆発後の冷却過程等を研究する上で、重大な役目を持っていることが議論されている。重い ハイパー核ほど深い束縛状態を形成するので、核物質中でのハイペロンの振舞を研究する上で有効である。特に最近では、中性子星中心付近における高密度核物質中に混在するハイペロンが、中性子星の最大質量や超新星爆発後の冷却過程等を研究する上で、重大な役目を持っていることが議論されている。重い ハイパー核から得られる ハイパー核から得られる 粒子の一体ポテンシャルの深さや核物質中での有効質量などのパラメータは、このような中性子星の諸性質に関する議論をより現実的なものにする可能性がある。 粒子の一体ポテンシャルの深さや核物質中での有効質量などのパラメータは、このような中性子星の諸性質に関する議論をより現実的なものにする可能性がある。 しかしながら、これまでの重い ハイパー核の分光学的研究は、実験的困難のために進展してこなかった。その理由の一つは、 ハイパー核の分光学的研究は、実験的困難のために進展してこなかった。その理由の一つは、 ハイパー核の生成に用いられてきた(K-, ハイパー核の生成に用いられてきた(K-, -)反応や静止(K-, -)反応や静止(K-, -)反応では、重い -)反応では、重い ハイパー核の深い束縛状態を効率良く生成できないことであった。これらに比べて、本研究で用いた( ハイパー核の深い束縛状態を効率良く生成できないことであった。これらに比べて、本研究で用いた( +,K+)反応は、反応時の運動量移行が大きく、深い束縛状態まで強く励起する。このことは、米国ブルックヘブン研究所(BNL)や高エネルギー加速器研究機構(KEK)での以前の実験において実証されている。しかしながら、以前の( +,K+)反応は、反応時の運動量移行が大きく、深い束縛状態まで強く励起する。このことは、米国ブルックヘブン研究所(BNL)や高エネルギー加速器研究機構(KEK)での以前の実験において実証されている。しかしながら、以前の( +,K+)反応のデータは、エネルギー分解能や統計精度の点で不十分であり、細かなレベル分離の観測は不可能であった。また、これらの反応では、 +,K+)反応のデータは、エネルギー分解能や統計精度の点で不十分であり、細かなレベル分離の観測は不可能であった。また、これらの反応では、 ハイパー核の質量をミッシングマスとして測定するので、絶対値にどうしてもある程度の不定性が生じてしまう。この意味でも、精度の良い測定データが待ち望まれていた。 ハイパー核の質量をミッシングマスとして測定するので、絶対値にどうしてもある程度の不定性が生じてしまう。この意味でも、精度の良い測定データが待ち望まれていた。 本研究(KEK-PS E369)では、KEKの陽子シンクロトロン(12 GeV-PS)のK6ビームラインから供給される1.05 GeV/cの +ビームを用いて、( +ビームを用いて、( +,K+)反応により生成される中重 +,K+)反応により生成される中重 ハイパー核、 ハイパー核、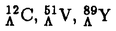 の励起準位を高分解能スペクトロメータSKSを用いて測定した。SKSは、1GeV/c領域で2MeV(FWHM)以下のエネルギー分解能と100msrの大立体角を合わせ持つ世界最高性能のスペクトロメータである。これまでに得られた最高分解能は、0.9g/cm2厚の12C標的を用いた12C( の励起準位を高分解能スペクトロメータSKSを用いて測定した。SKSは、1GeV/c領域で2MeV(FWHM)以下のエネルギー分解能と100msrの大立体角を合わせ持つ世界最高性能のスペクトロメータである。これまでに得られた最高分解能は、0.9g/cm2厚の12C標的を用いた12C( +,K+) +,K+) 反応で記録された1.9MeV(FWHM)である。今回の実験では、SKSの出入口にドリフトチェンバーを新たに設置して散乱K中間子の飛跡検出器系を強化した結果、エネルギー分解能を飛躍的に向上させることに成功した。本実験では、以前と同様の12C標的に対して、1.45MeV(FWHM)のエネルギー分解能を達成した(図1参照)。 反応で記録された1.9MeV(FWHM)である。今回の実験では、SKSの出入口にドリフトチェンバーを新たに設置して散乱K中間子の飛跡検出器系を強化した結果、エネルギー分解能を飛躍的に向上させることに成功した。本実験では、以前と同様の12C標的に対して、1.45MeV(FWHM)のエネルギー分解能を達成した(図1参照)。 , , に関しても、これまでにない高質のスペクトルを得ることができた。特に、 に関しても、これまでにない高質のスペクトルを得ることができた。特に、 スペクトルについては、エネルギー分解能が1.65MeV(FWHM)で、束縛領域に7000個の統計量を誇るこれまでで最高質のデータを取得した。 スペクトルについては、エネルギー分解能が1.65MeV(FWHM)で、束縛領域に7000個の統計量を誇るこれまでで最高質のデータを取得した。 図1に示される の励起スペクトルにみられる2つの大きなピーク(#1,#5)は、最外殻の中性子空孔状態と の励起スペクトルにみられる2つの大きなピーク(#1,#5)は、最外殻の中性子空孔状態と 軌道及び 軌道及び 軌道の 軌道の 粒子が結合した状態であり、過去の様々な実験ですでに観測されている。本実験では、この他に、11C芯核の励起準位に 粒子が結合した状態であり、過去の様々な実験ですでに観測されている。本実験では、この他に、11C芯核の励起準位に 軌道及び 軌道及び 軌道の 軌道の 粒子が結合した芯核励起状態(#2,#3,#4,#6)をきれいに分離観測することにはじめて成功した。中性子ピックアップ反応では、11Cの1/2-(2.0MeV)と3/2-(4.8MeV)状態が基底状態の10〜20%の強度で励起される。これまでの理論計算では、 粒子が結合した芯核励起状態(#2,#3,#4,#6)をきれいに分離観測することにはじめて成功した。中性子ピックアップ反応では、11Cの1/2-(2.0MeV)と3/2-(4.8MeV)状態が基底状態の10〜20%の強度で励起される。これまでの理論計算では、 の正パリティー状態を計算する際、上述のような11C芯核の負パリティー状態と の正パリティー状態を計算する際、上述のような11C芯核の負パリティー状態と 状態との結合のみが考慮されていた。しかし、このモデルでは、( 状態との結合のみが考慮されていた。しかし、このモデルでは、( +,K+)反応における#4ピークの出現を説明することができない。今回のスペクトルを再現するには、11C芯核のモデルスペースを拡張して、11C芯核の1/2+(6.34MeV),5/2+(6.90MeV),3/2+(7.50MeV)のような正パリティー1 +,K+)反応における#4ピークの出現を説明することができない。今回のスペクトルを再現するには、11C芯核のモデルスペースを拡張して、11C芯核の1/2+(6.34MeV),5/2+(6.90MeV),3/2+(7.50MeV)のような正パリティー1 励起状態と 励起状態と 状態との結合状態も考慮する必要があることが指摘されている。今回のスペクトルは、このように、 状態との結合状態も考慮する必要があることが指摘されている。今回のスペクトルは、このように、 軌道間の遷移( 軌道間の遷移( )を通じて、芯核のパリティーの異なる状態が混合することの重要性を初めて示すものとなった。また、これらの束縛エネルギーは、 )を通じて、芯核のパリティーの異なる状態が混合することの重要性を初めて示すものとなった。また、これらの束縛エネルギーは、 -核子相互作用のスピン依存部分に強く依存することが、これまでの理論的研究で明らかにされており、 -核子相互作用のスピン依存部分に強く依存することが、これまでの理論的研究で明らかにされており、 -核子間のスピン依存力に関する有効な情報を提供している。 -核子間のスピン依存力に関する有効な情報を提供している。 上述したように、( +,K+)反応における +,K+)反応における の励起スペクトルは、既に、BNL、KEKで観測されている。3.0MeVの分解能で観測されたBNLのスペクトルは、深く束縛した の励起スペクトルは、既に、BNL、KEKで観測されている。3.0MeVの分解能で観測されたBNLのスペクトルは、深く束縛した 粒子が独立粒子的に振舞っていることをはじめて明らかにした。KEKのスペクトルでは、各 粒子が独立粒子的に振舞っていることをはじめて明らかにした。KEKのスペクトルでは、各 粒子軌道に対応するピーク幅が、2.2MeVの実験分解能から予想されるよりも広く、 粒子軌道に対応するピーク幅が、2.2MeVの実験分解能から予想されるよりも広く、 粒子軌道におけるレベル分離を示唆する特徴的な構造がはじめて観測された。しかしながら、統計精度の点でこれを結論づけるに至らなかった。図2に本実験で観測した 粒子軌道におけるレベル分離を示唆する特徴的な構造がはじめて観測された。しかしながら、統計精度の点でこれを結論づけるに至らなかった。図2に本実験で観測した の励起スペクトルを示す。4つのピーク構造は、最外殻の中性子空孔状態( の励起スペクトルを示す。4つのピーク構造は、最外殻の中性子空孔状態( )と )と 軌道(l=0〜3)が結合した束縛状態に対応づけることができる。各軌道のピーク幅は、エネルギー分解能から予想されるよりも有意に広く、軌道角運動量が大きくなるにつれてその幅が広がっていることが見てとれる。特に、 軌道(l=0〜3)が結合した束縛状態に対応づけることができる。各軌道のピーク幅は、エネルギー分解能から予想されるよりも有意に広く、軌道角運動量が大きくなるにつれてその幅が広がっていることが見てとれる。特に、 -軌道においては、2本のピークに分離していることがはっきりと示された。このスペクトルに寄与する中性子空孔状態としては、 -軌道においては、2本のピークに分離していることがはっきりと示された。このスペクトルに寄与する中性子空孔状態としては、 状態以外に、より深い 状態以外に、より深い 状態等も考えられる。事実、中性子ピックアップ90Zr(p,d)89Zr反応では、5/2-(3.3MeV)と7/2-(10.3MeV)状態が基底状態の〜70%の強度で励起されることが知られている。しかしながら、これらの深い中性子空孔状態の状態幅は、非常に広い(3〜7MeV)ことが予想され、観測した各ピークの頂上付近のエネルギー領域のみを選べば、その寄与は非常に小さく、単に平坦で連続的なバックグラウンドを形成するにすぎない。それゆえ、各励起準位のエネルギーは、各ピークの頂上付近を、実験上のエネルギー分解能と同じ輻を持つ2つの(基底状態に対しては1つの)ガウス型ピークを用いてフィットすることにより求められた(図2参照)。各束縛エネルギーの大きさは、実験標的の直前に設置されたシンチレーションカウンター中で生成され、 状態等も考えられる。事実、中性子ピックアップ90Zr(p,d)89Zr反応では、5/2-(3.3MeV)と7/2-(10.3MeV)状態が基底状態の〜70%の強度で励起されることが知られている。しかしながら、これらの深い中性子空孔状態の状態幅は、非常に広い(3〜7MeV)ことが予想され、観測した各ピークの頂上付近のエネルギー領域のみを選べば、その寄与は非常に小さく、単に平坦で連続的なバックグラウンドを形成するにすぎない。それゆえ、各励起準位のエネルギーは、各ピークの頂上付近を、実験上のエネルギー分解能と同じ輻を持つ2つの(基底状態に対しては1つの)ガウス型ピークを用いてフィットすることにより求められた(図2参照)。各束縛エネルギーの大きさは、実験標的の直前に設置されたシンチレーションカウンター中で生成され、 データ収集中に同時に得られた データ収集中に同時に得られた スペクトルの基底状態の束縛エネルギーを参照することにより絶対値として、±0.10(stat.)±0.23(syst.)MeV以下の精度で得られた。重い スペクトルの基底状態の束縛エネルギーを参照することにより絶対値として、±0.10(stat.)±0.23(syst.)MeV以下の精度で得られた。重い ハイパー核の20MeV以上の広いエネルギーレンジにおける一連の ハイパー核の20MeV以上の広いエネルギーレンジにおける一連の 一粒子エネルギーをこの様な高精度で決定したのは、今回の実験がはじめてである。これらの束縛エネルギーから、 一粒子エネルギーをこの様な高精度で決定したのは、今回の実験がはじめてである。これらの束縛エネルギーから、 粒子の一体ポテンシャルの深さ( 粒子の一体ポテンシャルの深さ( =30MeV)と原子核中での =30MeV)と原子核中での 粒子の有効質量( 粒子の有効質量( / / =0.80)がこれまでにない精度で得られた。これらの量は、理論的なモデルに依存するが、実験データからの誤差は非常に小さい。 =0.80)がこれまでにない精度で得られた。これらの量は、理論的なモデルに依存するが、実験データからの誤差は非常に小さい。  図表図1: 図表図1: スペクトル / 図2: スペクトル / 図2: スペクトル スペクトル また、各軌道のピーク間隔は、1.37±0.20±0.10MeV( -軌道)、1.63±0.15±0.10MeV( -軌道)、1.63±0.15±0.10MeV( -軌道)、1.70±0.10±0.10MeV( -軌道)、1.70±0.10±0.10MeV( -軌道)と得られ、軌道角運動量が大きくなるにつれてエネルギー間隔も大きくなることが示された。これは、スピン-軌道分離に特有の特徴であるが、各軌道に仮定した2つのピークの右側のピークが、 -軌道)と得られ、軌道角運動量が大きくなるにつれてエネルギー間隔も大きくなることが示された。これは、スピン-軌道分離に特有の特徴であるが、各軌道に仮定した2つのピークの右側のピークが、 とは異った中性子空孔状態からの寄与と考えることもできる。この仮定では、その2つの中性子空孔状態間のエネルギー差と強度比は、各軌道間で等しくなると予想されるが、今回の解析結果は、それらの予想と相反するものである。また、右側のピークの強度は、左側のピークの70〜99%と得られたが、90Zr(p,d)89Zr反応では、最外殻中性子空孔状態から1.5MeV程度離れた位置に、そのような大きな強度で励起される中性子空孔状態はないことが知られている。以上のように、今回観測されたピーク構造は、2つの異った中性子空孔状態から形成されるという仮定のみでは、説明することはできない。また、 とは異った中性子空孔状態からの寄与と考えることもできる。この仮定では、その2つの中性子空孔状態間のエネルギー差と強度比は、各軌道間で等しくなると予想されるが、今回の解析結果は、それらの予想と相反するものである。また、右側のピークの強度は、左側のピークの70〜99%と得られたが、90Zr(p,d)89Zr反応では、最外殻中性子空孔状態から1.5MeV程度離れた位置に、そのような大きな強度で励起される中性子空孔状態はないことが知られている。以上のように、今回観測されたピーク構造は、2つの異った中性子空孔状態から形成されるという仮定のみでは、説明することはできない。また、 と同様のピーク構造は、 と同様のピーク構造は、 につても観測された。今回観測された重い につても観測された。今回観測された重い ハイパー核における特徴的なピーク構造の正確な解釈を得るには、スピン-軌道分離の寄与の可能性を含め、今後のより精密な理論的研究を待たねばならない。 ハイパー核における特徴的なピーク構造の正確な解釈を得るには、スピン-軌道分離の寄与の可能性を含め、今後のより精密な理論的研究を待たねばならない。 |