| 内容要旨 | | 要旨1.研究背景 日常の診療で広く用いられている針筋電図は侵襲的検査であり,もし表面電極を用いて非侵襲的に針筋電図検査と同等の情報を得ることができるならば患者・医療者双方にとって望ましい。針筋電図検査の最大の目的は,下位運動ニューロンに障害がある神経原性変化と筋線維そのものに障害のある筋原性変化との鑑別であるが,随意収縮時の表面筋電図を用いた過去の研究で,これを目指したものはほとんどない。電気刺激による誘発筋電図の表面電極記録において運動単位電位(MUP)を認識し,神経筋疾患を診断評価する検査法として,motor unit number estimate(MUNE)という方法があるが,方法論的に曖昧な点が多くて十分信頼できる検査として確立されているとは言い難く,臨床応用も広がっていない。 随意収縮時表面筋電図を用いた研究が過去にほとんどなされていない最大の理由は,表面筋電図ではMUPの重なりが針筋電図に比べてはるかに大きく,個々のMUPの評価が困難と考えられていた点にあると思われる。 2.目的 上記問題点を克服し,随意収縮時表面筋電図による神経原性・筋原性変化の診断を可能とする新たな方法を開発することを本研究の目的とする。 3.解析法の開発3.1電極配置の決定 MUNEを含む多くの過去の研究では,神経伝導検査同様探査電極を筋腹上,基準電極を筋の遠位端の腱などの上に配置している。これはMUNEに代表されるように筋全体の評価にこだわったためでもあるが,神経原性・筋原性の鑑別の目的を達成するためにはMUPがよく分離されるようなより選択的な電極配置を採用していけない理由はない。これが可能な筋として我々は前脛骨筋を選択した。即ち探査電極を筋腹上におき,基準電極は探査電極の内側近傍の脛骨面上に電極間距離を概ね2.5cmとなるように設置した。この筋-骨記録と通常の筋-腱記録を比較すると,明らかに前者の方が個々のMUPの分離が良いことがわかる(図1)。 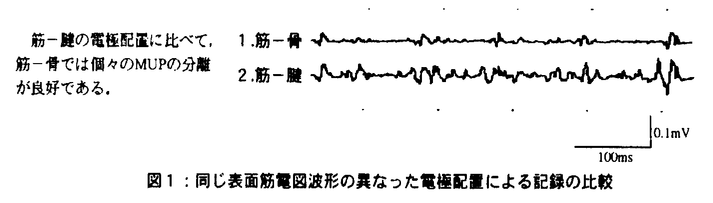 図1:同じ表面筋電図波形の異なった電極配置による記録の比較3.2神経原性・筋原性変化における表面筋電図波形(定性的印象) 図1:同じ表面筋電図波形の異なった電極配置による記録の比較3.2神経原性・筋原性変化における表面筋電図波形(定性的印象) 針筋電図においては,神経原性変化では運動単位数が減少するが個々のMUPは神経再支配のために巨大化するので,"large and sparse"と表現される筋電図波形を呈するのに対し,筋原性変化では運動単位数は保たれるが個々のMUPは筋線維変性のために小さくなって,"small and abundant"と表現される波形を呈することが知られている。 図2に示したように,上記の電極配置で記録された表面筋電図波形においても同様のパターンを明らかに認めることができた。 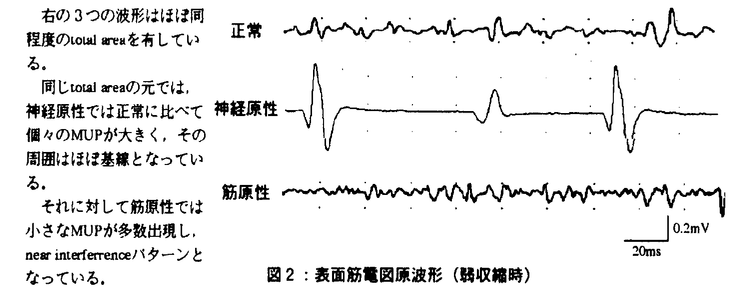 図2:表面筋電図原波形(弱収縮時) 図2:表面筋電図原波形(弱収縮時) 臨床的に有用な検査法とするためにはこのような定性的印象を定量化することが望ましいが,従来から存在する筋電図波形の定量法はいずれもこの問題の解決に必ずしも最適ではないと判断し,以下に述べるような全く新たな解析法を考案した。 3.3定性的印象の定量化:Clustering Indexの創案 筋電図信号の時系列においてMUPをおよそ含むような適切なwindowを設定すると,上記の神経原性と筋原性の差は"筋電図信号のtotal areaが個々のwindow内の信号のareaに時系列上でどのように分かれて分布しているか"という問題に還元される。即ち,神経原性変化においては,total areaは巨大MUPに対応する少数のwindowに集中(cluster)する一方,これら大きな面積を有するwindowの周囲は比較的平坦なので0に近い値を取る。これに対して,正常,さらには筋原性変化ではtotal areaはすべてのwindowにほぼまんべんなく分布することになる(図3)。 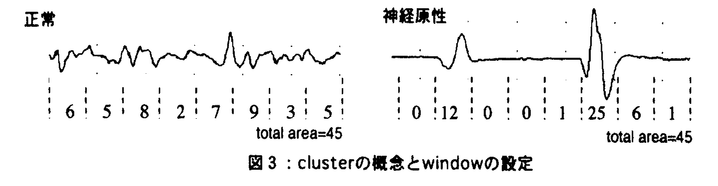 図3:clusterの概念とwindowの設定 図3:clusterの概念とwindowの設定 このようなクラスターの程度を定量化する方法として,標準偏差など値のばらつきを表現する指標がまず考えられるが,これらは時系列情報を生かしておらず不十分である。そこで,以下のような新たな指標を考案した。 window areaの値を時系列順に並べた数列を考える。すると,時系列上で値がクラスターするということは, "数列内の隣あった要素間の差が大きい"ということに対応する。そこで,元の数列の階差数列を作成してその二乗和をとると,クラスターの程度が強いほどその値は大きくなる。さらに,大きな値の孤立の度合をより鋭敏に表現するために,一つおき,二つおきの階差数列の二乗和もこれに加えた。これを元の数列の二乗和を用いて標準化した結果をClustering Index=CIと名付けた。 即ち,各window areaの値からなる数列をAiとすると, 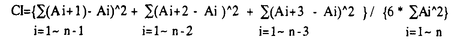 CIは0から1の範囲の値をとり,クラスターの程度が強いほど大きくなる。なおwindow幅については,神経原性の大きなMUPをほぼ包含することを条件とし,種々の値を用いて計算した試した上で15msecに設定した。 また,神経原性・正常・筋原性のいずれにおいても,筋の収縮レベルが上がるほど,MUPが豊富に出現し干渉波形に近づくためCIは小さくなる。従って,収縮強度レベルの指標として1秒間の筋電波形のtotal areaを横軸に,CIを縦軸にとった2次元プロットで評価を行うこととした。 4.本実験4.1対象 正常群:若年者(20-37歳)10例(男性6人,女性4人)老年者(60歳以上)3例(男性2人,女性2人)。いずれの被検者も下肢の痛み,脱力,しびれなどの臨床症状を有せず,また同時に行った前脛骨筋の針筋電図において異常を認めなかった。 患者群:神経原性患者12人。筋原性疾患患者15人。 対象患者としては診断が確定しており,前脛骨筋に針筋電図上対応する所見を認めた例を選択した。神経原性患者群はさらに針筋電図における定性診断に基づき,高度4人,中等度3人,軽度5人の3群に分類した。 4.2方法 記録電極には脳波用皿電極を用い,前述のように配置した。増幅器のゲインは50 V〜1mV/divのいずれかを使用,周波数帯域50Hz-1kHzとした。 V〜1mV/divのいずれかを使用,周波数帯域50Hz-1kHzとした。 前脛骨筋に弱収縮から最大収縮までの様々な強度の力を入れてもらい,この間の筋電図信号をすべてDATレコーダーに記録した。これをoff-lineで再生して,約20〜40の異なる収縮強度の部分から,なるべく収縮強度が一定した1秒間を選択し,解析用の筋電図計に読み込んだ。今回作成した解析プログラムを用いてこの1秒間の筋電信号のCIとareaの値を計算して,上記の2次元グラフにプロットした。即ち,一人の一回の検査から20〜40のポイントがグラフ上にプロットされることになる。 4.3結果 既述の理由で正常群でも収縮レベル,即ちareaの値が上がる程CIは小さくなった。 高度神経原性変化群では図4に示すように軽〜中等度の収縮においてCIは明らかに正常より高値をとったが強収縮では正常クラウドに重なった。同様の傾向は中等度の神経原性変化群についても認められたが,軽度変化群では正常群との区別はできなかった。 筋原性変化群では図に示すように,被検筋全例で弱収縮において正常群に比べてCIが低値をとる傾向を示した。 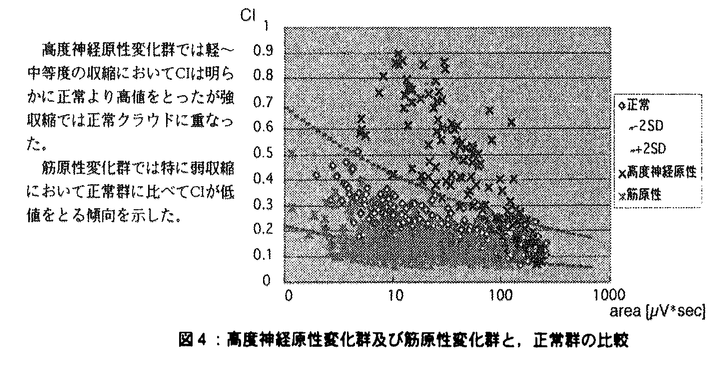 図4:高度神経原性変化群及び筋原性変化群と,正常群の比較5.考察 図4:高度神経原性変化群及び筋原性変化群と,正常群の比較5.考察 本研究では,電極配置の工夫と新たな解析法によってはじめて表面筋電図を用いて中等度以上の神経原性変化及び筋原性変化を正常群と区別することに初めて成功した。 我々の方法は,針筋電図施行前のスクリーニング,侵襲的検査が困難な患者,すなわち小児やAIDSなどの感染症患者での検査などに応用できると考えられる。 また,針筋電図よりも定量性に優れ,侵襲が少ないので経時的な繰り返し検査が容易であり,病気の進行のモニターや治療効果判定に有用であると推測される。 一方特に筋疾患においては,単なる針筋電図の代替にとどまらず,針筋電図よりも正確な診断を与える可能性がある。即ち,針筋電図波形は針先の探査電極面の近くの狭い領域の筋線維活動に左右される(=pickup areaが狭い)ので,筋疾患においても肥大線維や局所的な筋線維密度の増大のためにしばしば高振幅MUPが観察されて,神経原性と紛らわしい所見を呈することが知られている。これに対し,pickup areaが広く針筋電図に比べ選択性の低い表面筋電図は,このような局所の情報に左右されにくく,筋原性での運動単位全体としての起電力の低下を正確に表現できることが期待される。 今後の研究の展開としては,前脛骨筋以外の筋への応用,神経筋疾患診断における感受性・特異性についての針筋電図との詳細な比較などを進めていく予定である。 |
| 審査要旨 | | 本研究は神経筋疾患の評価・診断において広く用いられている針筋電図の最大の欠点が強い侵襲性であることを考え、侵襲性の無い表面筋電図で、前脛骨筋の神経原性・筋原性変化を診断する方法論を確立しようと試みたものである。 本研究では、表面筋電図による筋電波形解析の開発に際しては、 1.表面電極のuptake areaの広さによる、運動単位電位(MUP)の重なりを可能な限り軽減し、個々のMUPの分離を良くする電極配置を試みる。 2.現在診断精度が最も高いと考えられる針筋電図での定性診断の診断基準をそのまま使用できるような解析法を考案し、定量性をもたせる。 という点に留意した。 本研究で開発した解析法により、下記の結果を得ている。 1.前脛骨筋筋腹に活動電極を、近傍の前脛骨面上に基準電極を配置し、電極間距離を概ね2.5cmとなるように電極配置をおいたところ、基準電極を腱上においたときに比べ、明らかに個々のMUPの分離が良好となった。 2.そのような電極配置において、正常被検者・神経原性患者・筋原性患者の表面筋電図を採取、針筋電図での定性印象を同様の波形パターンを認めた。その為、このような定性印象をindex化することを目的としてClustering Index(CI)という新しいindexを考案した。 3.CIと、筋電図の活動レベルの指標としての一秒間の波形のtotal areaの2次元プロット表示として評価したところ、正常被検者では、若年者群(40才以下)で設定した正常範囲内に、高齢者群(60才以上)も重なり、年齢によるばらつきを無視して評価できた。 4.また、CI-areaプロット上、同一正常被検者において、電極位置をずらし電極間距離をかえて記録したが、データ上の大きなシフトは見られず、多少の電極配置による誤差は無視できると考えられた。 5.前脛骨筋針筋電図で異常を認めた神経原性変化群及び筋原性変化群のCI-areaプロットにおいて、筋原性変化群は下方(小さなCI値を取る傾向)ヘシフトし、正常群と良好に分離された。神経原性変化群は針筋電図の定性評価により高度、中等度、軽度変化群の3群に分けたが、高度及び中等度神経原性変化群では個々のMUPの分離が良いことを反映しプロットは正常群の上方ヘシフトし、正常群と区別できた。一方軽度神経原性変化群は正常群との重なりが大きかった。 6.統計学的にプロットと回帰直線上の残渣平均をとると、高度及び中等度神経原性変化群の全例と、軽度神経原性変化群5例のうち2例が正常の平均+-2SDを越えて異常高値をとった。残渣平均の値は高度変化群>中等度へ変化群>軽度変化群となり、針筋電図定性診断の結果と非常によく合致した。 筋原性変化群では針筋電図で12例中11例で異常低値となった。また、前脛骨筋の針筋電図では異常が認められなかった筋疾患患者3例について、1例で異常低値を、1例で異常高値を認めた。 7.total areaの最大値(Amax)の検討では、同レベルの筋力において神経原性変化患者に比べ、筋原性変化群の方が明らかに低値をとる傾向を認めた。Amaxの評価も合わせると、今回対象とした筋原性患者全例で異常を認め、少なくとも筋疾患においては針筋電図と同等の診断精度を有する可能性が示唆された。 8.さらに一例、針筋電図において高振幅MUPが目立った筋原性変化症例においてCI-areaプロットでは明らかな筋原性変化パターンとなった。これは表面電極のuptake areaが広く選択性が低いため、局所の変化に左右されることなくMUP全体の変化を捉え得た為と考えられた。 以上、本論文では前脛骨筋において非侵襲的かつ定量的に神経原性・筋原性変化を診断し得ることを明らかにした。本論文で開発された方法はなんら特殊な機器を使用することもなく、広い臨床応用も期待され、神経筋疾患の診断の臨床現場に重要な貢献をするものと考えられ、学位の授与に値するものと考えられる。 |