学位論文要旨
| No | 115774 | |
| 著者(漢字) | 村松,憲仁 | |
| 著者(英字) | ||
| 著者(カナ) | ムラマツ,ノリヒト | |
| 標題(和) | 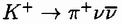 稀崩壊現象の実験的研究 稀崩壊現象の実験的研究 | |
| 標題(洋) | An Experimental Study of the Rare Decay : 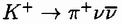 | |
| 報告番号 | 115774 | |
| 報告番号 | 甲15774 | |
| 学位授与日 | 2001.03.12 | |
| 学位種別 | 課程博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 博理第3876号 | |
| 研究科 | 理学系研究科 | |
| 専攻 | 物理学専攻 | |
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | K+中間子の稀崩壊現象K+→π+υυ-は、ストレンジクォーク(s)からダウンクォーク(d)へフレーバーが変わる中性カレント反応であり、標準模型においては1次の電弱相互作用による崩壊が禁止される。2次の相互作用をもとに理論計算される崩壊幅は、トップクォーク(t)とダウンクォーク(d)の混合を示すカビボ・小林・益川(CKM)行列要素Vtdに強く依存する。この崩壊の分岐比を実験的に測定することにより、いまだ精度良く測られていないVtdの大きさを求めることができる。特にK+→π+υυ-崩壊は、分岐比に対するチャームクォークの寄与が小さいだけでなく、始状態(K+中間子)における強い相互作用の寄与をK+→π0e+υ崩壊の分岐比から得ることができ、精度の良い理論計算がなされている。標準理論による分岐比の範囲は、これまでのCKM行列要素の測定結果を考慮することによって、(0.82±0.32)×10-10と計算されており、実験値との比較で標準模型を越える理論を探索することができる。 ブルックヘブン国立研究所(BNL)のE787実験は、K+→π+υυ-崩壊現象を探索することを目的としている。Alternating Gradient Synchrotron(AGS)加速器で24GeVに加速した陽子をプラチナ標的に当ててK+中間子ビームを作り、670-790MeV/cのK+中間子をE787スペクトロメータに導く。これらのK+中間子は、ビームライン上の検出器で識別されたあと、スペクトロメータの中心にあるアクティブ・ターゲットで止まる。アクティブ・ターゲットは、シンチレーション・ファイバーの束で出来ており、K+中間子とその崩壊生成物の軌跡を測ることができる。K+崩壊によって生成された荷電粒子は、アクティブ・ターゲットの周りを覆うドリフト・チェンバーで運動量が測られ、さらにその周りを覆うプラスティック・シンチレータの層(レンジ・スタック)で止まり、レンジと運動エネルギーが測定される。レンジ・スタックの信号は、500MHzのトランジエント・ディジタイザー(TD)で数μsecのあいだ波形が記録され、π+→μ+→e+の崩壊連鎖を起こす荷電粒子を同定することによって、π+の識別が行なわれる。全立体角は電磁カロリメータで覆われ、K+崩壊に伴う光子が検出される。 K+→π+υυ稀崩壊現象は、E787実験のPhase-I(1989-1991)で収集されたデータを解析した時点で見つかっていなかった。本論文では、E787実験で1995年から1997年までに収集されたデータ(3.2×1012K+トリガー)を解析した。 K+→π+υυ稀崩壊現象の探索は、K+崩壊で生成された荷電粒子の運動量が、2体崩壊であるK+→π+πo(Kπ2)とK+→μ+υ(Kμ2)の運動量ピーク(それぞれ、205MeV/cと236MeV/c)の間となる領域で行なった。バックグラウンドとなるプロセスは、これら[1]Kπ2崩壊、[2]Kμ2崩壊(K+→μ+υγを含む)と、ビーム中にπ+が混入することに起因するプロセス(ビーム・バックグラウンド)である。ビーム・バックグラウンドには、[3]ビーム中のπ+がアクティブ・ターゲットで反跳して、シグナル事象によるπ+に見えるシングルビーム・バックグラウンド、[4]K+がターゲットまで至って止まっている間、後から来たπ+がターゲットで反跳してシグナル事象に見えるダブルビーム・バックグラウンド、[5]ターゲットにおいてK+が荷電交換反応を起こしてK0Lが生成され、これがセミレプトニックに崩壊(K0e3、K0μ3)して生じたπ+がシグナル事象の崩壊生成物に見える荷電交換バックグラウンドが含まれる。収集されたデータの中に標準模型で予想されるシグナル事象は1事象程度であるので、検出されたシグナル事象の信頼度を高めるためには、これらの5つのバックグラウンドをコントロールして、シグナル事象の数より十分低く抑えることが重要である。 バックグラウンドに対するオフライン・カットを決定し、それらのカットをデータにかけた時に残るバックグラウンドのレベルを評価するために、「バイフルケーション法」(二股分割法)を用いた。バイフルケーション法は、考えているバックグラウンド・プロセスに対して大きな除去率を持つ2つの独立したカットを用意し、それぞれのカットの除去率を別々に求めて、最後に掛け合わせるという方法である。それぞれのカットの除去率を求めるには、残ったもう一方のカットで「除くことができる」事象をサンプルとして集めた。この方法の利点は、サンプルを集める時点でシグナル事象が混ざることがなく、統計量の多いバックグラウンド事象を多く集められることである。 シングルビーム・バックグラウンドに対しては、ターゲットにおけるK+信号とπ+信号の時間差が少なくとも2nsec以上であることを要求するカットと、ターゲットの直前にあるホドスコープに残されるエネルギー損失によりπ+が侵入してきた事象を除くカットを、バイフルケーション法の2つのカットとして選んだ。これにより評価されたシングルビーム・バックグラウンドの数は、1995-1997年のデータセットに対して0.005事象となった。また、ダブルビーム・バックグラウンドに対しては、ビームライン上流と下流において2粒子が検出された事象をそれぞれ除くカットが選択され、バックグラウンド・レベルは0.016事象と評価された。Kμ2バックグラウンドでは、荷電粒子の運動量、レンジ、運動エネルギーがKμ2またはK+→μ+υγに相当する事象を除くカットと、π+→μ+→e+崩壊連鎖が見つからなかった事象を除くカットを用いて、バックグラウンド・レベルが0.028事象と評価された。Kπ2バックグラウンドにおいては、荷電粒子の運動量等がKπ2に相当する事象を除くカットと、荷電粒子の検出された時間にπ0の崩壊生成物である光子が検出された事象を除くカットが用いられ、0.024事象のバックグラウンド・レベルが評価された。各バックグラウンドの評価は、シグナル領域に近いバックグラウンド事象の数と、その領域におけるバイフルケーション法による評価を比べることにより、点検された。最後に、荷電交換バックグラウンドは、モンテカルロ法で生成されたサンプルに、用意された全てのカットをかけることにより、バックグラウンド・レベルが0.010事象と評価された。以上により、用意された全てのカットを用いたときの全バックグラウンド・レベルは(0.083土0.019)事象と計算され、十分にバックグラウンドがコントロールされていることが確認された。 1995年から1997年に収集された全データに、用意された全てのカットをかけた結果、1事象が残った。この事象は、用意されたカットに対して相対アクセプタンスが33%、バックグラウンド・レベルが0.0065事象と評価される「黄金領域」に存在し、シグナル事象としての信頼度が高い。全てのトリガー条件、オフライン・カットのアクセプタンスは、モニター・トリガー・データから評価され、収集されたK+トリガーの全数とかけ合わせることにより、本解析での信号の感度が計算された。これを、シグナル事象が1事象観測された事実と合わせた結果、K+→π+υυ崩壊の分岐比は、 と求められた(信頼率68%の信頼区間)。この分岐比は、誤差の範囲内で標準模型と一致した。分岐比より導かれるVtdの範囲は、 であった。 | |
| 審査要旨 | 現在、素粒子物理学は、電弱相互作用を表すワインバーグ・サラムモデルと強い相互作用を記述する量子色力学を標準理論としているが、さらに、違った世代間のクオークの遷移に関連するクオーク混合を重要な要素として含む。クオークの質量の固有状態と弱い相互作用の固有状態は同じでない。その混合はカビボ・小林・益川(CKM)行列であらわされる。CKM行列要素は実験的に決定されなければならないが、まだ、実験的に決定されていない行列要素もある。素粒子の稀崩壊現象は、クオーク間の混合を決定するために重要であるばかりでなく、標準理論の予想値からのずれがあれば、標準理論を超える理論の存在を示唆し、その糸口を与える。 本論文の主題であるK+中間子の稀崩壊現象、K+→π+υυは、ストレンジクォークがダウンクォークへ遷移する崩壊である。しかしこの遷移は1次の電弱相互作用では禁止されている。2次の相互作用をもとに理論計算される崩壊寿命は、トップクォークとダウンクォークの混合を表すCKM行列要素Vtdに強く依存する。したがって、稀崩壊現象、K+→π+υυを測定することにより、CKM行列要素Vtdを決定できるとともに、標準理論による分岐比の予測、(0.82±0.32)×10-10、との比較で標準理論を超える理論を探索することが可能である。本論文は6章からなり、第1章は序論として、以上のような本論文の目的、意義が述べられている。 第2章は、実験装置および実験手法の説明、第3章はデータ解析の概略、第4章はバックグラウンドの考察がのべられている。本実験は米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)で行われた。BNLの陽子シンクロトロンで加速された陽子(24GeV)をプラチナ標的に当てて作られたK+中間子ビームをアクティブターゲット(シンチレーションファイバー)で停止させその崩壊を測定する。崩壊で出来た荷電粒子は、アクティブターゲット内でその軌跡が測定される。そして、それを取り囲むドリフトチェンバーで運動量が測られ、さらにその周りのレンジスタックと呼ばれるプラスティックシンチレータ層で飛程と運動エネルギーが測定される。1995年から97年までに収集された全データは3.2x1012事象である。(後に決定される)事象選択の効率は0.2%程度であり、信号として予想される数は多くて数事象である。したがって、シグナル領域に残るバックグラウンドを信号の数より十分小さくし、その数をいかに正確に見積もるかが本論文におけるデータ解析のポイントである。 K+→π+υυ崩壊で作られるπ+は連続スペクトルを持ち最大運動量が227MeV/cであるため、π+の運動量の探索範囲を、バックグラウンドであるK+→π+π0(Kπ2)、K+→μ+v(Kμ2)崩壊からの荷電粒子の運動量ピーク(それぞれ205MeV/c、236MeV/c)の間に設定した。バックグラウンドはこの他にビームに起因するものがある。それらは、1)シングルビームバックグラウンド:ビーム中に残っているπ+がアクティブターゲット内で相互作用をおこすもの、2)ダブルビームバックグラウンド:K+とπ+が同時にはいって、π+が散乱し、信号のように見えるもの、3)K+の荷電交換反応によるもの:生成されたKOLがセミレプトニック崩壊して生じたπ+が信号のように見えるもの。これらのバックグラウンドを十分に良くコントロールしなくてはならない。 このため、論文提出者は、「二股分割法」を適用し、バックグラウンドの除去効率、シグナル領域へのバックグラウンドの染み込みの評価をおこなった。「二股分割法」とは、2つの独立なカットを用いてお互いの除去効率を、データに基づいて相互評価する方法である。また、最後まで、シグナル領域を見ずにバックグラウンドの除去効率のみからカットを事前に決定するブラインド解析を行った。これは、シグナル領域をカット決定以前にみることにより、解析手法にかかるバイアスを防ぐことになる。 こうして決定されたカットをすべてかけることで、シグナル領域に最終的に0.083±0.019事象のバックグラウンドがあると見積もられた。このシグナル領域に見つかった事象は1事象である。これにより分岐比として(1.52+3.48-1.26)x10-10が得られた。これは、標準理論と良く一致している。また、CKM行列要素として0.0024<|Vtd|<0.038が得られた。この1事象は、もっと強いカット(33%の相対選択効率)を行いバックグラウンドを0.0065±0.0017事象とした解析でも残る非常にきれいな事象である。第5章にこれらの結果、第6章に結論が纏められている。 本論文提出者は、信頼性の有る方法を用いてK+→π+υυ-崩壊の事象を測定、解析した。そして、初めて有限の崩壊分岐比を測定し、カビボ・小林・益川行列要素Vtdの値の有限な範囲を決定した。標準理論の予想と矛盾ないことを示した。これらは、素粒子物理学にたいして、新しい知見を加えるものである。 データの解析は、本論文提出者および、国外の共同研究者を含む数人を中心に行われたが、本論文提出者は、全体の解析を中心となって行うとともに、とくに、ビーム起因のバックグラウンド、シングル/ダブルビームバックグラウンド、荷電交換によるバックグラウンドの評価を、データ自身で評価する「二股分割法」等を用いて主体的に行った。バックグラウンドの評価は本実験にとって、本質的なものであり論文提出者の寄与は十分なものであると判断される。また、本論文提出者は、エンドキャプ測定器の較正、調整、ビーム測定器関係の較正に責任をもっており、本実験への寄与も本質的なものであると認めた。また、同意承諾も完備している。 以上により、博士(理学)の学位を授与できると認める。 | |
| UTokyo Repositoryリンク |