学位論文要旨
| No | 211760 | |
| 著者(漢字) | 井上,邦雄 | |
| 著者(英字) | Inoue,Kunio | |
| 著者(カナ) | イノウエ,クニオ | |
| 標題(和) | 神岡実験における太陽ニュートリノの測定および太陽反ニュートリノの探索 | |
| 標題(洋) | Measurement of Neutrinos and Search for Anti-Neutrinos from the Sun at Kamiokande | |
| 報告番号 | 211760 | |
| 報告番号 | 乙11760 | |
| 学位授与日 | 1994.04.25 | |
| 学位種別 | 論文博士 | |
| 学位種類 | 博士(理学) | |
| 学位記番号 | 第11760号 | |
| 研究科 | ||
| 専攻 | ||
| 論文審査委員 | ||
| 内容要旨 | 太陽内での核融合反応は標準太陽模型(SSM)において慎重に計算されており、その反応列のなかで放出されるニュートリノのフラックスは理論的に予側できる。この太陽ニュートリノを検出することは、太陽のエネルギー生成機構を知るのに役立つ。また、太陽ニュートリノは豊富なve源としてニュートリノの性質を知るのにも利用できる。 このような太陽ニュートリノを観測する実験は1970年9月以来塩素をつかった放射化学的手法によるものが行なわれており、1991年7月までの結果を平均すると、予測値8.0SNU(1SNU=10-36captures/atom/sec)に対し2.28±0.23SNUしかなかった。また、神岡での3000トンの水チェレンコフ実験でも水中の電子との弾性散乱を使い、ニュートリノのフラックスだけでなく、太陽方向から来ているという証拠を得た。1987年1月から1990年4月までの神岡実験(Kam-2)の結果も、理論値の0.47±0.05±0.06しかなかった。さらに、1990年からガリウムをつかった放射化学的測定が行なわれ、2つの実験グループから理論値より少ないフラックスが発表された。それらを平均すると、理論値の0.59±0.10であった。このニュートリノの欠損が太陽ニュートリノ問題である。 さらに興味深いことに、塩素実験は、ニュートリノフラックスと太陽黒点数との反相関を示唆している。このような相関は、ニュートリノの磁気モーメントと太陽磁場との相互作用に起因するもの以外考えにくく、標準理論を越えたニュートリノの性質を直接示唆するものである。 1990年4月以降、死んだ光電子増倍管(PMT)の交換、PMTのまわりの鏡の取付け、新しい電子回路の導入、そして低エネルギーでのバックグラウンドを除去するためのラドン除去装置の設置等の改良を行ない、神岡における太陽ニュートリノ観測は1990年12月からKam-3として再開された。これらの改良により、位置、エネルギー、角度の各分解能が向上し、またラドンの低減もあって解析の敷居値を7.5MeVから7.0MeVに下げることにも成功した。Kam-3での1993年2月までの514日分の観側で、Kam-2の1043日分のデータと合わせて、観測史上22回目の太陽活動最大期を網羅し、ニュートリノフラックスと黒点数との相関に対する詳しい研究が可能となった。 Kam-3における太陽ニュートリノの測定では、次のような結果が得られた。 また、Kam-2のデータと合わせると、次のような結果になる。 全てのデータを合わせると神岡実験はこれまでに、439+36.6-31.4例の太陽ニュートリノ事象を観測したことに相当する。 また、これまで得られたすべての神岡実験のデータを使って、ニュートリノフラックスと黒点数(Nss)の関係を1次関数で表すと、 となり有為な相関は見られなかった。 太陽ニュートリノ問題を解決するためには、太陽モデルの変更だけでは神岡と塩素実験の結果との間で2 次に、塩素実験で示唆されている黒点数との反相関を統計的に解析すると、その有為さは2.7 このような、マヨラナニュートリノを仮定したハイブリッドモデルでは、 さらに、この 太陽ニュートリノ問題に対しては、まだ決定的な解が得られていないが、ニュートリノフラックスと黒点数の間に本当に相関があるのか、また、相関がなかったとしても、2つ残されたニュートリノ振動解のいずれかに本当に解があるのかは、現在建設中のスーパー神岡実験やその他の実験によって、高い統計での解析がなされ、近い将来決着がつくであろう。 | |
| 審査要旨 | 本論文は8章からなり、第1章では、この研究の背景及び動機となる太陽ニュートリノ問題とその実験的現状について述べられている。また、この問題を解決するには太陽模型の変更では難しく、ニュートリノの未知の性質からくる素粒子物理的な解が自然であると考察している。 第2章では、太陽ニュートリノ問題を解決するために必要と考えられるニュートリノの質量と磁気モーメントについて、これまでに得られている制限についてまとめられている。 第3章では、太陽ニュートリノ問題の解の候補である、真空中や物質中でのニュートリノ振動の機構について説明されており、さらに太陽ニュートリノフラックスの11年周期を説明するためには不可欠と考えられるニュートリノの磁気モーメントと太陽磁場の相互作用による磁気共鳴振動についても説明されている。 第4章では、本論文の中心となる実験装置である「Kamiokande」のニュートリノ検出機構や、検出器の基本構成装置である水タンク、光電子増倍管、電子回路及び放射性物質除去・測定装置について詳述されている。 第5章では、「Kamiokande」で得られたデータを使っての、必要データの抽出方法、理論との比較手段である検出器のシミュレーション、残留バックグラウンドの考察について詳述されている。 第6章では、抽出されたデータからの太陽ニュートリノフラックスの算出を行い、理論的予測の約半分の量しかニュートリノが到来していないとの結果を得ている。また、11年周期の拠り所となっている太陽黒点数とニュートリノフラックスの反相関について考察し、 「Kamiokande」では有為な相関はみられなかったと結論している。同時に「Kamiokande」のデータを使ってニュートリノのスペクトルを仮定しない反ニュートリノフラックスの制限を得ている。 第7章では、得られた結果を使い、太陽ニュートリノ問題を説明できるかどうかニュートリノ振動解の検定を行い、2世代間のニュートリノ振動では、物質中での共鳴振動解は存在するが、真空中での振動解は90%以上の信頼度で否定されるとの結論を出した。また、11年周期も同時に説明するために物質中での磁気共鳴振動を考察し、ハイブリッド解を発見している。さらに、反ニュートリノフラックスの制限を適用しハイブリッド解の一部を除外している。 第8章は以上のまとめである。 また、補遺として、検出装置部品の詳細や検出器の較正、将来実験についてまとめられている。 なお、Kamiokande実験自体は複数の研究者との共同実験であるが、論文提出者は、検出器の改良時から実験に参加しており、太陽ニュートリノを観測をする上で重要となる放射性物質の測定は、提出者が装置を作成し実行したものである。また、必要データの抽出は、提出者がプログラムを作成し中心となって行い、太陽ニュートリノフラックスの算出、反ニュートリノフラックスの制限、及びこれらの評価は論文提出者が行ったものである。したがって、論文提出者の寄与が十分であると判断する。 太陽ニュートリノ問題は、現在の標準的な理論では説明できない数少ない問題であり、素粒子物理の中でも重要なテーマである。この論文は、実験データの質および精度を向上しており、価値があるものと認められる。また、ニュートリノ欠損の解の可能性があると考えられていた真空中での振動解を、はじめて定量的に否定しているほか、11年周期も説明できるハイブリッド解もはじめて発見している。また、本論文で得られている反ニュートリノに対する制限は現在この実験のみで得られる重要な結果である。この制限は、いくつかのハイブリッド解に制限を加えるものであり、重要な結果であると認められる。したがって、博士(理学)を授与できると認める。 | |
| UTokyo Repositoryリンク | http://hdl.handle.net/2261/50651 |
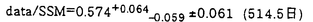
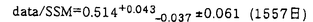

 以上の食い違いが生じてしまうため、ニュートリノのフレーバーに混合があり有限の質量があると生じるニュートリノ振動による説明が有力である。そこで、まずニュートリノフラックスと黒点数の相関はないものとして、ニュートリノ振動で3種類の全ての実験を説明できる解が存在するかを調べ、物質中での共鳴振動(MSW)領域において非断熱解と準真空解が解として許されることがわかった。さらに、これまで解でありうると考えられていた"Just-so"真空振動解は、MSW振動解との統一的な統計解析によって否定することができた。
以上の食い違いが生じてしまうため、ニュートリノのフレーバーに混合があり有限の質量があると生じるニュートリノ振動による説明が有力である。そこで、まずニュートリノフラックスと黒点数の相関はないものとして、ニュートリノ振動で3種類の全ての実験を説明できる解が存在するかを調べ、物質中での共鳴振動(MSW)領域において非断熱解と準真空解が解として許されることがわかった。さらに、これまで解でありうると考えられていた"Just-so"真空振動解は、MSW振動解との統一的な統計解析によって否定することができた。 Bに比べて、天体物理から来る制限の緩いマヨラナニュートリノを仮定した。また、太陽内の磁場の様子は正確には知られていないので、いくつかの磁場構造を試みた。そのため、太陽表面で期待されるニュートリノフラックスの値を得るのに非常にたくさんの計算が必要となったため、高速にニュートリノの伝搬を計算できるアルゴリズムを開発した。そして、これまで極く限られた磁場構造の仮定の元に行なわれていたハイブリッド解の探索に対して、より広範な磁場構造の計算を行ない、これまで正確には見つかっていなかったハイブリッド解について明確な結論を得ることができた。その解は、磁場構造に応じて、(s1)sin22
Bに比べて、天体物理から来る制限の緩いマヨラナニュートリノを仮定した。また、太陽内の磁場の様子は正確には知られていないので、いくつかの磁場構造を試みた。そのため、太陽表面で期待されるニュートリノフラックスの値を得るのに非常にたくさんの計算が必要となったため、高速にニュートリノの伝搬を計算できるアルゴリズムを開発した。そして、これまで極く限られた磁場構造の仮定の元に行なわれていたハイブリッド解の探索に対して、より広範な磁場構造の計算を行ない、これまで正確には見つかっていなかったハイブリッド解について明確な結論を得ることができた。その解は、磁場構造に応じて、(s1)sin22 -1,
-1, m2-2×10-9eV2(Akhmedovタイプ
m2-2×10-9eV2(Akhmedovタイプ によって
によって の生成が予測される。神岡実験の標的物質である水中の陽子は
の生成が予測される。神岡実験の標的物質である水中の陽子は
 3×10-5
3×10-5