【緒言】 頭頚部悪性腫瘍はしばしば直接浸潤性に、神経性に、またリンパ節転移として副咽頭間隙に進展する.ひとたび副咽頭間隙内に進展すると、この間隙にはその進展を阻止する解剖的なbarrierがなく、腫瘍は頭蓋底から舌骨部まで急速に拡大進展する.これら副咽頭間隙進展例の予後はこの間隙の解剖学的特殊性による診断の遅延に加え、進展の実態が不明であること、また有効な治療法がないため極めて不良であった. 近年、X線CTをはじめとする画像診断の進歩にともない、副咽頭間隙進展に関する診断は比較的容易かつ正確となり、一部では副咽頭間隙進展例に対して拡大手術が試みられている.しかし依然として副咽頭間隙進展の実態は未解明であり、また手術療法の臨床的評価もなされていない. 本研究は、著者らが副咽頭間隙進展例に対して試みている副咽頭間隙およびその周囲組織を系統的に郭清する副咽頭郭清術施行例の臨床病理学的検討から頭頚部悪性腫瘍の副咽頭間隙進展の実態を解明し、さらに本術式の臨床的有用性を明らかにするものである.さらに頭頚部悪性腫瘍の副咽頭間隙進展に関連して、口腔後部および中咽頭からのリンパ流と副咽頭間隙との関係を基礎的研究により明らかにするものである. I.臨床的研究-副咽頭郭清術施行例の臨床病理学的検討- 【対象】1978年11月から1992年1月までの14年3か月間に、原発腫瘍切除術、頚部郭清術とともに副咽頭郭清術を併施した頭頸部悪性腫瘍75例を対象とした.これらは全例、X線CT診断や臨床診断において副咽頭間隙へ腫瘍の進展を認める臨床的副咽頭間隙進展例であった. 年齢は23〜84歳(平均54.6歳)、新鮮例49例、再発例26例であった.Stage別ではII期8例、III期22例、IV期45例であり、また病理組織型別では扁平上皮癌52例、非扁平上皮癌23例であった. 【方法】1)摘出標本から3mm間隔の段階的連続切片を作成、副咽頭間隙進展の有無と進展様式を病理組織学的に検討した.また直接進展に関してはその進展経路を検討した。2)腫瘍の臨床病理学的特徴と組織学的副咽頭間隙進展との関連につき検討した。3)術前CT診断と組織学的副咽頭間隙進展を比較検討した。4)副咽頭郭清術の臨床的有用性を術後のlocoregional controlとcause specific survivalにより評価した。 【結果】組織学的副咽頭間隙進展は46例(61.3%)に認めた。このうち直接進展は34例(45.3%)に認め、臨床病理学的特徴との関係ではT進行度(P<0.01)、Stage進行度(P<0.05)、臨床的腫瘍発育様式(P<0.05)、組織学的深達度(P<0.01)およびリンパ管侵襲(P<0.05)との間に有意な関連を認めた.リンパ節進展は19例(25.3%)で認め、臨床病理学的特徴との関係ではStage進行度(P<0.01)、病理組織型(P<0.05)との間に有意な関連を認めた.また神経性進展は4例(5.3%)で認め、臨床病理学的特徴との関係では神経周囲浸潤(P<0.01)との間に有意な関連を認めた. 直接進展経路に関して、茎突舌筋や口蓋舌筋から上咽頭収縮筋の前端下部を経由する前内側下方経路は14例、口蓋舌筋から上咽頭収縮筋の前端上部を経由する前内側上方経路は3例、口蓋扁桃外側の上咽頭収縮筋を経由する内側中央経路は2例、内側翼突筋・筋膜を経由する前外側経路は10例、耳下腺深葉から連続性に浸潤する後外側経路は4例、さらに内頸動・静脈沿いに下方から進展する下方経路は1例に認めた. 副咽頭間隙進展に関する術前CT診断の正診率は直接進展73.9%、リンパ節進展98.6%、神経性進展0%であった.直接進展に関してはCT上でinfiltr-ative進展例で高率の進展を認めた. 副咽頭郭清術の有用性に関して、5年locoregional control rateは82.0%であり、また組織学的副咽頭間隙進展例77.4%、非進展例89.4%と制御率に有意差を認めず、良好に制御されていた(図1).遠隔成績に関して、5年cause specific survival rateは66.1%であり、組織学的副咽頭間隙進展例では56.9%とやや低いが、非進展例の80.4%と比較して有意差を認めなかった(図2). 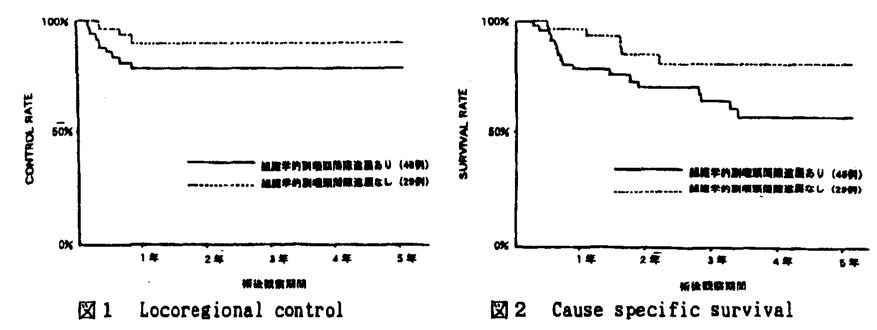 図表図1 Locoregional control / 図2 Cause specific survivalII.基礎的研究-副咽頭間隙へのリンパ流に関する検討- 図表図1 Locoregional control / 図2 Cause specific survivalII.基礎的研究-副咽頭間隙へのリンパ流に関する検討- 【対象】副咽頭郭清術を予定する20例の口腔、喉頭、中咽頭および下咽頭癌の新鮮例を対象とした。いづれも臨床的にリンパ節転移は認めないものの、原発腫瘍の局所進展範囲から副咽頭郭清術の適応ありと診断され、26〜40Gy(平均34.0Gy)の術前照射例である。なお全例、後述する微粒子活性炭CH40懸濁液の注入について同意がえられていた。 【方法】対象を4群に分け、手術施行の24時間前に副咽頭郭清術と同側の非腫瘍部の舌側縁後端、頬粘膜後端、軟口蓋の粘膜直下および口蓋扁桃上極に、微粒子活性炭CH40懸濁液0.2mlを注入した.そして術中および手術摘出標本において、副咽頭間隙ならびにKuttnerリンパ節、副咽頭リンパ節、咽頭後リンパ節の黒染状況を観察し、各注入部位からのリンパ流について検討した。 【結果】舌側縁後端群では茎突舌筋付着部の上咽頭収縮筋の黒染率がきわめて高く、舌側縁後端からの豊富なリンパ流は副咽頭間隙内側壁の前下部に流入していた。軟口蓋からのリンパ流は茎突舌筋上方の上咽頭収縮筋外側面に流入していた.また口蓋扁桃上極からのリンパ流は豊富で、外側に向い上咽頭収縮筋外側面に流入していた。一方、頬粘膜後端からのリンパ流の一部は内側翼突筋の下部に到達していた。 副咽頭間隙内側壁の著明な黒染とKuttnerリンパ節の高い黒染率および黒染度とから、口腔後部および中咽頭からのリンパ流の大部分は副咽頭間隙の壁沿いに下外方に流れ、Kuttnerリンパ節に流入するものと推測された。しかし、一部は副咽頭間隙内に疎ながらも存在することが明らかになったリンパ管を経由し、内頚静脈周囲から上行もしくは横走し、副咽頭リンパ節や咽頭後リンパ節にも直接流入していた。これは副咽頭リンパ節、咽頭後リンパ節が共に口腔後部および中咽頭の所属リンパ節、なかでも一次リンパ節である可能性を示すものと考えられた。また副咽頭リンパ節、咽頭後リンパ節の肉眼的および組織学的黒染率、黒染度の差は小さく、これらへのリンパ流が比較的豊富であることを示唆していた。 【考察】臨床的副咽頭間隙進展では高率に組織学的副咽頭間隙進展を認めることが明らかになった。組織学的進展様式では直接進展の頻度が最も高く、次いでリンパ節進展、神経性進展の順であった。 組織学的直接進展例の臨床病理学的特徴として、局所進行例、内向型の腫瘍発育様式、深達性癌およびリンパ管侵襲の存在が指摘され、これらは共に副咽頭間隙に連続する組織への浸潤と発達した粘膜下のリンパ管網への侵襲を高める因子と考えられる。組織学的リンパ節進展例の臨床病理学的特徴として、stageIVの進行例、扁平上皮癌を挙げることができた。基礎的研究から副咽頭リンパ節、咽頭後リンパ節が共に口腔後部および中咽頭の所属リンパ節、なかでも一次リンパ節である可能性が示唆されたが、臨床的研究においても一次リンパ節として転移することが確認された.また神経性進展例の臨床病理学的特徴として、神経周囲浸潤の存在が指摘された. 臨床的研究から、頭頸部領域から直接進展経路には前内側下方経路、前内側上方経路、内側中央経路、前外側経路、後外側経路および下方経路の6経路が存在することが明らかになった.また基礎的研究からも、これら6経路のうち前内側下方経路、前内側上方経路、内側中央経路および前外側経路にはそれぞれの経路に一致する方向特異性のリンパ流が存在することが明らかになり、リンパ解剖学的にも直接進展経路の存在を裏付けるものと考えられた. 術前のX線CT診断に関して、本研究に用いた診断基準は一部の直接進展や神経性進展を除き十分満足すべきものと考えられるが、より正確な診断のためには軟部組織分解能に優れるMRIによる診断基準の作成が待たれる. 副咽頭郭清術後の5年locoregional control rateは82.0%であり、組織学的副咽頭間隙進展例においても77.4%と優れていた。また5年cause specific survival rateは66.1%であり、組織学的副咽頭間隙進展例においても56.9%と優れ、さらに術後合併症の発生も比較的少なく、本副咽頭郭清術の臨床的有用性は極めて高いと考えられた. 【結語】本研究は頭頸部悪性腫瘍の副咽頭間隙進展を臨床病理学的およびリンパ解剖学的に検討し、その実態を解明したものである.また副咽頭間隙進展例に対する副咽頭郭清術の有用性を明らかにしたものである. |