| 【緒言】 1906年Goyanesが膝窩動脈瘤に対する血行再建術を行って以来、下肢動脈の血行再建術は様々な方法により、その成績の向上が図られてきたが、下腿動脈への血行再建の成績は必ずしも満足できるものではなかった。多田らは、膝窩動脈以下の吻合に剥離操作を最小限にし、血管鉗子を使用せず、エスマルヒ駆血帯による完全駆血下に端側吻合を行う吻合法(以下エスマルヒ駆血法)を用いることにより、遠隔開存率の画期的な向上を達成した。本研究の目的は、このエスマルヒ駆血法による下腿動脈血行再建術後の吻合部の経時的形態変化を、計画的に長期にわたり繰り返して施行した血管撮影所見にて観察することにより、良好な遠隔開存率を獲得した要因を研究し、もって末梢動脈血行再建術の成績向上に寄与することにある。 【対象および方法】 1982年以降1992年までに東京大学第二外科及び関連施設において、エスマルヒ駆血法により施行した膝関節以下の動脈への自家静脈バイパス術68例76肢のうち、遠隔期(術後6カ月以降)に血管撮影を施行し末梢吻合部を観察した21例23肢を対象とした(表1)。 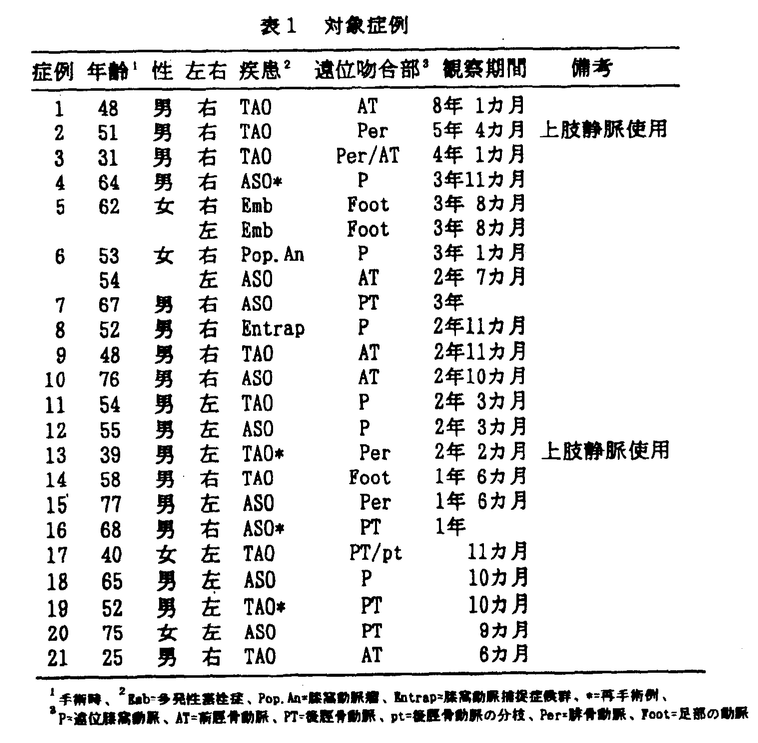 表1 対象症例 表1 対象症例 これらの血行再建術後、原則として2ないし3週間後(術後早期と称する)、および6ないし12カ月後に血管撮影を施行し、以降は1ないし2年毎に施行した。血管撮影による観察期間は6カ月〜8年1カ月(平均2年7カ月)であった。観察期間中に、中枢吻合部狭窄やグラフト体部の狭窄等の理由により再手術を行った症例が4例あった。 血管撮影は患側大腿動脈を直接穿刺しする方法(以下直接穿刺法)を標準とした。径の拡大縮小は10%以上の増減を示したときと定義した。 【結果】1.グラフト及び宿主動脈末梢側の径の変化 術後早期を含め直接穿刺法にて複数回の撮影行った16例について、末梢吻合部近くのグラフト及び宿主動脈末梢側の径を測定した。術後早期の撮影では2例を除いて末梢吻合部近くのグラフト径は宿主動脈末梢側の口径よりも大きかった。径の変化を見ると、宿主動脈径は12例(75%)において拡大を示したが、グラフト径は5例(31%)において縮小し、8例(50%)においてほぼ一定であった(表2)。グラフト径が拡大した3例中2例は上肢静脈を使用した症例で、他の1例は早期の撮影においてグラフト径が宿主動脈径よりも小さいものであった。 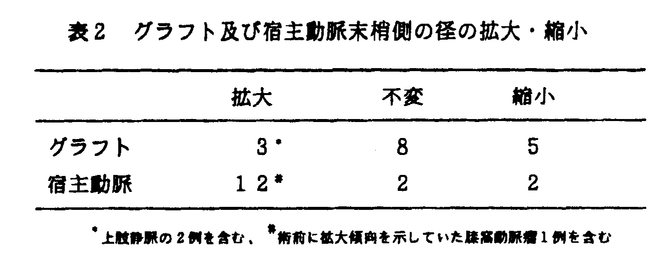 表2 グラフト及び宿主動脈末梢側の径の拡大・縮小 表2 グラフト及び宿主動脈末梢側の径の拡大・縮小 上肢静脈使用例と、すでに病的拡張を示していた動脈へのバイパス術であった膝窩動脈瘤例を除くと、グラフトと宿主動脈末梢側の口径差は術後早期には1.7±0.4mm(平均±S.E.、以下同様)であったものが、遠隔期には1.0±0.1mmと縮小する傾向にあった。 2.グラフトと宿主動脈末梢側のなす角度の変化 末梢吻合部において、グラフトと宿主動脈末梢側のなす角度(以下吻合角)の変化を、吻合部をほぼ同一の角度から複数回観察できた17例にて検討した。3例では術後早期より吻合角がほとんどなくほぼ直線化しており、残りの14例中11例(79%)では経過とともに明らかに吻合角は減じ、直線に近づくように変化した。また、吻合口径がグラフト径に対して十分には大きくなかったため大きな吻合角をもった2例では、吻合角を局所的に減じようとする変化のため、遠隔期において宿主動脈末梢側が蛇行した。 3.吻合部及び近傍のグラフトの形態変化 自家静脈バイパス術の端側吻合部は、コブラ頭状の膨大を示すことが多いが、この膨大が遠隔期には徐々に縮小するのが11例において、認められた。また、術後早期の血管撮影で結紮された枝がグラフトの突出として認められることがあったが、これらすべては遠隔期には消失あるいは縮小した。また、早期の撮影にて吻合部近くに不整な凹凸が見られるた6例では、遠隔期にはそれらが平坦化する傾向が観察された。さらに、早期に認められたわずかな狭窄像が、遠隔期には消失する例もあった。以上のように、術後早期に末梢吻合部近くのグラフトに認められたさまざまの不整像は補正され、口径が一定で凹凸の少ない導管に近づくように変化した。 4.宿主動脈の形態変化 吻合部末梢側の宿主動脈の形態変化が遠隔期の血管撮影で認められた症例は、先に述べた拡大、縮小、蛇行の他、閉塞性血栓血管炎例で、遠隔期に宿主動脈に蛇腹状変化が認められるようになった例があった。しかしながら、対象とした閉塞性動脈硬化症9例を含む21例23肢において、吻合部近傍末梢側に虫喰い状の壁不整等硬化性変化を示唆する所見が、遠隔期に出現するようになったものは1例もなつかた。宿主動脈の中枢側も、遠隔期において概ね良好に保たれていた。 5.末梢吻合部近傍の分枝の温存 吻合近接部を、吻合部及び吻合両端よりそれぞれ50mm以内の範囲と定義すると、吻合近接部より分枝する宿主動脈の枝が術後の血管撮影にて確認された症例は21例中16例(76%)であり、これらの分枝は1例を除いて術後遠隔期にも良好に開存していた。この範囲の分枝は、動脈の全周剥離を行い、血管鉗子を使用する従来の吻合方法では、到底温存できなかったものと考えられる。 【考察】 血行再建術後遠隔期の血管撮影が成績向上のため重要であると言われているにもかかわらず、下肢動脈の血行再建術後に系統的にこれを施行し、遠隔期の形態変化について詳細に検討した研究はほとんどなかった.本研究では、エスマルヒ駆血法による下腿動脈自家静脈バイパス後の吻合部の経時的形態変化を、計画的に長期にわたり繰り返して施行した血管撮影所見から観察した。 多田らは、従来の方法での下腿動脈血行再建術においては、手術操作に伴う吻合部周囲の瘢痕化により、吻合部内膜の線維性肥厚が加速されグラフト不全に至るという仮説のもとに、血管周囲の瘢痕化を極力防止するため、剥離操作を血管鞘前面までにとどめ、血管鉗子を用いず、エスマルヒ駆血帯による完全駆血下に吻合を行う方法(エスマルヒ駆血法)を考案し、下腿動脈への血行再建術に画期的な成績の向上をもたらした。 本研究で示された、宿主動脈末梢側の径の増大及び吻合角の縮小は、それを可能にするだけの血管周囲の可塑性が保持できたということであり、エスマルヒ駆血法考案の際の最大の目的である瘢痕化の防止が達成されたことを示す証左であると考えられる。 動脈硬化は内膜の傷害により惹起されること、ラットの腹部大動脈を全周剥離すると、まず内皮細胞の脱落が起こり、内膜肥厚がこれに続くこと、さらに、血流増加に伴う動脈径の増大は内皮細胞の存在下においてのみ起こることなどが、すでにいくつかの実験で証明されている.これらのことを考え併せると、動脈の全周を剥離し、血管鉗子を使用した従来の方法によるバイパス術では、剥離に伴う瘢痕形成に加え、内皮細胞の脱落により自律的な宿主動脈の径の増大を妨げ、また動脈硬化を助長し内膜肥厚を惹起することにより、グラフト血流の流出抵抗を増大させ、遠隔期閉塞の原因となっていたと考えられる。これに対し、エスマルヒ駆血法による吻合部においては、血流量の増加に応じた宿主動脈径の増大が起こることが観察されたが、これは、最小限に限定された侵襲が局所での動脈硬化を発現させる引金にはならず、内皮細胞を温存して自律的な動脈径の変化を保証していることを示唆している。動脈径の変化は壁ずり応力の変化に応じて血流量の増加に対応したものであると考えられる。 さらに、従来の方法では不可能であった末梢吻合近接部の分枝の温存が、エスマルヒ駆血法によれば容易であったことが明らかにされた。また、遠隔期においても、末梢吻合部中枢側への逆行性の血流がある程度保たれていることも示された。これらは、流出抵抗の増加を防ぎ、十分なバイパス流量を確保して、グラフト開存性を高めていると考えられる。このことは、支配領域の乏しい足部の動脈の血行再建術や、いわゆるrun-off不良例における血行再建術の際、特に重要となる。 以上のように、エスマルヒ駆血法を用いた下腿動脈へのバイパス術において、良好な遠隔成績が得られた要因は、末梢吻合部宿主動脈に対する手術侵襲を極めて限局させるという合理的な手術手技が、局所の瘢痕形成を最小限に抑え、宿主動派の硬化性変化を助長することなく自律的な径の変化を保証し、さらに吻合部近傍の分枝を温存して、遠隔期においても良好な吻合部形態の維持を可能にしている点にあることが遠隔期の系統的血管撮影によってはじめて立証された。 【結語】 エスマルヒ駆血法を用いた下腿動脈への自家静脈バイパス術後に計画的に施行した血管撮影により、末梢吻合部形態変化を観察した結果、術後遠隔期には、宿主動脈末梢側では口径が増大し、グラフトとの吻合角は減ずる傾向を示す一方、動脈硬化所見の進展はみられなかった。また、グラフトは一定の径を持つ凹凸のない導管に近づくように変化し、吻合部近傍の動脈の分枝は遠隔期においても良好に開存していた。これらのことにより、宿主動脈に対する手術侵襲を最小限に限定するエスマルヒ駆血法による吻合部は、高度の瘢痕形成を免れ、動脈硬化を惹起することなく、自律的な動脈の拡張を可能にしており、これらがきわめて良好な遠隔開存率を保持できる要因であると結論された。 |