ウラル基語の統語については、今まで断片的にしか扱われてこなかったし、それも数ページに及ぶのみであった。そこで、ウラル諸語の統語的実態を全般的に記述し、これを通して、ウラル基語の統語的特徴を解明しようと考えた次第である。 そのために、次のような手順を踏むことにした。 (1)ある統語的事項に関する各言語の用例をもとめる。 (2)こうした用例を比較して類型化を行なう。 (3)類型に基づいて、ウラル基語の統語的原型を再構する。 (4)この原型から各言語への統語的派生過程を究明する。 第1章格とその体系 ウラル語の特色のひとつとして名詞における変化格の数が多いということがある。フィンランド語が15格、ジリヤン語が17格といったところである。 こうした諸種の格の根底をなすのは場所格である。宇宙の事象は、まず動くものと動かないものとに識別される。静止するものは、その位置により、移動するものは、その方向によって認定される。移動方向は、移動して来た起点と移動して行く着点への方向で見分けられる。従って、基底格は認知の方式に基づき次のような体系を組むと考えられる。 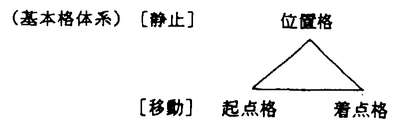 図表 図表 場所格はすべてこの基底格から導き出せる。 だが、文法格については、別な考察が必要である。 (a)John beat Mary.(動作主・作用・対象)「ジョンがメアリーをなぐった」 (b)John loves Mary.(感受者・作用・対象)「ジョンはメアリーが好きだ」 (a)と(b)の文は、意味的には括弧内に示されたような関係にあるが、文法的には、やはり主格のJohnが目的格のMaryにある行為を及ぼしていると、把握されている。従って、共に主格が行為の起点であり、目的語がその着点と見なされている。他方、属格であるが、Rafael’s picture(ラッファエルが動作主)、Mona Lisa’s picture(モナ・リザが対象)、Caesar’s love(シーザーが感受者)のように、修飾語と被修飾語の間に、さまざまな意味的脈絡を看取できる。しかし、いずれにしろ静的な関係状態を示すものであるから、属格を位置格的なものとして扱うことにする。 そこで 、文法格は左のような体系を組むことになる。なお、与格は場所の着点格に所属すと考えられる。  図表 図表 かくて、各種のパラメーターを用いて、基本格を増幅することにより、フィンランド語の15格を次のように分析することができる。 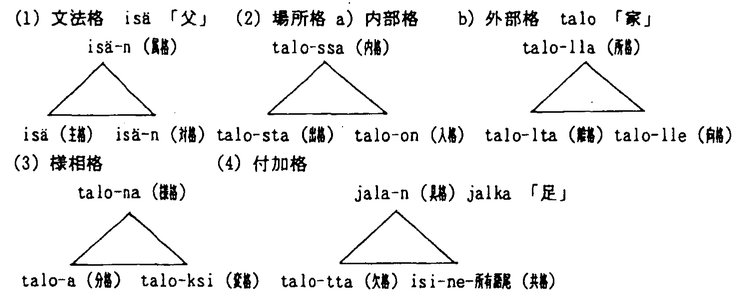 図表 図表 この方式に従って、エストニア語、南北ラップ語、エルジャ・モルドビン語、牧地チェレミス語、ジリヤン語、ボチャーク語、北ボグル語、北と東オスチャーク語、ハンガリー語、サモエード系のツンドラ・ネネツ語、森林ネネツ語、ガナサン語、セリクプ語、カマス語の格体系を明らかにした。 なお、ウラル基語の6格は、文法格と場所格の体系から成り立っていると推定されるので、こうした基語の格体系から各言語の格体系がいかにして派生したかを追求することになる。例えば、モルドビン語であるが、次のような展開を読み取ることができる。  図表第2章文の種類 図表第2章文の種類 文の種類としては、平叙文、否定文、疑問文が扱われている。 1.平叙文 (北ボグル語)nawram jon r-i.「子供(単数)が遊んでいる」 r-i.「子供(単数)が遊んでいる」 nawram-∂t jon -e -e ∂t.「子供たち(複数)が遊んでいる」 ∂t.「子供たち(複数)が遊んでいる」 nawram-i jon jon -e -e .「2人の子供(双数)が遊んでいる」 .「2人の子供(双数)が遊んでいる」 ウラル基語には、単、双、複の3数があり、主語と述語動詞の間に数の一致が要求されていた。だが、ラップ語、ウゴル語、サモエード語以外では、双数は複数に吸収されている。また、モルドビン語とサモエード語に見られる非動詞述語(名詞、形容詞、副詞)の発生過程を考究した。 例:(モルドビン語)son ucit’el’-s.「彼は先生だった」(過去) 2.否定文 ウラル諸語には、否定文に否定動詞を用いる言語と否定副詞による言語とがある。 例:(フィンランド語)Poika ei lue kirjaa.(eiは否定動詞) (ハンガリー語)A fiu nem olvas konyvet.(nemは否定副詞)いずれも「少年は本を読んでいない」の意。 フィン・ペルム語と北サモエード語における否定動詞の変化を記述し、その原型の復元を試みた。 3.疑問文 疑問詞疑問文における疑問詞の用法と一般疑問文における疑問辞*-koと*-aの用法につき論究した。 第3章文と文法的カテゴリー1.動詞の時制と相 ウラル基語の時制は現在と過去のみであったが、現代のウラル諸語には、未来形の発生や過去形の分裂、さらに相表現の展開が見られる。こうした発展の過程を追跡した。 例えば、ボチャーク語については次のような派生の経路を尋ねることができる。  図表2.対象活用 図表2.対象活用 自動詞や不定の目的に反応する主体活用と、定の目的に反応する対象活用の2種を備えているハンガリー語、ボグル語、オスチャーク語およびサモエード語、モルドビン語の語形変化と用法を記述し、その類型と発達の過程を考察した。モルドビン語の例: (1)t’ejt’er sormad-i sorma.「少女が(不定の)手紙を書いている」(主体) (2)t’ejt’er sormad-si sormant’.「少女が(定の)手紙を書いている」(対象) 3.動詞の態(1)受動態 ウラル諸語の受動文には次の4つのタイプがある。 (a)単一人称の語形で行為者不明のタイプ(フィンランド語) Liisa rakaste-taan.「リーサは(みんなに)愛されている」 (b)全人称で変化する行為者不明のタイプ(ラップ語) rahkest-uvlvo-t.「君は(みんなに)愛されている」 (c)全人称で変化する行為者明示のタイプ(ウゴル語) x jtnut w jtnut w rajan xum-n al-wes.「狼が・狩の・人に・殺された」(ボグル語) rajan xum-n al-wes.「狼が・狩の・人に・殺された」(ボグル語) (d)受動化が未発達のタイプ(ハンガリー、チェレミス、モルドビン、ペルム語) (d)の語群では、自動詞化や総称の3人称形で受け身の意味を表わしている。 (2)使役態 (フィンランド語)Vaapeli laula-tti alokkai-lla virren. 「軍曹は新兵に(所格)歌を歌わせた」 ウラル諸語では、動作主が(a)位置格、(b)着点格、(c)対格のいずれかで示されることを明らかにし、その理由を考察した。 4.法表現(a)義務的法 1)命令法における変化のタイプと、これから派生した願望法や希求法(チェレミス語、モルドビン語)のプロセスを追究した。 2)禁止法についても同じような手順を用いた。 (b)認識的法 1)フィンランド語は条件法と可能法を備えている。他の言語に見られる条件法や接法の用法を記述し、その派生の過程を解明した。 2)未確認用法 チェレミス語の過去には、a)話し手が目撃した事実を述べる確認用法と、2)話し手が伝聞による情報を提供する未確認用法とがある。 a)m j tunam tuneman j tunam tuneman  l’e.「私はそのとき勉強していた」 l’e.「私はそのとき勉強していた」 b)nuo codraste ilat ulmas.「彼らは森で生活していたそうだ」 ボチャーク語はさらに複雑であるが、タタール語の定と不定過去の影響によるものと推定した。さらに、ウゴル語とサモエード語の伝聞法の構成を分析し、エストニア語の斜格法にも言及している。 第4章準動詞の用法1.不定詞 ウラル諸語の不定詞の語形と用法を個々に詳述し、その結果として、ウラル基語において、義務(must)、許可(may)、可能(can)、要望(to want)を表わす法の補助動詞、および、開始(to begin)、終了(to finish)を意味する相の補助動詞と共に不定詞が用いられていたことを論証した。 2.分詞 ウラル諸語の分詞の語形と用法を検討し、基語に存在した現在と過去の2つの分詞からどのようにして現在使用されている分詞形が派生したかを分析した。例えば、チェレミス語とハンガリー語の未来分詞はチュルク系言語の影響によることを指摘した。 3.副動詞 副動詞は主動詞との間の時間的関係や様態を示す働きをもつ。各言語の語形と用法を調べ上げることにより、根源的に次のような構成をなしていることを立証した。 (a)同時性:語幹+副動詞語尾+位置格語尾 (b)先行性:語幹+副動詞語尾+起点格語尾 (c)後行性:語幹+副動詞語尾+着点格語尾 第5章単文内の構造1.所有構造には3つの類型のあることに着目した。 (a)存在動詞+所有者(位置格形) (b)存在動詞+所有者(属格形) (c)所有動詞+所有者(主格形) この内、(a)が基本的で、(b)はチュルク系言語の影響によるものである。(c)に関しては、その起源は未詳である。 2.知覚構造 フィンランド語の知覚動詞は、文法的に特有の挙動を示す。 Laulu kuuluu kaunii-lta.’The song sounds fine.’ 知覚の内容は離格形となる。さらに、分詞構文を組むことができる。 Nain pojan ui-van.’I saw the boy swimming.’ こうした知覚動詞による分詞構文を各言語について探り出し、これが基語の時代にまで遡るものと推定した。 第6章形容詞と後置詞 形容詞が名詞に先行すること、比較構文における基準が起点格で表示されることを述べ、各言語における後置詞の用例を紹介した。 第7章語順 ウラル諸語は語順により、次のように分類される。 (a)非SOV型:バルト・フィン語、ラップ、モルドビン語、ジリヤン語、ハンガリー語、山地チェレミス語 (b)SOV型:牧地チェレミス語、ボチャーク語、オビ・ウゴル語、サモエード語 しかし、牧地チェレミス語とボチャーク語はタタール語の影響で動詞末位に変ったこと、オビ・ウゴル語にもサモエード諸語にも非SOV型が散見されることから、ウラル基語はゆるやかなSOV型で、早い時期にフィン・ペルム語が非SOV型に変質したものと推定した。 第8章重文と複文 複文については、副詞節に関して、まず従位接続詞の体系を取出し、これに従って、ウラル諸語の従位節の用法を網羅的に検討し、ウラル基語時代の複文構造を考察した。なお、重文の同位接続詞についても同様な手法を適用した。 以上 |