酸化物高温超伝導の発見以来多くの実験的、理論的な研究がなされてきたが、その超伝導の発現機構についての理論的解明は未だ不完全である。 高温超伝導酸化物には共通してCuO2面が存在する。絶縁体状態ではCu(3d9)O(p6)という電子状態を有し、ホールは酸素サイトにドープされ、系は2次元の強相関電子系としての振る舞いを示す。 スピン励起は低エネルギーの電子物性に大きな役割を果たす。実験的には中性子散乱や核磁気共鳴(NMR)などの手段により調べることができる。中性子散乱の実験においてはLa2-xSrxCuO4(LSCO)とYBa2Cu3O6+x(YBCO)は波数ベクトル空間でそれぞれ非整合(IC)ピーク及び整合(C)ピークが見られ、超伝導状態においてそのICピークが崩れず、残るのに対して、Cピークは強度が弱くなることが明らかにされている。 これに対してNMRの実験はYBCOにおいては60K系物質と90K系物質で、本質的な違いがあることを示している。これは最初Riceによって指摘され、後に一般的に議論された。即ちKnight Shift K,核磁気緩和率 ,及び ,及び がドーピング領域で異なった振る舞いを示し、高濃度側(以下、H-regionと呼ぶ)ではそれぞれが極大値を持つ特徴的温度TS、TR、TCはほぼ一致するのに対して低濃度側(以下、L-regionと呼ぶ)ではTS>TR>TCの関係式が成り立つ(図1)。 がドーピング領域で異なった振る舞いを示し、高濃度側(以下、H-regionと呼ぶ)ではそれぞれが極大値を持つ特徴的温度TS、TR、TCはほぼ一致するのに対して低濃度側(以下、L-regionと呼ぶ)ではTS>TR>TCの関係式が成り立つ(図1)。 このような実験的なアプローチに対して理論的には、守谷、Pinesらは現象論的な見地から反強磁性的なスピンゆらぎに重点をおいた理論を展開している。一方BulutとScalapinoは単一バンドHubbard model、Levinらはd-p modelに基ついたミクロな見地からの説明を試みているがいずれも完全なものとは言えない。 本論文ではt-J modelに基づいた理論的考察を行う。 このt-J modelはCuO2平面の電子状態を表現するd-p modelから導出された単一バンドモデルであり、高温超伝導体の低エネルギー励起をよく記述するモデルと考えられている。 t-J modelについても多くの理論的な研究がなされてきた。特にNagaosaとLeeはslave-boson法に基ついてt-J modelによる輸送現象を調べ、一様なResonating Valence Bond(u-RVB)状態が高温超伝導体の常伝導相を記述する有望な候補であることを示した。このRVB理論は強い量子揺らぎにより磁気秩序が壊され、スピンが一種の液的状態になっている場合のスピン系を記述する理論で、Andersonにより1973年に提唱された。slave-boson法による平均場の範囲では電子のスピン自由度と電荷自由度は分離され、それぞれはspinon、holonと呼ばれる準粒子となる。一様RVB状態はこのspinonが大きなフェルミ面を持つ状態であり、実験と整合する。 本論文の目的はt-J modelの磁気的な性質を明らかにするところにあるが、本研究の主たる動機はSuzumuraらの示したt-J modelの平均場の相図と実験の相図の類似である(図2)。t-J modelの平均場には3つの特徴的な温度TD、(spinonとholonのcoherentな運動が生じる温度)TRVB、(spinonの一重項対の生じる温度)TB(holonがBose凝縮する温度)が現われ、L-regionではTRVB>TBの関係が、H-regionではTRVB<TBの関係がある。それぞれの領域においてTRVBとTBのうち低い方の温度を超伝導転移温度TCとみなすことが出来、実験的に得られているものと同様な相図が得られる。 我々はこのt-J modelの磁気的な性質をslave-boson法によりRPAに基ついた平均場理論の範囲で調べた。我々はt-J modelを拡張し、実験的に発見されているフェルミ面(典型的にはLSCO型とYBCO型)に合致するように次近接及び次々近接のtransfer integralを取り入れ、Knight Shiftや核磁気緩和率、中性子散乱などの実験に対応する物理量を計算した。 超伝導相(s-RVB状態)のクーパー対としては分子場近似の解であるd波を採用している。 t-J modelは以下のように与えられる、  slave-boson法では電子の演算子cisはスピン1/2のフェルミオンの自由度を持つ演算子fisと電荷eのボソンの自由度を持つ演算子biを用いてcis=bi+fisのように表される。この記述法を用いると各サイトに電子が二つ以上存在してはいけない説いう条件は、各サイトにおいて 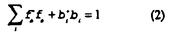 と表される。このような局所束縛条件はこのままでは解けないので、全系での平均的な条件(大局的束縛条件)で近似する。このとき式(1)に対して考えられる可能な分子場の秩序変数は、 、 、 及び 及び である。このうちで である。このうちで , , を取り、これらが(i-j)のみ依存すると仮定して分子場の連立方程式を自己無撞着に解く。このとき、電子のフェルミ面はspinonのそれであり、式(1)でtijを次近接(t’)及び次々近接(t")のサイトまで取り入れることにより、フェルミ面の形を光電子分光の実験の結果と一致させるようにする。LSCO型ではt’/t=-1/6,t"/t=0、YBCO型ではt’/t=-1/6,t"/t=1/5の値を取り入れた(図3(a)(b))。但し、フェルミ面の形だけ見れば、YBCO型はt’/t=-1/2,t"/t=0のように取ることができる(図3(c):YBCO(II))。 を取り、これらが(i-j)のみ依存すると仮定して分子場の連立方程式を自己無撞着に解く。このとき、電子のフェルミ面はspinonのそれであり、式(1)でtijを次近接(t’)及び次々近接(t")のサイトまで取り入れることにより、フェルミ面の形を光電子分光の実験の結果と一致させるようにする。LSCO型ではt’/t=-1/6,t"/t=0、YBCO型ではt’/t=-1/6,t"/t=1/5の値を取り入れた(図3(a)(b))。但し、フェルミ面の形だけ見れば、YBCO型はt’/t=-1/2,t"/t=0のように取ることができる(図3(c):YBCO(II))。 t-J modelでの動的帯磁率 ( ( , , )はJの項をRPAで取り扱うことにより得られ、 )はJの項をRPAで取り扱うことにより得られ、  で与えられる。ここで、 0( 0( , , )は自由なspinonの動的帯磁率、及びJq=J(cosqx+cosqy)である。以上の定式化により以下のような結果が得られた。 )は自由なspinonの動的帯磁率、及びJq=J(cosqx+cosqy)である。以上の定式化により以下のような結果が得られた。 まず、常伝導状態(u-RVB状態)ではフェルミ面の違いにより一様帯磁率 ( ( =0)の =0)の 依存性を計算した結果は実験的に知られている、LSCO型のIC構造とYBCOのC構造の違いを示すことが分かった(図4)。LSCO型のIC構造は 依存性を計算した結果は実験的に知られている、LSCO型のIC構造とYBCOのC構造の違いを示すことが分かった(図4)。LSCO型のIC構造は ( ( , , )の )の = = =( =( , , )付近のフェルミ面の強いnestingの結果であり、YBCO型の場合, )付近のフェルミ面の強いnestingの結果であり、YBCO型の場合, ( ( , , )自体はBrillouinゾーンのほぼ全領域にわたって同じ値をとり、むしろ )自体はBrillouinゾーンのほぼ全領域にわたって同じ値をとり、むしろ の の 依存性がC構造の性質を決定していることが分かった。更にLSCO型拡張t-J modelのIm 依存性がC構造の性質を決定していることが分かった。更にLSCO型拡張t-J modelのIm ( ( , , )に現れるICピークの高さの温度依存性は励起エネルギー )に現れるICピークの高さの温度依存性は励起エネルギー の値により異なった特徴を示す(図5)。 の値により異なった特徴を示す(図5)。 =0.01Jと =0.01Jと =0.05Jの場合は温度が下がるにつれてICピークの高さは増加し、T=TRVBでs-RVBのオーダーパラメーターの形成により減少しはじめる。これに対して =0.05Jの場合は温度が下がるにつれてICピークの高さは増加し、T=TRVBでs-RVBのオーダーパラメーターの形成により減少しはじめる。これに対して =0.1Jの場合はT=TRVB以下でも増加し続ける。これらの温度依存性はTC=TRVBとした場合、Masonらの中性子散乱の実験結果と一致する。彼らは図6で =0.1Jの場合はT=TRVB以下でも増加し続ける。これらの温度依存性はTC=TRVBとした場合、Masonらの中性子散乱の実験結果と一致する。彼らは図6で = = 及び 及び = = でのIm でのIm ( ( , , )の極大(図では )の極大(図では (T)及び (T)及び (T))がTC以下で同様の温度依存性を示すことから(図6(a))、この系の超伝導の対称性はcleanなd波ではなく、ギャップのないs波であろう、と緒論した。この実験結果に対して、我々は以下のような理由から超伝導の対称性がd波と矛盾しないものであることを示した。(1)d波の場合、低温ではIm (T))がTC以下で同様の温度依存性を示すことから(図6(a))、この系の超伝導の対称性はcleanなd波ではなく、ギャップのないs波であろう、と緒論した。この実験結果に対して、我々は以下のような理由から超伝導の対称性がd波と矛盾しないものであることを示した。(1)d波の場合、低温ではIm ( ( , , )がIm )がIm ( ( , , )より小さくなるのであるが、その一致する温度は不純物等の乱れにより低温側にシフトすること(図6(b))。(2)低温でも )より小さくなるのであるが、その一致する温度は不純物等の乱れにより低温側にシフトすること(図6(b))。(2)低温でも = = でのピークの高さは でのピークの高さは 空間である程度の広がりがあるのに対して、 空間である程度の広がりがあるのに対して、 = = では広がりが極めて狭い構造をしていることが実験での観測される強度を減らしていると考えられる。これらのことからMasonらの中性子散乱の実験結果はd波超伝導を否定するものではないと言える。 では広がりが極めて狭い構造をしていることが実験での観測される強度を減らしていると考えられる。これらのことからMasonらの中性子散乱の実験結果はd波超伝導を否定するものではないと言える。 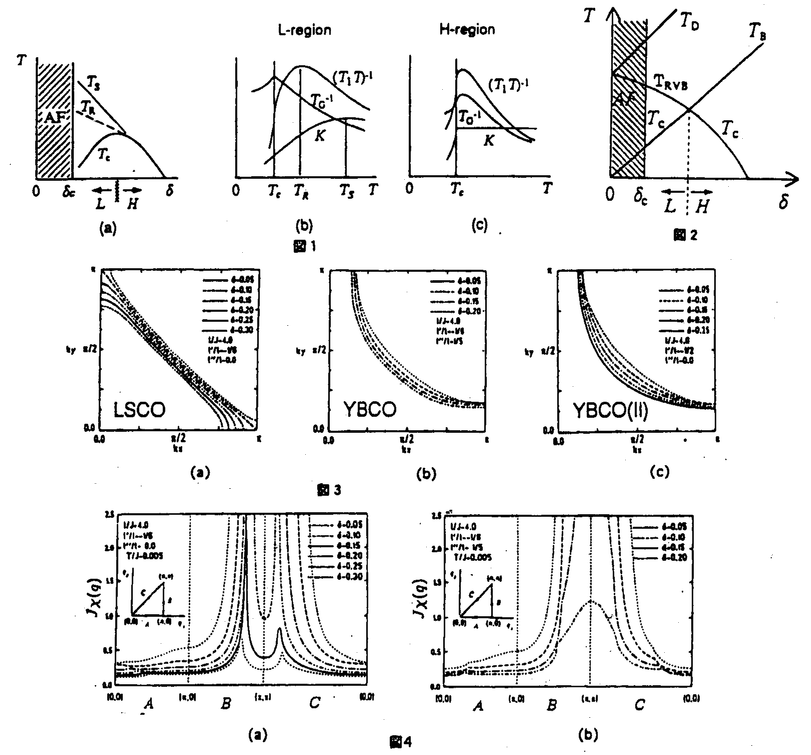 図表図1 / 図2 / 図3 / 図4 図表図1 / 図2 / 図3 / 図4 一方、YBCO型拡張t-J modelに対するIm ( ( , , )の温度及び )の温度及び 依存性はTC=TRVBとした場合Rossat-Mignodらの中性子散乱の実験結果とよい一致をする(図7)。これは、(1)Im 依存性はTC=TRVBとした場合Rossat-Mignodらの中性子散乱の実験結果とよい一致をする(図7)。これは、(1)Im ( ( , , )は常伝導状態(T>TRVB)で )は常伝導状態(T>TRVB)で の小さい領域で対して の小さい領域で対して に直線的に増加し、(2)s-RVB状態(T<TRVB)でスピンギャップ構造が見られる。(3) に直線的に増加し、(2)s-RVB状態(T<TRVB)でスピンギャップ構造が見られる。(3) 〜50meVでIm 〜50meVでIm ( ( , , )にcut-off構造が生じる。低温でのCピークの濃度依存性はLSCOの場合と同様に )にcut-off構造が生じる。低温でのCピークの濃度依存性はLSCOの場合と同様に の値により、特徴的な温度依存性を示す。これはTranquada等の実験結果と一致する。一方、実験結果との不一致も存在する。(1)スピンギャップのドーピング依存性は実験に比べて小さい。(2)TRVB以下でIm の値により、特徴的な温度依存性を示す。これはTranquada等の実験結果と一致する。一方、実験結果との不一致も存在する。(1)スピンギャップのドーピング依存性は実験に比べて小さい。(2)TRVB以下でIm (Q, (Q, )の励起エネルギーのピーク(〜20meV)は実験結果(〜50meV)と一致しない。これらのくい違いの原因は現在のところは未解決である。 )の励起エネルギーのピーク(〜20meV)は実験結果(〜50meV)と一致しない。これらのくい違いの原因は現在のところは未解決である。 Knight Shiftに対応する静的帯磁率 (q=0)の温度依存性はPauliのスピン常磁性と同じく常伝導状態(u-RVB状態)では温度依存性がない。これはcorrection factor、C-1( (q=0)の温度依存性はPauliのスピン常磁性と同じく常伝導状態(u-RVB状態)では温度依存性がない。これはcorrection factor、C-1( , , )=1+ )=1+  0( 0( , , )のq=0付近の振る舞いを反映したものであり、これは )のq=0付近の振る舞いを反映したものであり、これは と と の強い温度依存性の原因となるq=0付近のenhancement効果と対照的である。これらはH-regionでのLSCO及びYBCOの実験結果と一致している。核磁気共鳴の緩和率については、銅サイトのT1Tは高温領域で明瞭なCurie-Weissの法則を示す。実験と同じくWeiss温度はドーピング濃度に直線的に増加する。 の強い温度依存性の原因となるq=0付近のenhancement効果と対照的である。これらはH-regionでのLSCO及びYBCOの実験結果と一致している。核磁気共鳴の緩和率については、銅サイトのT1Tは高温領域で明瞭なCurie-Weissの法則を示す。実験と同じくWeiss温度はドーピング濃度に直線的に増加する。 K, , , の温度依存性はTCをTRVB同一視すればH-regionの実験とよい一致を示す(図8)。 の温度依存性はTCをTRVB同一視すればH-regionの実験とよい一致を示す(図8)。 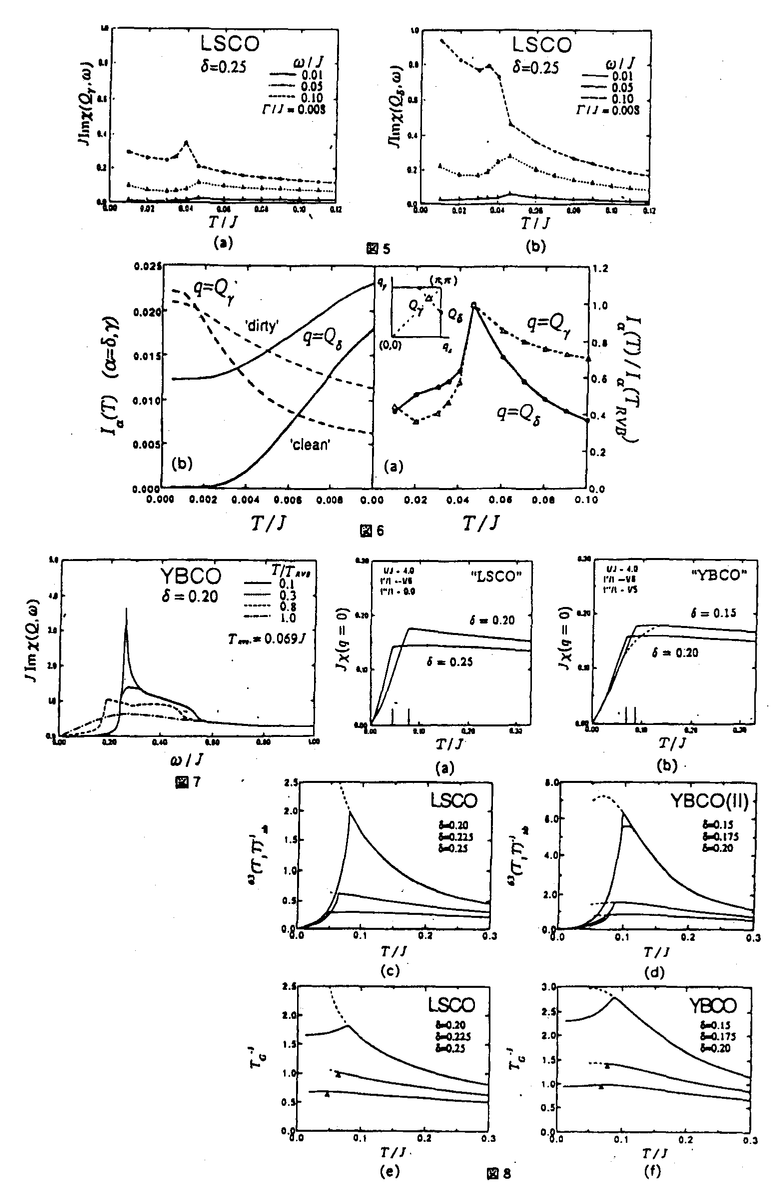 図表図5 / 図6 / 図7 / 図8 図表図5 / 図6 / 図7 / 図8 これに対してL-regionの場合は現在の平均場の範囲ではK、 , , の極大値の現れる温度の違いを説明することは出来ないが、TRをTRVBと同一視できる可能性を指摘される。 の極大値の現れる温度の違いを説明することは出来ないが、TRをTRVBと同一視できる可能性を指摘される。 このL-regionでの問題は本論文では考察しなかった分子場まわりの揺らぎであるゲージ場や或いは電子-フォノン作用の重要性を示唆している可能性もあるが、それを明らかにするのは今後の課題である。 以上本論文では平均場の範囲内で拡張t-J modelの磁気的な性質を調べその妥当性と限界を示した。その結果高温超伝導体の多くの性質を理解することが可能になったと同時に様々な問題についても基本的に指摘することが出来た。 |